2012/03/15
地震の備え、大地震がきたらどうするか考えてみる1
(2018.9.10. 修正、加筆)
地震への備えと対策について、さらに深く考えていきたいと思います。
具体的に大地震が来たらどうするか、を考えてみます。
ただし、情報はある程度調べてありますが、あくまで素人考えです。
また一応具体的にあげていきますが、最終的には臨機応変が必要です。
あくまでも参考、ということを忘れずに見てください。
そして、相変わらずの長文になると思います。
すみません。
長くなるかと思いますが、最後までお付き合いよろしくお願いします。
さて、ここでは内陸(信州)で自宅にいるとき、大地震が起きたことを想定していきたいと思います。
(といっても、プレート海溝型地震でも十分応用が利く内容だと思います)
内陸部で震度6以上の地震と想定すると、M6.0以上の直下型地震という可能性が高いでしょう。
直下型地震とは、私たちが住んでいる場所の足元、すぐ真下を震源として起きる地震のことです。
直下型の場合、まず初期振動がドンッとかズンッと突き上げるような独特の衝撃があり、そのコンマ何秒か後に、強い揺れが襲ってきます。
(一度松本にて直下型地震、震度5強を経験しました。本当に突然やってきます)
緊急地震速報も、直下型地震では正直ほとんど意味がありません。
揺れている最中か、揺れが終わってから緊急地震速報が届きます。
実際、松本の地震でも揺れが収まってから、携帯が鳴りました。
そうなると、直下型地震に対してはあらかじめ事前の備えをしっかりしておくことがもっとも肝要です。
特に前の記事で述べた、危険な大きい家具の転倒防止と寝床・ベッド付近の家具・家電などの転倒防止は、必ずやっておくべき備えだといえます。
当然ですが地震は自然現象の一つですから、地震には昼も夜も関係ありません。
夜間に起きる大地震は、大多数の方々が床についているために初めの行動が一歩遅く、危険性が非常に高まります。
寝ている間の被害を減らすためには、寝室と寝床・ベッドの周りの家具・家電の転倒防止は、事前に済ませておくしかありません。
特に寝床・ベッドの周囲には危険な家具・家電を置かないこと、家具・家電を置くならば転倒防止は必ずすることが大事です。
強い揺れが来たときは、まず自分の身を守ることが第一です。
とんでもない強い揺れの時は、逃げ道の確保とか火の始末とかは、すべて後回し。
とにかく自分の身を守ることに専念しましょう。
これが基本となります。
自分の身を守るということは、地震のあとで家族や近所の人の救助や手助けをすることができる、という意味があります。
自分がケガをしないことは、地震の時に最も重要なことの一つだと言えるのです。
(すぐ近くに守るべき子供がいる場合はこの限りではありませんが、違う部屋などにいて離れているときは、まずは自分の身を守るべきです)
地震から自分の身を守るには、まずその場で身をかがめること。
そして、とにかく頭を守ることがもっとも大切です。
手で頭を抱えるようにして守りますが、ポイントはあごを引くことと、倒壊などで挟まれた時に呼吸ができるよう、顔の前に空間ができるように腕を前から頭の上に回すこと、衝撃をワンクッションおくために頭には手が直接触れないように抱えると良いそうです。
ヘルメットをかぶったりクッションなどを頭に当てても良いでしょう。
その体勢のまま移動できる余裕があれば、危険が多い台所や倒れそうな家具から離れて、机の下などへもぐること。
テレビや冷蔵庫などの倒れやすい家電や熱湯が入ったポットなども危険ですので、なるべく離れるようにします。
ただしあわてて外へ飛び出したりせず、その場か周辺で揺れをしのぐようにしましょう。
むやみに大きく移動する方が、大怪我の危険性が高くなります。
寝ているときに地震が来たときは、布団の中にもぐりこんで小さくなること。
家具の転倒が予測されるときは、倒れてこないような位置までなるべく移動をします。
そしてどんな時でも、地震の時は頭を守る姿勢は必ず取りましょう。
とにかく地震の揺れが収まるまでは、その場その付近で自分の身を守ることだけに専念します。
(これら一連の動作を「シェイクアウト」といいます)
また、日ごろから「今この場所で大きい揺れがきたらどうすればいいか、どこが安全か?」と事前にイメージして考えておくのが良いです。
リビングなら棚やテレビを避けたこのあたりか机の下とか、寝室ならタンスから離れた扉の前かベッドの下とか。
寝ている間だったらまずはとにかく布団に潜り込むとか、家具が少ない方へごろんと転がるとか。
それぞれの部屋のそれぞれの状況にあわせて、「ここが比較的安全だろう」という場所を考えて探しておきましょう。
なんとなくでもイメージしておくと、いざというときに役に立ちます。
それでも、もし万一家具に挟まれたり、家が倒壊してまったく身動きがとれなくなったときは、すぐさま抜け出そうともがいたり、助けを求めてすぐに大声を出してはいけません。
無駄に体力を失ってしまいます。
まずは一呼吸をおいて、落ち着くこと。
慌ててパニックになることが一番危険です。
落ち着いたなら、無理なく抜け出せそうか冷静に考えてみましょう。
抜け出すのが無理だと思ったら、ここは割り切って救助や誰かが来るのを待ちます。(難しい話ですけど…)
携帯が手元にあってつながるなら、家族などへ連絡をするのも良いでしょう。
また救助が始まれば、かならず声をかけてきてくれるはずです。
その時になったら、声や音を出すようにします。
何となく人の気配を感じたときも、何か音などを出してみましょう。
自分で声を上げるとかなり体力を消耗しますので、一番良いのは笛やアラームなど音を出しやすいもの、また光で知らせられるライトなどが良いです。(両方あれば一番良い)
まだ救助が始まってないと思っても、数分に1回程度で音をならしつつ、待ちます。
しかし、頭部強打していたり腹部圧迫しているなどの場合は、生命の危険性が高いと言えます。
そういう場合は臨機応変に、すぐに助けを求めるために笛やアラームを鳴らし続けることも必要かもしれません。
笛などは神戸のおばちゃんみたいに、首から下げていつでも身につけておくのがベストです。
それか、常に枕元や居間などに置いておくと良いです。
また挟まれたりして怪我をしていたら、動ける無理のない程度で、分かる範囲で自分で応急処置をしましょう。
出血の応急処置の基本は傷口にタオルや布を当て、押し付けることです。
揺れが収まってとりあえず自分の体が無事だったなら、火の元の確認と始末をします。
(決して揺れてる最中に火を消しに行ったり、様子を見に行ったりしてはいけません。)
それから地震の情報収集と家にいた家族の安否確認をし、そして避難の準備を始めます。
地震が収まったら、まずはすぐに火の元の確認と始末が基本です。
火事は地震の後において、もっとも気をつけるべき点です。
家そのものが燃えてしまったら、家具に挟まれて動けなかっただけ、脳震とうで気を失っていただけ、といった助けられた命も助けられなくなってしまう可能性があります。
火の元を始末したら、テレビやラジオをつけて地震の情報を集めます。
大地震の後だとすぐに家族の安否確認とか家の中がぐちゃぐちゃなので片付け…と思ってしまうかも知れませんが、それは少しだけ後回し。
まずは震源と地震の規模、津波の有無や原発その他の情報、すぐ逃げるべきかどうかの判断材料を得ることが大事です。
東日本大震災のときも、多くの人が家の片付けや外に出ている家族の安否確認をしていました。
そのために、津波から逃げ出す初めの一歩が遅れてしまったという事例があります。
情報収集は停電の可能性もあるので、電池式などの小型の携帯ラジオがもっとも良いです。
この電池式の携帯ラジオ、ものすごく重宝します。
我が家にも松下製のものが一つありますが、連続つけっぱなしでも半月は持ちます。(音量にもよりますが)
仕事に使っているソニー製ラジオは、何回か落として見た目ぼろぼろですが、問題なく使用できます。
手回し充電式のラジオも良いですが、しょっちゅう回さなくてはならないので、電池式のが楽で良いと思います。
単三電池2本以上で動くような、日本メーカーのものをお薦めします。
携帯ラジオは必ず一つは家に用意しておくべき、重要な物だと私は思います。(できれば予備の電池も用意しておきましょう)
強い地震の直後は、揺れで落ちたガラスや陶器の破片が床に散乱していて、足元が非常に危険なときがあります。
緊急時は避難のために素早く行動することが求められる時もあるため、足元が危険で行動が一歩も二歩も遅れることはできれば避けたいところです。
なので、地震後の室内ではスリッパや靴などを履いて行動するようにします。
そのために、スリッパ等はいつどこで地震が起きても良いように、家のあちこちに備えておくことが大事だと言えます。
特に、寝床やベッドのすぐ近くには、緊急用の靴(靴底が厚めのスニーカーが良い)を置いておくと良いです。
それと、可能ならば防災頭巾や、ヘルメット等をすぐにかぶるのも大切です。
何度も言いますが、頭を守るのが最も大事です。
地震が起きたらすぐかぶる、くらいの気持ちでも良いと思います。
余震などで、また何が降ってくるか分かりません。
最悪は帽子やタオルなどでも良いし、バイク・自転車用ヘルメットなどをかぶればさらにOKでしょう。
効果は薄くても無いよりはましですので、頭には必ず何かを身につけるようにしましょう。
携帯ラジオを持って情報収集と同時に、家にいた家族に怪我がないか声かけて安否を確認します。
家族が怪我をしていたら分かる範囲で応急処置をしましょう。
もし家族が挟まれて動けないと分かったら、呼びかけてその状況を確認をします。
まず返事・意識があるか、挟まれた場所や部位の確認、まったく動けないのか、怪我はないか、など。
声の様子や見える範囲で状況を確認し、緊急性を判断します。(かなり難しい判断になりますが)
ポイントは、意識がはっきりあるか、頭や体、首、腰を強く打っていないか、腹部を強く挟まれていないか、出血しているときはその量、などで総合的に判断しましょう。
緊急に助け出した方が良いと判断したときは、すぐ近所や周辺の人に手を借りに行きます。
ここで大事なのは、決して一人で助けだそうとしないこと。
もし余震などでさらに崩れて二次災害にあったとき、どちらも動けなくなってしまって最悪のパターンになる事もありえます。
救助は必ず二人以上で行うのが鉄則です。
無事な家族が二人以上いれば家族で、いなければ近所の人に手を借りて救出を試みます。
ただし無理の無いように、やれる範囲でやること。
途中で助けるのが無理と思ったら、救助をやめるのも大切です。
さらに近所の手の空いている方を増やして、大人数で事に当たりましょう。
基本的には、レスキュー専門の方々に救助してもらったほうが安全で確実ですが、大地震においては専門の消防士の手助けはほぼないと考えたほうが良いそうです。
阪神淡路大震災の時、倒壊した家屋での死者のほとんどが地震後約10分くらいの圧死だったそうです。
そう考えると時間的余裕はあまりなく、取り残されている人がいるならば、とにかく早く助け出すことが先決です。
レスキューや消防は、地震の混乱とともに道路の破損などで、活動範囲が著しく狭くなります。
となると初期の救出活動は、隣近所の隣組や町内会レベルでの助け合いが、最も重要です。
救出する人手がないときは、隣組や近所の人に挟まって動けない家族がいることを伝えて人手が欲しい旨も伝え、家族へたまに声をかけ励ましつつ人手が集まるのを待ちます。
周囲に伝えておけば、救助の人手が来るのが早くなる可能性が高くなります。
また、隣近所の方々の家族構成や一人暮らしのお年寄りなどの情報を、ある程度共有しておくことも必要でしょう。
地震後に近所を回って、○○さんが見えないとか出てこないとかの確認の時に役に立ちます。
(近年の町内会・地域コミュニティの低下やプライバシーの問題などで、難しい問題でもあります)
あと、そのとき電話が使えるなら、いちおう119番か消防団へ連絡しておきましょう。
また人手を待っているときは、余震で再び崩れるかもしれないので、危険そうな場所からは離れて待ちます。
とはいうものの、やはりなるべく早く助け出すことが大事だといえます。
自分や家族が怪我をしていたら、その怪我の具合によって、すぐに病院へ行くべきかの判断します。
ポイントは先程と同じで、意識がはっきりしてるか、頭や体など強く打ったり挟んだりした所はないか、出血の量などで判断しましょう。
やばいな、と思ったらすぐに救急病院、または最寄りの災害時医療救護所へ行きます。
とりあえず大丈夫そうと思ったら、あわてずに災害時の医療救護所などに行き、責任者に怪我人がいることを伝え、対応してもらいましょう。
それから、いざというときどこへ行けば良いか迷わないように、救急病院と災害時の医療救護所がどこに設置されるのか、平時に確認しておきましょう。
自治体から配られていれば、ハザードマップや災害時マニュアルで確認しておきます。
無ければ、事前に直接自治体へ問い合わせておくことも大切です。
色々準備してる間や待っている間にも、ラジオで情報収集は常に怠らないようにします。
災害時の情報はとても重要です。
さて避難の準備ですが、やっぱり非常用持出袋、避難袋は常備しておくのがベストです。
緊急時にまず持ち出す一次持ち出し品(とりあえず1日を乗り切るもの)について、避難袋に入れるべきものを下記にざっと一覧をあげます。
長くなりますが、参考までに見てください。
缶入乾パン(1人1つ。最低限の食料として)
飲料水(1人1.5L。水は1人1日3Lの備えが必要とされるが、持ち運びの点から1.5Lとした)
懐中電灯(使い慣れたシンプルなもの、電池式は予備を忘れずに。1人1つがベスト)
ロウソク(2本。長時間の使用に適する)
ライター(ロウソク、暖房などの着火に。マッチより使い勝手が良い)
携帯ラジオ(情報収集に不可欠。予備電池も備えたい)
万能複合キッチンハサミ(ナイフ、缶切り、栓抜きなどの複合ツールだと便利。それぞれを用意するのも可)
軍手、革手袋またはゴム手袋(2セット。軍手は熱に強い綿100%のもの。革手、ゴム手は片付けや救助などで役立つ)
ロープ(7m以上。救助用、非難はしごの代わりとなる。人の体重を支えられる強度のあるものを)
救急袋(以下9個を入れる)
毛抜き(とげ抜き、ピンセットとして使える)
消毒薬(1本)
脱脂綿(適当量)
滅菌ガーゼ(2枚)
ばんそうこう(10枚~)
包帯(2巻)
三角巾(1~2枚)
マスク(2枚~。防寒にも使える)
常備薬・持病薬(常備薬は風邪薬、鎮痛薬、胃腸薬など。処方箋のコピーも用意しておくと良い)
(以上9個を救急袋へ入れる)
レジャーシート(2畳分1枚。1人あたり1畳は欲しい。避難先のスペース確保に)
サバイバルブランケット(屋外用緊急簡易毛布。非常用軽量防寒具。銀紙みたいなやつなど多種ある)
簡易トイレ(2個~。非常時のトイレは重要な問題。市販されている袋型のものを)
タオル(4枚~。汚れのふき取り、怪我の手当て、下着・おむつの代用など多用途。汎用性が高いので多めに用意したい)
ポリ袋(10枚~。大小あわせて10枚くらい。物入れ、雨具・防寒具の代用、トイレの代用など汎用性も高い)
トイレットペーパー(1つ。水に溶けるので、トイレ以外でも多用途)
ウェットティッシュ(2つ。水がないときに役立つ)
10円玉(約50枚。公衆電話用に数十枚ほしい。災害時には携帯電話、自宅電話が機能しない可能性がある。テレフォンカードなどは停電時は使えない)
布ガムテープ(1つ。伝言メモを貼るなど、多用途)
油性ペン(1本。太く大きいものの方が長持ち。伝言などを書く)
筆記用具(1セット。メモ帳とペン類。避難所などで得た情報を書きとめるのに必要)
(神戸防災センターの資料より)
以上一人分で31点です。
これが基本の品で、防災袋へ入れるとおよそ7kgとなります。
他に一次持ち出し品として、備えを検討すべきものは下記のとおり。
貴重品類など
現金、予備眼鏡、携帯電話・スマートフォン、携帯・スマホの充電器、携帯・スマホの予備バッテリ
通帳、免許証、保険証、パスポート・外国人登録証(以上4点はコピーや番号を控えておくのも良い、身分証明となる)、
印鑑、証書類、住民票、
ハザードマップ(緊急時の避難場所や医療救護所の確認のため。必要な部分のコピーでも良い)
女性用品
生理用品(長期の避難だと重要品といえる。傷の手当てなどガーゼの代用としても重宝する)、
笛付きライト(防犯・護身用)、
鏡、ブラシ、化粧品、
おりものシート(下着の代用にもなる)
高齢者用品
高齢者手帳、おむつ、着替え、
持病薬(処方箋のコピーも)、
予備眼鏡、老眼鏡、介護用品
赤ちゃん用品
粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、スプーン、
洗浄綿、バスタオル、ガーゼ、紙おむつ、
母子手帳、おもちゃ、着替え、
ベビーカー(荷物運搬にも役立つ、非常持ち出し袋には入らない)
以上、個々で必要に応じて準備しておきましょう。
特に、女性用品、高齢者用品、赤ちゃん用品は、避難所での物資配布では食料や水等に比べてどうしても二の次になってしまうものなので、災害初期ではなかなか手に入らない可能性が高いです。
最低限のもの(生理用品、介護用品、おむつ、粉ミルク、離乳食等)は事前にやや多めに用意・備蓄しておくことが大切です。
それから、携帯電話・スマートフォンは今や生活に欠かせない重要な複合ツールです。
特にスマホはもともと電池消耗が激しい物なので、停電で充電ができないとすぐ電池切れになって役に立たなくなってしまいます。
スマホの予備バッテリは防災グッズとして必要な物、と言えるかもしれません。
できれば2、3回充電できる容量の大きい物、または乾電池を使って充電するタイプの物が良いかと思います。(乾電池は比較的手に入れやすいので)
避難用品で足りないもの・気付いたものがあれば、なるべく急いで荷物の準備します。
大怪我などで緊急性を要するときは、とにかく避難袋を持ったらすぐに出発しましょう。
災害時の移動の基本は、「徒歩」とされます。
災害時においては、最終的に徒歩での移動が最も早いそうです。
怪我人が自分で動けるなら、徒歩が良いでしょう。
ただし、怪我がひどくて怪我人を担がなくてはならない場合などは、自動車という手もあります。
車が使えれば良いのですが、地震によっては道が陥没したり塀などが崩れたりして道路が使えなかったり、信号機の停電などによりひどく渋滞していたりします。
徒歩にしろ車にしろ、かなり時間がかかることは覚悟したほうが良いです。
またとりあえず119番へ電話することも試しておきましょう。
病院や救護所も、施設の被害状況によっては、違うところへ行ったほうが良いときもあります。
連絡がつくのなら、先に消防署や町内の消防団などにどこへ行けば良いのか、情報を求めたほうが良いです。
地震後の道路は、渋滞や道路の陥没、停電などで信号が消えていたりして、徒歩でも車でも危険が多いと思われます。
移動の際は、細心の注意をはらって移動してください。
車での移動は無理、と判断したら即座に徒歩に切り替えましょう。
車を途中で置いて移動するときは、車のキーを挿したまま路肩へ停め、ドアロックもかけずに置いていきましょう。
盗難等の危険もありますが、置いていった車が他の人や緊急車両の邪魔にならないように、いつでも動かせるようにしておく必要があります。
怪我人を担いで動かせない、というときは救急隊などに連絡を取り、待たなくてはならないかもしれません。
だいぶ長くなりました。
続きはまた次回に。m(_ _)m
地震への備えと対策について、さらに深く考えていきたいと思います。
具体的に大地震が来たらどうするか、を考えてみます。
ただし、情報はある程度調べてありますが、あくまで素人考えです。
また一応具体的にあげていきますが、最終的には臨機応変が必要です。
あくまでも参考、ということを忘れずに見てください。
そして、相変わらずの長文になると思います。
すみません。
長くなるかと思いますが、最後までお付き合いよろしくお願いします。
さて、ここでは内陸(信州)で自宅にいるとき、大地震が起きたことを想定していきたいと思います。
(といっても、プレート海溝型地震でも十分応用が利く内容だと思います)
内陸部で震度6以上の地震と想定すると、M6.0以上の直下型地震という可能性が高いでしょう。
直下型地震とは、私たちが住んでいる場所の足元、すぐ真下を震源として起きる地震のことです。
直下型の場合、まず初期振動がドンッとかズンッと突き上げるような独特の衝撃があり、そのコンマ何秒か後に、強い揺れが襲ってきます。
(一度松本にて直下型地震、震度5強を経験しました。本当に突然やってきます)
緊急地震速報も、直下型地震では正直ほとんど意味がありません。
揺れている最中か、揺れが終わってから緊急地震速報が届きます。
実際、松本の地震でも揺れが収まってから、携帯が鳴りました。
そうなると、直下型地震に対してはあらかじめ事前の備えをしっかりしておくことがもっとも肝要です。
特に前の記事で述べた、危険な大きい家具の転倒防止と寝床・ベッド付近の家具・家電などの転倒防止は、必ずやっておくべき備えだといえます。
当然ですが地震は自然現象の一つですから、地震には昼も夜も関係ありません。
夜間に起きる大地震は、大多数の方々が床についているために初めの行動が一歩遅く、危険性が非常に高まります。
寝ている間の被害を減らすためには、寝室と寝床・ベッドの周りの家具・家電の転倒防止は、事前に済ませておくしかありません。
特に寝床・ベッドの周囲には危険な家具・家電を置かないこと、家具・家電を置くならば転倒防止は必ずすることが大事です。
強い揺れが来たときは、まず自分の身を守ることが第一です。
とんでもない強い揺れの時は、逃げ道の確保とか火の始末とかは、すべて後回し。
とにかく自分の身を守ることに専念しましょう。
これが基本となります。
自分の身を守るということは、地震のあとで家族や近所の人の救助や手助けをすることができる、という意味があります。
自分がケガをしないことは、地震の時に最も重要なことの一つだと言えるのです。
(すぐ近くに守るべき子供がいる場合はこの限りではありませんが、違う部屋などにいて離れているときは、まずは自分の身を守るべきです)
地震から自分の身を守るには、まずその場で身をかがめること。
そして、とにかく頭を守ることがもっとも大切です。
手で頭を抱えるようにして守りますが、ポイントはあごを引くことと、倒壊などで挟まれた時に呼吸ができるよう、顔の前に空間ができるように腕を前から頭の上に回すこと、衝撃をワンクッションおくために頭には手が直接触れないように抱えると良いそうです。
ヘルメットをかぶったりクッションなどを頭に当てても良いでしょう。
その体勢のまま移動できる余裕があれば、危険が多い台所や倒れそうな家具から離れて、机の下などへもぐること。
テレビや冷蔵庫などの倒れやすい家電や熱湯が入ったポットなども危険ですので、なるべく離れるようにします。
ただしあわてて外へ飛び出したりせず、その場か周辺で揺れをしのぐようにしましょう。
むやみに大きく移動する方が、大怪我の危険性が高くなります。
寝ているときに地震が来たときは、布団の中にもぐりこんで小さくなること。
家具の転倒が予測されるときは、倒れてこないような位置までなるべく移動をします。
そしてどんな時でも、地震の時は頭を守る姿勢は必ず取りましょう。
とにかく地震の揺れが収まるまでは、その場その付近で自分の身を守ることだけに専念します。
(これら一連の動作を「シェイクアウト」といいます)
また、日ごろから「今この場所で大きい揺れがきたらどうすればいいか、どこが安全か?」と事前にイメージして考えておくのが良いです。
リビングなら棚やテレビを避けたこのあたりか机の下とか、寝室ならタンスから離れた扉の前かベッドの下とか。
寝ている間だったらまずはとにかく布団に潜り込むとか、家具が少ない方へごろんと転がるとか。
それぞれの部屋のそれぞれの状況にあわせて、「ここが比較的安全だろう」という場所を考えて探しておきましょう。
なんとなくでもイメージしておくと、いざというときに役に立ちます。
それでも、もし万一家具に挟まれたり、家が倒壊してまったく身動きがとれなくなったときは、すぐさま抜け出そうともがいたり、助けを求めてすぐに大声を出してはいけません。
無駄に体力を失ってしまいます。
まずは一呼吸をおいて、落ち着くこと。
慌ててパニックになることが一番危険です。
落ち着いたなら、無理なく抜け出せそうか冷静に考えてみましょう。
抜け出すのが無理だと思ったら、ここは割り切って救助や誰かが来るのを待ちます。(難しい話ですけど…)
携帯が手元にあってつながるなら、家族などへ連絡をするのも良いでしょう。
また救助が始まれば、かならず声をかけてきてくれるはずです。
その時になったら、声や音を出すようにします。
何となく人の気配を感じたときも、何か音などを出してみましょう。
自分で声を上げるとかなり体力を消耗しますので、一番良いのは笛やアラームなど音を出しやすいもの、また光で知らせられるライトなどが良いです。(両方あれば一番良い)
まだ救助が始まってないと思っても、数分に1回程度で音をならしつつ、待ちます。
しかし、頭部強打していたり腹部圧迫しているなどの場合は、生命の危険性が高いと言えます。
そういう場合は臨機応変に、すぐに助けを求めるために笛やアラームを鳴らし続けることも必要かもしれません。
笛などは神戸のおばちゃんみたいに、首から下げていつでも身につけておくのがベストです。
それか、常に枕元や居間などに置いておくと良いです。
また挟まれたりして怪我をしていたら、動ける無理のない程度で、分かる範囲で自分で応急処置をしましょう。
出血の応急処置の基本は傷口にタオルや布を当て、押し付けることです。
揺れが収まってとりあえず自分の体が無事だったなら、火の元の確認と始末をします。
(決して揺れてる最中に火を消しに行ったり、様子を見に行ったりしてはいけません。)
それから地震の情報収集と家にいた家族の安否確認をし、そして避難の準備を始めます。
地震が収まったら、まずはすぐに火の元の確認と始末が基本です。
火事は地震の後において、もっとも気をつけるべき点です。
家そのものが燃えてしまったら、家具に挟まれて動けなかっただけ、脳震とうで気を失っていただけ、といった助けられた命も助けられなくなってしまう可能性があります。
火の元を始末したら、テレビやラジオをつけて地震の情報を集めます。
大地震の後だとすぐに家族の安否確認とか家の中がぐちゃぐちゃなので片付け…と思ってしまうかも知れませんが、それは少しだけ後回し。
まずは震源と地震の規模、津波の有無や原発その他の情報、すぐ逃げるべきかどうかの判断材料を得ることが大事です。
東日本大震災のときも、多くの人が家の片付けや外に出ている家族の安否確認をしていました。
そのために、津波から逃げ出す初めの一歩が遅れてしまったという事例があります。
情報収集は停電の可能性もあるので、電池式などの小型の携帯ラジオがもっとも良いです。
この電池式の携帯ラジオ、ものすごく重宝します。
我が家にも松下製のものが一つありますが、連続つけっぱなしでも半月は持ちます。(音量にもよりますが)
仕事に使っているソニー製ラジオは、何回か落として見た目ぼろぼろですが、問題なく使用できます。
手回し充電式のラジオも良いですが、しょっちゅう回さなくてはならないので、電池式のが楽で良いと思います。
単三電池2本以上で動くような、日本メーカーのものをお薦めします。
携帯ラジオは必ず一つは家に用意しておくべき、重要な物だと私は思います。(できれば予備の電池も用意しておきましょう)
強い地震の直後は、揺れで落ちたガラスや陶器の破片が床に散乱していて、足元が非常に危険なときがあります。
緊急時は避難のために素早く行動することが求められる時もあるため、足元が危険で行動が一歩も二歩も遅れることはできれば避けたいところです。
なので、地震後の室内ではスリッパや靴などを履いて行動するようにします。
そのために、スリッパ等はいつどこで地震が起きても良いように、家のあちこちに備えておくことが大事だと言えます。
特に、寝床やベッドのすぐ近くには、緊急用の靴(靴底が厚めのスニーカーが良い)を置いておくと良いです。
それと、可能ならば防災頭巾や、ヘルメット等をすぐにかぶるのも大切です。
何度も言いますが、頭を守るのが最も大事です。
地震が起きたらすぐかぶる、くらいの気持ちでも良いと思います。
余震などで、また何が降ってくるか分かりません。
最悪は帽子やタオルなどでも良いし、バイク・自転車用ヘルメットなどをかぶればさらにOKでしょう。
効果は薄くても無いよりはましですので、頭には必ず何かを身につけるようにしましょう。
携帯ラジオを持って情報収集と同時に、家にいた家族に怪我がないか声かけて安否を確認します。
家族が怪我をしていたら分かる範囲で応急処置をしましょう。
もし家族が挟まれて動けないと分かったら、呼びかけてその状況を確認をします。
まず返事・意識があるか、挟まれた場所や部位の確認、まったく動けないのか、怪我はないか、など。
声の様子や見える範囲で状況を確認し、緊急性を判断します。(かなり難しい判断になりますが)
ポイントは、意識がはっきりあるか、頭や体、首、腰を強く打っていないか、腹部を強く挟まれていないか、出血しているときはその量、などで総合的に判断しましょう。
緊急に助け出した方が良いと判断したときは、すぐ近所や周辺の人に手を借りに行きます。
ここで大事なのは、決して一人で助けだそうとしないこと。
もし余震などでさらに崩れて二次災害にあったとき、どちらも動けなくなってしまって最悪のパターンになる事もありえます。
救助は必ず二人以上で行うのが鉄則です。
無事な家族が二人以上いれば家族で、いなければ近所の人に手を借りて救出を試みます。
ただし無理の無いように、やれる範囲でやること。
途中で助けるのが無理と思ったら、救助をやめるのも大切です。
さらに近所の手の空いている方を増やして、大人数で事に当たりましょう。
基本的には、レスキュー専門の方々に救助してもらったほうが安全で確実ですが、大地震においては専門の消防士の手助けはほぼないと考えたほうが良いそうです。
阪神淡路大震災の時、倒壊した家屋での死者のほとんどが地震後約10分くらいの圧死だったそうです。
そう考えると時間的余裕はあまりなく、取り残されている人がいるならば、とにかく早く助け出すことが先決です。
レスキューや消防は、地震の混乱とともに道路の破損などで、活動範囲が著しく狭くなります。
となると初期の救出活動は、隣近所の隣組や町内会レベルでの助け合いが、最も重要です。
救出する人手がないときは、隣組や近所の人に挟まって動けない家族がいることを伝えて人手が欲しい旨も伝え、家族へたまに声をかけ励ましつつ人手が集まるのを待ちます。
周囲に伝えておけば、救助の人手が来るのが早くなる可能性が高くなります。
また、隣近所の方々の家族構成や一人暮らしのお年寄りなどの情報を、ある程度共有しておくことも必要でしょう。
地震後に近所を回って、○○さんが見えないとか出てこないとかの確認の時に役に立ちます。
(近年の町内会・地域コミュニティの低下やプライバシーの問題などで、難しい問題でもあります)
あと、そのとき電話が使えるなら、いちおう119番か消防団へ連絡しておきましょう。
また人手を待っているときは、余震で再び崩れるかもしれないので、危険そうな場所からは離れて待ちます。
とはいうものの、やはりなるべく早く助け出すことが大事だといえます。
自分や家族が怪我をしていたら、その怪我の具合によって、すぐに病院へ行くべきかの判断します。
ポイントは先程と同じで、意識がはっきりしてるか、頭や体など強く打ったり挟んだりした所はないか、出血の量などで判断しましょう。
やばいな、と思ったらすぐに救急病院、または最寄りの災害時医療救護所へ行きます。
とりあえず大丈夫そうと思ったら、あわてずに災害時の医療救護所などに行き、責任者に怪我人がいることを伝え、対応してもらいましょう。
それから、いざというときどこへ行けば良いか迷わないように、救急病院と災害時の医療救護所がどこに設置されるのか、平時に確認しておきましょう。
自治体から配られていれば、ハザードマップや災害時マニュアルで確認しておきます。
無ければ、事前に直接自治体へ問い合わせておくことも大切です。
色々準備してる間や待っている間にも、ラジオで情報収集は常に怠らないようにします。
災害時の情報はとても重要です。
さて避難の準備ですが、やっぱり非常用持出袋、避難袋は常備しておくのがベストです。
緊急時にまず持ち出す一次持ち出し品(とりあえず1日を乗り切るもの)について、避難袋に入れるべきものを下記にざっと一覧をあげます。
長くなりますが、参考までに見てください。
缶入乾パン(1人1つ。最低限の食料として)
飲料水(1人1.5L。水は1人1日3Lの備えが必要とされるが、持ち運びの点から1.5Lとした)
懐中電灯(使い慣れたシンプルなもの、電池式は予備を忘れずに。1人1つがベスト)
ロウソク(2本。長時間の使用に適する)
ライター(ロウソク、暖房などの着火に。マッチより使い勝手が良い)
携帯ラジオ(情報収集に不可欠。予備電池も備えたい)
万能複合キッチンハサミ(ナイフ、缶切り、栓抜きなどの複合ツールだと便利。それぞれを用意するのも可)
軍手、革手袋またはゴム手袋(2セット。軍手は熱に強い綿100%のもの。革手、ゴム手は片付けや救助などで役立つ)
ロープ(7m以上。救助用、非難はしごの代わりとなる。人の体重を支えられる強度のあるものを)
救急袋(以下9個を入れる)
毛抜き(とげ抜き、ピンセットとして使える)
消毒薬(1本)
脱脂綿(適当量)
滅菌ガーゼ(2枚)
ばんそうこう(10枚~)
包帯(2巻)
三角巾(1~2枚)
マスク(2枚~。防寒にも使える)
常備薬・持病薬(常備薬は風邪薬、鎮痛薬、胃腸薬など。処方箋のコピーも用意しておくと良い)
(以上9個を救急袋へ入れる)
レジャーシート(2畳分1枚。1人あたり1畳は欲しい。避難先のスペース確保に)
サバイバルブランケット(屋外用緊急簡易毛布。非常用軽量防寒具。銀紙みたいなやつなど多種ある)
簡易トイレ(2個~。非常時のトイレは重要な問題。市販されている袋型のものを)
タオル(4枚~。汚れのふき取り、怪我の手当て、下着・おむつの代用など多用途。汎用性が高いので多めに用意したい)
ポリ袋(10枚~。大小あわせて10枚くらい。物入れ、雨具・防寒具の代用、トイレの代用など汎用性も高い)
トイレットペーパー(1つ。水に溶けるので、トイレ以外でも多用途)
ウェットティッシュ(2つ。水がないときに役立つ)
10円玉(約50枚。公衆電話用に数十枚ほしい。災害時には携帯電話、自宅電話が機能しない可能性がある。テレフォンカードなどは停電時は使えない)
布ガムテープ(1つ。伝言メモを貼るなど、多用途)
油性ペン(1本。太く大きいものの方が長持ち。伝言などを書く)
筆記用具(1セット。メモ帳とペン類。避難所などで得た情報を書きとめるのに必要)
(神戸防災センターの資料より)
以上一人分で31点です。
これが基本の品で、防災袋へ入れるとおよそ7kgとなります。
他に一次持ち出し品として、備えを検討すべきものは下記のとおり。
貴重品類など
現金、予備眼鏡、携帯電話・スマートフォン、携帯・スマホの充電器、携帯・スマホの予備バッテリ
通帳、免許証、保険証、パスポート・外国人登録証(以上4点はコピーや番号を控えておくのも良い、身分証明となる)、
印鑑、証書類、住民票、
ハザードマップ(緊急時の避難場所や医療救護所の確認のため。必要な部分のコピーでも良い)
女性用品
生理用品(長期の避難だと重要品といえる。傷の手当てなどガーゼの代用としても重宝する)、
笛付きライト(防犯・護身用)、
鏡、ブラシ、化粧品、
おりものシート(下着の代用にもなる)
高齢者用品
高齢者手帳、おむつ、着替え、
持病薬(処方箋のコピーも)、
予備眼鏡、老眼鏡、介護用品
赤ちゃん用品
粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、スプーン、
洗浄綿、バスタオル、ガーゼ、紙おむつ、
母子手帳、おもちゃ、着替え、
ベビーカー(荷物運搬にも役立つ、非常持ち出し袋には入らない)
以上、個々で必要に応じて準備しておきましょう。
特に、女性用品、高齢者用品、赤ちゃん用品は、避難所での物資配布では食料や水等に比べてどうしても二の次になってしまうものなので、災害初期ではなかなか手に入らない可能性が高いです。
最低限のもの(生理用品、介護用品、おむつ、粉ミルク、離乳食等)は事前にやや多めに用意・備蓄しておくことが大切です。
それから、携帯電話・スマートフォンは今や生活に欠かせない重要な複合ツールです。
特にスマホはもともと電池消耗が激しい物なので、停電で充電ができないとすぐ電池切れになって役に立たなくなってしまいます。
スマホの予備バッテリは防災グッズとして必要な物、と言えるかもしれません。
できれば2、3回充電できる容量の大きい物、または乾電池を使って充電するタイプの物が良いかと思います。(乾電池は比較的手に入れやすいので)
避難用品で足りないもの・気付いたものがあれば、なるべく急いで荷物の準備します。
大怪我などで緊急性を要するときは、とにかく避難袋を持ったらすぐに出発しましょう。
災害時の移動の基本は、「徒歩」とされます。
災害時においては、最終的に徒歩での移動が最も早いそうです。
怪我人が自分で動けるなら、徒歩が良いでしょう。
ただし、怪我がひどくて怪我人を担がなくてはならない場合などは、自動車という手もあります。
車が使えれば良いのですが、地震によっては道が陥没したり塀などが崩れたりして道路が使えなかったり、信号機の停電などによりひどく渋滞していたりします。
徒歩にしろ車にしろ、かなり時間がかかることは覚悟したほうが良いです。
またとりあえず119番へ電話することも試しておきましょう。
病院や救護所も、施設の被害状況によっては、違うところへ行ったほうが良いときもあります。
連絡がつくのなら、先に消防署や町内の消防団などにどこへ行けば良いのか、情報を求めたほうが良いです。
地震後の道路は、渋滞や道路の陥没、停電などで信号が消えていたりして、徒歩でも車でも危険が多いと思われます。
移動の際は、細心の注意をはらって移動してください。
車での移動は無理、と判断したら即座に徒歩に切り替えましょう。
車を途中で置いて移動するときは、車のキーを挿したまま路肩へ停め、ドアロックもかけずに置いていきましょう。
盗難等の危険もありますが、置いていった車が他の人や緊急車両の邪魔にならないように、いつでも動かせるようにしておく必要があります。
怪我人を担いで動かせない、というときは救急隊などに連絡を取り、待たなくてはならないかもしれません。
だいぶ長くなりました。
続きはまた次回に。m(_ _)m




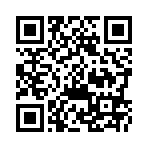


この記事へのコメント
平成28年4月14日から続く、熊本を中心とした九州の群発地震の被害に遭われている方々へ、心からお見舞い申し上げます。なにとぞご自愛くださいますよう願います。
そして、今回の地震で今までの直下型地震とは少し違う感じを覚えます。なにより、震度6を超える強烈な揺れがこう何度も襲うというのは、私は初めて見たようなきがします。この地震を受けて地震の記事を修正する必要があると考え、加筆修正していきます。自分自身少し気が抜けていたことへの自戒を込めて、今後少しずつですが修正していきます。よろしくお願いします。
Posted by 松宮 湊人 at 2016年04月16日 18:00
at 2016年04月16日 18:00
平成30年9月6日未明に起きた、北海道道南で起きた大地震に遭った方々へ、心からお見舞い申し上げます。なにとぞご自愛くださいますようお願い申し上げます。
今回の地震では直下地震で最大震度7の強い揺れが起き、前日までの雨と重なった土砂災害の被害がとてつもなかったことが、ニュース等から見て取れます。山が近くにあれば土砂災害はいつでも起こる可能性があるということを強く感じます。この地震を受けて再び自分の記事を修正したいと思いました。地震はやはり甘くないと自戒を込め、今後また修正していきます。m(_ _)m
Posted by 松宮 湊人 at 2018年09月09日 23:40
at 2018年09月09日 23:40