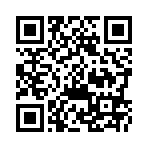2019/03/03
どうも、お久しぶりです。
最近、色々と周りが忙しくてなかなかブログがアップできない日々が続いております。(;^ ^)A 書いてみたいと思う記事内容もいくつか候補があるんですが、「もう少し時間が出来たら…」と思っているうちに2018年は終わり、今年も2月が終わりました。申し訳ないと思うばかりです。
と思っていたら、Yahoo!よりメールが届きまして、Y!ブログの閉鎖が伝えられました。どっちかというと近年はほったらかし感のあった私のY!ブログですが、いざ改めて見てみると車の話題を中心に41件の記事がアップされておりました。一部は消してもいいかなと思った記事もありましたが、大部分はただ消すのはもったいないと(個人的に)思う記事ばかりでした。なので、こちらのナガブロにY!ブログの記事を一部引っ越すことにしました。
10年くらい前の記事などを見ると、結構自身の若さも見られて恥ずかしい次第ですが、それも良いかなと思いなるべくそのままアップします。一部に間違いや失礼なところもあるかと思いますが、大目に見てやってください。また、新規の記事という訳でもないので数年前の記事という形にして、時間がある時に少しずつアップしていこうかと考えてます。
さて、これからも自分自身の修行?も兼ねてブログを続けていきたいと考えております。例によって筆は遅く、また雑文と眉唾もの?ばかりで申し訳ないと思いますが、長い目で見守っていただけたらありがたく存じます。
今後ともよろしくお願いいたします。m(_ _)m
松宮 湊人
最近、色々と周りが忙しくてなかなかブログがアップできない日々が続いております。(;^ ^)A 書いてみたいと思う記事内容もいくつか候補があるんですが、「もう少し時間が出来たら…」と思っているうちに2018年は終わり、今年も2月が終わりました。申し訳ないと思うばかりです。
と思っていたら、Yahoo!よりメールが届きまして、Y!ブログの閉鎖が伝えられました。どっちかというと近年はほったらかし感のあった私のY!ブログですが、いざ改めて見てみると車の話題を中心に41件の記事がアップされておりました。一部は消してもいいかなと思った記事もありましたが、大部分はただ消すのはもったいないと(個人的に)思う記事ばかりでした。なので、こちらのナガブロにY!ブログの記事を一部引っ越すことにしました。
10年くらい前の記事などを見ると、結構自身の若さも見られて恥ずかしい次第ですが、それも良いかなと思いなるべくそのままアップします。一部に間違いや失礼なところもあるかと思いますが、大目に見てやってください。また、新規の記事という訳でもないので数年前の記事という形にして、時間がある時に少しずつアップしていこうかと考えてます。
さて、これからも自分自身の修行?も兼ねてブログを続けていきたいと考えております。例によって筆は遅く、また雑文と眉唾もの?ばかりで申し訳ないと思いますが、長い目で見守っていただけたらありがたく存じます。
今後ともよろしくお願いいたします。m(_ _)m
松宮 湊人
2017/02/10
(この記事は私が過去 2015.3.2. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
続けて交通マナーについて、もう一つあげておきます。
近ごろ松本の街を車で走っていて気になっていたことに、信号無視をする車が多くなってきた、と感じています。
信号の変わり際で黄色、赤になるにも関わらず、無理矢理2、3台渡っていく車のことです。
1台目の微妙なタイミングの車は、百歩譲ってまあ許すとしましょう(法律上は違反ですが)。しかし次やその次の車は停止できないわけではないので、確実な信号無視、と言えます。その2台目3台目のような信号無視をする車が、ここ2、3年で急に増えたんじゃないかと思うのです。
年末から今年に入ってさらに信号無視の車が増えて、危険な交通環境になってきています。
私の勝手な考察ですが、たぶん松本曲がり?を減らすために、市や県警が積極的に右折用矢印信号を増やしている影響なんじゃないか、と考えています。
つまり、いままで矢印信号が無かった間に渡れていた直進と左折の車が、右折用矢印信号が優先されることによって渡れる時間・台数が減ったと感じている。または、時差式信号の時は渡れていた直進や左折の車が、右折用矢印信号への切り替えにより渡れなくなった。そういったところで交差点が渡れなくなった、矢印信号で「損」をしている、と感じている人が多いのではないか?、と推測しています。
だから信号の変わり際に無理にでも渡ってしまいたい、と思って無謀な信号無視が多くなってきたのではないか、、、と思うのです。
またもっと単純に、モラル・マナーの低下の現れなのかも知れません。
大震災後に省エネ運転が励行され、それとともに安全運転、交通マナーの向上が見られました。
しかし震災から四年近くが経ち、省エネ意識の低下が見受けられ、同時に交通マナーも悪化していると感じています。
松本は大阪などと違って、信号全方向が赤の時間が長いわけではありません。
(大阪は住民の性格のせいか、信号の変わり際の黄色・赤で無理に渡っていく車が多いため、全方向が赤の時間を意図的に長めに設定されています)
同時に、名古屋などのように信号が青になるのを見越して赤のうちから動きだす見切り発車も、松本では多く見られます。
この大阪と名古屋の交通環境が混在するような今の松本の状況で、信号無視が増えてきたことは非常に危険な状態といえます。
赤信号で無理に右折してきた車と見切り発車で青になる前に動きだした車が、事故になりそうになったシーンを、実際に何度も見かけています。今後こういった事故がさらに増えていきそうで、危惧を覚えています。
信号の遵守は、公共道路を交通する上で基本中の基本です。
道路交通法上では、信号の黄色も赤色も同じ「停止」という意味です。
ただ黄色については、信号が黄色になった時に交差点内に進入してしまっている時、または停止するのが困難なときは信号を通過しても良い、とされています。それ以外は原則として、信号無視として違反になります。
交差点に進入してしまっているかどうかの判断は、停止線で判断します。警察は基本的に、黄色になった時点で停止線を越えていた車がそのまま信号を通過しても取り締まらず、黄色時に停止線を越えていなかった車が信号を通過した時に違反として取り締まります。(その時々によって取り締まり方は違いますが、、、汗)
つまり、信号が黄色になった時に停止線より手前にいた車は、基本的には止まらなくてはならないのです。
(ちなみに信号で停止線を越えて停車するのも道交法上は「信号無視」になります。警察も現実的にそこまで取り締まることはほぼ無理だそうですが、停止線で確実に止まれる速度・状況なのにわざわざオーバーラインして止まるような車は取り締まったりすることもあるそうです。最近普通に停止線を越えて停車してる車を多く見かけますが、それは正確に言うと信号無視になり、道交法違反です。そもそも教習所では運転席からボンネット越しに停止線が見えるように停止するように習っているはずです。安全面でも停止線は越えないように停車しましょう)
それから、右折用矢印信号が無いような交差点で、対向車に右折車がいるときに信号が変わり始めたら、絶対に無理な信号無視はせず黄色になった時点で極力止まるようにしましょう。
交通量の多い時差や矢印信号が無い交差点では、右折車は青のうちにはなかなか曲がれないので、タイミングによっては信号の変わり際の赤になる時に曲がるしかありません。その時に、対向する直進車が何台も無理に突っ込んで来られると右折のタイミングを逃してしまうのです。そういう信号無視した対向直進車のせいで右折のタイミングを逃してしまい曲がれなかった右折車が、中途半端に交差点内で立ち往生して渋滞のもとになってしまうケースをよく見かけます。
自己中心的に「自分さえ渡れれば良し」と考えるのではではなく、交通全体がスムーズにうまく流れるように努めなければなりません。そこまで配慮するのが、格好の良い大人のドライバーだと私は考えます。
「黄色は止まれ」です。
ここを再認識するとともに、もっと気を引き締めなくてはならないと思います。ケースバイケースではありますが、無理無謀な信号無視をやめ、信号をきちんと守ること。
停止線手前で信号が黄色に変わったときは、なるたけ止まるようにしましょう。そうすることで交通環境を良くし、安全への意識向上にもつながります。
それから、公道は国民全体の共有の物です。
自動車を運転することは車内の閉鎖的環境もあって自分中心的になりがちですが、本来は公道を使う人みんなでお互いがお互いを気遣いながら有効的に使うべきものです。信号を守ること一つとっても、それをきちんと皆で守ることが交通環境全体の安全でスムーズな環境を作っていくことにつながっていきます。
ハンドルを握るドライバー全体で気持ちの良い交通環境を作っていけるよう、ぜひ皆さんも協力していってください。
m(_ _)m
続けて交通マナーについて、もう一つあげておきます。
近ごろ松本の街を車で走っていて気になっていたことに、信号無視をする車が多くなってきた、と感じています。
信号の変わり際で黄色、赤になるにも関わらず、無理矢理2、3台渡っていく車のことです。
1台目の微妙なタイミングの車は、百歩譲ってまあ許すとしましょう(法律上は違反ですが)。しかし次やその次の車は停止できないわけではないので、確実な信号無視、と言えます。その2台目3台目のような信号無視をする車が、ここ2、3年で急に増えたんじゃないかと思うのです。
年末から今年に入ってさらに信号無視の車が増えて、危険な交通環境になってきています。
私の勝手な考察ですが、たぶん松本曲がり?を減らすために、市や県警が積極的に右折用矢印信号を増やしている影響なんじゃないか、と考えています。
つまり、いままで矢印信号が無かった間に渡れていた直進と左折の車が、右折用矢印信号が優先されることによって渡れる時間・台数が減ったと感じている。または、時差式信号の時は渡れていた直進や左折の車が、右折用矢印信号への切り替えにより渡れなくなった。そういったところで交差点が渡れなくなった、矢印信号で「損」をしている、と感じている人が多いのではないか?、と推測しています。
だから信号の変わり際に無理にでも渡ってしまいたい、と思って無謀な信号無視が多くなってきたのではないか、、、と思うのです。
またもっと単純に、モラル・マナーの低下の現れなのかも知れません。
大震災後に省エネ運転が励行され、それとともに安全運転、交通マナーの向上が見られました。
しかし震災から四年近くが経ち、省エネ意識の低下が見受けられ、同時に交通マナーも悪化していると感じています。
松本は大阪などと違って、信号全方向が赤の時間が長いわけではありません。
(大阪は住民の性格のせいか、信号の変わり際の黄色・赤で無理に渡っていく車が多いため、全方向が赤の時間を意図的に長めに設定されています)
同時に、名古屋などのように信号が青になるのを見越して赤のうちから動きだす見切り発車も、松本では多く見られます。
この大阪と名古屋の交通環境が混在するような今の松本の状況で、信号無視が増えてきたことは非常に危険な状態といえます。
赤信号で無理に右折してきた車と見切り発車で青になる前に動きだした車が、事故になりそうになったシーンを、実際に何度も見かけています。今後こういった事故がさらに増えていきそうで、危惧を覚えています。
信号の遵守は、公共道路を交通する上で基本中の基本です。
道路交通法上では、信号の黄色も赤色も同じ「停止」という意味です。
ただ黄色については、信号が黄色になった時に交差点内に進入してしまっている時、または停止するのが困難なときは信号を通過しても良い、とされています。それ以外は原則として、信号無視として違反になります。
交差点に進入してしまっているかどうかの判断は、停止線で判断します。警察は基本的に、黄色になった時点で停止線を越えていた車がそのまま信号を通過しても取り締まらず、黄色時に停止線を越えていなかった車が信号を通過した時に違反として取り締まります。(その時々によって取り締まり方は違いますが、、、汗)
つまり、信号が黄色になった時に停止線より手前にいた車は、基本的には止まらなくてはならないのです。
(ちなみに信号で停止線を越えて停車するのも道交法上は「信号無視」になります。警察も現実的にそこまで取り締まることはほぼ無理だそうですが、停止線で確実に止まれる速度・状況なのにわざわざオーバーラインして止まるような車は取り締まったりすることもあるそうです。最近普通に停止線を越えて停車してる車を多く見かけますが、それは正確に言うと信号無視になり、道交法違反です。そもそも教習所では運転席からボンネット越しに停止線が見えるように停止するように習っているはずです。安全面でも停止線は越えないように停車しましょう)
それから、右折用矢印信号が無いような交差点で、対向車に右折車がいるときに信号が変わり始めたら、絶対に無理な信号無視はせず黄色になった時点で極力止まるようにしましょう。
交通量の多い時差や矢印信号が無い交差点では、右折車は青のうちにはなかなか曲がれないので、タイミングによっては信号の変わり際の赤になる時に曲がるしかありません。その時に、対向する直進車が何台も無理に突っ込んで来られると右折のタイミングを逃してしまうのです。そういう信号無視した対向直進車のせいで右折のタイミングを逃してしまい曲がれなかった右折車が、中途半端に交差点内で立ち往生して渋滞のもとになってしまうケースをよく見かけます。
自己中心的に「自分さえ渡れれば良し」と考えるのではではなく、交通全体がスムーズにうまく流れるように努めなければなりません。そこまで配慮するのが、格好の良い大人のドライバーだと私は考えます。
「黄色は止まれ」です。
ここを再認識するとともに、もっと気を引き締めなくてはならないと思います。ケースバイケースではありますが、無理無謀な信号無視をやめ、信号をきちんと守ること。
停止線手前で信号が黄色に変わったときは、なるたけ止まるようにしましょう。そうすることで交通環境を良くし、安全への意識向上にもつながります。
それから、公道は国民全体の共有の物です。
自動車を運転することは車内の閉鎖的環境もあって自分中心的になりがちですが、本来は公道を使う人みんなでお互いがお互いを気遣いながら有効的に使うべきものです。信号を守ること一つとっても、それをきちんと皆で守ることが交通環境全体の安全でスムーズな環境を作っていくことにつながっていきます。
ハンドルを握るドライバー全体で気持ちの良い交通環境を作っていけるよう、ぜひ皆さんも協力していってください。
m(_ _)m
2017/02/10
(この記事は私が過去 2014.8.26. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
久しぶりに交通マナーの話、いってみます…。
近ごろ松本の街を車で走っていて感じることは、必要のない場面で安易にオーバーラインをしている車が多いことです。
例えば、、。
道幅が広い交差点で左折をするとき、大きく右へ振ってから左折していく車。
あまりに右に寄りすぎて車線をはみ出してしまい、右レーンを走る車や右折車、対向車に無駄な減速、ブレーキをさせています。
実際、その行為が原因で右車線の車との接触、事故になっているケースも、多々あります。
大型トラックなど大回りをしなければ曲がれない大きい車ならまだわかりますが、普通車からコンパクト、軽といった小さな車まで、大回りをする必要のないサイズの車が、当たり前のように右へ大きく振ってから左折していくのを、よく見かけるのです。
日本車は世界的にも小回りが効く、とり回しの良い車がほとんどなのにも関わらず、大回りする車が多すぎです。
他に、先の見にくいカーブのある道で、先が十分見えない状況にも関わらず普通にセンターラインを越えて対向車線へ出て、ショートカットしていく車。
別にスピードを出してる訳でもなく、普通のスピードで当たり前のようにオーバーラインをしていく。
先がよく見えていて確実に安全が確保されていてやるのはまだ良いかと思いますが、カーブで先がほぼ見えない状況、不意に対向車が来るかもしれない危険な状況で、不用意にそして安易にオーバーラインをする車が結構多いと思います。
特に対向車線にはみ出すのは、その危険性から絶対にやってはならない行為です。
そして、同じように路肩の線(歩行者のための左側の線)を躊躇なく当たり前のように普通にオーバーラインしていく車が多いのも、危険であり問題な行為です。
キープレフト、そして車道のラインをはみ出さないように守って走ることは、日本の公道を走るうえで基本中の基本であり、基本を守れない危ないオーバーラインが横行しすぎています。
(もう一つ、信号等の停止線を普通にオーバー、越えて停車する車がいます。状況にもよるんですが、大体の車はちゃんと停止線手前で止まれるはずなのにわざわざ線をオーバーするように停車しているようです。こういった車が最近非常に多くみかけると感じています。特に狭い交差点などでこの停止線オーバーをやられてしまうと、大型トラックやけん引トラックが交差点を左折で曲がる時などで非常に邪魔になり、多いに危険であるとともに渋滞の元にもなります。教習所では停止線を越えて停まってはいけないと習っているはずですし、厳密にいうと停止線オーバーは道交法違反となります。そもそも交差点の停止線は大きな車でも曲がるのに支障が無いように計算されて停止線が引かれています。それを無視してオーバーするのは「ぶつかってください」と言わんばかりの行為であり、非常に危険です。(私なんかは逆に一切ぶつかられたくないので教習所時代並みに大分余裕をもって間を空けて停車してます) 停止線オーバーは危ないので絶対にやめてください)
どちらの例も、基本的には道路交通法違反となります。
前者の曲がるときに大回りしてしまうのは、教習所で習った左折のやり方と違います。
左折の正しいやり方は、車線の右に寄るのではなく左に寄らなくてはいけません。(右折の時は右に寄る)
そして徐行をしながら安全確認をしっかりして、ゆっくり曲がっていく…。
これが正しい曲がり方です。
しかし、多くの人は左側(内側、イン側)に寄りすぎると何となくぶつかりそうで、あまり寄りたくない、と思っていると推測します。
そういう人は、たぶん以前に左側に切り込みすぎて(イン側に寄りすぎて)縁石に乗り上げたり、車の横腹をこすったりした経験がある人なんだろうと、思います。
その経験から、できれば左側・内側に寄りたくない、との思いが無意識に出て、いつの間にか大回りが当たり前になってしまったのでしょう。
あと左折するときに歩行者や自転車などを確認しようと懸命にきょろきょろと目視をしているうちに、無意識に右へ寄っていってしまう、という車も見られます。
運転者はハンドルを動かしている意識がない場合もあるので、交差点進入前にはハンドルをセンターに維持し動かさないように、細心の注意を払いましょう。
それから、曲がる直前に交差点内の安全確認をするのではなく、交差点に入るだいぶ手前から安全確認をして、早め早めの段階で危険予測をしながら交差点に進入していくようにします。
(例えば歩行者や自転車などは、交差点のだいぶ手前からでも渡ろうとしている歩行者と自転車がいるかどうかくらいは確認できます。自分が曲がるタイミングで進路が交錯する(かち合う)歩行者などはいないか見える範囲で確認して予測し、いそうなら早めに減速して進路を譲るのか判断し、いないようなら交差点に侵入してから確認できる先(曲がった先など)の歩行者や自転車をメインに注意を払うようにします)
また車両感覚が分かりづらい、というのもあるかと思います。
慣れや習熟度によるかもしれませんが、最近の車が車両感覚をつかみにくくなっているという事実もあるかと思います。
最近の自動車は外見の格好良さ重視だったり、室内空間をとにかく広く見せようとウインドウを遠くへ押し出したり、必要以上に四角に張り出したデザインだったりして、車の大きさがつかみにくい車が多い気がします。(特に軽自動車)
不自然な形状がドライバーの錯覚と死角を生み、車が必要以上に大きく感じるのです。
結果、何でもなく普通に曲がれる広い交差点でも、左側(イン側)が当たるんじゃないかと気になってつい大回りをしてしまう、のでしょう。
車両感覚をつかむには、まずタイヤの位置を知るのが一番良いと私は思います。
誰かに協力してもらって、運転席に乗った状態でそれぞれの四つのタイヤの脇へ立ってもらい、タイヤの位置をまず知る。
特に後輪の位置を把握することは、右左折時の内輪差を知る上で重要といえます。
それからできれば空いている駐車場などで練習し、実際曲がるときのタイヤの位置を確認します。
パイロン、または目立つ色の1.5Lペットボトルを用意して地面に立てて置き、左右のサイドミラーをやや下向きにしておいて、そのパイロンやペットボトルになるべく寄るつもりで左へ曲がってみる。
サイドミラーでペットボトルを見ながらゆっくり曲がる練習を何回かしていくと、左後輪の位置がつかめてきます。
同じように右折でも練習すると良いでしょう。
(練習は必ず復数人で行い、オーディオを消し全窓全開にして外の人と意志疎通を確保してからやりましょう。安全には十分配慮してください)
それから、曲がる際にハンドルを早く切り過ぎている可能性もあります。
どうも最近、ハンドルを早く切る人が多い気がします。
早く曲がりたい、減速しないでさっさと曲がりたい、などと考えているのかも知れません。
交差点にあわせるようにスピード調整とハンドル操作をしないで、早く曲がりたいと十分な減速をしないで早くハンドルを切ってしまえば当然内側へ寄りすぎてしまい、こすったり乗り上げの原因となります。
ハンドルを手前から切らずに、交差点にまっすぐ入ってから素早くハンドルを切れば、左折時に右に振らなくても大回りぎみ(直角ぎみ)に曲がることは可能です。
文で説明するのは難しいのですが、左折時にはまずしっかり減速をすること。
まずは徐行くらいまでしっかり速度を下げることが大事です。
それから、曲がるのを待つ、遅らせるイメージで、すぐハンドルを切りはじめないこと。
交差点の縁石に左後ろのタイヤをあわせるように交差点内にある程度直進のまま侵入してから、素早く左へハンドルを切っていきます。(ハンドルを切り始めるのは車によって違いますが、普通車だとだいたい交差点の角がAピラー(フロント窓とサイド窓の間の柱部)か前席の横まで来たときくらいです)
そして内側(イン)につきすぎないように直角のように曲がり、左折した先の道路の右寄り(センターライン寄り)に寄せる感じで曲がっていきます。(余裕があれば、左サイドミラーで左後ろのタイヤが縁石に当たらないか見るのも良いです。ですが周囲の安全のが大切ですので、あまり注視しすぎないように)
ちょっと難しいかも知れませんが車を真上から見たとすると、早くハンドルを切って直線的にインをつくのではなくに、切りはじめを待ってから一気にハンドルを切って直角にくいっと曲がるイメージです。
さらに他の言い方でいうと、曲がった先のアウト側へつけるように曲がります。
何を言ってるか分からない…という方は、私の説明が悪いだけですのでこの件は忘れてください。汗
ごめんなさい。m(_ _)m
もし試しにやってみたいという方は、できれば広い交差点で他車や歩行者などがいない安全が確保されてるとき(深夜とかに照明で明るい交差点で)に、サイドミラーをやや下へ向けて後ろのタイヤが分かるようにして、練習してみてください。
二例目のカーブでのセンターラインオーバーは、基本的に絶対やってはいけない行為です。
センターラインオーバーは追越しや危険を避けるときだけ、しかもきちんと安全に安全を重ねて行うべきで、オーバーラインする必要がない場面では絶対にやってはいけない行為です。
道なりにカーブを走るときは、カーブを見てすんなりスマートに曲がるにはどのくらいの減速が必要か、カーブのきつさを瞬時に判断してどのくらいのスピードなら同乗者に不快感を与えずにきれいにはみ出さずに曲がれるか、というドライバーの腕の見せ所です。
逆にいうと、それをスマートにできるかどうかは、ドライバーの経験にもよります。
ドライバーがただ自分の思い通りに飛ばして走るのは、私的にはダメなドライブといえます。
同乗者が不快に思わない速度と曲がり方(ロール、横Gのかけ方)をしながらも、もしカーブ中に歩行者や自転車がいたとか事故車が停車していたり対向車がこちらの車線にはみ出したりしたとしても、何とか対処できるスピードとその予測を常にしながら、自分の走行車線からはみ出すことなく狙った走行ラインでスマートにカーブを曲がる走りができたら、私の中では合格といえます。
これが、スマートで格好の良いワインディングドライブだと、私は勝手に考えています。
三例目の路肩の線をオーバーしない、というのは道交法上の基本でもあります。
そもそも、道路を普通にまっすぐ走るだけならば、通常はセンターラインと路肩線のどちらにも寄らない、中央(真ん中)を走るのが安全な走行です。
街を走る車を見ると、障害物や危険がない状況でも、常に左の路肩線をオーバーして走っている車や、逆に常に右寄りでセンターラインを時々オーバーしながら走っている車も見かけることもあります。
もしかして右ハンドルから左ハンドルの車に乗り換えたのかな?(又はその逆?)、とか思うこともありますが、見ていてとても危なく感じます。
路肩線は本来、歩行者用の歩道の代わりの線です。
つまり、車道と歩行者用通路を分け隔てる線であり、線より外・左側は歩行者のためのゾーンになります。
車両である自動車は、基本的に路肩線を越えて走ってはいけないのです。
(同じように自転車は本来「軽車両」ですから車道を走らねばならず、本当は路肩線より左へ出て走ってはいけません。ですが、安全上そこまでは警察も取り締まりはせず、自転車は歩行者がいなければ路肩線の外側を走ることを黙認されています。(歩行者と事故となったときは違反を指摘される可能性はあります)
センターラインは言わずもがな、不用意にオーバーラインすることは非常に危ないのでしてはいけません。
ちなみに、路肩線とセンターラインの中央を走っているか確認するためには、サイドミラーで確認するのが良いでしょう。
停車時など安全なときに、左右両側のサイドミラーを見比べて、ミラーに移る路肩線とセンターラインとの間が、ほぼ同じくらいであれば車線の中央を走れていることになります。
どちらかに寄っている…と感じたら、若干修正をしてみてください。
あまり急に変えたりすると危ないこともあるので、気を付けながら少しづつ直していくと良いと思います。
あと、なんとなく前の車につられて左右どちらかに寄って走ってしまう、ということもあると思います。
これは人間が元から持っている癖になるんでしょうか、前に倣えと前走車に合わせて走ってしまうことがあります。
前の車とは関係なしに「自分は自分で安全走行をするんだ」と思って、周りの車にあまりつられないように?走行することも必要でしょう。
(ただし、逆に自分よがりになりすぎるのもよろしくありません。前の車が急に路肩線を超えるくらい左へ寄りだした?でも自分は真ん中を走る続けるぞ…、とそのまま走ってたら後ろから救急車がやってきた…汗。なんてこともあるかもしれません。安全運転を基軸にしながらも、すべてにおいては臨機応変が大事、です)
この記事を読んだ方は、日ごろ不用意にオーバーラインした走りをしてないか、改めて自分の運転を確認していただき、より良い運転ができるように見なおしてみてください。
「自分の運転が誰に見せても胸を張れる、良い運転ができているか?」
そんなことをいつも自己採点しながら、私は日々運転をしています。
いまだ満点を採るような納得のいく運転はできていませんが、その日々の努力に意味があると考えてます。
皆さんも、スマートで周りに優しい安全な運転を目指していって欲しいと思っています。
久しぶりに交通マナーの話、いってみます…。
近ごろ松本の街を車で走っていて感じることは、必要のない場面で安易にオーバーラインをしている車が多いことです。
例えば、、。
道幅が広い交差点で左折をするとき、大きく右へ振ってから左折していく車。
あまりに右に寄りすぎて車線をはみ出してしまい、右レーンを走る車や右折車、対向車に無駄な減速、ブレーキをさせています。
実際、その行為が原因で右車線の車との接触、事故になっているケースも、多々あります。
大型トラックなど大回りをしなければ曲がれない大きい車ならまだわかりますが、普通車からコンパクト、軽といった小さな車まで、大回りをする必要のないサイズの車が、当たり前のように右へ大きく振ってから左折していくのを、よく見かけるのです。
日本車は世界的にも小回りが効く、とり回しの良い車がほとんどなのにも関わらず、大回りする車が多すぎです。
他に、先の見にくいカーブのある道で、先が十分見えない状況にも関わらず普通にセンターラインを越えて対向車線へ出て、ショートカットしていく車。
別にスピードを出してる訳でもなく、普通のスピードで当たり前のようにオーバーラインをしていく。
先がよく見えていて確実に安全が確保されていてやるのはまだ良いかと思いますが、カーブで先がほぼ見えない状況、不意に対向車が来るかもしれない危険な状況で、不用意にそして安易にオーバーラインをする車が結構多いと思います。
特に対向車線にはみ出すのは、その危険性から絶対にやってはならない行為です。
そして、同じように路肩の線(歩行者のための左側の線)を躊躇なく当たり前のように普通にオーバーラインしていく車が多いのも、危険であり問題な行為です。
キープレフト、そして車道のラインをはみ出さないように守って走ることは、日本の公道を走るうえで基本中の基本であり、基本を守れない危ないオーバーラインが横行しすぎています。
(もう一つ、信号等の停止線を普通にオーバー、越えて停車する車がいます。状況にもよるんですが、大体の車はちゃんと停止線手前で止まれるはずなのにわざわざ線をオーバーするように停車しているようです。こういった車が最近非常に多くみかけると感じています。特に狭い交差点などでこの停止線オーバーをやられてしまうと、大型トラックやけん引トラックが交差点を左折で曲がる時などで非常に邪魔になり、多いに危険であるとともに渋滞の元にもなります。教習所では停止線を越えて停まってはいけないと習っているはずですし、厳密にいうと停止線オーバーは道交法違反となります。そもそも交差点の停止線は大きな車でも曲がるのに支障が無いように計算されて停止線が引かれています。それを無視してオーバーするのは「ぶつかってください」と言わんばかりの行為であり、非常に危険です。(私なんかは逆に一切ぶつかられたくないので教習所時代並みに大分余裕をもって間を空けて停車してます) 停止線オーバーは危ないので絶対にやめてください)
どちらの例も、基本的には道路交通法違反となります。
前者の曲がるときに大回りしてしまうのは、教習所で習った左折のやり方と違います。
左折の正しいやり方は、車線の右に寄るのではなく左に寄らなくてはいけません。(右折の時は右に寄る)
そして徐行をしながら安全確認をしっかりして、ゆっくり曲がっていく…。
これが正しい曲がり方です。
しかし、多くの人は左側(内側、イン側)に寄りすぎると何となくぶつかりそうで、あまり寄りたくない、と思っていると推測します。
そういう人は、たぶん以前に左側に切り込みすぎて(イン側に寄りすぎて)縁石に乗り上げたり、車の横腹をこすったりした経験がある人なんだろうと、思います。
その経験から、できれば左側・内側に寄りたくない、との思いが無意識に出て、いつの間にか大回りが当たり前になってしまったのでしょう。
あと左折するときに歩行者や自転車などを確認しようと懸命にきょろきょろと目視をしているうちに、無意識に右へ寄っていってしまう、という車も見られます。
運転者はハンドルを動かしている意識がない場合もあるので、交差点進入前にはハンドルをセンターに維持し動かさないように、細心の注意を払いましょう。
それから、曲がる直前に交差点内の安全確認をするのではなく、交差点に入るだいぶ手前から安全確認をして、早め早めの段階で危険予測をしながら交差点に進入していくようにします。
(例えば歩行者や自転車などは、交差点のだいぶ手前からでも渡ろうとしている歩行者と自転車がいるかどうかくらいは確認できます。自分が曲がるタイミングで進路が交錯する(かち合う)歩行者などはいないか見える範囲で確認して予測し、いそうなら早めに減速して進路を譲るのか判断し、いないようなら交差点に侵入してから確認できる先(曲がった先など)の歩行者や自転車をメインに注意を払うようにします)
また車両感覚が分かりづらい、というのもあるかと思います。
慣れや習熟度によるかもしれませんが、最近の車が車両感覚をつかみにくくなっているという事実もあるかと思います。
最近の自動車は外見の格好良さ重視だったり、室内空間をとにかく広く見せようとウインドウを遠くへ押し出したり、必要以上に四角に張り出したデザインだったりして、車の大きさがつかみにくい車が多い気がします。(特に軽自動車)
不自然な形状がドライバーの錯覚と死角を生み、車が必要以上に大きく感じるのです。
結果、何でもなく普通に曲がれる広い交差点でも、左側(イン側)が当たるんじゃないかと気になってつい大回りをしてしまう、のでしょう。
車両感覚をつかむには、まずタイヤの位置を知るのが一番良いと私は思います。
誰かに協力してもらって、運転席に乗った状態でそれぞれの四つのタイヤの脇へ立ってもらい、タイヤの位置をまず知る。
特に後輪の位置を把握することは、右左折時の内輪差を知る上で重要といえます。
それからできれば空いている駐車場などで練習し、実際曲がるときのタイヤの位置を確認します。
パイロン、または目立つ色の1.5Lペットボトルを用意して地面に立てて置き、左右のサイドミラーをやや下向きにしておいて、そのパイロンやペットボトルになるべく寄るつもりで左へ曲がってみる。
サイドミラーでペットボトルを見ながらゆっくり曲がる練習を何回かしていくと、左後輪の位置がつかめてきます。
同じように右折でも練習すると良いでしょう。
(練習は必ず復数人で行い、オーディオを消し全窓全開にして外の人と意志疎通を確保してからやりましょう。安全には十分配慮してください)
それから、曲がる際にハンドルを早く切り過ぎている可能性もあります。
どうも最近、ハンドルを早く切る人が多い気がします。
早く曲がりたい、減速しないでさっさと曲がりたい、などと考えているのかも知れません。
交差点にあわせるようにスピード調整とハンドル操作をしないで、早く曲がりたいと十分な減速をしないで早くハンドルを切ってしまえば当然内側へ寄りすぎてしまい、こすったり乗り上げの原因となります。
ハンドルを手前から切らずに、交差点にまっすぐ入ってから素早くハンドルを切れば、左折時に右に振らなくても大回りぎみ(直角ぎみ)に曲がることは可能です。
文で説明するのは難しいのですが、左折時にはまずしっかり減速をすること。
まずは徐行くらいまでしっかり速度を下げることが大事です。
それから、曲がるのを待つ、遅らせるイメージで、すぐハンドルを切りはじめないこと。
交差点の縁石に左後ろのタイヤをあわせるように交差点内にある程度直進のまま侵入してから、素早く左へハンドルを切っていきます。(ハンドルを切り始めるのは車によって違いますが、普通車だとだいたい交差点の角がAピラー(フロント窓とサイド窓の間の柱部)か前席の横まで来たときくらいです)
そして内側(イン)につきすぎないように直角のように曲がり、左折した先の道路の右寄り(センターライン寄り)に寄せる感じで曲がっていきます。(余裕があれば、左サイドミラーで左後ろのタイヤが縁石に当たらないか見るのも良いです。ですが周囲の安全のが大切ですので、あまり注視しすぎないように)
ちょっと難しいかも知れませんが車を真上から見たとすると、早くハンドルを切って直線的にインをつくのではなくに、切りはじめを待ってから一気にハンドルを切って直角にくいっと曲がるイメージです。
さらに他の言い方でいうと、曲がった先のアウト側へつけるように曲がります。
何を言ってるか分からない…という方は、私の説明が悪いだけですのでこの件は忘れてください。汗
ごめんなさい。m(_ _)m
もし試しにやってみたいという方は、できれば広い交差点で他車や歩行者などがいない安全が確保されてるとき(深夜とかに照明で明るい交差点で)に、サイドミラーをやや下へ向けて後ろのタイヤが分かるようにして、練習してみてください。
二例目のカーブでのセンターラインオーバーは、基本的に絶対やってはいけない行為です。
センターラインオーバーは追越しや危険を避けるときだけ、しかもきちんと安全に安全を重ねて行うべきで、オーバーラインする必要がない場面では絶対にやってはいけない行為です。
道なりにカーブを走るときは、カーブを見てすんなりスマートに曲がるにはどのくらいの減速が必要か、カーブのきつさを瞬時に判断してどのくらいのスピードなら同乗者に不快感を与えずにきれいにはみ出さずに曲がれるか、というドライバーの腕の見せ所です。
逆にいうと、それをスマートにできるかどうかは、ドライバーの経験にもよります。
ドライバーがただ自分の思い通りに飛ばして走るのは、私的にはダメなドライブといえます。
同乗者が不快に思わない速度と曲がり方(ロール、横Gのかけ方)をしながらも、もしカーブ中に歩行者や自転車がいたとか事故車が停車していたり対向車がこちらの車線にはみ出したりしたとしても、何とか対処できるスピードとその予測を常にしながら、自分の走行車線からはみ出すことなく狙った走行ラインでスマートにカーブを曲がる走りができたら、私の中では合格といえます。
これが、スマートで格好の良いワインディングドライブだと、私は勝手に考えています。
三例目の路肩の線をオーバーしない、というのは道交法上の基本でもあります。
そもそも、道路を普通にまっすぐ走るだけならば、通常はセンターラインと路肩線のどちらにも寄らない、中央(真ん中)を走るのが安全な走行です。
街を走る車を見ると、障害物や危険がない状況でも、常に左の路肩線をオーバーして走っている車や、逆に常に右寄りでセンターラインを時々オーバーしながら走っている車も見かけることもあります。
もしかして右ハンドルから左ハンドルの車に乗り換えたのかな?(又はその逆?)、とか思うこともありますが、見ていてとても危なく感じます。
路肩線は本来、歩行者用の歩道の代わりの線です。
つまり、車道と歩行者用通路を分け隔てる線であり、線より外・左側は歩行者のためのゾーンになります。
車両である自動車は、基本的に路肩線を越えて走ってはいけないのです。
(同じように自転車は本来「軽車両」ですから車道を走らねばならず、本当は路肩線より左へ出て走ってはいけません。ですが、安全上そこまでは警察も取り締まりはせず、自転車は歩行者がいなければ路肩線の外側を走ることを黙認されています。(歩行者と事故となったときは違反を指摘される可能性はあります)
センターラインは言わずもがな、不用意にオーバーラインすることは非常に危ないのでしてはいけません。
ちなみに、路肩線とセンターラインの中央を走っているか確認するためには、サイドミラーで確認するのが良いでしょう。
停車時など安全なときに、左右両側のサイドミラーを見比べて、ミラーに移る路肩線とセンターラインとの間が、ほぼ同じくらいであれば車線の中央を走れていることになります。
どちらかに寄っている…と感じたら、若干修正をしてみてください。
あまり急に変えたりすると危ないこともあるので、気を付けながら少しづつ直していくと良いと思います。
あと、なんとなく前の車につられて左右どちらかに寄って走ってしまう、ということもあると思います。
これは人間が元から持っている癖になるんでしょうか、前に倣えと前走車に合わせて走ってしまうことがあります。
前の車とは関係なしに「自分は自分で安全走行をするんだ」と思って、周りの車にあまりつられないように?走行することも必要でしょう。
(ただし、逆に自分よがりになりすぎるのもよろしくありません。前の車が急に路肩線を超えるくらい左へ寄りだした?でも自分は真ん中を走る続けるぞ…、とそのまま走ってたら後ろから救急車がやってきた…汗。なんてこともあるかもしれません。安全運転を基軸にしながらも、すべてにおいては臨機応変が大事、です)
この記事を読んだ方は、日ごろ不用意にオーバーラインした走りをしてないか、改めて自分の運転を確認していただき、より良い運転ができるように見なおしてみてください。
「自分の運転が誰に見せても胸を張れる、良い運転ができているか?」
そんなことをいつも自己採点しながら、私は日々運転をしています。
いまだ満点を採るような納得のいく運転はできていませんが、その日々の努力に意味があると考えてます。
皆さんも、スマートで周りに優しい安全な運転を目指していって欲しいと思っています。
2017/02/10
(この記事は私が過去 2013.2.2. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
この間、若い方や免許を取りたての方、またハンドル握って十数年のベテランドライバーなど、いろいろな世代に会って車のお話をする機会がありました。
いろんな話で盛り上がって楽しかったのですが、ただ一点気になることがありました。
何ていうか話を聞いていると、話しぶりから自動車を甘く見ている、どこか車をなめている?ような感じを覚えたのです。
私もおじさんになったせいか(汗)、あれこれそれとなく諭したつもりですが、なんでしょうか「車の安全」に対する考え方に壁を感じるのです。
結局、そのまま納得してもらうことはできず、集まりはお開きとなってしまいました。
自分の力足らずを感じるところです。
交通安全という点で最近思うことは、歩道のない道路で若い子の自転車や歩行者の方が自動車とすれ違うときに、その自転車や歩行者が少しでも避けようとか、うまくやり過ごそうとするそぶりすら見せず、ただ何も考えずに真っすぐ進むだけ、といった人を多く見るようになったことです。
「自分の身は自分で守る」という生きていく上で重要なことができなくなってきているのか、平和惚けの延長なのか、はたまたモラルの低下なのか何だか分かりませんが、車の怖さを甘く見ているなあ、と感じます。
またそれは車を運転する側にも言えることで、歩行者や自転車とすれ違うとき、まったく減速はしないし少しでも避けてあげようともしない自動車が結構増えてきていると感じます。
自動車がどれだけすごいことをしていて、かつどれだけ危険なものなのか、運転手自身の理解も薄いということでしょう。
経済の成熟した日本では、今や「自動車」はあって当たり前、持っていて当たり前の時代となり、日本人にはとても身近な存在になりました。
車は誰でも乗れて動かせる簡単で便利な道具、と思っている方もたくさんいるかも知れません。
そして、公共交通網の発達していない地方においては、なくてはならない重要な移動手段のひとつとなっています。
しかしながら、その便利な道具の表裏一体として、いつでも他人を傷つける凶器になりうる危険な乗り物であることを深く理解しているのか?
疑問を感じることが多々あります。
そのせいなのか、相変わらず狭い抜け道を車で飛ばして走って歩行者や自転車と事故を起こしたり、飲酒運転も全体で減ってはいるものの一向になくならず、ひき逃げ事故の原因の一つになっています。
また以前から言っているように、車を安全に正しく操作するにはそれなりに「腕(技量)」が必要です。
運転は誰でも簡単にできる、という考えは間違っています。
きちんと正しい知識を得て、安全に運転する技を身に付け修得することは、自分の身を守り、家族など親しい同乗者の命を守り、愛車を守り、まわりの他人の安全と交通環境を守り、しいては地球環境を守り、めぐりめぐって自分の生活と人生を守ることなんだと、私は考えています。(大げさかもしれませんが)
自動車とそれを運転することは、決して甘く見てはいけないのです。
さて、今回は工学的で知識的な話をします。
ちょっと古典的な方法ですが、車がどれだけすごいことをしている機械なのか改めて検証していき、便利だけど危険を伴うものだということの理解を深めていただきたいと思っています。
車の性能を表す言葉に「馬力」というのがあるのはご存知かと思います。
(ここでいう馬力は、日本や欧州で使われているメートル法のフランス馬力を表します。米英で使われているヤードポンド法のイギリス馬力とはちょっとだけ違います)
馬力というのは、蒸気機関車を発明したかのジェームス・ワット氏が作ったもので、蒸気機関車を売り込むために当時主流であった馬に例えてその仕事の能力を分かりやすく換算したものです。
単純に1馬力は馬1頭分の仕事率を表し、正確には75kgの重さの物を1秒間に1m動かす仕事の能力(仕事率)を表します。
(本来ワットが作った英馬力は、550ポンドの重さの物を1秒間に1フィート動かすという仕事率)
といっても現代の日本人にとって、馬はすでに身近なものではなくなっていて、馬何頭分といわれてもいまいち理解しがたいところがあります。(^^;
でも、75kgを1秒間に1m動かすって、人間がやったらかなりきついことです。
たとえば、普通の大人ひとりが持ち上げて動かせる重さは、せいぜい50~60kgぐらいです。(馬力は引っ張って動かす力を表しますが)
さらに毎秒1mで長時間動かし続ける…となったら、人間には到底不可能な話です。
簡単にいうと、1馬力は人間(大人の男性)およそ3~4人分の仕事率にあたります。
仕事率は瞬間的な力ではなく、力を出し続けて荷物を動かし続けることを意味します。
人間1人が出し続けられる仕事率は、およそ0.3馬力程度しかありません。
そう考えると馬って結構すごいことが、何となく分かるかと思います。
さて、近年の一般的なミドルサイズクラス1500ccの普通の乗用車(カローラとか)は最大で100馬力以上出るエンジンを普通に積んでます。
単純に馬に換算して100頭分、人間ならば300人分のパワーに相当します。
エンジンが最大馬力を出せば、計算上実に9トン(!)の物を動かすことができることになります。
いまいちピンと来ないかも知れませんが、たいして大きくない車のエンジンでも、単純に馬100頭以上、人間なら大人300人以上分のパワーがあるということです。
そのとんでもない力を、私たちドライバーは右足の小さなペダルひとつでコントロールして動かしていることになります。
人間300人分のパワーを持つ自動車が、生身の人間のすぐ脇を、何百台何千台と走っているのが、現代の日常なのです。
さて、自動車は、軽自動車でも1トン(1000kg)近くの重さがあり、ミニバンなどの大きい車なら1.5~2トン(1500~2000kg)もある、鉄?の塊です。
そんな重たい鉄の塊が、アクセルペダルをちょっと踏んだだけで軽く時速40kmのスピードを出すことができます。
さらに踏み込めば時速100km以上もスピードが出ます。
人間がトップアスリート並みに全速力で走っても、短距離走で瞬間的に時速40kmくらい、マラソンならば平均で時速20kmくらいです。
一般男性が体重約60kgとするならば、自動車は実に人間の20倍もの重さでありながら、人間の3~5倍の時速100km以上を出すことができます。
人間の運動能力以上の、本来ならば人間には想像できない以上の運動能力を持っているのが、自動車です。
では、1トン以上ある鉄の塊が人間以上のスピードで動く車には、どれだけの運動エネルギーを持つのか?、考えてみます。
一般的なミドルサイズの普通乗用車を例として、1.3トン(1300kg)の車が時速40kmで壁にぶつかったときの衝突力は、どのくらいだと思いますか?
物理はあまり得意ではないんですが(汗)、計算してみますと、その衝突の力はおよそ14トン(!)です。
さらに、もし時速100kmでぶつかったとすると、実に36トン(!!)もの衝突力となります。
(実際はぶつかる壁の性質やぶつかり方で変わります。壁は剛体としぶつかり方も深く考えないものとして、衝突時間0.1秒で計算してます)
14トンにしろ36トンにしろ、とても生身の人間には適わないことは明らかです。
歩行者とすれ違うときにちょっと接触しただけでも、速度と当たり方によっては死に至ることも十分に考えられます。
そういう危険なものが、私たちの生活のすぐ傍を日常的に走っています。
このように自動車を数字で見ていくと、とても人間には適わないすごい能力が備わっているのが、多少分かるかと思います。
その辺で普通に走っている車に、それだけの能力が当たり前に備わっているのです。
逆に言えば、自動車が走ること自体がすでに危険だということでもあります。
一歩間違えれば、ただの凶器です。
そしてそれは、ハンドルを握るドライバーにすべて委ねられます。
人間の体と能力を大幅に超える自動車を、主にハンドル、アクセル、ブレーキだけで操らなければならず、単純ゆえに難しい。
だから「腕(技量)」が要るのです。
また上記の具体的な数字を見れば、自動車が歩行者や自転車のすぐ脇を減速も避けもせずに走り抜けることが、いかに危険なことか分かります。
狭くて車道と歩道がきちんと別れていない道路で、歩行者と自転車とすれ違うときは、減速をしてしっかり避けてあげること。
対向車がいるとか狭すぎてしっかり避けられない時は、とにかく減速をしゆっくりすれ違うこと。
もし万が一接触したとしても、当たった時の速度が遅ければ遅いほど相手に与える衝突力は少なく、大怪我をさせずに済む可能性が高くなるのです。
車が1トン近く、またはそれ以上の重さがあることを考えれば、当然のことといえます。
そして車と人がすぐ近くですれ違うような狭く先が見えづらいような道路を、抜け道として時速40km以上で飛ばして行くことが、いかに危険な行為か。
ドライバーには十分理解していただきたいと思います。
また歩行者・自転車側も、動いている自動車に不用意に近づくことはとても危険であり、一歩間違えば死に至るということを、再認識しなくてはなりません。
歩行者優先、交通弱者の優先は、日本の道交法では基本中の基本ではあります。
ですが、公道は誰でもみんなが使うものです。
狭い道だとしても自動車が通ってはいけない、ということはありません。(車両進入禁止の道はありますが)
歩行者優先だからといって、歩行者がまったく避けなくても良い、避ける必要がない、ということにはなりません。
自分の身は自分で守るのは生物としての基本ですし、「お互いさま」という社会モラルの問題でもあります。
歩道のない狭い道で自動車とすれ違うときは、歩行者・自転車側も避けられるときは少しでも避ける努力をするべきです。
特に自動車を運転したことのない若い世代の方は、自動車の怖さや自分より大きな車を動かす運転しにくさを分からないためか、それとも反抗期の表れなのか分かりませんが、どこかで「車をなめてる」感じを見受けます。
狭い道で車が来ても避けようとすらしないで道の真ん中を歩く中学生の歩行者集団とか、視界の悪い横道から減速も一時停止もせず猛スピードのまま車道を横切っていく高校生の自転車とかを見かけるたび、すごく残念な気持ちになります。
大きな事故につながる前に、改めて自動車が生身の人間には到底適わない鉄の塊なんだ、と再認識して欲しいと思います。
以上、自動車の能力に関して、いろいろな数字を見てみました。
悲しい事故を少しでも減らすために、参考にしてみてください。
みんなで安全な交通環境を整えていく努力をしていきましょう。
m(_ _)m
この間、若い方や免許を取りたての方、またハンドル握って十数年のベテランドライバーなど、いろいろな世代に会って車のお話をする機会がありました。
いろんな話で盛り上がって楽しかったのですが、ただ一点気になることがありました。
何ていうか話を聞いていると、話しぶりから自動車を甘く見ている、どこか車をなめている?ような感じを覚えたのです。
私もおじさんになったせいか(汗)、あれこれそれとなく諭したつもりですが、なんでしょうか「車の安全」に対する考え方に壁を感じるのです。
結局、そのまま納得してもらうことはできず、集まりはお開きとなってしまいました。
自分の力足らずを感じるところです。
交通安全という点で最近思うことは、歩道のない道路で若い子の自転車や歩行者の方が自動車とすれ違うときに、その自転車や歩行者が少しでも避けようとか、うまくやり過ごそうとするそぶりすら見せず、ただ何も考えずに真っすぐ進むだけ、といった人を多く見るようになったことです。
「自分の身は自分で守る」という生きていく上で重要なことができなくなってきているのか、平和惚けの延長なのか、はたまたモラルの低下なのか何だか分かりませんが、車の怖さを甘く見ているなあ、と感じます。
またそれは車を運転する側にも言えることで、歩行者や自転車とすれ違うとき、まったく減速はしないし少しでも避けてあげようともしない自動車が結構増えてきていると感じます。
自動車がどれだけすごいことをしていて、かつどれだけ危険なものなのか、運転手自身の理解も薄いということでしょう。
経済の成熟した日本では、今や「自動車」はあって当たり前、持っていて当たり前の時代となり、日本人にはとても身近な存在になりました。
車は誰でも乗れて動かせる簡単で便利な道具、と思っている方もたくさんいるかも知れません。
そして、公共交通網の発達していない地方においては、なくてはならない重要な移動手段のひとつとなっています。
しかしながら、その便利な道具の表裏一体として、いつでも他人を傷つける凶器になりうる危険な乗り物であることを深く理解しているのか?
疑問を感じることが多々あります。
そのせいなのか、相変わらず狭い抜け道を車で飛ばして走って歩行者や自転車と事故を起こしたり、飲酒運転も全体で減ってはいるものの一向になくならず、ひき逃げ事故の原因の一つになっています。
また以前から言っているように、車を安全に正しく操作するにはそれなりに「腕(技量)」が必要です。
運転は誰でも簡単にできる、という考えは間違っています。
きちんと正しい知識を得て、安全に運転する技を身に付け修得することは、自分の身を守り、家族など親しい同乗者の命を守り、愛車を守り、まわりの他人の安全と交通環境を守り、しいては地球環境を守り、めぐりめぐって自分の生活と人生を守ることなんだと、私は考えています。(大げさかもしれませんが)
自動車とそれを運転することは、決して甘く見てはいけないのです。
さて、今回は工学的で知識的な話をします。
ちょっと古典的な方法ですが、車がどれだけすごいことをしている機械なのか改めて検証していき、便利だけど危険を伴うものだということの理解を深めていただきたいと思っています。
車の性能を表す言葉に「馬力」というのがあるのはご存知かと思います。
(ここでいう馬力は、日本や欧州で使われているメートル法のフランス馬力
馬力というのは、蒸気機関車を発明したかのジェームス・ワット氏が作ったもので、蒸気機関車を売り込むために当時主流であった馬に例えてその仕事の能力を分かりやすく換算したものです。
単純に1馬力は馬1頭分の仕事率を表し、正確には75kgの重さの物を1秒間に1m動かす仕事の能力(仕事率)を表します。
(本来ワットが作った英馬力は、550ポンドの重さの物を1秒間に1フィート動かすという仕事率)
といっても現代の日本人にとって、馬はすでに身近なものではなくなっていて、馬何頭分といわれてもいまいち理解しがたいところがあります。(^^;
でも、75kgを1秒間に1m動かすって、人間がやったらかなりきついことです。
たとえば、普通の大人ひとりが持ち上げて動かせる重さは、せいぜい50~60kgぐらいです。(馬力は引っ張って動かす力を表しますが)
さらに毎秒1mで長時間動かし続ける…となったら、人間には到底不可能な話です。
簡単にいうと、1馬力は人間(大人の男性)およそ3~4人分の仕事率にあたります。
仕事率は瞬間的な力ではなく、力を出し続けて荷物を動かし続けることを意味します。
人間1人が出し続けられる仕事率は、およそ0.3馬力程度しかありません。
そう考えると馬って結構すごいことが、何となく分かるかと思います。
さて、近年の一般的なミドルサイズクラス1500ccの普通の乗用車(カローラとか)は最大で100馬力以上出るエンジンを普通に積んでます。
単純に馬に換算して100頭分、人間ならば300人分のパワーに相当します。
エンジンが最大馬力を出せば、計算上実に9トン(!)の物を動かすことができることになります。
いまいちピンと来ないかも知れませんが、たいして大きくない車のエンジンでも、単純に馬100頭以上、人間なら大人300人以上分のパワーがあるということです。
そのとんでもない力を、私たちドライバーは右足の小さなペダルひとつでコントロールして動かしていることになります。
人間300人分のパワーを持つ自動車が、生身の人間のすぐ脇を、何百台何千台と走っているのが、現代の日常なのです。
さて、自動車は、軽自動車でも1トン(1000kg)近くの重さがあり、ミニバンなどの大きい車なら1.5~2トン(1500~2000kg)もある、鉄?の塊です。
そんな重たい鉄の塊が、アクセルペダルをちょっと踏んだだけで軽く時速40kmのスピードを出すことができます。
さらに踏み込めば時速100km以上もスピードが出ます。
人間がトップアスリート並みに全速力で走っても、短距離走で瞬間的に時速40kmくらい、マラソンならば平均で時速20kmくらいです。
一般男性が体重約60kgとするならば、自動車は実に人間の20倍もの重さでありながら、人間の3~5倍の時速100km以上を出すことができます。
人間の運動能力以上の、本来ならば人間には想像できない以上の運動能力を持っているのが、自動車です。
では、1トン以上ある鉄の塊が人間以上のスピードで動く車には、どれだけの運動エネルギーを持つのか?、考えてみます。
一般的なミドルサイズの普通乗用車を例として、1.3トン(1300kg)の車が時速40kmで壁にぶつかったときの衝突力は、どのくらいだと思いますか?
物理はあまり得意ではないんですが(汗)、計算してみますと、その衝突の力はおよそ14トン(!)です。
さらに、もし時速100kmでぶつかったとすると、実に36トン(!!)もの衝突力となります。
(実際はぶつかる壁の性質やぶつかり方で変わります。壁は剛体としぶつかり方も深く考えないものとして、衝突時間0.1秒で計算してます)
14トンにしろ36トンにしろ、とても生身の人間には適わないことは明らかです。
歩行者とすれ違うときにちょっと接触しただけでも、速度と当たり方によっては死に至ることも十分に考えられます。
そういう危険なものが、私たちの生活のすぐ傍を日常的に走っています。
このように自動車を数字で見ていくと、とても人間には適わないすごい能力が備わっているのが、多少分かるかと思います。
その辺で普通に走っている車に、それだけの能力が当たり前に備わっているのです。
逆に言えば、自動車が走ること自体がすでに危険だということでもあります。
一歩間違えれば、ただの凶器です。
そしてそれは、ハンドルを握るドライバーにすべて委ねられます。
人間の体と能力を大幅に超える自動車を、主にハンドル、アクセル、ブレーキだけで操らなければならず、単純ゆえに難しい。
だから「腕(技量)」が要るのです。
また上記の具体的な数字を見れば、自動車が歩行者や自転車のすぐ脇を減速も避けもせずに走り抜けることが、いかに危険なことか分かります。
狭くて車道と歩道がきちんと別れていない道路で、歩行者と自転車とすれ違うときは、減速をしてしっかり避けてあげること。
対向車がいるとか狭すぎてしっかり避けられない時は、とにかく減速をしゆっくりすれ違うこと。
もし万が一接触したとしても、当たった時の速度が遅ければ遅いほど相手に与える衝突力は少なく、大怪我をさせずに済む可能性が高くなるのです。
車が1トン近く、またはそれ以上の重さがあることを考えれば、当然のことといえます。
そして車と人がすぐ近くですれ違うような狭く先が見えづらいような道路を、抜け道として時速40km以上で飛ばして行くことが、いかに危険な行為か。
ドライバーには十分理解していただきたいと思います。
また歩行者・自転車側も、動いている自動車に不用意に近づくことはとても危険であり、一歩間違えば死に至るということを、再認識しなくてはなりません。
歩行者優先、交通弱者の優先は、日本の道交法では基本中の基本ではあります。
ですが、公道は誰でもみんなが使うものです。
狭い道だとしても自動車が通ってはいけない、ということはありません。(車両進入禁止の道はありますが)
歩行者優先だからといって、歩行者がまったく避けなくても良い、避ける必要がない、ということにはなりません。
自分の身は自分で守るのは生物としての基本ですし、「お互いさま」という社会モラルの問題でもあります。
歩道のない狭い道で自動車とすれ違うときは、歩行者・自転車側も避けられるときは少しでも避ける努力をするべきです。
特に自動車を運転したことのない若い世代の方は、自動車の怖さや自分より大きな車を動かす運転しにくさを分からないためか、それとも反抗期の表れなのか分かりませんが、どこかで「車をなめてる」感じを見受けます。
狭い道で車が来ても避けようとすらしないで道の真ん中を歩く中学生の歩行者集団とか、視界の悪い横道から減速も一時停止もせず猛スピードのまま車道を横切っていく高校生の自転車とかを見かけるたび、すごく残念な気持ちになります。
大きな事故につながる前に、改めて自動車が生身の人間には到底適わない鉄の塊なんだ、と再認識して欲しいと思います。
以上、自動車の能力に関して、いろいろな数字を見てみました。
悲しい事故を少しでも減らすために、参考にしてみてください。
みんなで安全な交通環境を整えていく努力をしていきましょう。
m(_ _)m
2017/02/10
(この記事は私が過去 2012.10.15. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
また追い越しの話です。
今度は走っている車を追い越す、本来の追い越しの安全なやり方を考えてみたいと思います。
高速でも一般道でも使える話ですが、いちおう一般道での話としておきます。
片側一車線の公道を場合を想定して話を進めます。
では、正しく安全な追い越しのやり方を考えていきます。
まず、追い越しできるか否かを正しく判断しなくてはなりません。
基本的なこととして、追い越し禁止されていないか、追い越し等に伴う車線変更が禁止されていないか、制限速度を越えないで追い越しできるか、確認が必要です。
追い越し等に伴う車線変更禁止の区間は、センターラインがオレンジ色(赤?)です。
センターラインがオレンジ色の時には、車線変更、すなわちセンターラインをオーバーしてはいけません。
(センターラインを越えなければ、いちおう追い越しは可能です)
また、本来追い越しは制限速度内で行うものです。
結構皆さんかなりのスピードで追い越しをしていきますが、原則として制限速度は超えてはいけません。
(しかしながら安全に素早く追い越しをするなら、制限速度+20km/hくらいの速度オーバーは必要かも知れません。ただし速度違反であることに変わりありません)
つまり、前の車が制限速度ちょうどで走っている場合は、追い越しできないことになります。
制限速度を越えることは道交法上で違反となりますが、最低速度が決まっていなければどんなにのろのろでゆっくり走っても違反とはならないのです。
(ただし、制限速度を下回って走るときは、後続車が詰まってきたらすみやかに進路を譲らなくてはならないと規定されています。逆に言えば制限速度ちょうどくらいの時は、後続車が混んでも無理をして進路を譲る必要はありません)
要は、前の車が制限速度よりも低い速度で走っているときは追い越しができますが、制限速度ちょうどの時は追い越しをしてはいけないと考えるべきです。
よく、郊外の広くそこそこ空いた片側一車線の道(松本近辺なら東山や西山の山麓線など)で、制限速度よりやや超過して走っている車でも、当たり前のように猛スピードで追い越しをしていく車を結構見かけますが、それは道交法違反となります。
そういう時は、追い越ししても良い区間でも、前の車が遅いと思っても(制限速度前後で走っている車をを遅いと思うほうが間違いなんです)、追い越しをしてはいけないのです。
そのあたり、決して間違えないように注意してください。
さて、上の条件がそろって実際に前の車を追い越すとき、カーブのない見通しの良い直線道路で追い越すなども大事ですが、さらに注意すべきポイントは追い越しをかける前に車間をしっかり空けておくことです。
よく前の車が遅いと、まるで煽るかのように前の車のすぐ後ろにピッタリくっついていく車がいますが、安全に追い越しをするという観点からいえば、それは良くありません。
対向車線へ出て追い越しをかける場合、安全上最も注意しなければならないのは、対向車線へ飛び出している時間をいかに少なくするかということです。
前の車のすぐ真後ろから追い越しをかけるとなると、加速は対向車線へ出てからすることになります。
すると追い越しをするのに時間がかかるうえ、対向車線へ出ている時間も長くなり、危険が大きく大事故の確率も高くなってしまいます。
安全でスマートな追い越しは、しっかり車間を空けておき、追い越しのウインカーを出しながら今自分がいる車線である程度加速をしておいてから追い越しをかけること。
あらかじめしっかり加速しておいてから追い越しすれば、対向車線へ出ている時間が短くて済みます。
また車間をしっかり空けて自分の走行車線で加速するようにすれば、もし急に対向車が来たりしても対向車線に出る前ならばすぐに追い越しを止めることができ、安全度も増します。
安全上大事なのは、対向車線に出ている時間をとにかく短くすること。
そして、車間をしっかり空けた上、事前に自分の走行車線でしっかり加速しスピードを上げておいてから追い越しをかけること。
この2点です。
では具体的に順を追って、安全な追い越しを見ていきます。
まずは、追い越ししても良い場所か確認します。
追い越し禁止でないか、車線変更禁止でないか。
カーブの少ない見通しの良い、追い越しに適した直線道路か。
追い越そうとする車が制限速度より低い速度かどうか。
などなど、確認しておくことはたくさんあります。
全部OKならば追い越しを試みましょう。
もしダメだと思ったなら、すっぱりあきらめるのも大切です。
このブログでは何度も言っていますが、公道を車で走る上でもっとも重要なことは「安全」です。
少しでも危険をともなうような行為は、絶対にしてはいけません。
特に追い越しのような、一歩間違えば大事故になりかねないことをするときは、まさしく石橋を叩くような細心の注意が必要だということです。
上の条件の一つでもダメなことがあったときは、すっぱりとあきらめましょう。
追い越しできると判断し、やろうと思ったなら、対向車の流れを見て追い越しをかけます。
基本は、見通せる範囲に対向車がいないときに追い越しをかけること。
しかし、公道ですから対向車がいるのはある意味当たり前です。
場合によっては対向車がいる中で、交通の流れのタイミングを見計らって追い越しをしなくてはなりません。
このときの追い越しのタイミングは、かなり難しいものがあります。
同じ方向へ走っている車を追い越すのには、思ったよりも多く時間がかかります。
加えて対向車はこちらへ向かって走ってくるのでお互いが距離を縮めることになり、対向車は思ったよりも早く近づいてくるものです。
経験とそれに合わせたイメージがものを言うところもありますので、自信が無い場合やうまく抜けるイメージが湧かないのなら、対向車がいる時は追い越ししない方が良いです。
特にイメージがしにくいであろう初心者などの方は、十分気を付けてください。
自分の身を守るために、少しでも不安を感じたなら、ここでもすっぱりやめておきましょう。
追い越しができるタイミングが計れたら、実行に移します。
事前に追い越す車との車間をしっかり空けておきます。
車間は実際の速度と個人の感覚的なところもありますが、車が1~2台入るくらい、20m以上は空けておいた方が安全だと思います。
ここで追い越しを実行するためウインカーを出すのですが、その前にサイドミラーとルームミラーで後方確認をしておきましょう。
後続車やバイクなどが、自分の車を含めて無理な追い越しをしかけてきているかもしれないからです。
特にバイクについては、車が混んでくると右から左から隙間を縫うように追い越しをしてくるバイクも結構います。
追い越しにおいては、先に進路変更した方が優先されます。(前後の道路状況にもよりますが)
対向車だけでなく後続車にも目を配らなくてはなりません。
後方確認が済んだら、ウインカーを出して走行車線の右へ寄ります。
これから追い越しかけますよ、という合図です。
この時、センターライン上か少し越えるようにすると、まわりへの追い越しのアピールになります。(はみ出し過ぎはダメです)
そして事前に安全をよくよく判断した上で「行くぞ」と決めたならば、中途半端は禁物です。
アクセルをしっかり踏んでしっかり加速をします。(それでもあくまでまわりの状況によりますが)
目標を制限速度+20km/hくらいまでしっかり加速するつもりで加速しましょう。
加速しつつ前の車との車間が狭まったら、車線を変更し対向車線へ完全に出て追い越します。
その間、ウインカーは右へ出しっぱなし。
これは追い越ししてますよという合図でもありますので、完全に抜くまで右へウインカーを出し続けます。
ルームミラーごしに追い越した車が見えたら完全に追い抜いたので(教習所で習った通りです)、左へウインカーを出しながら元の車線へと戻ります。
あとは周りへ危険が無い程度に減速しましょう。
以上で完了です。
先程述べたとおり、もし追い越しの途中で急に対向車が来たりして危険が迫ったときは、対向車線へ完全に出る前だったらすぐに加速を止めて元の車線へ戻ります。
完全に対向車線へ出ていても、追い越す車の横に並ぶ前なら追い越しを止めるという選択肢もありますが、多くの場合は対向車線へ完全に出て追い越し始めていたならば、追い越しを完遂させる方がベターなことが多いです。
と言っても臨機応変は重要です。
危険だ、と判断したならどんな状況でも追い越しを止める必要もあるでしょう。
その辺りの判断も難しいところです。
それでも何度もいうように、「安全」が最も大切です。
自分の身を守ることを第一に考えながら判断と行動すれば、かなり安全な行動ができるはずです。
さて話がそれますが、追い越しされる側の、安全で正しい追い越され方にも触れておきます。
追い越しされる側の基本としては、追い越し中には絶対加速しないということ。
これは道交法に定められています。
安全にスムーズに追い越しをさせてあげるために、少し左に寄りつつ若干スピードを落としてあげる、くらいのことをしても良いと思います。
「安全」という意味では、大切なことです。
しかし、制限速度をやや超えたくらいの速い速度で走っていても、中には追い越しをしていく車も多くいます。(郊外の空いた道だとなおさらです)
自分が特に遅いというわけでもないのに、煽られたり追い越しされると、正直すごく気分が悪いものです。
しかし、何度も言うように「安全」が第一です。
追い越しをかけられたら、相手が無事安全に追い越しができるよう配慮してあげましょう。
変に意地悪?でもして事故にでもなったら、自分に危険が降り掛かってくる可能性があります。
嫌悪感を覚えつつでも自分の身を守るため、無事安全に追い越しが終わるよう、広い心をもってやや減速しやや左に寄ってあげましょう。
追い越しは対向車線へ飛び出す行為なので、常に危険が付きまとう行為です。
この記事を参考にしていただいて、安全かつスマートな追い越しができるよう、気を付けてみてください。
m(_ _)m
また追い越しの話です。
今度は走っている車を追い越す、本来の追い越しの安全なやり方を考えてみたいと思います。
高速でも一般道でも使える話ですが、いちおう一般道での話としておきます。
片側一車線の公道を場合を想定して話を進めます。
では、正しく安全な追い越しのやり方を考えていきます。
まず、追い越しできるか否かを正しく判断しなくてはなりません。
基本的なこととして、追い越し禁止されていないか、追い越し等に伴う車線変更が禁止されていないか、制限速度を越えないで追い越しできるか、確認が必要です。
追い越し等に伴う車線変更禁止の区間は、センターラインがオレンジ色(赤?)です。
センターラインがオレンジ色の時には、車線変更、すなわちセンターラインをオーバーしてはいけません。
(センターラインを越えなければ、いちおう追い越しは可能です)
また、本来追い越しは制限速度内で行うものです。
結構皆さんかなりのスピードで追い越しをしていきますが、原則として制限速度は超えてはいけません。
(しかしながら安全に素早く追い越しをするなら、制限速度+20km/hくらいの速度オーバーは必要かも知れません。ただし速度違反であることに変わりありません)
つまり、前の車が制限速度ちょうどで走っている場合は、追い越しできないことになります。
制限速度を越えることは道交法上で違反となりますが、最低速度が決まっていなければどんなにのろのろでゆっくり走っても違反とはならないのです。
(ただし、制限速度を下回って走るときは、後続車が詰まってきたらすみやかに進路を譲らなくてはならないと規定されています。逆に言えば制限速度ちょうどくらいの時は、後続車が混んでも無理をして進路を譲る必要はありません)
要は、前の車が制限速度よりも低い速度で走っているときは追い越しができますが、制限速度ちょうどの時は追い越しをしてはいけないと考えるべきです。
よく、郊外の広くそこそこ空いた片側一車線の道(松本近辺なら東山や西山の山麓線など)で、制限速度よりやや超過して走っている車でも、当たり前のように猛スピードで追い越しをしていく車を結構見かけますが、それは道交法違反となります。
そういう時は、追い越ししても良い区間でも、前の車が遅いと思っても(制限速度前後で走っている車をを遅いと思うほうが間違いなんです)、追い越しをしてはいけないのです。
そのあたり、決して間違えないように注意してください。
さて、上の条件がそろって実際に前の車を追い越すとき、カーブのない見通しの良い直線道路で追い越すなども大事ですが、さらに注意すべきポイントは追い越しをかける前に車間をしっかり空けておくことです。
よく前の車が遅いと、まるで煽るかのように前の車のすぐ後ろにピッタリくっついていく車がいますが、安全に追い越しをするという観点からいえば、それは良くありません。
対向車線へ出て追い越しをかける場合、安全上最も注意しなければならないのは、対向車線へ飛び出している時間をいかに少なくするかということです。
前の車のすぐ真後ろから追い越しをかけるとなると、加速は対向車線へ出てからすることになります。
すると追い越しをするのに時間がかかるうえ、対向車線へ出ている時間も長くなり、危険が大きく大事故の確率も高くなってしまいます。
安全でスマートな追い越しは、しっかり車間を空けておき、追い越しのウインカーを出しながら今自分がいる車線である程度加速をしておいてから追い越しをかけること。
あらかじめしっかり加速しておいてから追い越しすれば、対向車線へ出ている時間が短くて済みます。
また車間をしっかり空けて自分の走行車線で加速するようにすれば、もし急に対向車が来たりしても対向車線に出る前ならばすぐに追い越しを止めることができ、安全度も増します。
安全上大事なのは、対向車線に出ている時間をとにかく短くすること。
そして、車間をしっかり空けた上、事前に自分の走行車線でしっかり加速しスピードを上げておいてから追い越しをかけること。
この2点です。
では具体的に順を追って、安全な追い越しを見ていきます。
まずは、追い越ししても良い場所か確認します。
追い越し禁止でないか、車線変更禁止でないか。
カーブの少ない見通しの良い、追い越しに適した直線道路か。
追い越そうとする車が制限速度より低い速度かどうか。
などなど、確認しておくことはたくさんあります。
全部OKならば追い越しを試みましょう。
もしダメだと思ったなら、すっぱりあきらめるのも大切です。
このブログでは何度も言っていますが、公道を車で走る上でもっとも重要なことは「安全」です。
少しでも危険をともなうような行為は、絶対にしてはいけません。
特に追い越しのような、一歩間違えば大事故になりかねないことをするときは、まさしく石橋を叩くような細心の注意が必要だということです。
上の条件の一つでもダメなことがあったときは、すっぱりとあきらめましょう。
追い越しできると判断し、やろうと思ったなら、対向車の流れを見て追い越しをかけます。
基本は、見通せる範囲に対向車がいないときに追い越しをかけること。
しかし、公道ですから対向車がいるのはある意味当たり前です。
場合によっては対向車がいる中で、交通の流れのタイミングを見計らって追い越しをしなくてはなりません。
このときの追い越しのタイミングは、かなり難しいものがあります。
同じ方向へ走っている車を追い越すのには、思ったよりも多く時間がかかります。
加えて対向車はこちらへ向かって走ってくるのでお互いが距離を縮めることになり、対向車は思ったよりも早く近づいてくるものです。
経験とそれに合わせたイメージがものを言うところもありますので、自信が無い場合やうまく抜けるイメージが湧かないのなら、対向車がいる時は追い越ししない方が良いです。
特にイメージがしにくいであろう初心者などの方は、十分気を付けてください。
自分の身を守るために、少しでも不安を感じたなら、ここでもすっぱりやめておきましょう。
追い越しができるタイミングが計れたら、実行に移します。
事前に追い越す車との車間をしっかり空けておきます。
車間は実際の速度と個人の感覚的なところもありますが、車が1~2台入るくらい、20m以上は空けておいた方が安全だと思います。
ここで追い越しを実行するためウインカーを出すのですが、その前にサイドミラーとルームミラーで後方確認をしておきましょう。
後続車やバイクなどが、自分の車を含めて無理な追い越しをしかけてきているかもしれないからです。
特にバイクについては、車が混んでくると右から左から隙間を縫うように追い越しをしてくるバイクも結構います。
追い越しにおいては、先に進路変更した方が優先されます。(前後の道路状況にもよりますが)
対向車だけでなく後続車にも目を配らなくてはなりません。
後方確認が済んだら、ウインカーを出して走行車線の右へ寄ります。
これから追い越しかけますよ、という合図です。
この時、センターライン上か少し越えるようにすると、まわりへの追い越しのアピールになります。(はみ出し過ぎはダメです)
そして事前に安全をよくよく判断した上で「行くぞ」と決めたならば、中途半端は禁物です。
アクセルをしっかり踏んでしっかり加速をします。(それでもあくまでまわりの状況によりますが)
目標を制限速度+20km/hくらいまでしっかり加速するつもりで加速しましょう。
加速しつつ前の車との車間が狭まったら、車線を変更し対向車線へ完全に出て追い越します。
その間、ウインカーは右へ出しっぱなし。
これは追い越ししてますよという合図でもありますので、完全に抜くまで右へウインカーを出し続けます。
ルームミラーごしに追い越した車が見えたら完全に追い抜いたので(教習所で習った通りです)、左へウインカーを出しながら元の車線へと戻ります。
あとは周りへ危険が無い程度に減速しましょう。
以上で完了です。
先程述べたとおり、もし追い越しの途中で急に対向車が来たりして危険が迫ったときは、対向車線へ完全に出る前だったらすぐに加速を止めて元の車線へ戻ります。
完全に対向車線へ出ていても、追い越す車の横に並ぶ前なら追い越しを止めるという選択肢もありますが、多くの場合は対向車線へ完全に出て追い越し始めていたならば、追い越しを完遂させる方がベターなことが多いです。
と言っても臨機応変は重要です。
危険だ、と判断したならどんな状況でも追い越しを止める必要もあるでしょう。
その辺りの判断も難しいところです。
それでも何度もいうように、「安全」が最も大切です。
自分の身を守ることを第一に考えながら判断と行動すれば、かなり安全な行動ができるはずです。
さて話がそれますが、追い越しされる側の、安全で正しい追い越され方にも触れておきます。
追い越しされる側の基本としては、追い越し中には絶対加速しないということ。
これは道交法に定められています。
安全にスムーズに追い越しをさせてあげるために、少し左に寄りつつ若干スピードを落としてあげる、くらいのことをしても良いと思います。
「安全」という意味では、大切なことです。
しかし、制限速度をやや超えたくらいの速い速度で走っていても、中には追い越しをしていく車も多くいます。(郊外の空いた道だとなおさらです)
自分が特に遅いというわけでもないのに、煽られたり追い越しされると、正直すごく気分が悪いものです。
しかし、何度も言うように「安全」が第一です。
追い越しをかけられたら、相手が無事安全に追い越しができるよう配慮してあげましょう。
変に意地悪?でもして事故にでもなったら、自分に危険が降り掛かってくる可能性があります。
嫌悪感を覚えつつでも自分の身を守るため、無事安全に追い越しが終わるよう、広い心をもってやや減速しやや左に寄ってあげましょう。
追い越しは対向車線へ飛び出す行為なので、常に危険が付きまとう行為です。
この記事を参考にしていただいて、安全かつスマートな追い越しができるよう、気を付けてみてください。
m(_ _)m
2017/02/08
(この記事は私が過去 2013.4.18. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
近ごろ、長野県含め地方の高速道路で、夜間の痛ましい事故が続いています。
それらの重大事故には共通点があると思います。
ひとつは、夜間とくに深夜から未明にかけての事故であること。
もうひとつは、はじめ故障や単独事故などで路肩や走行車線にはみ出したり、または塞ぐような形で事故車両が停まり、そこに後続車が突っ込んで大きな事故となる、というものです。
これは、都会ではなく地方における高速道路上において、深夜・未明の時間だからこそ起きる事故だと考えられます。
その辺りを踏まえて、検証と対策を考えてみたいと思います。
まず、都会と地方の高速道路の違い、そして深夜・未明の時と昼間や早い時間の夜間とは何が違うのでしょうか?
平たく言ってしまうと、暗くて遠くまでしっかり見通せないことと、通行量が少なすぎて道路の状況を把握しづらいこと、です。
昼間だと、当然ながら見通しが良くきき、道路がこの先どちらに曲がっていくかとか、登り坂なのか下り坂なのかとか、道全体の交通状況を目で見て確認できます。
また道路上の落下物とか、故障・事故車がいるとかの発見も、いち早く確認ができます。
それから、都会の高速道路だと夜間でも大抵明る過ぎるくらいにずらっと道路灯があるので、夜でも道路の状況は比較的簡単に確認できます。
一方、地方・田舎の高速道路だと明かりがきちんとあるのはI.C.やP.A.、JCTなどの付近だけで、夜間は基本的にほぼ真っ暗な中で車のライトだけを頼りに走ることが多くなります。
加えて深夜・未明の時間帯は交通量が少なすぎて、逆に道路状況が把握しづらいのです。
ある程度混みあった道ならば、どこかで事故・故障車や落下物などがあっても、前を走る車の動きやブレーキのかけ方、交通の流れなどで、「この先に何かある」と判断をすることができます。
しかし、地方の高速にて深夜にほぼ真っ暗の中、自分の車一台だけで走っているような状況だと、前方に事故・故障車や落下物があっても自分の車のライトだけで判断するしかなく、気付くのがかなり遅くなってしまうのです。
暗くて閑散とした中で運転してると、道に何かあるのか自体も発見が遅くなるし、停まっている事故・故障車のライトが光っていたとしてもそれが事故や故障で停まっている車とは瞬時には判断できず、「ん?なんだろう?」と思っている間に近づきすぎてしまい(相手は止まっていて自分は100km/hくらいで走っているので、あっという間に近づいてしまいます)、「まずい!」と気付いたときにはもう遅く、追突したり避けようとしてさらなる多重事故となってしまうのです。
特に、夜間故障などで普通に路肩に停めている場合、後続車は閑散とした暗い中を走っていて少し集中力も低下してるため、路肩にただ停車してる車のライトを見ても一目で停まっている車とは認識できず、普通に前を走っている先行車と勘違いしてしまう時があります。
その勘違いをすると、無意識に路肩の停車してる車の後ろについて走ろうと、停止してる車に近づいていってしまい、追突事故になってしまいます。
たいした故障でなくて不用意に夜間に路肩へ停車することは、とても危険な行為です。
移動ができるならば、P.A.や高速バス停留所など道幅が広くて明らかに停車している車と分かる場所で停車するようにしましょう。
さて、高速道路上で故障・事故などで停車せざるをえないときは、後続車に異変を明確に伝えるための行動が必要になります。
もっとも手っ取り早いのは、ハザードランプ(非常警告灯)です。
非常時には、まずとにかくハザードを点けることが大切です。
ハザードを点けてさらに余裕があれば、発煙筒をつけましょう。
発煙筒・発光筒は、明らかに普段とは違う光を放つので、後続車へ危険を知らせるのには、とても有効な手段です。
以前もいいましたが、決して値段の高いものではないので、安全のために積極的に使うべきです。
また不用意に車から降りると、後続車にひかれてしまう可能性があります。
降りる前に後続車に分かるよう、窓を開けて発煙筒をつけ車の外へ見せながら、発煙筒を持ったまま車から降りるようにします。
車が動かなくてドアも歪んで降りれないときでも、発煙筒をつけて車の外の後方へ放り投げておくだけでも、かなり有効といえます。
確実に後続車に危険を知らせるためには、できれば2、3本発煙筒を車載しておくと良いと思います。
続いて、深夜・未明の暗い中で高速を走るときには、何に気を付けて走ると良いのでしょう?
夜間、不意な故障・事故車や落下物などをいち早く見つけるためには、何をするべきか?
答えは、ライトのハイビーム(遠目)を多用することです。
結構皆さん知らないようですが、夜間安全に車を走らせるためには、ライトは常にハイビームというのが基本となります。
夜間暗いとき、本来はハイビームのまま走り、対向車や他の車、歩行者や自転車などがいるときにロービーム(近目)にするのが、夜間走行の本来の走り方です。
ハイビームは、最低100m先のものが認識できる明るさが備わっています。
一方ロービームは認識できる距離が30~50m以下と、ハイビームの半分以下となってしまいます。
高速道路では、おおかた100km/h前後のスピードで走る車が多く、100km/hでの制動距離(急ブレーキで停まるときに必要な距離)は普通自動車で約100mくらいとされます。
つまり、高速では最低100m先の状況が分かっていないと危険がともなう可能性があり、すなわち夜間の高速道路ではライトは常にハイビームでないと安全性が十分ではないといえるのです。
とはいってもなかなかハイビームは使いづらい、という人もいるかと思います。
そういうときは、普段ロービームにしておいて、たまにこまめにハイビームにするようにすると良いと思います。
先が真っ暗で見えづらいとき、カーブを抜けた先、路上に何か違和感を覚えたときなど、気になることがあったときは積極的にハイビームにしましょう。
数秒ハイビームにして何もないのを確認したあと、ロービームにして、また見づらいとか気になるときはハイビームにする。
面倒くさいかもしれませんが、ちかちかと光の当て方を何度も変えたほうが、路上の変化や状況の把握がしやすい効果があり、安全面で有効です。
あまり周りを気にせず、けれど周りに迷惑をかけすぎない程度で、どんどんとハイビームを使ってほしいと思います。(周囲に車がいる時は迷惑・危険となる時もあるので、ハイビームはなるべく使わないようにしましょう)
また一般道においても、市街地を走るときは常に周りに車や歩行者がいるのでロービームが基本かと思いますが、車が少ない道や深夜・未明ならば、対向車がいないときなどでは積極的にハイビームを使うようにしましょう。
以上のように、地方の高速道路の深夜・未明の走行は、都会の高速や昼間に比べると、危険性が思ったより高くなります。
「空いてるから楽だ」という人もいるし、割引もあるのでわざと深夜・未明の時間帯を選ぶ人もいますが、安全面でいえば昼間よりも危険性が高い、ということを認識しておく必要があります。
そういう地方の高速の運転に慣れていれば良いのですが、まだ慣れていない人にはそれなりに難しいかもしれません。
特に初心者の人などは、なるべく深夜・未明の時間は避けた方が良いかと思います。
まずはともあれ、深夜・未明の高速道路の危険性を、知っておいてほしいと思います。
近ごろ、長野県含め地方の高速道路で、夜間の痛ましい事故が続いています。
それらの重大事故には共通点があると思います。
ひとつは、夜間とくに深夜から未明にかけての事故であること。
もうひとつは、はじめ故障や単独事故などで路肩や走行車線にはみ出したり、または塞ぐような形で事故車両が停まり、そこに後続車が突っ込んで大きな事故となる、というものです。
これは、都会ではなく地方における高速道路上において、深夜・未明の時間だからこそ起きる事故だと考えられます。
その辺りを踏まえて、検証と対策を考えてみたいと思います。
まず、都会と地方の高速道路の違い、そして深夜・未明の時と昼間や早い時間の夜間とは何が違うのでしょうか?
平たく言ってしまうと、暗くて遠くまでしっかり見通せないことと、通行量が少なすぎて道路の状況を把握しづらいこと、です。
昼間だと、当然ながら見通しが良くきき、道路がこの先どちらに曲がっていくかとか、登り坂なのか下り坂なのかとか、道全体の交通状況を目で見て確認できます。
また道路上の落下物とか、故障・事故車がいるとかの発見も、いち早く確認ができます。
それから、都会の高速道路だと夜間でも大抵明る過ぎるくらいにずらっと道路灯があるので、夜でも道路の状況は比較的簡単に確認できます。
一方、地方・田舎の高速道路だと明かりがきちんとあるのはI.C.やP.A.、JCTなどの付近だけで、夜間は基本的にほぼ真っ暗な中で車のライトだけを頼りに走ることが多くなります。
加えて深夜・未明の時間帯は交通量が少なすぎて、逆に道路状況が把握しづらいのです。
ある程度混みあった道ならば、どこかで事故・故障車や落下物などがあっても、前を走る車の動きやブレーキのかけ方、交通の流れなどで、「この先に何かある」と判断をすることができます。
しかし、地方の高速にて深夜にほぼ真っ暗の中、自分の車一台だけで走っているような状況だと、前方に事故・故障車や落下物があっても自分の車のライトだけで判断するしかなく、気付くのがかなり遅くなってしまうのです。
暗くて閑散とした中で運転してると、道に何かあるのか自体も発見が遅くなるし、停まっている事故・故障車のライトが光っていたとしてもそれが事故や故障で停まっている車とは瞬時には判断できず、「ん?なんだろう?」と思っている間に近づきすぎてしまい(相手は止まっていて自分は100km/hくらいで走っているので、あっという間に近づいてしまいます)、「まずい!」と気付いたときにはもう遅く、追突したり避けようとしてさらなる多重事故となってしまうのです。
特に、夜間故障などで普通に路肩に停めている場合、後続車は閑散とした暗い中を走っていて少し集中力も低下してるため、路肩にただ停車してる車のライトを見ても一目で停まっている車とは認識できず、普通に前を走っている先行車と勘違いしてしまう時があります。
その勘違いをすると、無意識に路肩の停車してる車の後ろについて走ろうと、停止してる車に近づいていってしまい、追突事故になってしまいます。
たいした故障でなくて不用意に夜間に路肩へ停車することは、とても危険な行為です。
移動ができるならば、P.A.や高速バス停留所など道幅が広くて明らかに停車している車と分かる場所で停車するようにしましょう。
さて、高速道路上で故障・事故などで停車せざるをえないときは、後続車に異変を明確に伝えるための行動が必要になります。
もっとも手っ取り早いのは、ハザードランプ(非常警告灯)です。
非常時には、まずとにかくハザードを点けることが大切です。
ハザードを点けてさらに余裕があれば、発煙筒をつけましょう。
発煙筒・発光筒は、明らかに普段とは違う光を放つので、後続車へ危険を知らせるのには、とても有効な手段です。
以前もいいましたが、決して値段の高いものではないので、安全のために積極的に使うべきです。
また不用意に車から降りると、後続車にひかれてしまう可能性があります。
降りる前に後続車に分かるよう、窓を開けて発煙筒をつけ車の外へ見せながら、発煙筒を持ったまま車から降りるようにします。
車が動かなくてドアも歪んで降りれないときでも、発煙筒をつけて車の外の後方へ放り投げておくだけでも、かなり有効といえます。
確実に後続車に危険を知らせるためには、できれば2、3本発煙筒を車載しておくと良いと思います。
続いて、深夜・未明の暗い中で高速を走るときには、何に気を付けて走ると良いのでしょう?
夜間、不意な故障・事故車や落下物などをいち早く見つけるためには、何をするべきか?
答えは、ライトのハイビーム(遠目)を多用することです。
結構皆さん知らないようですが、夜間安全に車を走らせるためには、ライトは常にハイビームというのが基本となります。
夜間暗いとき、本来はハイビームのまま走り、対向車や他の車、歩行者や自転車などがいるときにロービーム(近目)にするのが、夜間走行の本来の走り方です。
ハイビームは、最低100m先のものが認識できる明るさが備わっています。
一方ロービームは認識できる距離が30~50m以下と、ハイビームの半分以下となってしまいます。
高速道路では、おおかた100km/h前後のスピードで走る車が多く、100km/hでの制動距離(急ブレーキで停まるときに必要な距離)は普通自動車で約100mくらいとされます。
つまり、高速では最低100m先の状況が分かっていないと危険がともなう可能性があり、すなわち夜間の高速道路ではライトは常にハイビームでないと安全性が十分ではないといえるのです。
とはいってもなかなかハイビームは使いづらい、という人もいるかと思います。
そういうときは、普段ロービームにしておいて、たまにこまめにハイビームにするようにすると良いと思います。
先が真っ暗で見えづらいとき、カーブを抜けた先、路上に何か違和感を覚えたときなど、気になることがあったときは積極的にハイビームにしましょう。
数秒ハイビームにして何もないのを確認したあと、ロービームにして、また見づらいとか気になるときはハイビームにする。
面倒くさいかもしれませんが、ちかちかと光の当て方を何度も変えたほうが、路上の変化や状況の把握がしやすい効果があり、安全面で有効です。
あまり周りを気にせず、けれど周りに迷惑をかけすぎない程度で、どんどんとハイビームを使ってほしいと思います。(周囲に車がいる時は迷惑・危険となる時もあるので、ハイビームはなるべく使わないようにしましょう)
また一般道においても、市街地を走るときは常に周りに車や歩行者がいるのでロービームが基本かと思いますが、車が少ない道や深夜・未明ならば、対向車がいないときなどでは積極的にハイビームを使うようにしましょう。
以上のように、地方の高速道路の深夜・未明の走行は、都会の高速や昼間に比べると、危険性が思ったより高くなります。
「空いてるから楽だ」という人もいるし、割引もあるのでわざと深夜・未明の時間帯を選ぶ人もいますが、安全面でいえば昼間よりも危険性が高い、ということを認識しておく必要があります。
そういう地方の高速の運転に慣れていれば良いのですが、まだ慣れていない人にはそれなりに難しいかもしれません。
特に初心者の人などは、なるべく深夜・未明の時間は避けた方が良いかと思います。
まずはともあれ、深夜・未明の高速道路の危険性を、知っておいてほしいと思います。
2017/02/08
(この記事は私が過去 2012.8.23. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です。一部に追記あり)
先日も高速道路で痛ましい事故が起きました。
何とも残念です。
この記事が役に立つことを信じて、さらに続けていこうと思います。
さて、高速を走るための前準備を考えていこうと思います。
まずは、高速道路を走るにあたって、安全上載せておかなくてはならないものがあります。
何だか分かりますか?
答えは停止表示器材です。
後方からくる車に「この先に車が停止してる」と知らせるための器材です。
形を説明すると、一辺が50cmくらいの赤い正三角形のものです。
三角表示器材ともいいます。
反射材でできていたり、電池で三角形が光るものがあり、たたんでしまえるものもあります。
さて、高速を走るには停止表示器材を車に載せておかなければなりません。
私の記憶では、必ず載せなければならなかったものだったと思います。(違ったかな?汗)
みなさん、停止表示器材、車に載っていますか?
たぶん載せていない方も、結構多いと思います。
昔は車を買った時に結構ついていたんですが、今はほぼついていません。
ディーラーやホームセンターなどで自分で買う必要があります。
荷室など調べてみて、載ってない方は、これを機に買って車に載せておくことをお薦めします。
高速道路でも一般道でも、トラブルなどで路上停車しなくてはならないとき、かなり役に立つものです。
実際使うときは、車の後方30~50mくらい離れた路上に置いて使用します。(一般道の時は10~20mくらい後方)
また発煙筒(発光筒)が載っているか、そして使用期限が切れていないか、確認しておきましょう。
こちらもトラブルなどで路上停車するときは、とても役に立ちます。
特に夜間においては、非常に高い効果を発揮します。
値段もそんなに高いものではないので、ちょっとしたトラブルでも、もったいぶらずがんがん積極的?に使いましょう。
安全が第一です。
無かったり期限切れの時は、買ってきてちゃんと載せておきましょう。
ホームセンターなどで売っています。
使うときは、停止表示器材と併用し、停止表示器材と同じように車の後方に30~50m間隔で離して置いていくと良いです。
あと2019年から、高速のチェーン走行規制時にはチェーンを必ず装着しなければ走行できない区間ができました。
長野県でいうと、上信越道の新潟県境と群馬県境、中央道の岐阜県境と山梨以東などの坂道のある山間降雪区間です。
この区間は、スタッドレスタイヤ・スノータイヤを装着していても、降雪時にチェーン規制が出た時は、チェーンがなければ走行できません。(スタッドレスタイヤの上にさらにチェーンを着けます)
降雪が予想される時期にこの区間を走行する場合は、事前にチェーンを用意しておかないと、強制的に高速道路を下されてしまう可能性があります。
冬に高速道路を使用する可能性がある方は、チェーンを準備しておく必要があると思います。
さてさらに高速の前準備として、最低限の車の点検をしておくと良いでしょう。
車の免許を取るときに、教習所でやりましたよね?
それ以来一度もやったことない、という人も多いと思います。
本当は毎日乗る前にやらなくてはいけないのですが(私も正直やってません汗)、高速道路を使って、長い距離を普段より速いスピードで走るときなどは、良い機会ですから安全のためにきちんと点検しておきましょう。
ボンネット(エンジンルーム)を開けて、ラジエータ液(冷却水)量とエンジンオイル量、ブレーキオイルとパワステオイル(電動パワステのときはありません)の量、ウォッシャー液量とベルト類の確認。
次にタイヤの外見・溝と空気圧をチェック、あとワイパーゴムの状態とライト類がきちんと灯くか、確認しましょう。
高速を走る上で個人的に一番気を付けるべきだと思うのは、ラジエータ液量とタイヤの空気圧です。
ラジエータ液は冷却水のことで、文字通りエンジンの熱を冷やす重要な役割があります。
基本的にはただの水なので、放っておいても少しずつ減っていくものです。
長く確認してないと結構減っていて、そういうときに高速(特に夏場)を走ったりすると、オーバーヒートをしてしまう事があります。
液量が上限と下限の間の適正量か確認し、もし減っていたら、市販の冷却水補充液を買ってきて足すか、水道水を足しておきましょう。
なお市販の補充液を足すときは、色を間違えないように。
トヨタ系は赤色、日産系は青色で、もし混ぜてしまうと黒くなってしまいます。(性能的には問題ありませんが、整備上に問題があり、最終的に後日車検時等に全量交換となってしまいます)
冷却水を買う前に、ボンネットを開けてよく色を確認しておきましょう。
タイヤの空気圧は、運転席ドアを開けた付近に書いてある適正空気圧量を見て、調整しておきましょう。
セルフでないガソリンスタンドで「高速を走るので、タイヤの空気圧を見てください」といえば、無料で点検してくれます。
余裕があれば、空気圧を少し高めにするのが良いです。
割合的には1割増し、数字的には10~20kPaくらい上げても、タイヤ的には問題はありません。
ただ、若干操作性や乗り心地が変わるので、気になるようでしたら適正値に戻しましょう。
また、秋・冬に向かっていく時期だと、タイヤの空気圧は温度に応じて下がっていく傾向があるので、気を付けてください。
外気温が下がってくるので、必然的に空気圧が下がるわけです。
空気圧が下がると、高速走行ではバースト(破裂)が起きやすくなります。
この先涼しくなっていくようなシーズンには、まめに空気圧チェックすることをお薦めします。
さて、前準備としてはあとひとつ。
正しい姿勢でシートに座ることと、正しく全席でシートベルトを締めること、です。
車が走行するにあたり、乗員がもっとも安全なのは、シートにきちんと座り、しっかりシートベルトを締めることです。
以前の記事で取り上げたので、詳細は省きますが、だいたい下の通りです。
・シートのリクライニングは倒しすぎない(起こし過ぎかな?と思うくらいが良い)
・シート前後の位置はハンドルを握る腕が伸び切るようではダメ(これも近いかな?と思うくらいが良い)
・シートの深いところへ腰骨をぐっと押しつけるように座る
・背もたれへはベタッと背中を付けない(肩甲骨辺りまで)
・シートベルトは、腰は腰骨からへその下を通るようになるべく下の方へ、肩は鎖骨でなくその外側を通るようにする
・腰のベルトは若干きつめに、肩はきつくない程度に(ゆる過ぎはダメです)
・お子さんでベルトの肩の位置が合わない、特に首にかかってしまうような場合は、必ずチャイルドシートやジュニアシートを使うこと
以上です。
何度も言いますが、車が走行するにあたって、乗員はシートにきちんと座ってきちんとシートベルトを締めていることがもっとも安全で、事故にあったときの生存率も高いのです。
高速道路ならなおさらだし、今は高速は全席シートベルト着用が義務付けられています。
タクシーやバスなんかだと、ベルトを締めないお客さんもまだ多いそうです。
でもはっきり言わせてもらえば、死にたくなかったらシートベルトをちゃんと締めるべきです。
近年の高速における事故は、トラックやバスなど大型車による事故が多くなっています。
つまり事故自体が、規模の大きい悲惨な事故になりやすいということ。
自分の乗った車が事故を起こさなくても、大型車がからんだ大事故に巻き込まれてしまうかもしれない。
自分の身は自分で守る、という観点から言えば、タクシーでもバスでも、自分の車でも友達の車でも、シートベルトをきちんと締めて車に乗ることが、とても大事です。
また、たまにミニバンとかの後部座席などで、子供がシートに座らずベルトも締めずに車内をうろちょろしている車を見かけますが、絶対にやめてください。
子供が泣こうがわめこうが、安全のためにシートにくくり付けるくらいの気持ちで、車に乗せてください。
それが、子供にとってもっとも安全なことだからであり、親である大人の責任です。
育児に厳しい他国だと、子供にシートベルトを締めないで車に乗せたら育児放棄と幼児虐待で捕まります。
シートに座ってベルトを締めなければ、万一の時に子供の命を守ることはできません。
ほんとに、肝に銘じてください。
お願いします。
前準備としてはこんなところでしょうか。
また気付いたことがあったら加筆・修正していきたいと思います。
参考にしてみてください。
m(_ _)m
先日も高速道路で痛ましい事故が起きました。
何とも残念です。
この記事が役に立つことを信じて、さらに続けていこうと思います。
さて、高速を走るための前準備を考えていこうと思います。
まずは、高速道路を走るにあたって、安全上載せておかなくてはならないものがあります。
何だか分かりますか?
答えは停止表示器材です。
後方からくる車に「この先に車が停止してる」と知らせるための器材です。
形を説明すると、一辺が50cmくらいの赤い正三角形のものです。
三角表示器材ともいいます。
反射材でできていたり、電池で三角形が光るものがあり、たたんでしまえるものもあります。
さて、高速を走るには停止表示器材を車に載せておかなければなりません。
私の記憶では、必ず載せなければならなかったものだったと思います。(違ったかな?汗)
みなさん、停止表示器材、車に載っていますか?
たぶん載せていない方も、結構多いと思います。
昔は車を買った時に結構ついていたんですが、今はほぼついていません。
ディーラーやホームセンターなどで自分で買う必要があります。
荷室など調べてみて、載ってない方は、これを機に買って車に載せておくことをお薦めします。
高速道路でも一般道でも、トラブルなどで路上停車しなくてはならないとき、かなり役に立つものです。
実際使うときは、車の後方30~50mくらい離れた路上に置いて使用します。(一般道の時は10~20mくらい後方)
また発煙筒(発光筒)が載っているか、そして使用期限が切れていないか、確認しておきましょう。
こちらもトラブルなどで路上停車するときは、とても役に立ちます。
特に夜間においては、非常に高い効果を発揮します。
値段もそんなに高いものではないので、ちょっとしたトラブルでも、もったいぶらずがんがん積極的?に使いましょう。
安全が第一です。
無かったり期限切れの時は、買ってきてちゃんと載せておきましょう。
ホームセンターなどで売っています。
使うときは、停止表示器材と併用し、停止表示器材と同じように車の後方に30~50m間隔で離して置いていくと良いです。
あと2019年から、高速のチェーン走行規制時にはチェーンを必ず装着しなければ走行できない区間ができました。
長野県でいうと、上信越道の新潟県境と群馬県境、中央道の岐阜県境と山梨以東などの坂道のある山間降雪区間です。
この区間は、スタッドレスタイヤ・スノータイヤを装着していても、降雪時にチェーン規制が出た時は、チェーンがなければ走行できません。(スタッドレスタイヤの上にさらにチェーンを着けます)
降雪が予想される時期にこの区間を走行する場合は、事前にチェーンを用意しておかないと、強制的に高速道路を下されてしまう可能性があります。
冬に高速道路を使用する可能性がある方は、チェーンを準備しておく必要があると思います。
さてさらに高速の前準備として、最低限の車の点検をしておくと良いでしょう。
車の免許を取るときに、教習所でやりましたよね?
それ以来一度もやったことない、という人も多いと思います。
本当は毎日乗る前にやらなくてはいけないのですが(私も正直やってません汗)、高速道路を使って、長い距離を普段より速いスピードで走るときなどは、良い機会ですから安全のためにきちんと点検しておきましょう。
ボンネット(エンジンルーム)を開けて、ラジエータ液(冷却水)量とエンジンオイル量、ブレーキオイルとパワステオイル(電動パワステのときはありません)の量、ウォッシャー液量とベルト類の確認。
次にタイヤの外見・溝と空気圧をチェック、あとワイパーゴムの状態とライト類がきちんと灯くか、確認しましょう。
高速を走る上で個人的に一番気を付けるべきだと思うのは、ラジエータ液量とタイヤの空気圧です。
ラジエータ液は冷却水のことで、文字通りエンジンの熱を冷やす重要な役割があります。
基本的にはただの水なので、放っておいても少しずつ減っていくものです。
長く確認してないと結構減っていて、そういうときに高速(特に夏場)を走ったりすると、オーバーヒートをしてしまう事があります。
液量が上限と下限の間の適正量か確認し、もし減っていたら、市販の冷却水補充液を買ってきて足すか、水道水を足しておきましょう。
なお市販の補充液を足すときは、色を間違えないように。
トヨタ系は赤色、日産系は青色で、もし混ぜてしまうと黒くなってしまいます。(性能的には問題ありませんが、整備上に問題があり、最終的に後日車検時等に全量交換となってしまいます)
冷却水を買う前に、ボンネットを開けてよく色を確認しておきましょう。
タイヤの空気圧は、運転席ドアを開けた付近に書いてある適正空気圧量を見て、調整しておきましょう。
セルフでないガソリンスタンドで「高速を走るので、タイヤの空気圧を見てください」といえば、無料で点検してくれます。
余裕があれば、空気圧を少し高めにするのが良いです。
割合的には1割増し、数字的には10~20kPaくらい上げても、タイヤ的には問題はありません。
ただ、若干操作性や乗り心地が変わるので、気になるようでしたら適正値に戻しましょう。
また、秋・冬に向かっていく時期だと、タイヤの空気圧は温度に応じて下がっていく傾向があるので、気を付けてください。
外気温が下がってくるので、必然的に空気圧が下がるわけです。
空気圧が下がると、高速走行ではバースト(破裂)が起きやすくなります。
この先涼しくなっていくようなシーズンには、まめに空気圧チェックすることをお薦めします。
さて、前準備としてはあとひとつ。
正しい姿勢でシートに座ることと、正しく全席でシートベルトを締めること、です。
車が走行するにあたり、乗員がもっとも安全なのは、シートにきちんと座り、しっかりシートベルトを締めることです。
以前の記事で取り上げたので、詳細は省きますが、だいたい下の通りです。
・シートのリクライニングは倒しすぎない(起こし過ぎかな?と思うくらいが良い)
・シート前後の位置はハンドルを握る腕が伸び切るようではダメ(これも近いかな?と思うくらいが良い)
・シートの深いところへ腰骨をぐっと押しつけるように座る
・背もたれへはベタッと背中を付けない(肩甲骨辺りまで)
・シートベルトは、腰は腰骨からへその下を通るようになるべく下の方へ、肩は鎖骨でなくその外側を通るようにする
・腰のベルトは若干きつめに、肩はきつくない程度に(ゆる過ぎはダメです)
・お子さんでベルトの肩の位置が合わない、特に首にかかってしまうような場合は、必ずチャイルドシートやジュニアシートを使うこと
以上です。
何度も言いますが、車が走行するにあたって、乗員はシートにきちんと座ってきちんとシートベルトを締めていることがもっとも安全で、事故にあったときの生存率も高いのです。
高速道路ならなおさらだし、今は高速は全席シートベルト着用が義務付けられています。
タクシーやバスなんかだと、ベルトを締めないお客さんもまだ多いそうです。
でもはっきり言わせてもらえば、死にたくなかったらシートベルトをちゃんと締めるべきです。
近年の高速における事故は、トラックやバスなど大型車による事故が多くなっています。
つまり事故自体が、規模の大きい悲惨な事故になりやすいということ。
自分の乗った車が事故を起こさなくても、大型車がからんだ大事故に巻き込まれてしまうかもしれない。
自分の身は自分で守る、という観点から言えば、タクシーでもバスでも、自分の車でも友達の車でも、シートベルトをきちんと締めて車に乗ることが、とても大事です。
また、たまにミニバンとかの後部座席などで、子供がシートに座らずベルトも締めずに車内をうろちょろしている車を見かけますが、絶対にやめてください。
子供が泣こうがわめこうが、安全のためにシートにくくり付けるくらいの気持ちで、車に乗せてください。
それが、子供にとってもっとも安全なことだからであり、親である大人の責任です。
育児に厳しい他国だと、子供にシートベルトを締めないで車に乗せたら育児放棄と幼児虐待で捕まります。
シートに座ってベルトを締めなければ、万一の時に子供の命を守ることはできません。
ほんとに、肝に銘じてください。
お願いします。
前準備としてはこんなところでしょうか。
また気付いたことがあったら加筆・修正していきたいと思います。
参考にしてみてください。
m(_ _)m
2017/02/08
(この記事は私が過去 2012.8.15. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
さて今回からは、すこし高速道路での安全運転について主に触れていきたいと思います。
以前述べましたが、ETCが爆発的に普及したことと、土日(に偏ったあまりよくない)割引制度などのおかげで、高速を走る車がとても増えたと思います。
そして同時に、あまり高速に慣れていないドライバーが急に増えた感じを強く受けました。
それが影響しているのかいないのか不明ですが、高速道路における事故が近年増えてきているそうです。
私の知識が役に立つか分かりませんが、高速の安全運転について知っている情報を、少し発信していきたいと思います。
安全運転の参考にしてみてください。m(_ _)m
さて、高速道路上でなく一般道でもそうですが、安全運転の基本中の基本は、車間をしっかり空けること、だと思います。
車間がしっかり空いていれば、何か予期せぬことが起きてもある程度対応ができると思います。
しかしながらドライバーの多くは、車の運転に慣れ速度にも慣れてくると、ついつい車間を詰めてしまう傾向があると思います。
加えて高速道路のように、信号などが無く、車が同じ方向へ一定に流れて走る環境だと、その流れに慣れてしまい車間を空けなくても大丈夫なような錯覚になります。
さらに混雑や渋滞のように、ドライバーへストレスを与える道路状況になると、なおさら車間を詰めてしまうと思います。
なんとなく車間を詰めたくなりがちなのですが、そこを抑えて安全のためにしっかり車間をとりたいところです。
しかし、どの程度車間を空ければ良いのか、ちょっと悩むところです。
高速走行時には、制動距離(急ブレーキをかけて完全に止まるまでの距離)は当然ながら長くなります。
おおよそ制動距離については、時速40kmなら40m、時速100kmなら100m、と一定の分かりやすい法則があります。
でも実際の公道、加えて高速で走る高速道路では、距離感がつかみづらく、車間を100mにしたくてもよく分からないと思います。
たまに車間確認の標識があるところもありますが、いつでも確認できるわけではないので、少し困ります。
そこでよく言われるのが、時間で車間距離を確認する方法です。
前を行く車が、看板や道路指標などの目印になるものを通り過ぎてから「ゼロ、いち、に」と数を数えて、「に」と同時かそれ以上かかって自分の車が目印を通り過ぎるくらいが、適切な車間距離だ、と言われます。
実際海外の国では、こうやって車間距離をとるようにと教習所で教えているそうです。
この方法だと、いつでもどこでも車間距離が確認できるし、高速でも一般道でも適切な車間距離が分かります。
危なくない程度にやってみてください。
結構、役に立ちます。
真面目に?車間を空けていると、他から車線変更してくる車がきて、割り込みされた気がして気分が悪くなる、といったことをたまに聞きます。
でもそれは、あなたがちゃんと車間がとれているという証拠なのです。
逆に、自分が後ろから来る速い車に進路を譲ったり、ジャンクションなどの分岐で車線を変更しなければならないときに、十分に車間を空けていてくれている車がいれば、すごく有り難いし安全にスムーズに車線変更ができますよね。
車間をきちんとしっかり空けることは、安全な交通環境を作り出すことにつながるのです。
私たちは人間ですから、割り込みされたと不快に思うのは、致し方ないことでしょう。
しかし、車間をしっかり空けることは安全な道路状況を作り、そしてそれは巡り巡って自分と同乗者の身を守ることにつながっていきます。
また車間をしっかり空けることにより、無駄な渋滞を減らすことにも貢献できます。(実験により証明されています)
ただ車間を空けるというだけで、安全にも交通環境にもCO2削減にもつながる、まさに一石三鳥の効果があるのです。
(おおげさかもしれませんが…)
ともかく、まずはしっかり車間を空けること。
そして、空けた車間に車が入ってきても不快に思わず、また改めてしっかり車間を空けること。
やれる範囲でぜひやってみてください。
m(_ _)m
さて今回からは、すこし高速道路での安全運転について主に触れていきたいと思います。
以前述べましたが、ETCが爆発的に普及したことと、土日(に偏ったあまりよくない)割引制度などのおかげで、高速を走る車がとても増えたと思います。
そして同時に、あまり高速に慣れていないドライバーが急に増えた感じを強く受けました。
それが影響しているのかいないのか不明ですが、高速道路における事故が近年増えてきているそうです。
私の知識が役に立つか分かりませんが、高速の安全運転について知っている情報を、少し発信していきたいと思います。
安全運転の参考にしてみてください。m(_ _)m
さて、高速道路上でなく一般道でもそうですが、安全運転の基本中の基本は、車間をしっかり空けること、だと思います。
車間がしっかり空いていれば、何か予期せぬことが起きてもある程度対応ができると思います。
しかしながらドライバーの多くは、車の運転に慣れ速度にも慣れてくると、ついつい車間を詰めてしまう傾向があると思います。
加えて高速道路のように、信号などが無く、車が同じ方向へ一定に流れて走る環境だと、その流れに慣れてしまい車間を空けなくても大丈夫なような錯覚になります。
さらに混雑や渋滞のように、ドライバーへストレスを与える道路状況になると、なおさら車間を詰めてしまうと思います。
なんとなく車間を詰めたくなりがちなのですが、そこを抑えて安全のためにしっかり車間をとりたいところです。
しかし、どの程度車間を空ければ良いのか、ちょっと悩むところです。
高速走行時には、制動距離(急ブレーキをかけて完全に止まるまでの距離)は当然ながら長くなります。
おおよそ制動距離については、時速40kmなら40m、時速100kmなら100m、と一定の分かりやすい法則があります。
でも実際の公道、加えて高速で走る高速道路では、距離感がつかみづらく、車間を100mにしたくてもよく分からないと思います。
たまに車間確認の標識があるところもありますが、いつでも確認できるわけではないので、少し困ります。
そこでよく言われるのが、時間で車間距離を確認する方法です。
前を行く車が、看板や道路指標などの目印になるものを通り過ぎてから「ゼロ、いち、に」と数を数えて、「に」と同時かそれ以上かかって自分の車が目印を通り過ぎるくらいが、適切な車間距離だ、と言われます。
実際海外の国では、こうやって車間距離をとるようにと教習所で教えているそうです。
この方法だと、いつでもどこでも車間距離が確認できるし、高速でも一般道でも適切な車間距離が分かります。
危なくない程度にやってみてください。
結構、役に立ちます。
真面目に?車間を空けていると、他から車線変更してくる車がきて、割り込みされた気がして気分が悪くなる、といったことをたまに聞きます。
でもそれは、あなたがちゃんと車間がとれているという証拠なのです。
逆に、自分が後ろから来る速い車に進路を譲ったり、ジャンクションなどの分岐で車線を変更しなければならないときに、十分に車間を空けていてくれている車がいれば、すごく有り難いし安全にスムーズに車線変更ができますよね。
車間をきちんとしっかり空けることは、安全な交通環境を作り出すことにつながるのです。
私たちは人間ですから、割り込みされたと不快に思うのは、致し方ないことでしょう。
しかし、車間をしっかり空けることは安全な道路状況を作り、そしてそれは巡り巡って自分と同乗者の身を守ることにつながっていきます。
また車間をしっかり空けることにより、無駄な渋滞を減らすことにも貢献できます。(実験により証明されています)
ただ車間を空けるというだけで、安全にも交通環境にもCO2削減にもつながる、まさに一石三鳥の効果があるのです。
(おおげさかもしれませんが…)
ともかく、まずはしっかり車間を空けること。
そして、空けた車間に車が入ってきても不快に思わず、また改めてしっかり車間を空けること。
やれる範囲でぜひやってみてください。
m(_ _)m
2017/02/08
(この記事は私が過去 2012.4.21. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
近ごろ久しぶりに高速道路を走りましたが、何ていうか、、、いろんな意味で怖かったです。(;^_^A
一番感じたことは、ETCの割引のせいか、あまり高速道路に慣れていない方が多く走るようになったことです。
ETCのおかげで高速は身近になったけれど、安全で無理のない走り方をよく知らずに走っている、という車が多くなったのだと思います。
今度JAFの冊子で、改めて高速の走り方の基本的なレクチャーを連載してほしいなぁ、、。
とまあ、それはさて置き、高速を走っているとき、やや強めに雨が降ってきました。
雨天による速度規制がなされました。
が、多くの車が速度を落とすことなく、100km/h近いスピードで普通に走っていました。
きちんとスピード落として走っている車が少なかったのは、非常に残念です。
皆さん、雨の怖さをあまり知らないんだな、と思いました。
私が考えるには、高速走行において、雨は雪なみに怖い、ということです。
簡易的に路面の滑りやすさを10段階で現すとします。
10がまったく滑らない~1がつるつるに滑るとします。
色々な資料と私の経験を含めると、雨の滑りやすさは8~3、雪は5~1、といった感じです。
雨での高速走行は、全然滑らないときもあれば、簡単に滑るときがあります。
速度と路面の状況によってその滑りやすさに大きな幅があるため、その読みが結構難しい、、。
だから雨の高速道路は危険が大きいのです。
降雪の場合は、皆さん「滑る」「危ない」という意識が強いのでしょう。
雪が降り始めると多くの車がすぐ減速しはじめます。
しかし雨天の時は、近年のタイヤ技術の向上もあって「そんなに滑らない」「結構平気」と思い込んでいる人がかなり多いと思います。
確かに一般道の50km/hくらいなら、雨で滑ることはまずありません。
しかし、それ以上速い速度になってくると、状況によってスリップしやすくなってきます。
高速で走るということは、それだけ危険も大きくなりやすいことを認識しましょう。
また、路面のわだちやうねり等の雨水が溜まっているところは、非常に滑りやすくなります。
いわゆる、ハイドロプレーニング現象です。
よく起きる事故に、追越し車線から走行車線に戻ったとき、そのままつーっとスリップしていって路肩へ突っ込んでいったり、スピンしたりする事故です。
追越し(右側)車線より走行(左側)車線のほうが、トラックやバスなどの重い車がよく走るので、路面の荒れやわだちが多くなっています。
追越し車線は比較的路面の状態が良いので、雨天で100km/hくらいで走ってもそうそうスリップしたりせず、結構普通に走れます。
でも調子にのって?そのスピードのまま、荒れて水が溜まった路面の走行車線へすっと急に車線変更したりすると、上のようにつーっとそのままスリップして制御不能になり、危険な事故になります。
雨天時は、路面状況で事故が起こりやすいことを理解しておきましょう。
それから、近年流行りのエコタイヤと呼ばれる、燃費向上タイヤにも注意が必要です。
燃費が良いということは、摩擦が少なく転がり係数が良いということ。
つまり、基本はスリップしやすいものなのです。
最近のものは、燃費とグリップ性能の両立ができてきましたが、それでもウェット性能はまだまだ良くないと思います。
特に、燃費を売りにしてる近年の国産エコカーが、最初から標準で履いているタイヤは、問題ありです。
そういうタイヤは自動車メーカーがカタログ燃費を良くするためにタイヤメーカーに作らせた特注品で、燃費重視のためにウェット性能などは二の次、つまりはっきり言うとスリップしやすいタイヤなんです。
雨の高速道路を100km/h以上で激走するプ○ウスなどを見かけると、私なんかは怖くて非常にビクビクしてます。(;- -A
燃費が売りの俗にエコカーと呼ばれる国産車に乗っていて、タイヤが買った時のままの方は、特に注意していただきたいと思います。
ともかく、高速道路にて速度規制がされるということは、それなりにきちんとした意味があるのです。
「雨なんてたいしたことない」とどこかで思っている方、足元をすくわれないように気を付けてください。
速度規制が出たらスピードを落とす、これが基本です。
それから、行楽シーズンとなってきました。
車で遠くへ遊びにいく方もたくさんいらっしゃると思います。
以前も言いましたが、知らない土地、知らない道での運転は事故に遭う確率が大きくなります。
どうぞ安全運転で、無理・無茶・無駄のないようお願いします。
乗員全員がシートへ正しく座り、正しくシートベルトを締めてください。
なにとぞご自愛くださいますよう、常にディフェンシブドライブを心がけるようにお願いします。
m(_ _)m
近ごろ久しぶりに高速道路を走りましたが、何ていうか、、、いろんな意味で怖かったです。(;^_^A
一番感じたことは、ETCの割引のせいか、あまり高速道路に慣れていない方が多く走るようになったことです。
ETCのおかげで高速は身近になったけれど、安全で無理のない走り方をよく知らずに走っている、という車が多くなったのだと思います。
今度JAFの冊子で、改めて高速の走り方の基本的なレクチャーを連載してほしいなぁ、、。
とまあ、それはさて置き、高速を走っているとき、やや強めに雨が降ってきました。
雨天による速度規制がなされました。
が、多くの車が速度を落とすことなく、100km/h近いスピードで普通に走っていました。
きちんとスピード落として走っている車が少なかったのは、非常に残念です。
皆さん、雨の怖さをあまり知らないんだな、と思いました。
私が考えるには、高速走行において、雨は雪なみに怖い、ということです。
簡易的に路面の滑りやすさを10段階で現すとします。
10がまったく滑らない~1がつるつるに滑るとします。
色々な資料と私の経験を含めると、雨の滑りやすさは8~3、雪は5~1、といった感じです。
雨での高速走行は、全然滑らないときもあれば、簡単に滑るときがあります。
速度と路面の状況によってその滑りやすさに大きな幅があるため、その読みが結構難しい、、。
だから雨の高速道路は危険が大きいのです。
降雪の場合は、皆さん「滑る」「危ない」という意識が強いのでしょう。
雪が降り始めると多くの車がすぐ減速しはじめます。
しかし雨天の時は、近年のタイヤ技術の向上もあって「そんなに滑らない」「結構平気」と思い込んでいる人がかなり多いと思います。
確かに一般道の50km/hくらいなら、雨で滑ることはまずありません。
しかし、それ以上速い速度になってくると、状況によってスリップしやすくなってきます。
高速で走るということは、それだけ危険も大きくなりやすいことを認識しましょう。
また、路面のわだちやうねり等の雨水が溜まっているところは、非常に滑りやすくなります。
いわゆる、ハイドロプレーニング現象です。
よく起きる事故に、追越し車線から走行車線に戻ったとき、そのままつーっとスリップしていって路肩へ突っ込んでいったり、スピンしたりする事故です。
追越し(右側)車線より走行(左側)車線のほうが、トラックやバスなどの重い車がよく走るので、路面の荒れやわだちが多くなっています。
追越し車線は比較的路面の状態が良いので、雨天で100km/hくらいで走ってもそうそうスリップしたりせず、結構普通に走れます。
でも調子にのって?そのスピードのまま、荒れて水が溜まった路面の走行車線へすっと急に車線変更したりすると、上のようにつーっとそのままスリップして制御不能になり、危険な事故になります。
雨天時は、路面状況で事故が起こりやすいことを理解しておきましょう。
それから、近年流行りのエコタイヤと呼ばれる、燃費向上タイヤにも注意が必要です。
燃費が良いということは、摩擦が少なく転がり係数が良いということ。
つまり、基本はスリップしやすいものなのです。
最近のものは、燃費とグリップ性能の両立ができてきましたが、それでもウェット性能はまだまだ良くないと思います。
特に、燃費を売りにしてる近年の国産エコカーが、最初から標準で履いているタイヤは、問題ありです。
そういうタイヤは自動車メーカーがカタログ燃費を良くするためにタイヤメーカーに作らせた特注品で、燃費重視のためにウェット性能などは二の次、つまりはっきり言うとスリップしやすいタイヤなんです。
雨の高速道路を100km/h以上で激走するプ○ウスなどを見かけると、私なんかは怖くて非常にビクビクしてます。(;- -A
燃費が売りの俗にエコカーと呼ばれる国産車に乗っていて、タイヤが買った時のままの方は、特に注意していただきたいと思います。
ともかく、高速道路にて速度規制がされるということは、それなりにきちんとした意味があるのです。
「雨なんてたいしたことない」とどこかで思っている方、足元をすくわれないように気を付けてください。
速度規制が出たらスピードを落とす、これが基本です。
それから、行楽シーズンとなってきました。
車で遠くへ遊びにいく方もたくさんいらっしゃると思います。
以前も言いましたが、知らない土地、知らない道での運転は事故に遭う確率が大きくなります。
どうぞ安全運転で、無理・無茶・無駄のないようお願いします。
乗員全員がシートへ正しく座り、正しくシートベルトを締めてください。
なにとぞご自愛くださいますよう、常にディフェンシブドライブを心がけるようにお願いします。
m(_ _)m
2017/02/08
(この記事は私が過去 2012.2.26. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
今回の安全運転の話は、追い越しについてです。
追い越し、正確には車線変更を伴う追い越しは、常に危険をともなうものです。
特に片側一車線の道では、対向車線に出て追い越しをするのでさらに危険です。
とは言っても、危ないから追い越しなんて滅多にやらない、という方もいるでしょう。
でも追い越しとは、前を走っている遅い車を追い越すことだけではありません。
路肩に路上駐車している車などを対向車線へはみ出しつつ抜いていくのも、追い越しとなります。
こっちなら、皆さん日常的にしていると思いますので、今回は駐停車の追い越しの話です。
松本では狭い片側一車線の道が多いため、そういう道路での路上駐車は車線をふさぐようにしか駐車できないため、後ろから来る車は車線を越えて追い越しをせざるをえません。
対向車の動き・流れを見て、タイミング良く追い越しをするのですが…。
ここでも信州人・松本人の間違った地方ルールが見られます。
追い越しをする先頭の車は、危険が無いようタイミング見て追い越しをしてる(はずな)のですが、その後続の車がろくに前方の安全確認もせずに、ぞろぞろと何台もついてくるのです。
仮に対向車が来ていても、「ついて行っちゃえ」、「先に行ったもん勝ち」、のような感じで、交通の流れを無視して次々に突っ込んで来ます。
そのため、対向車の流れが乱れ、本来は譲らなくても良いのに対向車は減速・停車せざるをえません。
そのせいで渋滞の原因にもなり、総合的に地球環境にもよろしくない。
とにかく、無理矢理ぞろぞろ何台も続いて飛び出し来るので、非常に危険だし明らかに道交法違反です。
またぞろぞろ連なってくる車の多くが、ただ前の車について行ってるだけだと思われ、さらに問題です。
自分の車の安全を自分自身で十分確認もせず、ただ前の車についていくという行為は、他人任せであり、ハンドルを握るドライバーとして軽率で問題のある行動です。
自分の身は自分で守るというのは当然だし、まわりの車への配慮が足りない。
ハンドルを握った信州人・松本人の自己中心的なところが、目に見える場面です。
(でも車から降りると、皆さんおっとりとした優しい人ばっかりなんですよね。普段おっとりしてる分、ストレス溜まってるのかな汗。信州のなぞの一つです)
正しく安全な駐停車への追い越しは下の通りとなります。
路肩に駐車している車を見つけたら、先頭の時は対向車の流れと停車してる車の動きを見つつ、かならずウインカーを出し減速や停車をまじえて、タイミングを見計らって追い越しします。
二台目以降の時は、まずは減速して前走車との車間を広くとります。
車間をとると、視野が広がり対向車や前走車の動きふくめ、交通全体の流れがわかりやすくなります。
また対向車などがいて、急な減速や停車が必要になっても、車間が十分ならば対応がしやすいという点もあります。
ちなみに視野については、常日頃から交通の流れの先の先まで見ることができるように、目を鍛えておきましょう。
できれば、3~5台先の車の動きや流れが見えるようになっておくと、スマートでスムーズな運転ができるようになります。
次に追い越しをするタイミングを見計らうのですが、先に追い越す車のせいでやはり対向車が見づらいときがあります。
安全確認のコツとしては、先に述べたとおり、まずはウインカーを必ず出して減速をすること、そして車間を十分とることです。
そして前走車のウインドウ(リア~フロント)を通して、その先の対向車線を見ます。
またミニバンやトラックなどで見えないときは、前の車が追い越している最中(抜く車の横に並んでるとき)や、前の車が追い越し終わって元の車線に戻るときなど、見ようと思えば車と車の間から対向車を見ることは十分に可能です。
そうやって、自分の目で安全をしっかり確認して、それから追い越しをします。
安全確認は自分自身でしっかりすること、他人任せは絶対にいけません。
もし対向車がいたならば、必ず停車すること。
この場合の優先は、指定された車線を通常に走っている、対向車です。
対向車は優先的に譲らなくてはいけません。
対向車を減速させたり停止させる行動は、一番やってはいけないことだと、認識しましょう。
あと、追い越すときはウインカーを必ず出します。
周りに「追い越しします」という合図になるし、車線変更時には必ず出さなくてはならないと、法律で決まっています。
それと、駐車している車の動きにも注意してください。
急にドアが開いて人が降りてきたり、発進しだしたりすることがあるからです。
(気を付けることが、たくさんあります。そこがドライビングの奥が深いところです)
とにかくも、安全は自分自身で確認し、自分で確保することを忘れてはいけません。
事故など何かあっても、ついていった前の車が責任を取ってくれることは無いのです。
自分の身は自分で守る、ディフェンシブドライブを心がけていきましょう。
今回の安全運転の話は、追い越しについてです。
追い越し、正確には車線変更を伴う追い越しは、常に危険をともなうものです。
特に片側一車線の道では、対向車線に出て追い越しをするのでさらに危険です。
とは言っても、危ないから追い越しなんて滅多にやらない、という方もいるでしょう。
でも追い越しとは、前を走っている遅い車を追い越すことだけではありません。
路肩に路上駐車している車などを対向車線へはみ出しつつ抜いていくのも、追い越しとなります。
こっちなら、皆さん日常的にしていると思いますので、今回は駐停車の追い越しの話です。
松本では狭い片側一車線の道が多いため、そういう道路での路上駐車は車線をふさぐようにしか駐車できないため、後ろから来る車は車線を越えて追い越しをせざるをえません。
対向車の動き・流れを見て、タイミング良く追い越しをするのですが…。
ここでも信州人・松本人の間違った地方ルールが見られます。
追い越しをする先頭の車は、危険が無いようタイミング見て追い越しをしてる(はずな)のですが、その後続の車がろくに前方の安全確認もせずに、ぞろぞろと何台もついてくるのです。
仮に対向車が来ていても、「ついて行っちゃえ」、「先に行ったもん勝ち」、のような感じで、交通の流れを無視して次々に突っ込んで来ます。
そのため、対向車の流れが乱れ、本来は譲らなくても良いのに対向車は減速・停車せざるをえません。
そのせいで渋滞の原因にもなり、総合的に地球環境にもよろしくない。
とにかく、無理矢理ぞろぞろ何台も続いて飛び出し来るので、非常に危険だし明らかに道交法違反です。
またぞろぞろ連なってくる車の多くが、ただ前の車について行ってるだけだと思われ、さらに問題です。
自分の車の安全を自分自身で十分確認もせず、ただ前の車についていくという行為は、他人任せであり、ハンドルを握るドライバーとして軽率で問題のある行動です。
自分の身は自分で守るというのは当然だし、まわりの車への配慮が足りない。
ハンドルを握った信州人・松本人の自己中心的なところが、目に見える場面です。
(でも車から降りると、皆さんおっとりとした優しい人ばっかりなんですよね。普段おっとりしてる分、ストレス溜まってるのかな汗。信州のなぞの一つです)
正しく安全な駐停車への追い越しは下の通りとなります。
路肩に駐車している車を見つけたら、先頭の時は対向車の流れと停車してる車の動きを見つつ、かならずウインカーを出し減速や停車をまじえて、タイミングを見計らって追い越しします。
二台目以降の時は、まずは減速して前走車との車間を広くとります。
車間をとると、視野が広がり対向車や前走車の動きふくめ、交通全体の流れがわかりやすくなります。
また対向車などがいて、急な減速や停車が必要になっても、車間が十分ならば対応がしやすいという点もあります。
ちなみに視野については、常日頃から交通の流れの先の先まで見ることができるように、目を鍛えておきましょう。
できれば、3~5台先の車の動きや流れが見えるようになっておくと、スマートでスムーズな運転ができるようになります。
次に追い越しをするタイミングを見計らうのですが、先に追い越す車のせいでやはり対向車が見づらいときがあります。
安全確認のコツとしては、先に述べたとおり、まずはウインカーを必ず出して減速をすること、そして車間を十分とることです。
そして前走車のウインドウ(リア~フロント)を通して、その先の対向車線を見ます。
またミニバンやトラックなどで見えないときは、前の車が追い越している最中(抜く車の横に並んでるとき)や、前の車が追い越し終わって元の車線に戻るときなど、見ようと思えば車と車の間から対向車を見ることは十分に可能です。
そうやって、自分の目で安全をしっかり確認して、それから追い越しをします。
安全確認は自分自身でしっかりすること、他人任せは絶対にいけません。
もし対向車がいたならば、必ず停車すること。
この場合の優先は、指定された車線を通常に走っている、対向車です。
対向車は優先的に譲らなくてはいけません。
対向車を減速させたり停止させる行動は、一番やってはいけないことだと、認識しましょう。
あと、追い越すときはウインカーを必ず出します。
周りに「追い越しします」という合図になるし、車線変更時には必ず出さなくてはならないと、法律で決まっています。
それと、駐車している車の動きにも注意してください。
急にドアが開いて人が降りてきたり、発進しだしたりすることがあるからです。
(気を付けることが、たくさんあります。そこがドライビングの奥が深いところです)
とにかくも、安全は自分自身で確認し、自分で確保することを忘れてはいけません。
事故など何かあっても、ついていった前の車が責任を取ってくれることは無いのです。
自分の身は自分で守る、ディフェンシブドライブを心がけていきましょう。