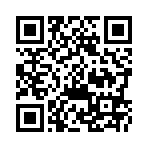2017/02/08
(この記事は私が過去 2011.11.12. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
今回の交通マナーの話は、全方向が一時停止の交差点についてです。
この全方向一時停止の交差点は、信州はじめ松本でもあまり見かけませんが、東京など都会郊外の住宅街ではわりとよく見られます。
松本にもあるはあるんですが、めったにないせいか、皆さんすごい危険な通行をしていて、危ない場所となっています。
事故が多いから、信州においてはどちらか一方が優先道路になっている交差点が多いのかもしれません。
全方向一時停止の交差点の走り方については、私も関東出身の知人に言われて、少し前に初めて知りました。(;^_^A
言われてみれば「ああ、納得」な話ですが、信州ではそうはいかないようです。
それだけ、すべて一時停止の交差点は松本人・信州人には馴染みがないし、危険な地方ルールになっている訳です。
さて、私が関東の知人から言われたのは「きちんと一時停止すれば、問題なく交互にスムーズに流れるはず」と指摘されました。
はじめ、「?」と思いました。
まったく理解できなかった情けない自分がいます。
それだけ、私も松本ルールに染まっていたわけです。
具体的に言うと、基本は先に交差点に入った車が優先となります。
(ほぼ同時に進入したときは、左方優先となります)
たとえば自分が交差点に入る前に、右からの車のほうが早く進入したとする。
その車が優先なので、一時停止して右からの車が通るのを待つ。
その待っている間に、自分は一時停止が済んでいるはずなので、右からの車が渡った次に渡れます。
その間に左右から別の車が来ていたとしても、まだ一時停止していないはずなので、その車が一時停止をしている間に自分の車が渡れるわけです。
つまり、前後方向の車が一時停止している間に左右方向の車が渡る。
次の左右の車が一時停止している間に、先に一時停止し終わっていた前後の車が渡る。
次の前後の車が一時停止している間に、先に一時停止し終わっていた左右の車が渡る。
…以下繰り返しで、交互に順番に流れていく訳です。
きちんと一時停止が出来ていれば、普通にスムーズに流れるはずなんですね。
言われてみれば、ああそうかと思いませんか?(苦笑)
では実際の信州や松本ではどうなっているか見てみましょう。
まず、皆さん一時停止をほとんどしません。
良くて徐行程度。
ていうかまじめに一時停止すると、他の車は「譲ってくれたんだ」と思い込むらしく、ここぞとばかりに他方向からの車が次から次へと一時停止もせずに突っ込んできて、金魚の糞のようにぞろぞろと渡っていきます…。(- -;
なぜか、まじめに一時停止したほうが損をする気がしてしまう。
だから皆さん多くの車が、停まったら負け(?)みたいな、きちんと一時停止をしないで「先に行かせろ」ばりに主張する車が増えてしまうのかも知れません。
そんな状況なので、優先もへったくれもなく、先に動いたもの勝ちみたいに、まるで無法状態のようになっている所もあります。
まさしく危険な場所ですね…。(;^ ^)A
ここで重要なのは、逆説的ですが本来はきちんと一時停止をし終わった車が優先されるべきだ、ということです。
きちんと一時停止をしていない車が、きちんと一時停止している車より先に交差点を渡ることは、よくよく考えてみるとありえないことなんです。
だから、ちゃんと一時停止をした車は、後から交差点に進入してくる車や一時停止をまだしていない車より先に渡れるはずなので、そこは堂々と動くべきです。
確かに、ちゃんと一時停止してない車が止まらず動き続けていると、危険を感じて自分は動けなくなってしまいます。
しかし、ここは臆せずに少しだけ動いてみましょう。
だいたいの車は、こちらが一時停止後に動きだせば、「譲ってくれてるんじゃないんだ」と気付いて(その発想が間違っているんですが…汗)相手は停まってくれます。
ただし、中には本当に一時停止をまったくせずに無理矢理渡っていく車もいますので、その辺りは事故のないよう臨機応変に対応してください。
また、松本のように狭い道がごちゃごちゃしているところでは、変則的な交差点もあり、注意が必要です。
例えば三方は一時停止で一方だけ優先されている道とか。
よく知らない道だと、全方一時停止の道だと思っていて、自分が一時停止して発進しようとしたら、実は優先道路があってそちらからの車がノンストップで走ってきて危ない目に遭う、ということがありえると思います。
一時停止が済めば自分が優先だ、と思い込み過ぎないことも大切です。
基本は、一時停止がし終わった車から渡っていく、これを肝に銘じておきましょう。
みんながきちんとちゃんと一時停止をしていれば、自然とスムーズに交互に流れていくのです。
ただし、最終的には危険のないよう、事故のないようにしなくてはなりません。
時には臨機応変に、安全第一で行きましょう。
今回の交通マナーの話は、全方向が一時停止の交差点についてです。
この全方向一時停止の交差点は、信州はじめ松本でもあまり見かけませんが、東京など都会郊外の住宅街ではわりとよく見られます。
松本にもあるはあるんですが、めったにないせいか、皆さんすごい危険な通行をしていて、危ない場所となっています。
事故が多いから、信州においてはどちらか一方が優先道路になっている交差点が多いのかもしれません。
全方向一時停止の交差点の走り方については、私も関東出身の知人に言われて、少し前に初めて知りました。(;^_^A
言われてみれば「ああ、納得」な話ですが、信州ではそうはいかないようです。
それだけ、すべて一時停止の交差点は松本人・信州人には馴染みがないし、危険な地方ルールになっている訳です。
さて、私が関東の知人から言われたのは「きちんと一時停止すれば、問題なく交互にスムーズに流れるはず」と指摘されました。
はじめ、「?」と思いました。
まったく理解できなかった情けない自分がいます。
それだけ、私も松本ルールに染まっていたわけです。
具体的に言うと、基本は先に交差点に入った車が優先となります。
(ほぼ同時に進入したときは、左方優先となります)
たとえば自分が交差点に入る前に、右からの車のほうが早く進入したとする。
その車が優先なので、一時停止して右からの車が通るのを待つ。
その待っている間に、自分は一時停止が済んでいるはずなので、右からの車が渡った次に渡れます。
その間に左右から別の車が来ていたとしても、まだ一時停止していないはずなので、その車が一時停止をしている間に自分の車が渡れるわけです。
つまり、前後方向の車が一時停止している間に左右方向の車が渡る。
次の左右の車が一時停止している間に、先に一時停止し終わっていた前後の車が渡る。
次の前後の車が一時停止している間に、先に一時停止し終わっていた左右の車が渡る。
…以下繰り返しで、交互に順番に流れていく訳です。
きちんと一時停止が出来ていれば、普通にスムーズに流れるはずなんですね。
言われてみれば、ああそうかと思いませんか?(苦笑)
では実際の信州や松本ではどうなっているか見てみましょう。
まず、皆さん一時停止をほとんどしません。
良くて徐行程度。
ていうかまじめに一時停止すると、他の車は「譲ってくれたんだ」と思い込むらしく、ここぞとばかりに他方向からの車が次から次へと一時停止もせずに突っ込んできて、金魚の糞のようにぞろぞろと渡っていきます…。(- -;
なぜか、まじめに一時停止したほうが損をする気がしてしまう。
だから皆さん多くの車が、停まったら負け(?)みたいな、きちんと一時停止をしないで「先に行かせろ」ばりに主張する車が増えてしまうのかも知れません。
そんな状況なので、優先もへったくれもなく、先に動いたもの勝ちみたいに、まるで無法状態のようになっている所もあります。
まさしく危険な場所ですね…。(;^ ^)A
ここで重要なのは、逆説的ですが本来はきちんと一時停止をし終わった車が優先されるべきだ、ということです。
きちんと一時停止をしていない車が、きちんと一時停止している車より先に交差点を渡ることは、よくよく考えてみるとありえないことなんです。
だから、ちゃんと一時停止をした車は、後から交差点に進入してくる車や一時停止をまだしていない車より先に渡れるはずなので、そこは堂々と動くべきです。
確かに、ちゃんと一時停止してない車が止まらず動き続けていると、危険を感じて自分は動けなくなってしまいます。
しかし、ここは臆せずに少しだけ動いてみましょう。
だいたいの車は、こちらが一時停止後に動きだせば、「譲ってくれてるんじゃないんだ」と気付いて(その発想が間違っているんですが…汗)相手は停まってくれます。
ただし、中には本当に一時停止をまったくせずに無理矢理渡っていく車もいますので、その辺りは事故のないよう臨機応変に対応してください。
また、松本のように狭い道がごちゃごちゃしているところでは、変則的な交差点もあり、注意が必要です。
例えば三方は一時停止で一方だけ優先されている道とか。
よく知らない道だと、全方一時停止の道だと思っていて、自分が一時停止して発進しようとしたら、実は優先道路があってそちらからの車がノンストップで走ってきて危ない目に遭う、ということがありえると思います。
一時停止が済めば自分が優先だ、と思い込み過ぎないことも大切です。
基本は、一時停止がし終わった車から渡っていく、これを肝に銘じておきましょう。
みんながきちんとちゃんと一時停止をしていれば、自然とスムーズに交互に流れていくのです。
ただし、最終的には危険のないよう、事故のないようにしなくてはなりません。
時には臨機応変に、安全第一で行きましょう。
2017/02/08
(この記事は私が過去 2011.10.17. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
秋が本格的に深まり始める10月。
この時期になると、松本では次第に教習車が公道に増えてきます。
そのほとんどは、進路の決まった学生さんたちでしょう。
毎年の風景なので、私にはひとつの風物詩のように感じています。
さて免許が取れて、晴れて自分の車を手に入れるとき、どこのどんな車が良いのでしょう?
私の独断と偏見?ですが、初心者の皆さんにアドバイスを発しておこうかと思い、この記事をアップします。
一つの参考にしていただけると良いかと思います。
さて、初心者ドライバーで初めての自分の車は、やはり「良い車」に乗るべきでしょう。
私の定義する良い車とは、自然なフィーリングと素直な素質の車です。
……分かりにくいですね(苦笑)。
例としては、ドライバーがこのくらい加速しようとアクセルを踏んだとき、ドライバーが思っていたとおりに加速していく。
ドライバーがこのくらい曲がりたいと思ってハンドルを切ったときに、思っていたとおりに車が曲がっていく。
道路の段差や路面の変化をハンドルに素直に伝えてくれる。
……こんな感じの車です。
「何、そんなの当たり前のことでしょ」という声が聞こえてきそうですが、その当たり前がきちんと出来ている車は意外と少ないのです。
最近の車はどれも良くできているから、どれを選んでも同じ…と考えている方、それは違います。
私に言わせてもらえば、最近の車は私が言いたい「良い車」からはどんどん悪くなっています。
逆に良い車を探すのが、とても難しくなっていると感じます。
また、人間というのはとても適応能力の高い生物で、例えばあまり出来のよろしくない車に乗ったとしても、それに体が慣れてしまい、悪いなりに合わせた運転技術を身につけていきます。
良くない車に合わせた、くせのある技術を身につけてしまうと、あとあと修正するのが難しくなります。
それが、初心者ならばなおさらです。
だから初めての車は、よくよく考えて良い車を選んでほしいのです。
初心者ドライバーが初めて乗る車は、なるべく自然なフィーリングで素直な素質を持った車を選ぶべきです。
自然で素直な素質の良い車で、車のいろいろな挙動を体で覚えて自分の運転技術を向上させる。
最近は「車なんて誰でも簡単に運転できるもの」と思われがちですが、それは違います。
他の自動車やバイク、自転車、歩行者など様々に通行が行き交い、刻一刻と状況が変化する公道において、自分の身を守るとともに周りの人たちにも気を配る、真の安全運転をするには、それなりの技術、腕が必要です。
安全運転だけでも非常に奥が深い、だからドライビングは難しく、そして楽しいのです。
私も日々修業のつもりでハンドルを握っています。
自分のものにした技術は、今後の自動車生活の中で、必ず役に立ちます。
だから、安全で正しい運転技術を身につけるには、まず自然で素質の良い車に乗るべきだと考えているのです。
では、実際私が勝手に考える、初心者が選ぶべき良い車の条件を挙げていきます。
荒っぽく言うと、以下のとおりです。
1.トランスミッションがCVTの車には乗らない
2.足回りがやわらかい車を選ぶ、カーブできちんとロールする(車体が傾く)車を選ぶ
3.乗り心地が良い車は選ばない、静粛性の良すぎる車は選ばない
いやあ、自分で書いててもびっくりのすごい条件ですね(笑)。
1.のCVTは、そもそもが不自然な駆動システムだからです。
ドライバーの普通の感覚としては、アクセルを踏めばそれに応じてエンジンが吹けて回転が上がり、それに応じ速度が上がっていく…、これが自然。
しかしCVTはどんなにアクセルを踏み込んでも、踏み込んだ量に応じてエンジンの回転が上がるわけではありません。
エンジン回転はある一定のままで、速度だけがすーっと上がっていくのがCVT。
またCVTは、例えば40km/hまで加速したいと思って踏み込んでも、たいていはどんどん加速して40km/hをオーバーしてしまいます。
以前の記事で述べたとおり、CVTは強く加速しようと踏み込むと延々と加速していきます。
意識的にアクセルを戻さないと加速が止まりません。
CVTはアクセルの感覚と操作が不自然で、これから技術を身につけていく初心者にはあまり向かないのです。
2.の足回りがやわらかく、カーブで車体がきちんとロールする(傾く)車を選ぶというのは、その方が車の挙動が分かりやすく、技術を身につけるには良いからです。
どうも最近の日本車は、足回りが硬い車が多い。
私が推測するに、車体がロールしてふらつくのをユーザーが嫌がるからでしょう。
ふらつくと同乗者に不快感を与えます。
特に近年人気のミニバン・SUVなどは、車体が大きく背が高く重たいので、ロールして大きくふらつくことが多いのでしょう。
それを防ぐために、足回りを硬くしロールしないようにして車体がふらつくのを抑えれば、安定した走りが出来る…とメーカーは考えているんだと思います。
しかし、カーブで車体がロールするのはある意味車として当たり前だし、ロールをすることはタイヤをうまく使うために本来必要な挙動です。
私に言わせてもらえば、車がふらついて同乗者に不快感をあたえるのは、ドライバーの腕(技術)が悪いからです。
乗員の数と重量と速度、ロールの出方を考えて、カーブではそれ相応にしっかり減速してゆっくり舵を切っていき、またカーブ出口はゆっくり舵を戻していく…、そうすれば不快感を与えるロールは本来発生しません。
要は、ロールが大きく急に出ないように、ドライバーがロールの出方をコントロールしてあげるんです。
その技術がなく、しっかり減速もせず荒っぽく適当にハンドル操作するから、ふらっと大きく振られてしまうのです。
その技術を身につけるには、足回りが柔らかめでロールがきちんとする車でないと、身につきません。
どのくらいの速度でどのくらい舵を切ると、どういうロールの仕方をして、どれだけ傾くのか。
それが体感的に分かる、足が柔らかめの車だと、技術が身につきやすい。
また正しくロールする車だと、荷重移動が分かりやすく、車の挙動がつかみやすくなります。
荷重移動がわかると、どのタイヤにどれだけ負荷がかかっているか分かりやすいし、滑りだしの限界もつかみやすい。
ロールのさせ方と荷重移動が何となくでも身についていると、劇的に運転がうまくなります。
また、どんな大きさのどんな車を運転しても、その応用が使えます。
だから、初心者の方には足回りのやわらかいロールがしっかり分かる車に乗って、車の挙動を体で覚えてもらいたいのです。
3.の乗り心地の良い車、静粛性の高い車は選ばないというのは、そういう車だとタイヤから伝わる路面の状況がつかみにくくなってしまうからです。
ユーザーとしては乗り心地が良く静粛性が高いほうが、良い車だと思いがちです。
しかし、静粛性があまりに良すぎてしまうと、路面から伝わる本来必要な情報まで消してしまいます。
情報とは、タイヤからハンドルやシートへ伝わる振動などの感覚です。
例えば、小石など何か物をタイヤが踏んだときの揺れや、道の段差・うねり、路面の濡れや凍結の感覚、雪を踏む感触などなど、これらは車の運転に必要な情報です。
本当に良い車だと、ハンドルを切ったときにタイヤが向きを変えてゴムがたわむ感触も、ハンドルに伝わってきます。
でも、ユーザーは乗り心地の良さや静粛性を求めてしまうので、メーカーはそれらをとにかく良くしようと本来必要な情報もみんな消してしまう傾向があります。
また、上で述べたとおり最近は足回りが硬い車が増えてます。
本来乗り心地は、足がやわらかくないと良くならない。
足を硬くすると悪くなるのは当然です。
そこで、サスペンション本体のスプリング(バネ)やダンパーは硬くし、車台との取り付け部分にやわらかいゴム(ブッシュ)を付けて、そこで細かい振動を消す、という車が多いのです。
本来乗り心地はスプリングやダンパーで作るのですが、やわらかいブッシュで乗り心地をごまかして?作り出しています。
そのやわらかいゴムを介してしまうので、必要な路面からの情報まで消えてしまうのです。
試乗すれば分かります。
ほとんどロールしない硬い足なのに、乗り心地が何故か良いという車は、私には良い車とは言えません。
乗り心地が多少悪くても、ドライバーに必要な情報が豊かに伝わる車のほうが、初心者には向いていると考えます。
初心者の皆さんには、上記の3つの条件の2つくらいは満たしている車を選んで欲しいな、と思います。
最後に、具体的に今選べる良い車を挙げておきたいと思います。
価格、デザイン他は無視して、上の3つの条件に近い車だけ、私の知ってる範囲ですがざーっと挙げていきます。
あくまで参考程度で見てくださいね。
(2011年10月15日現在)
トヨタ bB、シエンタ
日産 ティーダ、Xトレイル
ホンダ フリード
マツダ アクセラ
三菱 ギャラン
スバル エクシーガ
ダイハツ 一つ前のムーブ
スズキ 一つ前のスイフト、パレット
VW ゴルフTSI、ポロTSI
プジョー 207、307
ルノー カングー
ミニ クーパー(3ドアハッチバック)
フィアット 500
こんな感じかな?
一番ベストなのは、VW ゴルフ(6代目) 1.2TSIです。
ゴルフは現在、世界で一番出来の良い車と言っても過言ではない車でしょう。
値段は高いけど、ほぼパーフェクトな車です。
私も欲しい…。(笑)
現行は高いので、一つ前のモデルのTSIシリーズを中古で買うという手もあります。
VWゴルフは(いつの時代でも)ほんとに良い車なので、買う気はなくても一度は試乗してみることをお薦めします。
私が言いたい「良い車」の基準が分かる車です。
初心者でない方でも、騙されたと思って一度は乗っていただきたい車ですね。
(ゴルフをひとつの基準に、車選びをするのも良いと思います)
以上、かなりの長文となってしまいました。
あくまで私的な見方ですが、参考になったならば幸いです。m(_ _)m
秋が本格的に深まり始める10月。
この時期になると、松本では次第に教習車が公道に増えてきます。
そのほとんどは、進路の決まった学生さんたちでしょう。
毎年の風景なので、私にはひとつの風物詩のように感じています。
さて免許が取れて、晴れて自分の車を手に入れるとき、どこのどんな車が良いのでしょう?
私の独断と偏見?ですが、初心者の皆さんにアドバイスを発しておこうかと思い、この記事をアップします。
一つの参考にしていただけると良いかと思います。
さて、初心者ドライバーで初めての自分の車は、やはり「良い車」に乗るべきでしょう。
私の定義する良い車とは、自然なフィーリングと素直な素質の車です。
……分かりにくいですね(苦笑)。
例としては、ドライバーがこのくらい加速しようとアクセルを踏んだとき、ドライバーが思っていたとおりに加速していく。
ドライバーがこのくらい曲がりたいと思ってハンドルを切ったときに、思っていたとおりに車が曲がっていく。
道路の段差や路面の変化をハンドルに素直に伝えてくれる。
……こんな感じの車です。
「何、そんなの当たり前のことでしょ」という声が聞こえてきそうですが、その当たり前がきちんと出来ている車は意外と少ないのです。
最近の車はどれも良くできているから、どれを選んでも同じ…と考えている方、それは違います。
私に言わせてもらえば、最近の車は私が言いたい「良い車」からはどんどん悪くなっています。
逆に良い車を探すのが、とても難しくなっていると感じます。
また、人間というのはとても適応能力の高い生物で、例えばあまり出来のよろしくない車に乗ったとしても、それに体が慣れてしまい、悪いなりに合わせた運転技術を身につけていきます。
良くない車に合わせた、くせのある技術を身につけてしまうと、あとあと修正するのが難しくなります。
それが、初心者ならばなおさらです。
だから初めての車は、よくよく考えて良い車を選んでほしいのです。
初心者ドライバーが初めて乗る車は、なるべく自然なフィーリングで素直な素質を持った車を選ぶべきです。
自然で素直な素質の良い車で、車のいろいろな挙動を体で覚えて自分の運転技術を向上させる。
最近は「車なんて誰でも簡単に運転できるもの」と思われがちですが、それは違います。
他の自動車やバイク、自転車、歩行者など様々に通行が行き交い、刻一刻と状況が変化する公道において、自分の身を守るとともに周りの人たちにも気を配る、真の安全運転をするには、それなりの技術、腕が必要です。
安全運転だけでも非常に奥が深い、だからドライビングは難しく、そして楽しいのです。
私も日々修業のつもりでハンドルを握っています。
自分のものにした技術は、今後の自動車生活の中で、必ず役に立ちます。
だから、安全で正しい運転技術を身につけるには、まず自然で素質の良い車に乗るべきだと考えているのです。
では、実際私が勝手に考える、初心者が選ぶべき良い車の条件を挙げていきます。
荒っぽく言うと、以下のとおりです。
1.トランスミッションがCVTの車には乗らない
2.足回りがやわらかい車を選ぶ、カーブできちんとロールする(車体が傾く)車を選ぶ
3.乗り心地が良い車は選ばない、静粛性の良すぎる車は選ばない
いやあ、自分で書いててもびっくりのすごい条件ですね(笑)。
1.のCVTは、そもそもが不自然な駆動システムだからです。
ドライバーの普通の感覚としては、アクセルを踏めばそれに応じてエンジンが吹けて回転が上がり、それに応じ速度が上がっていく…、これが自然。
しかしCVTはどんなにアクセルを踏み込んでも、踏み込んだ量に応じてエンジンの回転が上がるわけではありません。
エンジン回転はある一定のままで、速度だけがすーっと上がっていくのがCVT。
またCVTは、例えば40km/hまで加速したいと思って踏み込んでも、たいていはどんどん加速して40km/hをオーバーしてしまいます。
以前の記事で述べたとおり、CVTは強く加速しようと踏み込むと延々と加速していきます。
意識的にアクセルを戻さないと加速が止まりません。
CVTはアクセルの感覚と操作が不自然で、これから技術を身につけていく初心者にはあまり向かないのです。
2.の足回りがやわらかく、カーブで車体がきちんとロールする(傾く)車を選ぶというのは、その方が車の挙動が分かりやすく、技術を身につけるには良いからです。
どうも最近の日本車は、足回りが硬い車が多い。
私が推測するに、車体がロールしてふらつくのをユーザーが嫌がるからでしょう。
ふらつくと同乗者に不快感を与えます。
特に近年人気のミニバン・SUVなどは、車体が大きく背が高く重たいので、ロールして大きくふらつくことが多いのでしょう。
それを防ぐために、足回りを硬くしロールしないようにして車体がふらつくのを抑えれば、安定した走りが出来る…とメーカーは考えているんだと思います。
しかし、カーブで車体がロールするのはある意味車として当たり前だし、ロールをすることはタイヤをうまく使うために本来必要な挙動です。
私に言わせてもらえば、車がふらついて同乗者に不快感をあたえるのは、ドライバーの腕(技術)が悪いからです。
乗員の数と重量と速度、ロールの出方を考えて、カーブではそれ相応にしっかり減速してゆっくり舵を切っていき、またカーブ出口はゆっくり舵を戻していく…、そうすれば不快感を与えるロールは本来発生しません。
要は、ロールが大きく急に出ないように、ドライバーがロールの出方をコントロールしてあげるんです。
その技術がなく、しっかり減速もせず荒っぽく適当にハンドル操作するから、ふらっと大きく振られてしまうのです。
その技術を身につけるには、足回りが柔らかめでロールがきちんとする車でないと、身につきません。
どのくらいの速度でどのくらい舵を切ると、どういうロールの仕方をして、どれだけ傾くのか。
それが体感的に分かる、足が柔らかめの車だと、技術が身につきやすい。
また正しくロールする車だと、荷重移動が分かりやすく、車の挙動がつかみやすくなります。
荷重移動がわかると、どのタイヤにどれだけ負荷がかかっているか分かりやすいし、滑りだしの限界もつかみやすい。
ロールのさせ方と荷重移動が何となくでも身についていると、劇的に運転がうまくなります。
また、どんな大きさのどんな車を運転しても、その応用が使えます。
だから、初心者の方には足回りのやわらかいロールがしっかり分かる車に乗って、車の挙動を体で覚えてもらいたいのです。
3.の乗り心地の良い車、静粛性の高い車は選ばないというのは、そういう車だとタイヤから伝わる路面の状況がつかみにくくなってしまうからです。
ユーザーとしては乗り心地が良く静粛性が高いほうが、良い車だと思いがちです。
しかし、静粛性があまりに良すぎてしまうと、路面から伝わる本来必要な情報まで消してしまいます。
情報とは、タイヤからハンドルやシートへ伝わる振動などの感覚です。
例えば、小石など何か物をタイヤが踏んだときの揺れや、道の段差・うねり、路面の濡れや凍結の感覚、雪を踏む感触などなど、これらは車の運転に必要な情報です。
本当に良い車だと、ハンドルを切ったときにタイヤが向きを変えてゴムがたわむ感触も、ハンドルに伝わってきます。
でも、ユーザーは乗り心地の良さや静粛性を求めてしまうので、メーカーはそれらをとにかく良くしようと本来必要な情報もみんな消してしまう傾向があります。
また、上で述べたとおり最近は足回りが硬い車が増えてます。
本来乗り心地は、足がやわらかくないと良くならない。
足を硬くすると悪くなるのは当然です。
そこで、サスペンション本体のスプリング(バネ)やダンパーは硬くし、車台との取り付け部分にやわらかいゴム(ブッシュ)を付けて、そこで細かい振動を消す、という車が多いのです。
本来乗り心地はスプリングやダンパーで作るのですが、やわらかいブッシュで乗り心地をごまかして?作り出しています。
そのやわらかいゴムを介してしまうので、必要な路面からの情報まで消えてしまうのです。
試乗すれば分かります。
ほとんどロールしない硬い足なのに、乗り心地が何故か良いという車は、私には良い車とは言えません。
乗り心地が多少悪くても、ドライバーに必要な情報が豊かに伝わる車のほうが、初心者には向いていると考えます。
初心者の皆さんには、上記の3つの条件の2つくらいは満たしている車を選んで欲しいな、と思います。
最後に、具体的に今選べる良い車を挙げておきたいと思います。
価格、デザイン他は無視して、上の3つの条件に近い車だけ、私の知ってる範囲ですがざーっと挙げていきます。
あくまで参考程度で見てくださいね。
(2011年10月15日現在)
トヨタ bB、シエンタ
日産 ティーダ、Xトレイル
ホンダ フリード
マツダ アクセラ
三菱 ギャラン
スバル エクシーガ
ダイハツ 一つ前のムーブ
スズキ 一つ前のスイフト、パレット
VW ゴルフTSI、ポロTSI
プジョー 207、307
ルノー カングー
ミニ クーパー(3ドアハッチバック)
フィアット 500
こんな感じかな?
一番ベストなのは、VW ゴルフ(6代目) 1.2TSIです。
ゴルフは現在、世界で一番出来の良い車と言っても過言ではない車でしょう。
値段は高いけど、ほぼパーフェクトな車です。
私も欲しい…。(笑)
現行は高いので、一つ前のモデルのTSIシリーズを中古で買うという手もあります。
VWゴルフは(いつの時代でも)ほんとに良い車なので、買う気はなくても一度は試乗してみることをお薦めします。
私が言いたい「良い車」の基準が分かる車です。
初心者でない方でも、騙されたと思って一度は乗っていただきたい車ですね。
(ゴルフをひとつの基準に、車選びをするのも良いと思います)
以上、かなりの長文となってしまいました。
あくまで私的な見方ですが、参考になったならば幸いです。m(_ _)m
2017/02/07
(この記事は私が過去 2011.9.9. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
これは特に信州だけの話ではないのですが、信号待ちで混んでいるとき、対向車線に飛び出して前の車を何台も抜いて無理に右折レーンへ行く車をよく見かけませんか?
朝のラッシュ時や渋滞の時に急いでいるのは分かりますが、あまりに無謀で危険なタイミングだったり、また十台以上も追い抜いて突っ込んでいく車もいて、大変危険を感じます。
で、そういう事をしている車が一台でもいると、他の車もやってるから良いんだとばかりに、同じように無謀に突っ込んでいく車が増えていきます。
そしていつのまにか、それが当たり前のようになっていくと、いわゆる松本ルールの一つになってしまう。
すると日常に危険な状況が生まれるという、悪い流れが起きるのです。
すでに当たり前のように右折車が対向車線に出ながら十台も二十台も追い抜いていく交差点は、松本にいくつもあります。
具体例としては、やまびこ道路を出川から西へ行く、国道19号とぶつかる高宮の交差点。
駅前通りとやまびこ道路の、秀峰学校前交差点など。
どちらも道路がやや広いため、交差点から80~100mも手前から右折車が反対車線にはみ出しながら、当たり前のように右折レーンへ向かっていきます。
高宮はホテルの前の丁字路辺りから、秀峰前は元ホテルがあった辺りから、その先の道路状況も分からないのに突っ込んでいく車もいます。
直進、左折車もそれを助長するように、左いっぱいに路肩のラインを越えて停車してます。
2車線という標識もないのに、まるで既成の2車線道路になってしまっている。
これこそ松本ルールですね。
「あそこはそんなに事故が起きてるわけじゃないし、渋滞緩和にもなってるから別に良いじゃん」
という声も聞こえてきそうですが、問題点は地元以外の人にはそのルールが分かっていないことです。
道路は公共のものですからどこの誰が使っても、同じように理解ができて使える道路状況でなくてはならないのです。
公共のルールに則って運転していて、ローカルルールを知らないがために、危険な目にあったりすることは、あってはなりません。
ましてや、松本はじめ信州は観光地なのですから、県外の方でもだれもが普通に使える道路環境を目指すのは当然です。
それからよく考えほしいのですが、無茶をして右折レーンへ突っ込んだとしても、だいたいすぐには右折できず、無理に突っ込んでも突っ込まなくてまじめ?に右折レーンへ行っても、7-8割ちかくの確率で結果は変わらないはずです。
リスクを取るわりには、早く曲がれるわけではないのなら、やる必要はないと思うのです。
私だったら危険を犯してまではやらないし、安全な方を選びますが、皆さんはどうですか?
よくよく思い出して、考えてみてください。
もしどうしても右折レーンへ突っ込むにしても、危険度を減らしてなるたけ安全に行うべきです。
まず、追い抜くとしても良くて五台程度でしょう。
それ以上は何かあったとき、急に車が出て来た時など、危険が高くなるので止めましょう。
また対向車がいるときは絶対にやらない。
対向車の通行を妨げることは、絶対に許されません。
広い道で対向車線に少ししかはみ出さないような場所でも、対向車がいるうちはやらないように。
交差点、信号の様子を見て的確に判断します。
それから、右折レーンが混んでて実際行けないのに、何も確認せずにただ突っ込んでいってはいけません。
安全を確認できないときはやらない。
公道において最も大切なのは、常に安全を選択することです。
また、直進・左折レーンにいるときも、路肩のラインを越えて左に寄せてはいけません。
右にスペースを空けると、右折レーンへの無謀な突っ込みを促しかねません。
そもそもオーバーラインはやってはいけない、基本中の基本なはずです。
オンザラインは良くても、オーバーラインはいけません。
不用意に路肩のライン、センターラインは越えてはいけないのです。
路肩は本来、歩行者の安全を確保するための車両進入禁止のゾーンです。
道路状況を良く見て、的確に判断してください。
だめならだめで、きっぱり諦めること。
安全が確認できて誰にも迷惑がかからないのが明確なら、詰めても良いとは思います。
もっと危険を予測し、危険を避ける努力をみんなでしていきませんか。
これは特に信州だけの話ではないのですが、信号待ちで混んでいるとき、対向車線に飛び出して前の車を何台も抜いて無理に右折レーンへ行く車をよく見かけませんか?
朝のラッシュ時や渋滞の時に急いでいるのは分かりますが、あまりに無謀で危険なタイミングだったり、また十台以上も追い抜いて突っ込んでいく車もいて、大変危険を感じます。
で、そういう事をしている車が一台でもいると、他の車もやってるから良いんだとばかりに、同じように無謀に突っ込んでいく車が増えていきます。
そしていつのまにか、それが当たり前のようになっていくと、いわゆる松本ルールの一つになってしまう。
すると日常に危険な状況が生まれるという、悪い流れが起きるのです。
すでに当たり前のように右折車が対向車線に出ながら十台も二十台も追い抜いていく交差点は、松本にいくつもあります。
具体例としては、やまびこ道路を出川から西へ行く、国道19号とぶつかる高宮の交差点。
駅前通りとやまびこ道路の、秀峰学校前交差点など。
どちらも道路がやや広いため、交差点から80~100mも手前から右折車が反対車線にはみ出しながら、当たり前のように右折レーンへ向かっていきます。
高宮はホテルの前の丁字路辺りから、秀峰前は元ホテルがあった辺りから、その先の道路状況も分からないのに突っ込んでいく車もいます。
直進、左折車もそれを助長するように、左いっぱいに路肩のラインを越えて停車してます。
2車線という標識もないのに、まるで既成の2車線道路になってしまっている。
これこそ松本ルールですね。
「あそこはそんなに事故が起きてるわけじゃないし、渋滞緩和にもなってるから別に良いじゃん」
という声も聞こえてきそうですが、問題点は地元以外の人にはそのルールが分かっていないことです。
道路は公共のものですからどこの誰が使っても、同じように理解ができて使える道路状況でなくてはならないのです。
公共のルールに則って運転していて、ローカルルールを知らないがために、危険な目にあったりすることは、あってはなりません。
ましてや、松本はじめ信州は観光地なのですから、県外の方でもだれもが普通に使える道路環境を目指すのは当然です。
それからよく考えほしいのですが、無茶をして右折レーンへ突っ込んだとしても、だいたいすぐには右折できず、無理に突っ込んでも突っ込まなくてまじめ?に右折レーンへ行っても、7-8割ちかくの確率で結果は変わらないはずです。
リスクを取るわりには、早く曲がれるわけではないのなら、やる必要はないと思うのです。
私だったら危険を犯してまではやらないし、安全な方を選びますが、皆さんはどうですか?
よくよく思い出して、考えてみてください。
もしどうしても右折レーンへ突っ込むにしても、危険度を減らしてなるたけ安全に行うべきです。
まず、追い抜くとしても良くて五台程度でしょう。
それ以上は何かあったとき、急に車が出て来た時など、危険が高くなるので止めましょう。
また対向車がいるときは絶対にやらない。
対向車の通行を妨げることは、絶対に許されません。
広い道で対向車線に少ししかはみ出さないような場所でも、対向車がいるうちはやらないように。
交差点、信号の様子を見て的確に判断します。
それから、右折レーンが混んでて実際行けないのに、何も確認せずにただ突っ込んでいってはいけません。
安全を確認できないときはやらない。
公道において最も大切なのは、常に安全を選択することです。
また、直進・左折レーンにいるときも、路肩のラインを越えて左に寄せてはいけません。
右にスペースを空けると、右折レーンへの無謀な突っ込みを促しかねません。
そもそもオーバーラインはやってはいけない、基本中の基本なはずです。
オンザラインは良くても、オーバーラインはいけません。
不用意に路肩のライン、センターラインは越えてはいけないのです。
路肩は本来、歩行者の安全を確保するための車両進入禁止のゾーンです。
道路状況を良く見て、的確に判断してください。
だめならだめで、きっぱり諦めること。
安全が確認できて誰にも迷惑がかからないのが明確なら、詰めても良いとは思います。
もっと危険を予測し、危険を避ける努力をみんなでしていきませんか。
2017/02/07
(この記事は私が過去 2011.6.29. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
今回は、交通マナーの話をします。
皆さんは松本や信州で大きい主要道路を走っているとき、横の脇道からそのままノンストップで突っ込んできそうな速いスピードで走ってきて、頭が出るかどうかぎりぎりの所でびたっと急に止まる、という怖い車に出会いませんか?
こちらが優先だとわかっていても、もし本当に飛び出して来たら…と恐怖したりしませんか?
それとも信州では日常茶飯事で、もう当たり前に感じてる方も多いかもしれません。(それはそれでまずいのですが…)
ちなみに県外(特に東京など都会)の方は、横から車がそのまま突っ込んでくるのかと思って、かなり恐怖を感じているそうです。
信州は有名な観光地なのに、県外車に恐怖感を与えてる交通事情なんて、何とも情けないと思いませんか?
そもそも、そういう運転する車は初めから停止するつもりがあまりなく、車がいなければそのまま一時停止せずに行くつもりで、スピードを落とさず突っ込んでいるのが大半でしょう。
考え方自体が、初めから間違っているのです。
「他の車がいたらちゃんと止まるから別に良いじゃん」と反論する方もいるかも知れませんが、優先道路を走る車に恐怖感、プレッシャーを与えている時点で問題なんです。
そのプレッシャーが、思わぬ事故の元になる可能性は十分考えられます。
また、そういうことをする車のほとんどが停止線を素通りして、歩道があっても無視をして歩道を塞ぐように直接車道へ飛び出すように止まります。
そんなに頭を出しても出してなくても、曲がれるかどうかは交通の流れによるので、その行為はあんまり意味がないと、私は思います。
逆に、本来一番優先されるべき歩道をいく歩行者の通行を妨げ危険にさらすので、かなり問題です。
そしてよくあるのが、脇道から優先道路へ左折をするのに、車がいなければ一時停止せずに曲がろうとしていて注意力が右側だけになり、左側から来る自転車や歩行者に気付かず衝突、巻き込むという事故です。
初めから左側の歩行者等に注意力が向いていないのでブレーキが遅れ、かなり巻き込んでしまうという、悲惨な事故が多いそうです。
脇道から優先道路への進入は、必ず停止線で一時停止すること。
またそのつもりで、いつでも止まれるスピードまで速度を落として進入すること。
この、そもそもの一時停止のルールが、信州人・松本人にはすっぽ抜けているような気がします。
教習所で習うには、一時停止の線を越える手前で約1秒間完全に停止することが、一時停止のルールであるはずです。
それ以外は基本的に一時停止無視の違反となり、警察が見ていれば確実に捕まります。
基本中の基本であり、当たり前のことです。
加えて以前にも言ったとおり、優先道路を通行する歩行者が、最も優先されるべき存在です。
その歩行者の通行を妨げることは、一番やってはいけないことです。
だから、初めから歩道をふさぐような停車はしてはいけないのです。
正しい一時停止は、初めにきちんと停止線手前で約1秒間一時停止をして左右の安全を確認し、歩行者等に邪魔にならない程度にそろそろと少し前に出て、見える範囲で交通の流れを見ます。
すぐに渡れない・曲がれないと判断したら、必ず歩行者・自転車が通行できるよう間を空けたまま待ちしましょう。
いけそうだなと判断してからじわりと動くのですが、その時交錯する歩行者がいたら絶対に動いてはいけません。
何度も言いますが、最も優先されるべきは歩行者です。
必ず進路を譲ることが義務付けられています。
それじゃいったいいつ曲がるの?と思う方もいるかも知れませんが、脇道はあくまで脇道です。
タイミングが悪ければ、いつまで経っても渡れない・曲がれないのが本来の姿なのです。
優先道路の通行を乱してまで、無理矢理に進入してはいけません。
よく、「入れろ、入れろ」とアピールするようにじわじわと脇道から車道に出てくる危険な車もいますが、あれも絶対にやってはいけないことです。
車を運転する上で一番大切なことは、安全な運転をしなくてはならない、危険と思われる運転をしてはならない、という安全運転義務です。
これは道路交通法にある通り、車を運転する者が全員しなければならない義務です。
これができない者は、本来は車を運転する資格がないのです。
自分さえ良ければよい、とにかく渡れれば良い、急いでいるし無理やりにでも、、、という独りよがりは最もしてはならない行為だと認識しましょう。
何が優先されるべきか、信州の車はもっと分をわきまえなくてはならない、と私は考えます。
とにかく、脇道から優先道路へ出るときは、一時停止線の手前で必ず止まること。
交差点へはゆっくりなスピードで進入すること。
優先道路を通行する歩行者の通行と安全を妨げることは絶対にしてはならない、と心がけましょう。
信州、松本の交通安全のため、これからもお互いに気を付けていきましょう。
m(_ _)m
今回は、交通マナーの話をします。
皆さんは松本や信州で大きい主要道路を走っているとき、横の脇道からそのままノンストップで突っ込んできそうな速いスピードで走ってきて、頭が出るかどうかぎりぎりの所でびたっと急に止まる、という怖い車に出会いませんか?
こちらが優先だとわかっていても、もし本当に飛び出して来たら…と恐怖したりしませんか?
それとも信州では日常茶飯事で、もう当たり前に感じてる方も多いかもしれません。(それはそれでまずいのですが…)
ちなみに県外(特に東京など都会)の方は、横から車がそのまま突っ込んでくるのかと思って、かなり恐怖を感じているそうです。
信州は有名な観光地なのに、県外車に恐怖感を与えてる交通事情なんて、何とも情けないと思いませんか?
そもそも、そういう運転する車は初めから停止するつもりがあまりなく、車がいなければそのまま一時停止せずに行くつもりで、スピードを落とさず突っ込んでいるのが大半でしょう。
考え方自体が、初めから間違っているのです。
「他の車がいたらちゃんと止まるから別に良いじゃん」と反論する方もいるかも知れませんが、優先道路を走る車に恐怖感、プレッシャーを与えている時点で問題なんです。
そのプレッシャーが、思わぬ事故の元になる可能性は十分考えられます。
また、そういうことをする車のほとんどが停止線を素通りして、歩道があっても無視をして歩道を塞ぐように直接車道へ飛び出すように止まります。
そんなに頭を出しても出してなくても、曲がれるかどうかは交通の流れによるので、その行為はあんまり意味がないと、私は思います。
逆に、本来一番優先されるべき歩道をいく歩行者の通行を妨げ危険にさらすので、かなり問題です。
そしてよくあるのが、脇道から優先道路へ左折をするのに、車がいなければ一時停止せずに曲がろうとしていて注意力が右側だけになり、左側から来る自転車や歩行者に気付かず衝突、巻き込むという事故です。
初めから左側の歩行者等に注意力が向いていないのでブレーキが遅れ、かなり巻き込んでしまうという、悲惨な事故が多いそうです。
脇道から優先道路への進入は、必ず停止線で一時停止すること。
またそのつもりで、いつでも止まれるスピードまで速度を落として進入すること。
この、そもそもの一時停止のルールが、信州人・松本人にはすっぽ抜けているような気がします。
教習所で習うには、一時停止の線を越える手前で約1秒間完全に停止することが、一時停止のルールであるはずです。
それ以外は基本的に一時停止無視の違反となり、警察が見ていれば確実に捕まります。
基本中の基本であり、当たり前のことです。
加えて以前にも言ったとおり、優先道路を通行する歩行者が、最も優先されるべき存在です。
その歩行者の通行を妨げることは、一番やってはいけないことです。
だから、初めから歩道をふさぐような停車はしてはいけないのです。
正しい一時停止は、初めにきちんと停止線手前で約1秒間一時停止をして左右の安全を確認し、歩行者等に邪魔にならない程度にそろそろと少し前に出て、見える範囲で交通の流れを見ます。
すぐに渡れない・曲がれないと判断したら、必ず歩行者・自転車が通行できるよう間を空けたまま待ちしましょう。
いけそうだなと判断してからじわりと動くのですが、その時交錯する歩行者がいたら絶対に動いてはいけません。
何度も言いますが、最も優先されるべきは歩行者です。
必ず進路を譲ることが義務付けられています。
それじゃいったいいつ曲がるの?と思う方もいるかも知れませんが、脇道はあくまで脇道です。
タイミングが悪ければ、いつまで経っても渡れない・曲がれないのが本来の姿なのです。
優先道路の通行を乱してまで、無理矢理に進入してはいけません。
よく、「入れろ、入れろ」とアピールするようにじわじわと脇道から車道に出てくる危険な車もいますが、あれも絶対にやってはいけないことです。
車を運転する上で一番大切なことは、安全な運転をしなくてはならない、危険と思われる運転をしてはならない、という安全運転義務です。
これは道路交通法にある通り、車を運転する者が全員しなければならない義務です。
これができない者は、本来は車を運転する資格がないのです。
自分さえ良ければよい、とにかく渡れれば良い、急いでいるし無理やりにでも、、、という独りよがりは最もしてはならない行為だと認識しましょう。
何が優先されるべきか、信州の車はもっと分をわきまえなくてはならない、と私は考えます。
とにかく、脇道から優先道路へ出るときは、一時停止線の手前で必ず止まること。
交差点へはゆっくりなスピードで進入すること。
優先道路を通行する歩行者の通行と安全を妨げることは絶対にしてはならない、と心がけましょう。
信州、松本の交通安全のため、これからもお互いに気を付けていきましょう。
m(_ _)m
2017/02/07
(この記事は私が過去 2011.6.21. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
今回も、安全に関する話です。
さて、これから車を運転しようと運転席に座ったとき、皆さんはどんな準備をしていますか?
まずはシートの前後位置を合わせて、背もたれ角度を調整。
ハンドルの位置を合わせたら、ミラーを合わせて、シートベルトをしっかり締めて、さあ出発…。
ちょっと待ってください、忘れていますよ、ヘッドレストの調整。
ヘッドレストはシートベルトと同じく、れっきとした安全装置です。
ただの頭部当てではありません、まちがいのないように。
きちんとセットしないと、安全装置としての役目を果たしません。
自分の頭の後ろ、後頭部の真後ろにヘッドレストがくるように、引き伸ばしたり縮めたりして調整します。
前席でも後席でも、ついているのなら、ちゃんと使わなきゃ意味がないです。
最近、ヘッドレストを縮めたままや、どうせ使わないからとわざわざひっこ抜いてしまう方がいます。
世間では、安全装置としての認識が薄いんですね。
ヘッドレストは追突されたときや激しく車体が動くような事故の時、効果を発揮します。
特に追突されたときの鞭打ち防止には重要な装置です。
追突などで後ろから衝撃を受けたとき、車内の人間は後ろへのけ反るように動きます。
その時、体はシートが支えてくれますが、頭はヘッドレストがないと「カクン」と後ろへ強く振られてしまいます。
人間の首は急所の一つで、特に後ろへ反るように強く振られると、頸椎(けいつい)損傷で鞭打ち症になってしまいます。
もっとひどい時は、首の神経が傷ついて首から下が麻痺してしまうこともあります。
他にも、脳幹損傷や脳髄膜液減少により、最悪死に至る可能性もあります。
比較的ゆっくりの時速20km/hで追突されただけでも、鞭打ち症で3ヵ月歩けなかったという、事例もあります。
ヘッドレストは、頭が後ろへのけ反らないように防ぐための、大切な安全装置なんです。
車内のシートへ座ったら、ヘッドレストの高さもしっかり調整しましょう。
シートに座って後ろへのけ反ってみて、後頭部にヘッドレストがきちんと当たり、首が後ろへ反らないことを確認しましょう。
ヘッドレストを甘く見てはいけません。
今回も、安全に関する話です。
さて、これから車を運転しようと運転席に座ったとき、皆さんはどんな準備をしていますか?
まずはシートの前後位置を合わせて、背もたれ角度を調整。
ハンドルの位置を合わせたら、ミラーを合わせて、シートベルトをしっかり締めて、さあ出発…。
ちょっと待ってください、忘れていますよ、ヘッドレストの調整。
ヘッドレストはシートベルトと同じく、れっきとした安全装置です。
ただの頭部当てではありません、まちがいのないように。
きちんとセットしないと、安全装置としての役目を果たしません。
自分の頭の後ろ、後頭部の真後ろにヘッドレストがくるように、引き伸ばしたり縮めたりして調整します。
前席でも後席でも、ついているのなら、ちゃんと使わなきゃ意味がないです。
最近、ヘッドレストを縮めたままや、どうせ使わないからとわざわざひっこ抜いてしまう方がいます。
世間では、安全装置としての認識が薄いんですね。
ヘッドレストは追突されたときや激しく車体が動くような事故の時、効果を発揮します。
特に追突されたときの鞭打ち防止には重要な装置です。
追突などで後ろから衝撃を受けたとき、車内の人間は後ろへのけ反るように動きます。
その時、体はシートが支えてくれますが、頭はヘッドレストがないと「カクン」と後ろへ強く振られてしまいます。
人間の首は急所の一つで、特に後ろへ反るように強く振られると、頸椎(けいつい)損傷で鞭打ち症になってしまいます。
もっとひどい時は、首の神経が傷ついて首から下が麻痺してしまうこともあります。
他にも、脳幹損傷や脳髄膜液減少により、最悪死に至る可能性もあります。
比較的ゆっくりの時速20km/hで追突されただけでも、鞭打ち症で3ヵ月歩けなかったという、事例もあります。
ヘッドレストは、頭が後ろへのけ反らないように防ぐための、大切な安全装置なんです。
車内のシートへ座ったら、ヘッドレストの高さもしっかり調整しましょう。
シートに座って後ろへのけ反ってみて、後頭部にヘッドレストがきちんと当たり、首が後ろへ反らないことを確認しましょう。
ヘッドレストを甘く見てはいけません。
2017/02/07
(この記事は私が過去 2011.5.3. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
今回は安全に関する話です。
最近、助手席にチャイルドシートを取り付けてお子さんを乗せて走っている車をよく見かける気がするので、とにかく警告します。
それはとても危険なので、すぐやめましょう!
基本的に、チャイルドシートは助手席(前列の席)に取り付けてはいけません。
ちゃんと車の取扱説明書にも、チャイルドシートの取説にも書いてあります。
その理由はエアバッグです。
助手席にチャイルドシートを取り付けた状態でエアバッグが開くと、チャイルドシートに当たってチャイルドシートが上方向へ跳ね上がります。
特に、0~4歳用のチャイルドシート(後ろ向きで取り付けるタイプ)の場合は、エアバッグにより後ろ方向への危険な衝撃を与え、子供が背もたれと挟まれるような状況になります。
非常に危険ですので、エアバッグの付いた助手席には、絶対にチャイルドシートを付けてはいけないのです。
最近の乗用車は助手席エアバッグはほとんど標準で付いています。
助手席にはチャイルドシートを取り付けないというのが、基本だと考えてください。
また、4歳以上の大きい子用、いわゆるジュニアシートについても、エアバッグが開いたときに足を骨折するなどの危ない事故があるそうです。
全ての子供用の補助シートは後部座席へ取り付けるもの、と割り切って覚えたほうが良いと思います。
また、エアバッグはたいした衝撃でなくても開く事例が多くあります。
大きい段差で車体が揺れたときとか、軽くフロントをコツンと当てただけでも開く場合があります。
大げさに言えば、エアバッグはいつ突然開いてもおかしくないのです。
助手席のチャイルドシートに乗せていて、事故でもないのに突然エアバッグが開いて子供が死亡した、という事例も海外にはあります。
私も子を持つ親なので、助手席にお子さんを座らせたい気持ちは良く分かります。
特に乳幼児の時は、様子を見たりあやしたりするのに、すぐ隣の助手席の方がすごく楽ですよね。
しかし、お子さんの安全のためには背に腹は代えられません。
私も後部座席の子どもの面倒見るのに、すごく大変でしたが、何とかやりきりました。
せっかくお子さんの安全のためにチャイルドシートに乗せたのに、そのチャイルドシートのせいでお子さんが怪我でもしたら、やりきれないじゃないですか…。
少し面倒でも、チャイルドシート・ジュニアシートは必ず後部座席へ取り付けましょう。
ちなみに、海外メーカー車や一部高級車には、助手席にチャイルドシートが置けるよう、助手席エアバッグを無効にするスイッチがある車があります。
海外メーカー車や高級車に乗ってる方は、一度取扱説明書で確認しましょう。
一般の日本車にはそういうスイッチは、今のところ約9割の車には付いていません。
安全に対する考え方と、ユーザーにとって何が便利なのかという、考える力の差でしょうね。
なんとも残念なことです。
今回は安全に関する話です。
最近、助手席にチャイルドシートを取り付けてお子さんを乗せて走っている車をよく見かける気がするので、とにかく警告します。
それはとても危険なので、すぐやめましょう!
基本的に、チャイルドシートは助手席(前列の席)に取り付けてはいけません。
ちゃんと車の取扱説明書にも、チャイルドシートの取説にも書いてあります。
その理由はエアバッグです。
助手席にチャイルドシートを取り付けた状態でエアバッグが開くと、チャイルドシートに当たってチャイルドシートが上方向へ跳ね上がります。
特に、0~4歳用のチャイルドシート(後ろ向きで取り付けるタイプ)の場合は、エアバッグにより後ろ方向への危険な衝撃を与え、子供が背もたれと挟まれるような状況になります。
非常に危険ですので、エアバッグの付いた助手席には、絶対にチャイルドシートを付けてはいけないのです。
最近の乗用車は助手席エアバッグはほとんど標準で付いています。
助手席にはチャイルドシートを取り付けないというのが、基本だと考えてください。
また、4歳以上の大きい子用、いわゆるジュニアシートについても、エアバッグが開いたときに足を骨折するなどの危ない事故があるそうです。
全ての子供用の補助シートは後部座席へ取り付けるもの、と割り切って覚えたほうが良いと思います。
また、エアバッグはたいした衝撃でなくても開く事例が多くあります。
大きい段差で車体が揺れたときとか、軽くフロントをコツンと当てただけでも開く場合があります。
大げさに言えば、エアバッグはいつ突然開いてもおかしくないのです。
助手席のチャイルドシートに乗せていて、事故でもないのに突然エアバッグが開いて子供が死亡した、という事例も海外にはあります。
私も子を持つ親なので、助手席にお子さんを座らせたい気持ちは良く分かります。
特に乳幼児の時は、様子を見たりあやしたりするのに、すぐ隣の助手席の方がすごく楽ですよね。
しかし、お子さんの安全のためには背に腹は代えられません。
私も後部座席の子どもの面倒見るのに、すごく大変でしたが、何とかやりきりました。
せっかくお子さんの安全のためにチャイルドシートに乗せたのに、そのチャイルドシートのせいでお子さんが怪我でもしたら、やりきれないじゃないですか…。
少し面倒でも、チャイルドシート・ジュニアシートは必ず後部座席へ取り付けましょう。
ちなみに、海外メーカー車や一部高級車には、助手席にチャイルドシートが置けるよう、助手席エアバッグを無効にするスイッチがある車があります。
海外メーカー車や高級車に乗ってる方は、一度取扱説明書で確認しましょう。
一般の日本車にはそういうスイッチは、今のところ約9割の車には付いていません。
安全に対する考え方と、ユーザーにとって何が便利なのかという、考える力の差でしょうね。
なんとも残念なことです。
2017/02/07
(この記事は私が過去 2012.6.1. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です。分かりやすいように投稿順を差し替えて再アップしています)
もう行楽シーズン終わってますが、高速道路での省エネ運転をやっておきたいと思います。
いまさらなんですが、やり忘れたと言うのもありますので、遅蒔きながらやります。(;^_^A
単刀直入に言うと表題どおり「高速は95km/hの一定速度で走る」のが、燃費が良くスムーズに走れます。
(あくまで私が調べた結果です)
高速走行で車の燃費を悪化させるのは、なんだと思いますか?
急な加速とか、無駄な加減速(アクセルワーク)とかもそうですが、実は高速での一番の燃費の敵は「空気」すなわち「風」です。
以前の記事でも述べましたが、エンジンはずーっと同じ回転数で仕事をし続けたほうが、負荷なく無駄なく力を出し続けることができます。
高速道路のように、ある一定速度で、長く走り続けるところは、基本的に燃費が良くなるのです。
しかし、速く一定で走っていても速度が100km/h超えるあたりから、急に燃費が悪くなってきます。
空気の壁(風圧)がものすごい負荷となってくるからです。
100km/hでは、車体には実に1t以上の風圧がかかっているといわれます。
100km/h以上では、スピードを上げれば上げるほどどんどん風圧が強くなって、燃費も急激に悪くなってきます。
高速で燃費を良くしたいなら、スピードを出しすぎてはいけません。
また何となーくで、漠然と100km/hくらいで走っていてもいけません。
私が調べた情報と自分の経験から言うと、もっとも燃費が良くなる速度は、90km/hです。
ただ、90km/hだと周りの交通の流れより遅いペースとなってしまいます。
多くのみなさんが、きりが良い100km/h前後で走っているからです。
そこで、周りのペースに合わせられて燃費も良いちょうど良い速度が、95km/hとなります。
この95km/hを一つの基準にして走ると、スムーズで燃費も良く走れます。
私の愛車の燃費は、一般道でリッター7km前後。
(燃費は悪いけど、良い車で気に入っているので、なかなか乗り換えられない…汗)
でも高速で95km/hで走ると、リッター10km以上が当たり前になります。
ちなみに愛車の燃費最高記録は、一般道での燃費のほぼ倍のリッター13km。
もっと燃費の良い車なら、リッター20km、30kmも十分いけると思います。
さて、95km/hで一定速走行するのですが、以前の記事で述べたとおりずーっと95km/hで走り続けられるよう、アクセルで微調整しながら走ります。
登り坂では速度が落ちないように、坂の手前から早めにアクセルを踏み増し速度を調整する。
逆に下り坂は速度が出すぎないよう、早めにアクセルをゆるめて速度が一定になるようにします。
常に道路状況と交通の流れを読みながら、なるべく95km/hの一定速度で走るよう、心がけて走りましょう。
ただし、速度を気にしすぎて事故など危険がないようにしてください。
燃費より安全のが大切です。
それから、車体の形で燃費の良い速度は若干変わってきます。
95km/hは、セダンやステーションワゴンのような車体のときの速度です。
ミニバンや1BOX、トラックなどは空気抵抗が大きいので、95km/hより速度が低い方が燃費が良くなると思います。
試しに95km/hで走ってみて、思ったより燃費が伸びないと思ったら、少し速度を調整してみてください。
とにかく安全第一で、試してみてください。
お願いします。
m(_ _)m
もう行楽シーズン終わってますが、高速道路での省エネ運転をやっておきたいと思います。
いまさらなんですが、やり忘れたと言うのもありますので、遅蒔きながらやります。(;^_^A
単刀直入に言うと表題どおり「高速は95km/hの一定速度で走る」のが、燃費が良くスムーズに走れます。
(あくまで私が調べた結果です)
高速走行で車の燃費を悪化させるのは、なんだと思いますか?
急な加速とか、無駄な加減速(アクセルワーク)とかもそうですが、実は高速での一番の燃費の敵は「空気」すなわち「風」です。
以前の記事でも述べましたが、エンジンはずーっと同じ回転数で仕事をし続けたほうが、負荷なく無駄なく力を出し続けることができます。
高速道路のように、ある一定速度で、長く走り続けるところは、基本的に燃費が良くなるのです。
しかし、速く一定で走っていても速度が100km/h超えるあたりから、急に燃費が悪くなってきます。
空気の壁(風圧)がものすごい負荷となってくるからです。
100km/hでは、車体には実に1t以上の風圧がかかっているといわれます。
100km/h以上では、スピードを上げれば上げるほどどんどん風圧が強くなって、燃費も急激に悪くなってきます。
高速で燃費を良くしたいなら、スピードを出しすぎてはいけません。
また何となーくで、漠然と100km/hくらいで走っていてもいけません。
私が調べた情報と自分の経験から言うと、もっとも燃費が良くなる速度は、90km/hです。
ただ、90km/hだと周りの交通の流れより遅いペースとなってしまいます。
多くのみなさんが、きりが良い100km/h前後で走っているからです。
そこで、周りのペースに合わせられて燃費も良いちょうど良い速度が、95km/hとなります。
この95km/hを一つの基準にして走ると、スムーズで燃費も良く走れます。
私の愛車の燃費は、一般道でリッター7km前後。
(燃費は悪いけど、良い車で気に入っているので、なかなか乗り換えられない…汗)
でも高速で95km/hで走ると、リッター10km以上が当たり前になります。
ちなみに愛車の燃費最高記録は、一般道での燃費のほぼ倍のリッター13km。
もっと燃費の良い車なら、リッター20km、30kmも十分いけると思います。
さて、95km/hで一定速走行するのですが、以前の記事で述べたとおりずーっと95km/hで走り続けられるよう、アクセルで微調整しながら走ります。
登り坂では速度が落ちないように、坂の手前から早めにアクセルを踏み増し速度を調整する。
逆に下り坂は速度が出すぎないよう、早めにアクセルをゆるめて速度が一定になるようにします。
常に道路状況と交通の流れを読みながら、なるべく95km/hの一定速度で走るよう、心がけて走りましょう。
ただし、速度を気にしすぎて事故など危険がないようにしてください。
燃費より安全のが大切です。
それから、車体の形で燃費の良い速度は若干変わってきます。
95km/hは、セダンやステーションワゴンのような車体のときの速度です。
ミニバンや1BOX、トラックなどは空気抵抗が大きいので、95km/hより速度が低い方が燃費が良くなると思います。
試しに95km/hで走ってみて、思ったより燃費が伸びないと思ったら、少し速度を調整してみてください。
とにかく安全第一で、試してみてください。
お願いします。
m(_ _)m
2017/02/07
(この記事は私が過去 2011.4.19. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
最近増えてきたハイブリッドカー(以下HV。ハイブリッドビークルの略)。
そのままでも燃費は良いのですが、ちょっと仕組みを理解して運転の仕方を変えるともっと良くなると思います。
一番のポイントは回生ブレーキの使い方と、エンジンがかからないように走る(モーターのみで走る、いわゆるEVモード)アクセルワークです。
回生ブレーキは、ブレーキ機構に発電装置を付けて発電をして減速、ブレーキをかけるものです。
これを使って、摩擦熱としてただ棄てていた回転エネルギーを電気に変換し、バッテリーに蓄めます。
その電気を使ってモーターのみで走れば、実質燃料を使わないで走っていることになります。
すなわち、ブレーキを使って発電することは、燃費向上につながります。
一般の内燃エンジン車では、エンジンブレーキを多用すると、燃費が向上しますが、HVの場合はエンジンブレーキより普通のフットブレーキを使って回生ブレーキを多く使い、発電したほうがその燃費に貢献すると思います。
そのため、なるべく多くフットブレーキを使うようにすると良いです。
また回生ブレーキは、ある程度の早いスピードからグーッと強めにブレーキをかけたときに、発電効率が高くなります。
したがって、HVがもっとも燃費が良くなる場面は、郊外の程よく空いた幹線道路です。
60km/hくらいの速めのスピードから、たまに赤信号でグーッと強めに減速して停車する、というサイクルを繰り返す道だと、かなり燃費が伸びてきます。
ただ強いブレーキは、一人のときは良いかもしれませんが、同乗者がいるときは不快に感じない程度のブレーキを心掛けましょう。
燃費も大事かもしれませんが、快適なドライブも大切です。
さらに、HVの燃費の良いアクセル操作はかなり難しいと言えます。
CVTの時と同様、加速モードにならないように走るのが基本となります。
その設定はとてもシビアで、ちょっと強く踏んだだけですぐ加速モードになってぐんぐん加速、あっという間に電力を消費してしまいます。
これではせっかく回生ブレーキで溜めた電力が無駄に使われてしまいます。
高速の合流など、強い加速が必要なとき以外は、加速モードに極力ならないようにしましょう。
しかしながら、そのためにはまさに足がつるほどの微細なアクセルワークが必要になります。
実際につってしまったら危ないので、無理のないようほどほどで挑戦してください。
安全が第一ですから、気を付けてください。
最近増えてきたハイブリッドカー(以下HV。ハイブリッドビークルの略)。
そのままでも燃費は良いのですが、ちょっと仕組みを理解して運転の仕方を変えるともっと良くなると思います。
一番のポイントは回生ブレーキの使い方と、エンジンがかからないように走る(モーターのみで走る、いわゆるEVモード)アクセルワークです。
回生ブレーキは、ブレーキ機構に発電装置を付けて発電をして減速、ブレーキをかけるものです。
これを使って、摩擦熱としてただ棄てていた回転エネルギーを電気に変換し、バッテリーに蓄めます。
その電気を使ってモーターのみで走れば、実質燃料を使わないで走っていることになります。
すなわち、ブレーキを使って発電することは、燃費向上につながります。
一般の内燃エンジン車では、エンジンブレーキを多用すると、燃費が向上しますが、HVの場合はエンジンブレーキより普通のフットブレーキを使って回生ブレーキを多く使い、発電したほうがその燃費に貢献すると思います。
そのため、なるべく多くフットブレーキを使うようにすると良いです。
また回生ブレーキは、ある程度の早いスピードからグーッと強めにブレーキをかけたときに、発電効率が高くなります。
したがって、HVがもっとも燃費が良くなる場面は、郊外の程よく空いた幹線道路です。
60km/hくらいの速めのスピードから、たまに赤信号でグーッと強めに減速して停車する、というサイクルを繰り返す道だと、かなり燃費が伸びてきます。
ただ強いブレーキは、一人のときは良いかもしれませんが、同乗者がいるときは不快に感じない程度のブレーキを心掛けましょう。
燃費も大事かもしれませんが、快適なドライブも大切です。
さらに、HVの燃費の良いアクセル操作はかなり難しいと言えます。
CVTの時と同様、加速モードにならないように走るのが基本となります。
その設定はとてもシビアで、ちょっと強く踏んだだけですぐ加速モードになってぐんぐん加速、あっという間に電力を消費してしまいます。
これではせっかく回生ブレーキで溜めた電力が無駄に使われてしまいます。
高速の合流など、強い加速が必要なとき以外は、加速モードに極力ならないようにしましょう。
しかしながら、そのためにはまさに足がつるほどの微細なアクセルワークが必要になります。
実際につってしまったら危ないので、無理のないようほどほどで挑戦してください。
安全が第一ですから、気を付けてください。
2017/02/07
(この記事は私が過去 2011.3.26. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
これまでは主に方法論的な省エネを載せてきました。
今回は「目」・「目線」の話となります。
燃費に役立つ「目」は、まさに交通状況を的確に把握する目です。
一定速度走行のときにも少し触れましたが、先の流れを読む目は非常に大切です。
例えば、信号が青になってぐっと加速したはいいけど、すぐ次の信号が赤ですぐ停止…なんてことありませんか?
この青になったときに、もしその先の信号が赤もしくは黄色になるのに気づいていれば、無駄に加速をしなくて済んだはずです。
そこに気づいて加速を半分ぐらいにしただけでも、燃費は良くなります。
そういう積み重ねは、燃費に大きく影響してくるものです。
また、なるべく早く道路の先で信号が赤になったり渋滞などを見つけたら、早い段階でアクセルをオフにしてエンジンブレーキを使うことも、燃費には有効です。
エンジンブレーキ(ギアをつないだ状態でアクセルオフにして減速すること)は、最近の車ならアクセルオフにすると自動で燃料供給をカットするので、フットブレーキよりなるべく多く使ったほうが燃費が向上します。
(ただしハイブリッド車に関してはエンジンブレーキを使うよりフットブレーキのほうが燃費が良くなります。それについてはまた別にします)
他にも数台先の先行車がウインカーを出すのをいち早く確認できれば、その後減速するのが予想できるので、早くアクセルを緩めることができるなど、先を見る目は燃費に重要となってきます。
信号や流れなど交通状況を的確に判断して、加速の仕方や減速の仕方を臨機応変に変えていく。
まずはそれを判断する「目」を、少しずつ鍛えていきましょう。
燃費を良くしたいなら、なんとなく前の車に合わせて走っていてはいけません。
常になるべく遠くを見て、交通全体の流れを見ること。
やれることは、結構たくさんあるものです。
また、日ごろ毎日通勤などで同じ道を使っている方は、その道の信号の流れを覚えましょう。
信号と車の流れを覚えて、「ここが青になっても次の信号が青になるのは遅いから、あまり加速しないでおこう」などの対応が取れます。
そういう積み重ねも大切なのです。
重要なのは、流れを読む目で状況を的確に判断し、そのときに必要な力を必要なだけ使って、車を走らせることです。
また、この「目」は安全運転をする上でも、非常に大切な要素となってきます。
ちょっと難しいかもしれませんが、こつこつやっていけばきっと身につくと思います。
私もまだまだ修行中の身です。
良い「目」が身につくよう、がんばっていきましょう。
これまでは主に方法論的な省エネを載せてきました。
今回は「目」・「目線」の話となります。
燃費に役立つ「目」は、まさに交通状況を的確に把握する目です。
一定速度走行のときにも少し触れましたが、先の流れを読む目は非常に大切です。
例えば、信号が青になってぐっと加速したはいいけど、すぐ次の信号が赤ですぐ停止…なんてことありませんか?
この青になったときに、もしその先の信号が赤もしくは黄色になるのに気づいていれば、無駄に加速をしなくて済んだはずです。
そこに気づいて加速を半分ぐらいにしただけでも、燃費は良くなります。
そういう積み重ねは、燃費に大きく影響してくるものです。
また、なるべく早く道路の先で信号が赤になったり渋滞などを見つけたら、早い段階でアクセルをオフにしてエンジンブレーキを使うことも、燃費には有効です。
エンジンブレーキ(ギアをつないだ状態でアクセルオフにして減速すること)は、最近の車ならアクセルオフにすると自動で燃料供給をカットするので、フットブレーキよりなるべく多く使ったほうが燃費が向上します。
(ただしハイブリッド車に関してはエンジンブレーキを使うよりフットブレーキのほうが燃費が良くなります。それについてはまた別にします)
他にも数台先の先行車がウインカーを出すのをいち早く確認できれば、その後減速するのが予想できるので、早くアクセルを緩めることができるなど、先を見る目は燃費に重要となってきます。
信号や流れなど交通状況を的確に判断して、加速の仕方や減速の仕方を臨機応変に変えていく。
まずはそれを判断する「目」を、少しずつ鍛えていきましょう。
燃費を良くしたいなら、なんとなく前の車に合わせて走っていてはいけません。
常になるべく遠くを見て、交通全体の流れを見ること。
やれることは、結構たくさんあるものです。
また、日ごろ毎日通勤などで同じ道を使っている方は、その道の信号の流れを覚えましょう。
信号と車の流れを覚えて、「ここが青になっても次の信号が青になるのは遅いから、あまり加速しないでおこう」などの対応が取れます。
そういう積み重ねも大切なのです。
重要なのは、流れを読む目で状況を的確に判断し、そのときに必要な力を必要なだけ使って、車を走らせることです。
また、この「目」は安全運転をする上でも、非常に大切な要素となってきます。
ちょっと難しいかもしれませんが、こつこつやっていけばきっと身につくと思います。
私もまだまだ修行中の身です。
良い「目」が身につくよう、がんばっていきましょう。
2017/02/06
(この記事は私が過去 2011.3.21. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
続いて一定速度走行(巡航走行)の時の省エネ運転方法です。
一定速度走行とは、発進から加速が終わって、50km/hなら50km/hのまま同じ速度でずーっと走り続けることです。
これができるようになると、燃費がかなり良くなってくるのです。
ここでのポイントは、速度を常に一定で走らせることです。
一定で走らせるなんて簡単じゃないの?、と思っている方、実はこれが案外難しいのです。
道路とは平坦ではなく、常に上り坂や下り坂、うねり、段差など、路面の変化が常にあります。
そんな中を何も考えずにただ走れば、当然ながら車の速度は落ちたり、速くなったりします。
なので、速度を一定にして走り続けるのは実はそれなりに難しく、技量が要るのです。
速度が下がればそれにあわせてほんの少しアクセルを踏んで加速し、また速度が出すぎたらほんの少しアクセルを戻して減速して、常に一定の速度で走るよう調整しながら走ります。
また一定速度で走るコツは、道路状況をなるべく先読みすることです。
道路状況を先読みして、前もって少し速度を上げたり下げたりすることが重要になってきます。
そのためには、まず道路状況を先読みする「目」を鍛えましょう。
「もうすぐ上り坂だな」と認識したら、坂に入る前に先んじて少しアクセルを踏み増して加速しておき、上り坂で速度が落ちないようにします。
逆に下り坂なら前もって早めにアクセルを緩めておき、下り坂で速度が出過ぎないようにする。
その読みが外れたり見逃したりすると、燃料を多く消費してしまう大きな原因となります。
特に上り坂などでは先読みにしくじると、大きく減速してしまってから加速をすることになってしまい、燃費は悪くなります。
上り坂で大きく減速してしまうと、減速してしまった分と登り坂で力強い加速が必要な分とで多くの燃料を使わなければ元の速度まで戻れません。
さらに広い目で見ると、後続の車も減速をさせてしまうことになり、坂道での減速は環境に与える影響は実はかなり大きくなります。
道路状況を的確に見てとって、先読みする「目」を身に付けると、燃費が改善する余地がかなり広がり、さらに一定速度で走るのが格段に楽になります。
また一定速度走行は、アクセルを微妙に踏み込んだり、戻したり、まさに微細なアクセルワークが必要となってきます。
一定速度走行では、常にじわじわアクセルを意識して操作をします。
ここでグッと強く踏み込んでしまうと、無駄に加速をしてしまい、燃料を多く使ってしまうことになります。
加速しすぎないように、また減速しすぎないように、うまーく転がしていくイメージです。
このときのエンジン回転数は低ければ低いほど燃費が良くなる傾向があります。
目安としては、なるべく2000rpm以下をキープするようにしましょう。
さらに、CVTにおいてはもっと注意が必要です。
CVTではほんのちょっと強く踏んだだけで、例の加速モードとなってしまう、シビアな設定の車があります。
加速モードになってしまうと変速を始めてしまい、すぐに加速しないばかりか2~4秒後に強い加速力がやってきます。
そうなると、ほんのちょっと加速したいだけなのにぐぐっと強く加速してしまい、目標の速度を軽くオーバーしてしまいます。
また逆に、アクセルを緩めるときも多く戻しすぎてしまうと、今度は俗にいう減速モード(?)になってしまう可能性があります。
この減速モードになると、強いエンジンブレーキがかかってしまって、急激に速度が落ちてしまいます。
となると何が起きるかというと…、
アクセル踏む → 加速モードになる → 加速しすぎる → 速度オーバー → あわててアクセル戻す → 減速モードになる → 減速しすぎる → 大きく速度が低下 → またアクセル踏み込む → また加速モードになる ・・・以下繰り返し・・・
という、魔のCVTスパイラル(?)に陥ってしまいます。
これに陥ると、CVT車は急激に燃費が悪化します。
このスパイラルは絶対に回避したいところです。
(これがあるのでCVT車は思ったより燃費が伸びてこないのだと思われます)
となると、とにかくCVTは一定速度走行においては、この加速モードと減速モードにさせないことが重要となってきます。
そのためには、ふくらはぎがつるくらいの微細なアクセルワークが必要です。
本当にミリ単位で操作できるテクニックが必要になるので、CVT車は難しいのです。
じわじわのさらに上を行くくらい、ゆーっくりじわーっとアクセルを操作していきます。
もし途中で加速モードになってしまったら、あわてず踏み増しを止めて、ほんの少しだけアクセルを戻して止めて待ち、加速モードが収まるのを待ちます。
逆に減速モードになって急に減速が始まったら、ほんの少しずつ踏み増していって、減速モードを止めます。
減速モードが止まったのがわかったら踏み増しをすぐやめて、今度は加速しすぎるのを防ぐようにします。
やってはいけないのは、「速度が出すぎたっ」と思って一気にアクセルをゼロまで戻す(アクセル踏んでいない状態まで離す)ことと、「減速しすぎてるっ」とあわてて一気にアクセルを多く踏み込むことです。
衝突や事故などの危険がない状況の時は、なるべくじわじわアクセルの操作をして、アクセル操作だけでゆっくり加減速するように心がけてください。
(ちなみにプリ○スなど特に燃費を売りにしている車のCVTは、加速モード・減速モードの切り替わりの設定が特にシビアになので注意してください)
(
また、たまに走り去る車のエンジン音を聞いてると、「ブオッ…、ブオッ…、ブオッ」という風に、アクセルを踏んで離して、踏んで戻して…、という走り方をしている車を見かけることがあります。
これは、アクセルを踏んだ時に現れる加速が、運転しているドライバーが想像している加速の仕方とずれている(急に加速しすぎる)から、無意識にそういう運転になってしまっているのでしょう。
特にCVTの車に多いような気がします。
こういうアクセルワークも燃費には良くありません。
以前も言ったとおり、内燃エンジンは同じ回転数でずーっと回り続ける方が燃費も効率も良くなります。
自動車のエンジンは駆動の構造上同じ回転数で回り続けることはめったにないのですが、それでも上の「ブオッ…、ブオッ…」というアクセルワークよりは、じわっと踏んでいってピタッと止めるアクセルワーク、「ブオォォォー…」というようなエンジン音が出るような運転の方が、確実に燃費は良くなります。
)
さて、一定走行・巡行走行では、このようになるべく低いエンジン回転で、転がすイメージで走ります。
MT、AT(トルコン)についてはそんなには難しくないかもしれません。
CVTについては難しいかもしれませんが、やはり無理や危険の無いよう試してみてください。
また、周りの交通状況に合わせて走ることも重要です。
「自分は40km/hで走るんだ」と、車の流れや混雑具合を無視して、頑なに40km/hで走ろうとするのは危険極まりない運転です。
公道ではあくまで安全に走ることが最も大切なことです。
安全が第一であって燃費は二の次です。
そこは間違いのないようにしてください。
逆に周りの交通状況に合わせながらも、その中でなるべく一定走行ができるよう、また無駄な燃料消費がないようにアクセル調整ができるようになると、非常にスマートでクールなドライビングテクニックだと思います。
難しくてレベルが高いけれど、そんな格好いいドライビングができるように、お互いに努力していきたいですね。
続いて一定速度走行(巡航走行)の時の省エネ運転方法です。
一定速度走行とは、発進から加速が終わって、50km/hなら50km/hのまま同じ速度でずーっと走り続けることです。
これができるようになると、燃費がかなり良くなってくるのです。
ここでのポイントは、速度を常に一定で走らせることです。
一定で走らせるなんて簡単じゃないの?、と思っている方、実はこれが案外難しいのです。
道路とは平坦ではなく、常に上り坂や下り坂、うねり、段差など、路面の変化が常にあります。
そんな中を何も考えずにただ走れば、当然ながら車の速度は落ちたり、速くなったりします。
なので、速度を一定にして走り続けるのは実はそれなりに難しく、技量が要るのです。
速度が下がればそれにあわせてほんの少しアクセルを踏んで加速し、また速度が出すぎたらほんの少しアクセルを戻して減速して、常に一定の速度で走るよう調整しながら走ります。
また一定速度で走るコツは、道路状況をなるべく先読みすることです。
道路状況を先読みして、前もって少し速度を上げたり下げたりすることが重要になってきます。
そのためには、まず道路状況を先読みする「目」を鍛えましょう。
「もうすぐ上り坂だな」と認識したら、坂に入る前に先んじて少しアクセルを踏み増して加速しておき、上り坂で速度が落ちないようにします。
逆に下り坂なら前もって早めにアクセルを緩めておき、下り坂で速度が出過ぎないようにする。
その読みが外れたり見逃したりすると、燃料を多く消費してしまう大きな原因となります。
特に上り坂などでは先読みにしくじると、大きく減速してしまってから加速をすることになってしまい、燃費は悪くなります。
上り坂で大きく減速してしまうと、減速してしまった分と登り坂で力強い加速が必要な分とで多くの燃料を使わなければ元の速度まで戻れません。
さらに広い目で見ると、後続の車も減速をさせてしまうことになり、坂道での減速は環境に与える影響は実はかなり大きくなります。
道路状況を的確に見てとって、先読みする「目」を身に付けると、燃費が改善する余地がかなり広がり、さらに一定速度で走るのが格段に楽になります。
また一定速度走行は、アクセルを微妙に踏み込んだり、戻したり、まさに微細なアクセルワークが必要となってきます。
一定速度走行では、常にじわじわアクセルを意識して操作をします。
ここでグッと強く踏み込んでしまうと、無駄に加速をしてしまい、燃料を多く使ってしまうことになります。
加速しすぎないように、また減速しすぎないように、うまーく転がしていくイメージです。
このときのエンジン回転数は低ければ低いほど燃費が良くなる傾向があります。
目安としては、なるべく2000rpm以下をキープするようにしましょう。
さらに、CVTにおいてはもっと注意が必要です。
CVTではほんのちょっと強く踏んだだけで、例の加速モードとなってしまう、シビアな設定の車があります。
加速モードになってしまうと変速を始めてしまい、すぐに加速しないばかりか2~4秒後に強い加速力がやってきます。
そうなると、ほんのちょっと加速したいだけなのにぐぐっと強く加速してしまい、目標の速度を軽くオーバーしてしまいます。
また逆に、アクセルを緩めるときも多く戻しすぎてしまうと、今度は俗にいう減速モード(?)になってしまう可能性があります。
この減速モードになると、強いエンジンブレーキがかかってしまって、急激に速度が落ちてしまいます。
となると何が起きるかというと…、
アクセル踏む → 加速モードになる → 加速しすぎる → 速度オーバー → あわててアクセル戻す → 減速モードになる → 減速しすぎる → 大きく速度が低下 → またアクセル踏み込む → また加速モードになる ・・・以下繰り返し・・・
という、魔のCVTスパイラル(?)に陥ってしまいます。
これに陥ると、CVT車は急激に燃費が悪化します。
このスパイラルは絶対に回避したいところです。
(これがあるのでCVT車は思ったより燃費が伸びてこないのだと思われます)
となると、とにかくCVTは一定速度走行においては、この加速モードと減速モードにさせないことが重要となってきます。
そのためには、ふくらはぎがつるくらいの微細なアクセルワークが必要です。
本当にミリ単位で操作できるテクニックが必要になるので、CVT車は難しいのです。
じわじわのさらに上を行くくらい、ゆーっくりじわーっとアクセルを操作していきます。
もし途中で加速モードになってしまったら、あわてず踏み増しを止めて、ほんの少しだけアクセルを戻して止めて待ち、加速モードが収まるのを待ちます。
逆に減速モードになって急に減速が始まったら、ほんの少しずつ踏み増していって、減速モードを止めます。
減速モードが止まったのがわかったら踏み増しをすぐやめて、今度は加速しすぎるのを防ぐようにします。
やってはいけないのは、「速度が出すぎたっ」と思って一気にアクセルをゼロまで戻す(アクセル踏んでいない状態まで離す)ことと、「減速しすぎてるっ」とあわてて一気にアクセルを多く踏み込むことです。
衝突や事故などの危険がない状況の時は、なるべくじわじわアクセルの操作をして、アクセル操作だけでゆっくり加減速するように心がけてください。
(ちなみにプリ○スなど特に燃費を売りにしている車のCVTは、加速モード・減速モードの切り替わりの設定が特にシビアになので注意してください)
(
また、たまに走り去る車のエンジン音を聞いてると、「ブオッ…、ブオッ…、ブオッ」という風に、アクセルを踏んで離して、踏んで戻して…、という走り方をしている車を見かけることがあります。
これは、アクセルを踏んだ時に現れる加速が、運転しているドライバーが想像している加速の仕方とずれている(急に加速しすぎる)から、無意識にそういう運転になってしまっているのでしょう。
特にCVTの車に多いような気がします。
こういうアクセルワークも燃費には良くありません。
以前も言ったとおり、内燃エンジンは同じ回転数でずーっと回り続ける方が燃費も効率も良くなります。
自動車のエンジンは駆動の構造上同じ回転数で回り続けることはめったにないのですが、それでも上の「ブオッ…、ブオッ…」というアクセルワークよりは、じわっと踏んでいってピタッと止めるアクセルワーク、「ブオォォォー…」というようなエンジン音が出るような運転の方が、確実に燃費は良くなります。
)
さて、一定走行・巡行走行では、このようになるべく低いエンジン回転で、転がすイメージで走ります。
MT、AT(トルコン)についてはそんなには難しくないかもしれません。
CVTについては難しいかもしれませんが、やはり無理や危険の無いよう試してみてください。
また、周りの交通状況に合わせて走ることも重要です。
「自分は40km/hで走るんだ」と、車の流れや混雑具合を無視して、頑なに40km/hで走ろうとするのは危険極まりない運転です。
公道ではあくまで安全に走ることが最も大切なことです。
安全が第一であって燃費は二の次です。
そこは間違いのないようにしてください。
逆に周りの交通状況に合わせながらも、その中でなるべく一定走行ができるよう、また無駄な燃料消費がないようにアクセル調整ができるようになると、非常にスマートでクールなドライビングテクニックだと思います。
難しくてレベルが高いけれど、そんな格好いいドライビングができるように、お互いに努力していきたいですね。