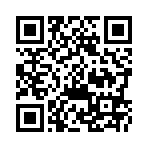2017/02/06
(この記事は私が過去 2011.3.19. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
CVTの続き…と思ったのですが、それは一定速度走行の時にまとめて載せます。
先にMT(マニュアルトランスミッション)での省エネ加速方法をやります。
すいません。
MTはエンジンの回転がそのまま駆動力に反映するので、シンプルでわかりやすいと思います。
ここで簡単に内燃エンジンについて工学的な話をします。
前にも書きましたが、内燃エンジンは回転が低いとき力(トルク)が出にくい性質があります。
一般的なエンジンだと1800~3500rpmくらいがトルクも大きく燃料消費もそこそこ良い範囲だといわれています。
いわば、エンジン出力のおいしいところです。
つまり力を必要とする加速時には、このおいしいところをなるべく使ったほうが燃費に貢献します。
しかし、一般道で50km/h程度への加速のときは回転数低め、2500rpmくらいまでにしたほうが良いようです。
高速道路で100km/h近くまで加速するときは、3500rpmくらいまである程度回してしっかりと加速します。
よってMTではタコメーター(エンジン回転計)を注視していきます。
ただし気にしすぎて危険のないように気をつけましょう。
また変速時は、クラッチを切っている間やつなぎの時に駆動力は当然失われます。
そのロスを減らすため、MTでは飛ばしシフトを使います。
1速→3速→4速とか1速→3速→5速のように目的速度に応じて、変速の回数を減らします。
回数を減らせばその分ロスも減るわけです。
では実際の方法です。
ミートクラッチで発進したあとは、じわじわアクセルでゆっくり加速していきます。
10~15km/hくらいまでじわりと加速したら、じわじわアクセルは終わりです。
あとはトルコンATと同じように、アクセルをある程度一度に踏み込み、例のおいしいところを使って加速していきます。
必要な力を必要なだけ作り出すように、加速しすぎたり逆に足りなくないように、程よくある程度踏み込むこと。
クッと一気に踏み込んだらそのまま足を止めて「待つ」イメージです。
踏み増したり戻したりしないよう、何度か試して踏み込み量を覚えましょう。
目安としては、一般道なら過不足なくすんなりと、すーっと自然な感じで2500rpmまで加速するくらいの踏み込み量です。
1速でおいしいところ、2500rpm(高速なら3500rpm)くらいまで使って加速し、3速へ飛ばしシフトします。
発進時以降はあまりじわじわアクセルは使いません。
3速につないだら、ある程度踏み込んで過不足ないよう2500rpmまで加速したらまた飛ばしシフト…と続けていきます。
目的の速度に到達したらアクセルを緩めて加速を止めて、一定速度走行へと移っていきます。
では次回は一定速度走行での省エネのやり方となります。
何度も言いますが、この方法を試すときは無理や危険が無いよう、十分注意して試してください。
よろしくお願いします。
CVTの続き…と思ったのですが、それは一定速度走行の時にまとめて載せます。
先にMT(マニュアルトランスミッション)での省エネ加速方法をやります。
すいません。
MTはエンジンの回転がそのまま駆動力に反映するので、シンプルでわかりやすいと思います。
ここで簡単に内燃エンジンについて工学的な話をします。
前にも書きましたが、内燃エンジンは回転が低いとき力(トルク)が出にくい性質があります。
一般的なエンジンだと1800~3500rpmくらいがトルクも大きく燃料消費もそこそこ良い範囲だといわれています。
いわば、エンジン出力のおいしいところです。
つまり力を必要とする加速時には、このおいしいところをなるべく使ったほうが燃費に貢献します。
しかし、一般道で50km/h程度への加速のときは回転数低め、2500rpmくらいまでにしたほうが良いようです。
高速道路で100km/h近くまで加速するときは、3500rpmくらいまである程度回してしっかりと加速します。
よってMTではタコメーター(エンジン回転計)を注視していきます。
ただし気にしすぎて危険のないように気をつけましょう。
また変速時は、クラッチを切っている間やつなぎの時に駆動力は当然失われます。
そのロスを減らすため、MTでは飛ばしシフトを使います。
1速→3速→4速とか1速→3速→5速のように目的速度に応じて、変速の回数を減らします。
回数を減らせばその分ロスも減るわけです。
では実際の方法です。
ミートクラッチで発進したあとは、じわじわアクセルでゆっくり加速していきます。
10~15km/hくらいまでじわりと加速したら、じわじわアクセルは終わりです。
あとはトルコンATと同じように、アクセルをある程度一度に踏み込み、例のおいしいところを使って加速していきます。
必要な力を必要なだけ作り出すように、加速しすぎたり逆に足りなくないように、程よくある程度踏み込むこと。
クッと一気に踏み込んだらそのまま足を止めて「待つ」イメージです。
踏み増したり戻したりしないよう、何度か試して踏み込み量を覚えましょう。
目安としては、一般道なら過不足なくすんなりと、すーっと自然な感じで2500rpmまで加速するくらいの踏み込み量です。
1速でおいしいところ、2500rpm(高速なら3500rpm)くらいまで使って加速し、3速へ飛ばしシフトします。
発進時以降はあまりじわじわアクセルは使いません。
3速につないだら、ある程度踏み込んで過不足ないよう2500rpmまで加速したらまた飛ばしシフト…と続けていきます。
目的の速度に到達したらアクセルを緩めて加速を止めて、一定速度走行へと移っていきます。
では次回は一定速度走行での省エネのやり方となります。
何度も言いますが、この方法を試すときは無理や危険が無いよう、十分注意して試してください。
よろしくお願いします。
2017/02/06
(この記事は私が過去 2011.3.19. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
(2023.9.5. 加筆・修正)
では、最近日本で増えている、CVT(無段階変速機)での省エネ運転方法です。
結論から言ってしまうと、CVTはかなり難しい!です。
「CVT=燃費が良い」と認識されがちですが、それはカタログ燃費に表れる話であって現実の燃費ではそう簡単ではありません。
軽自動車など軽い車については確かに燃費は良くなりますが、普通車以上の車重では普通のトルコンATをうまく使ったほうが、燃費が良くなるのではないかと私は考えます。
と技術的な話は後回しにして、CVTでの省エネ運転です…。
一番のコツは「アクセルを踏み増ししてはいけない」ことでしょうか。
クリープ現象を使って発進した後は、別にふんわりアクセルではなく、最初からそれなりにグッとアクセルを踏んで大丈夫です。
トルコンATの時と同じように、加速するときはある程度アクセルを踏み込んでおいて、加速が来るのを待つイメージです。
しかし、CVTの場合強い加速を得ようとすると、俗にいう加速モード(?)に切り替わります。
そのモードはエンジン回転がグワ~と上がるくせに加速するまでに時間がかかるため、実際に加速力が出るにはたいてい2~4秒ほど時間ロスがかかってしまいます。(これがCVTの欠点でもあります)
その間アクセルを踏み増すのを我慢して、待っていないといけません。
人間の心理として、加速しようとアクセルを踏んだのに加速力がすぐ得られないと、無意識にさらに踏み込んでしまいがちです。
そしてついつい踏み込みすぎてしまうと、あとから踏んだ分の加速をしようと、強い加速がやってきて速度が出すぎてしまいます。
そうすると、本来加速に必要なだけの燃料以上を使ってしまうことになるので、当然燃料を無駄に使ってしまいます。
アクセルをある程度踏み込んだら、加速がすぐ来なくても踏み増すのを我慢して、じっと待つ…。
ここがCVTの一番のポイントです。
そのままアクセルを踏み増すのを我慢して待っていると、後から加速力が来る感じで加速し始めます。
そして目的の速度に達したら、アクセルをやや多めに戻して加速を止めます。
CVTの場合、トルコンATよりもはっきりと分かるようにアクセルを多めに戻して、加速終了の意思を示さないと、延々と加速し続ける傾向があります。
CVT車に乗っていて、気付いたら10km/hも20km/hも目的速度よりオーバーしていた、という経験ありませんか?
アクセルをある程度しっかり戻して、加速モードを終わりにする必要があるのです。
ただし、アクセルを戻しすぎると今度は俗にいう減速モード(?)になって、強いエンジンブレーキがかかって急に減速を始めてしまうこともあります。これは車種によって差がありますので、自分の車はどのくらいのアクセル操作すればちょうど良いのかは、皆さんそれぞれで確認してみてください。(安全第一でおねがいします)
ここまでが初級でしょうか。
ここから先の定速走行がまた難しいのですが…。
難しいし長くなるので、また別の記事にします。(^ ^;;
さて、ここからは技術的な解説です。
アクセルを少し多く踏み込むと、CVTの場合「グワ~」とエンジンの回転は上がりますが反応が鈍く、ちっとも加速しない!という経験ありませんか?
このエンジンは回っているのに加速しない(駆動力が増えない)という現象は、CVTが強い加速力を得ようと変速をするときの時間差ロスから起きています。
変速が始まると、その間駆動力(速度)が変わらないようにしながらギア比を変える動作を始めるので変速に時間がかかり、その間は力(トルク)はタイヤに伝わらず加速しません。
CVTの変速は具体的に言うと、加速のためにエンジン効率が良いエンジン回転数にしようとする→今の速度をキープしたまま変速するためにギア比を変えながらエンジン回転上げる→ギア比とエンジン回転数のすり合わせをする→加速開始、という動作をするため、強い加速力を得るのに2~4秒ほど時間がかかってしまうのです。
その間加速力は得られないので、エンジンは空吹かしのような状態となり、無駄に燃料を使っていることになります。
変速の回数(加速モードのオン・オフ)が多くなってしまうと、無駄な燃料を多く使ってしまうこととなるのです。
しかし、この加速モード(?)はしっかり加速したいときには、効率も良く有効なモードです。
前にも述べたとおり、内燃エンジンは回転が低いと力(トルク)が出ません。
CVTはエンジンの力が出る回転をキープしながら、加速をするために無段階に変速するものです。
(普通の有段変速機だと、2速なら2速でアクセルを踏んだ分だけエンジンの回転数が上がり、グワーンと回った分に応じで速度が出ます。これは2速のギア比が機械的に固定しているからです。
しかしCVTは変速機のギア比は自在であり固定されていません。CVTの場合はエンジン回転は3000なら3000rpmで固定したまま、速度だけが上がっていきます。つまりエンジン回転数が固定のままで変速機側のギア比の方が変化するので車が加速するのです)
加速モードになるとエンジン回転はおおよそ2500~3800rpm付近で固定されたままとなります。
つまりその回転がエンジンのおいしいところ(効率よく力が出る回転数)なんです。
なので、走り出しの加速時や高速で十分加速を得たいときなどには、加速モードをしっかり使って素早く加速を終えたほうが効率が良いと考えてます。
この加速モードを有効に使いつつ、CVTの変速の回数(加速モードへのオン・オフ)をなるべく減らして走るのが、CVTの理想的な省エネ運転方法、となると考えてます。
(CVTの定速走行(巡航走行)については→こちらを続けてみてください)
以上、続きはまた次回にします。
m(_ _)m
(2011.4.13. 追記)
すいません。m(_ _)m
後付けの補足・訂正です。
高速などでしっかり加速したいときは、上記の加速モードを使ってしっかり加速したほうが良いのですが、一般道40km/hくらいへの加速のときは、加速モードを使わないほうが燃費が良くなるようです。
やり方としては、加速モードにならないようにじわじわアクセルで加速していきます。
変速してグワ~とエンジン回転が上がらないよう、じんわり踏んでいきます。
しかしながら、実はこれ、かなり難しいです。(^ ^;;
最近の車はちょっと強めにアクセルを踏んだだけで過度に加速モードになり、変速を始めてしまうCVT車が多いのです。
もし加速モードになったとしても、あわてずに踏み込むのを止めて少しだけアクセルを戻し、そのまま待ちましょう。
待っているうちに目的速度になったら、アクセルをある程度戻して一定速度走行へと移ります。
まだ加速がいるときは、加速モードにならないよう、再びじわじわと踏み増していきます。
こうすると燃費が良くなるようですが、無理をすると足がつります。(汗)
無理のないようお願いします。
(2023.9.5. 加筆・修正)
では、最近日本で増えている、CVT(無段階変速機)での省エネ運転方法です。
結論から言ってしまうと、CVTはかなり難しい!です。
「CVT=燃費が良い」と認識されがちですが、それはカタログ燃費に表れる話であって現実の燃費ではそう簡単ではありません。
軽自動車など軽い車については確かに燃費は良くなりますが、普通車以上の車重では普通のトルコンATをうまく使ったほうが、燃費が良くなるのではないかと私は考えます。
と技術的な話は後回しにして、CVTでの省エネ運転です…。
一番のコツは「アクセルを踏み増ししてはいけない」ことでしょうか。
クリープ現象を使って発進した後は、別にふんわりアクセルではなく、最初からそれなりにグッとアクセルを踏んで大丈夫です。
トルコンATの時と同じように、加速するときはある程度アクセルを踏み込んでおいて、加速が来るのを待つイメージです。
しかし、CVTの場合強い加速を得ようとすると、俗にいう加速モード(?)に切り替わります。
そのモードはエンジン回転がグワ~と上がるくせに加速するまでに時間がかかるため、実際に加速力が出るにはたいてい2~4秒ほど時間ロスがかかってしまいます。(これがCVTの欠点でもあります)
その間アクセルを踏み増すのを我慢して、待っていないといけません。
人間の心理として、加速しようとアクセルを踏んだのに加速力がすぐ得られないと、無意識にさらに踏み込んでしまいがちです。
そしてついつい踏み込みすぎてしまうと、あとから踏んだ分の加速をしようと、強い加速がやってきて速度が出すぎてしまいます。
そうすると、本来加速に必要なだけの燃料以上を使ってしまうことになるので、当然燃料を無駄に使ってしまいます。
アクセルをある程度踏み込んだら、加速がすぐ来なくても踏み増すのを我慢して、じっと待つ…。
ここがCVTの一番のポイントです。
そのままアクセルを踏み増すのを我慢して待っていると、後から加速力が来る感じで加速し始めます。
そして目的の速度に達したら、アクセルをやや多めに戻して加速を止めます。
CVTの場合、トルコンATよりもはっきりと分かるようにアクセルを多めに戻して、加速終了の意思を示さないと、延々と加速し続ける傾向があります。
CVT車に乗っていて、気付いたら10km/hも20km/hも目的速度よりオーバーしていた、という経験ありませんか?
アクセルをある程度しっかり戻して、加速モードを終わりにする必要があるのです。
ただし、アクセルを戻しすぎると今度は俗にいう減速モード(?)になって、強いエンジンブレーキがかかって急に減速を始めてしまうこともあります。これは車種によって差がありますので、自分の車はどのくらいのアクセル操作すればちょうど良いのかは、皆さんそれぞれで確認してみてください。(安全第一でおねがいします)
ここまでが初級でしょうか。
ここから先の定速走行がまた難しいのですが…。
難しいし長くなるので、また別の記事にします。(^ ^;;
さて、ここからは技術的な解説です。
アクセルを少し多く踏み込むと、CVTの場合「グワ~」とエンジンの回転は上がりますが反応が鈍く、ちっとも加速しない!という経験ありませんか?
このエンジンは回っているのに加速しない(駆動力が増えない)という現象は、CVTが強い加速力を得ようと変速をするときの時間差ロスから起きています。
変速が始まると、その間駆動力(速度)が変わらないようにしながらギア比を変える動作を始めるので変速に時間がかかり、その間は力(トルク)はタイヤに伝わらず加速しません。
CVTの変速は具体的に言うと、加速のためにエンジン効率が良いエンジン回転数にしようとする→今の速度をキープしたまま変速するためにギア比を変えながらエンジン回転上げる→ギア比とエンジン回転数のすり合わせをする→加速開始、という動作をするため、強い加速力を得るのに2~4秒ほど時間がかかってしまうのです。
その間加速力は得られないので、エンジンは空吹かしのような状態となり、無駄に燃料を使っていることになります。
変速の回数(加速モードのオン・オフ)が多くなってしまうと、無駄な燃料を多く使ってしまうこととなるのです。
しかし、この加速モード(?)はしっかり加速したいときには、効率も良く有効なモードです。
前にも述べたとおり、内燃エンジンは回転が低いと力(トルク)が出ません。
CVTはエンジンの力が出る回転をキープしながら、加速をするために無段階に変速するものです。
(普通の有段変速機だと、2速なら2速でアクセルを踏んだ分だけエンジンの回転数が上がり、グワーンと回った分に応じで速度が出ます。これは2速のギア比が機械的に固定しているからです。
しかしCVTは変速機のギア比は自在であり固定されていません。CVTの場合はエンジン回転は3000なら3000rpmで固定したまま、速度だけが上がっていきます。つまりエンジン回転数が固定のままで変速機側のギア比の方が変化するので車が加速するのです)
加速モードになるとエンジン回転はおおよそ2500~3800rpm付近で固定されたままとなります。
つまりその回転がエンジンのおいしいところ(効率よく力が出る回転数)なんです。
なので、走り出しの加速時や高速で十分加速を得たいときなどには、加速モードをしっかり使って素早く加速を終えたほうが効率が良いと考えてます。
この加速モードを有効に使いつつ、CVTの変速の回数(加速モードへのオン・オフ)をなるべく減らして走るのが、CVTの理想的な省エネ運転方法、となると考えてます。
(CVTの定速走行(巡航走行)については→こちらを続けてみてください)
以上、続きはまた次回にします。
m(_ _)m
(2011.4.13. 追記)
すいません。m(_ _)m
後付けの補足・訂正です。
高速などでしっかり加速したいときは、上記の加速モードを使ってしっかり加速したほうが良いのですが、一般道40km/hくらいへの加速のときは、加速モードを使わないほうが燃費が良くなるようです。
やり方としては、加速モードにならないようにじわじわアクセルで加速していきます。
変速してグワ~とエンジン回転が上がらないよう、じんわり踏んでいきます。
しかしながら、実はこれ、かなり難しいです。(^ ^;;
最近の車はちょっと強めにアクセルを踏んだだけで過度に加速モードになり、変速を始めてしまうCVT車が多いのです。
もし加速モードになったとしても、あわてずに踏み込むのを止めて少しだけアクセルを戻し、そのまま待ちましょう。
待っているうちに目的速度になったら、アクセルをある程度戻して一定速度走行へと移ります。
まだ加速がいるときは、加速モードにならないよう、再びじわじわと踏み増していきます。
こうすると燃費が良くなるようですが、無理をすると足がつります。(汗)
無理のないようお願いします。
2017/02/06
(この記事は私が過去 2011.3.16. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
つづいて、発進後の加速のアクセル操作について、です。
よく「ふんわりアクセルが良い」とか「エンジン回転数は低いほうが良い」とか言われていますが、厳密に言うと違います。
いつもふんわりアクセル使ってエンジン回転を2000rpm以上に上げないように走っている方…、残念ですが状況によってはあまり燃費が伸びないかも。
正確には、ある場面ではふんわりアクセルをし、ある場面では回転を低く抑えるのが良い、のです。
加速をする場面では、ある程度アクセルを踏んだほうが燃費が良い時もあります。
要はケースバイケース。
では、どういう場面でどうアクセル操作をするのが燃費に良いのか、説明していきます。
AT(トルコン)車で説明します。
クリープ現象を使って発進した後は、ふんわりアクセルでゆっくり加速します。
ふんわりというより、じわじわアクセルと言ったほうがニュアンスとしては合っている気がします。
じわーっと加速していって、スピードが15~20km/hに達したらじわじわアクセルは終わり。
後は普段通りのアクセルワークでもかまいません。
前回も言いましたが、発進からある程度の加速までが一番車の燃料を喰う場面です。
初めの加速だけでもゆっくりと加速すれば、それなりの省エネ効果を発揮します。
初級としてはここまでです。
さらに燃費を良くしたい方は難度が上がりますが、続きを見てください。
じわじわアクセルの後は、目的のスピードまでアクセルをある程度グッと踏み込みます。
たとえば50km/hまで加速したいときは、ふんわりアクセルでだらだらと時間をかけて加速していくよりも、15km/hあたりからある程度しっかり加速をして早く50km/hに到達し、あとは回転を抑えた一定速走行で走ったほうが燃費が良くなります。
感覚としては、じわじわ踏んできた踏み込み量と同じ分だけ一気にクッと踏み込む感じ。(わかりにくい?)
エンジン回転は3000rpmあたりまで使ってよいので、それなりに素早く、しっかり加速します。
(高速道路で100km/hくらいまで加速するときは、3500~4000rpmくらいまで回してしっかり加速すると良いでしょう)
ただし加速のし過ぎ、つまり急加速はダメです。
当然その分燃費が悪化します。
目的のスピードに応じて、加速の仕方、すなわちアクセル踏み込む量をうまく調整します。
高速で100km/hまで加速するなら、多めにアクセルを踏み込んで加速し、50km/hならそれ相応に踏み込む…。
目安は目的の速度へ過不足なくすんなり加速するようにします。
理想は、目的が50km/hならすいーっと(すんなり?)50km/hまで加速したうえで、アクセルを動かさなくてもそのまま50km/h程度で一定速で走れるくらいの踏み込み量です。
難しいですけど、必要なエネルギー(加速力)を必要なだけ、アクセルで作り出してあげる感覚でアクセルを踏みましょう。
それから、加速に必要だと思う適正な踏み込み量を一度にぐっと踏んだら、そのまま足を止めるようにします。
加速の最中はアクセルを踏み増したり戻したりせず、踏んだら止めて「待つ」イメージです。
(明らかに加速し過ぎのときは、危険ですのでアクセルを戻しましょう)
加速をして、目的の速度になったらアクセルをやや戻して加速を止めます。
近年の車は、アクセルを動かさずに止めたままでは加速が一向に止まらない、という車があります。
そういう車では必ずアクセルを少し戻して、「加速は終わり」という意思を見せないといけないようです。
加速し続けて目的速度を超過してしまうと、無駄な燃料を使ってしまうことになります。
加速を止めたら、後は一定速度で走るようにします。
一定速度で走るときは、なるべくエンジン回転をなるべく低く抑えるように走ります。
このときはエンジン回転は低ければ低いほど燃費は良い。
そして一定の速度を保つために、微細にアクセルを踏んだり戻したりして、速度を調整しながら走ります。
転がす…といったイメージでしょうか。
(これについては別の記事にするつもりです)
これがAT車の燃費の良い加速のやり方です。
いうなれば、はじめチョロチョロなかパッパ、という感じでしょうか。
後半のアクセル操作は少し難しいので、必ず無理の無いよう危険の無いようにお願いします。
それと、これはあくまでトルコン(トルクコンバーター)式ATでのアクセル操作です。
近年国産AT車で増えているCVT(無段階変速機)のときは、また違った方法になりますので、注意してください。
CVTとMTの省エネのアクセル操作と、その詳しい理由については、また別の記事にします。
つづいて、発進後の加速のアクセル操作について、です。
よく「ふんわりアクセルが良い」とか「エンジン回転数は低いほうが良い」とか言われていますが、厳密に言うと違います。
いつもふんわりアクセル使ってエンジン回転を2000rpm以上に上げないように走っている方…、残念ですが状況によってはあまり燃費が伸びないかも。
正確には、ある場面ではふんわりアクセルをし、ある場面では回転を低く抑えるのが良い、のです。
加速をする場面では、ある程度アクセルを踏んだほうが燃費が良い時もあります。
要はケースバイケース。
では、どういう場面でどうアクセル操作をするのが燃費に良いのか、説明していきます。
AT(トルコン)車で説明します。
クリープ現象を使って発進した後は、ふんわりアクセルでゆっくり加速します。
ふんわりというより、じわじわアクセルと言ったほうがニュアンスとしては合っている気がします。
じわーっと加速していって、スピードが15~20km/hに達したらじわじわアクセルは終わり。
後は普段通りのアクセルワークでもかまいません。
前回も言いましたが、発進からある程度の加速までが一番車の燃料を喰う場面です。
初めの加速だけでもゆっくりと加速すれば、それなりの省エネ効果を発揮します。
初級としてはここまでです。
さらに燃費を良くしたい方は難度が上がりますが、続きを見てください。
じわじわアクセルの後は、目的のスピードまでアクセルをある程度グッと踏み込みます。
たとえば50km/hまで加速したいときは、ふんわりアクセルでだらだらと時間をかけて加速していくよりも、15km/hあたりからある程度しっかり加速をして早く50km/hに到達し、あとは回転を抑えた一定速走行で走ったほうが燃費が良くなります。
感覚としては、じわじわ踏んできた踏み込み量と同じ分だけ一気にクッと踏み込む感じ。(わかりにくい?)
エンジン回転は3000rpmあたりまで使ってよいので、それなりに素早く、しっかり加速します。
(高速道路で100km/hくらいまで加速するときは、3500~4000rpmくらいまで回してしっかり加速すると良いでしょう)
ただし加速のし過ぎ、つまり急加速はダメです。
当然その分燃費が悪化します。
目的のスピードに応じて、加速の仕方、すなわちアクセル踏み込む量をうまく調整します。
高速で100km/hまで加速するなら、多めにアクセルを踏み込んで加速し、50km/hならそれ相応に踏み込む…。
目安は目的の速度へ過不足なくすんなり加速するようにします。
理想は、目的が50km/hならすいーっと(すんなり?)50km/hまで加速したうえで、アクセルを動かさなくてもそのまま50km/h程度で一定速で走れるくらいの踏み込み量です。
難しいですけど、必要なエネルギー(加速力)を必要なだけ、アクセルで作り出してあげる感覚でアクセルを踏みましょう。
それから、加速に必要だと思う適正な踏み込み量を一度にぐっと踏んだら、そのまま足を止めるようにします。
加速の最中はアクセルを踏み増したり戻したりせず、踏んだら止めて「待つ」イメージです。
(明らかに加速し過ぎのときは、危険ですのでアクセルを戻しましょう)
加速をして、目的の速度になったらアクセルをやや戻して加速を止めます。
近年の車は、アクセルを動かさずに止めたままでは加速が一向に止まらない、という車があります。
そういう車では必ずアクセルを少し戻して、「加速は終わり」という意思を見せないといけないようです。
加速し続けて目的速度を超過してしまうと、無駄な燃料を使ってしまうことになります。
加速を止めたら、後は一定速度で走るようにします。
一定速度で走るときは、なるべくエンジン回転をなるべく低く抑えるように走ります。
このときはエンジン回転は低ければ低いほど燃費は良い。
そして一定の速度を保つために、微細にアクセルを踏んだり戻したりして、速度を調整しながら走ります。
転がす…といったイメージでしょうか。
(これについては別の記事にするつもりです)
これがAT車の燃費の良い加速のやり方です。
いうなれば、はじめチョロチョロなかパッパ、という感じでしょうか。
後半のアクセル操作は少し難しいので、必ず無理の無いよう危険の無いようにお願いします。
それと、これはあくまでトルコン(トルクコンバーター)式ATでのアクセル操作です。
近年国産AT車で増えているCVT(無段階変速機)のときは、また違った方法になりますので、注意してください。
CVTとMTの省エネのアクセル操作と、その詳しい理由については、また別の記事にします。
2017/02/05
(この記事は私が過去 2011.3.15. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
はじめに…。
このたび東北関東大震災(東日本大震災)に被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
まだまだ長く混乱が続くかと思いますが、悲観したりせずなにとぞご自愛ください。
さて、大震災にあたって私がブログでできること…、と考えて「省エネ運転のやり方」にたどり着きました。
今後化石燃料は供給不足になるとともに、被災地へと優先的に送られるでしょう。
日本全体で少しでも燃料消費を抑えてあげれば、それだけ被災地へ送ることができるはず。
また、どうせなら普段よく聞くエコ運転法より、若干我流となりますがもう一段上の省エネ運転方法を載せたいと思っています。
本題とはそれますが、なるべくわかりやすく説明していきたいと思います。
(基本文章だけとなるので、限界はあると思います…)
少し難しいところもあるかもしれませんが、無理や危険のないように試してみてください。
よろしくお願いします。
ではさっそく省エネ運転の話へいきましょう。
まず、自動車を走らせる上でもっとも燃料を消費する時とは、発進の時です。
車は軽でも最低700kg、普通車なら1t以上、ミニバンなら2t近くの車体重量があります。
この重たい車を初速ゼロから発進させるには、多くのエネルギーが必要になります。
また内燃エンジンは回転数が低い時が、もっとも効率が悪いものです。
つまり、停止状態からの発進は最も燃料を喰います。
ここを改善すれば燃費にかなり貢献してくるのです。
方法としては、AT車なら必ずクリープ現象(ブレーキを離すと車が自然に動くこと)を使って、1、2、と2秒ほど待ってからアクセルを踏み始めること。
MT車ならばミートクラッチを使います。
アクセル踏まずにまず半クラにし、当たりの感触があったらアクセルをゆっくり踏みつつ、同時にゆっくりとクラッチをつないでいきます。
ミートクラッチは初めてやると少し難しいかも知れません。(エンストぎりぎりで発進するような感じです)
無理のないよう、危険のないようにやってみてください。
イメージとしては、スゥーッと、またはスィーっと発進するような感じです。
一方、発進時にアクセルを一気に踏み込んでグワッと加速するのは、力学的にも非常に効率が悪く燃料を無駄に消費する行為です。
都会でよく見られるような青信号スタートダッシュ(?)は、ただ無駄に燃料を消費するだけなので、基本的にはやめましょう。
省エネ運転第1回としては、まずはここまでにします。
皆さん、余裕があれば試してみてください。
はじめに…。
このたび東北関東大震災(東日本大震災)に被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
まだまだ長く混乱が続くかと思いますが、悲観したりせずなにとぞご自愛ください。
さて、大震災にあたって私がブログでできること…、と考えて「省エネ運転のやり方」にたどり着きました。
今後化石燃料は供給不足になるとともに、被災地へと優先的に送られるでしょう。
日本全体で少しでも燃料消費を抑えてあげれば、それだけ被災地へ送ることができるはず。
また、どうせなら普段よく聞くエコ運転法より、若干我流となりますがもう一段上の省エネ運転方法を載せたいと思っています。
本題とはそれますが、なるべくわかりやすく説明していきたいと思います。
(基本文章だけとなるので、限界はあると思います…)
少し難しいところもあるかもしれませんが、無理や危険のないように試してみてください。
よろしくお願いします。
ではさっそく省エネ運転の話へいきましょう。
まず、自動車を走らせる上でもっとも燃料を消費する時とは、発進の時です。
車は軽でも最低700kg、普通車なら1t以上、ミニバンなら2t近くの車体重量があります。
この重たい車を初速ゼロから発進させるには、多くのエネルギーが必要になります。
また内燃エンジンは回転数が低い時が、もっとも効率が悪いものです。
つまり、停止状態からの発進は最も燃料を喰います。
ここを改善すれば燃費にかなり貢献してくるのです。
方法としては、AT車なら必ずクリープ現象(ブレーキを離すと車が自然に動くこと)を使って、1、2、と2秒ほど待ってからアクセルを踏み始めること。
MT車ならばミートクラッチを使います。
アクセル踏まずにまず半クラにし、当たりの感触があったらアクセルをゆっくり踏みつつ、同時にゆっくりとクラッチをつないでいきます。
ミートクラッチは初めてやると少し難しいかも知れません。(エンストぎりぎりで発進するような感じです)
無理のないよう、危険のないようにやってみてください。
イメージとしては、スゥーッと、またはスィーっと発進するような感じです。
一方、発進時にアクセルを一気に踏み込んでグワッと加速するのは、力学的にも非常に効率が悪く燃料を無駄に消費する行為です。
都会でよく見られるような青信号スタートダッシュ(?)は、ただ無駄に燃料を消費するだけなので、基本的にはやめましょう。
省エネ運転第1回としては、まずはここまでにします。
皆さん、余裕があれば試してみてください。
2017/02/05
(この記事は、私が過去 2010.12.3. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
すいません、また間が空きました。
どうもPCの調子が悪くて…、なんとかしないといけないかな。^^;
さて、今回はウインカー、方向指示器の話です。
皆さんは周りの車に迷惑がかからないよう、ちゃんと早めに出せていますか?
私は信州の車は基本的にウインカーは「遅め」、と感じます。
車で走っていて、「もうちょっと早めにウインカー出してよ」と思った経験はありませんか?
ウインカーは車にとって、自分の行動を周りの車に知らせるための大事な機能の一つです。
自分が何をしたいのか、これから何をするのか、周りにきちんと知らせるためには、ウインカーは早めに点けなければ意味がありません。
逆にそれが遅いということは、いつ事故が起きてもおかしくないということです。
法律ではウインカーは、交差点の30m手前から出すようになっています。
これはよく免許の試験に出るので、知っている方も多いでしょう。
でも実際に公道で30m手前からウインカーを出したら、どこで曲がるんだか分からなくて逆に困りますね。
ちょっと実情に合わない規定かもしれませんが、でも間際で突然出されるよりかは安全といえます。
個人的にはその半分の15mくらい手前からウインカー出すのがベターなんじゃないかと思っています。
目安としては、交差点手前の道路上に矢印の標識(右折、直進左折とか)がありますが、あれは5m(または10m)ごとに表示されています。
つまり交差点手前の矢印の3つ目あたりからウインカーを出すと、ちょうどよく感じます。
また、一般的な普通乗用車の長さもおよそ5m。
3台前の車が交差点にいるころには、ウインカーを出しておきたいところです。
また、矢印などがない小さい交差点を曲がるときでも、ブレーキを踏む前に必ずウインカーを出しましょう。
ウインカーを出してからブレーキランプが点けば、後続車は曲がるために減速するんだな、と分かります。
そうすればその後どう行動するか分かるし、後続車は何に気をつければ良いのか予想しやすくなり、安全性は増します。
ちなみに、ウインカーをつけてから2回ほど点滅してブレーキを踏めるようにウインカーを出すのが、個人的に良いと思います。
毎日気をつけてウインカーを早めに出すようにしていると、自然に癖がついていつでも早めに出せるようになっていきます。
ぜひ取り組んでみてください。
ウインカーを早めにきちんと出すことは、自分と自分の車、そして同乗者を交通事故から守るための、大切なことだと思います。
以前のライトの話と同様、自分で自分の首を絞めることにならないように、的確にきちんとウインカーを出していきましょう。
すいません、また間が空きました。
どうもPCの調子が悪くて…、なんとかしないといけないかな。^^;
さて、今回はウインカー、方向指示器の話です。
皆さんは周りの車に迷惑がかからないよう、ちゃんと早めに出せていますか?
私は信州の車は基本的にウインカーは「遅め」、と感じます。
車で走っていて、「もうちょっと早めにウインカー出してよ」と思った経験はありませんか?
ウインカーは車にとって、自分の行動を周りの車に知らせるための大事な機能の一つです。
自分が何をしたいのか、これから何をするのか、周りにきちんと知らせるためには、ウインカーは早めに点けなければ意味がありません。
逆にそれが遅いということは、いつ事故が起きてもおかしくないということです。
法律ではウインカーは、交差点の30m手前から出すようになっています。
これはよく免許の試験に出るので、知っている方も多いでしょう。
でも実際に公道で30m手前からウインカーを出したら、どこで曲がるんだか分からなくて逆に困りますね。
ちょっと実情に合わない規定かもしれませんが、でも間際で突然出されるよりかは安全といえます。
個人的にはその半分の15mくらい手前からウインカー出すのがベターなんじゃないかと思っています。
目安としては、交差点手前の道路上に矢印の標識(右折、直進左折とか)がありますが、あれは5m(または10m)ごとに表示されています。
つまり交差点手前の矢印の3つ目あたりからウインカーを出すと、ちょうどよく感じます。
また、一般的な普通乗用車の長さもおよそ5m。
3台前の車が交差点にいるころには、ウインカーを出しておきたいところです。
また、矢印などがない小さい交差点を曲がるときでも、ブレーキを踏む前に必ずウインカーを出しましょう。
ウインカーを出してからブレーキランプが点けば、後続車は曲がるために減速するんだな、と分かります。
そうすればその後どう行動するか分かるし、後続車は何に気をつければ良いのか予想しやすくなり、安全性は増します。
ちなみに、ウインカーをつけてから2回ほど点滅してブレーキを踏めるようにウインカーを出すのが、個人的に良いと思います。
毎日気をつけてウインカーを早めに出すようにしていると、自然に癖がついていつでも早めに出せるようになっていきます。
ぜひ取り組んでみてください。
ウインカーを早めにきちんと出すことは、自分と自分の車、そして同乗者を交通事故から守るための、大切なことだと思います。
以前のライトの話と同様、自分で自分の首を絞めることにならないように、的確にきちんとウインカーを出していきましょう。
2017/02/05
(この記事は私が過去 2010.9.20. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
暑すぎた夏も過ぎて涼しくなると共に、日が落ちるのもだいぶ早くなってきました。
さて、皆さんは日が傾いて薄暗くなってきたとき、どのタイミングで車のライトを点けていますか?
よく「ライトは早めに点けましょう」と言われていますが、実際松本の街の車を見るとだいぶ暗くなってもライトを点けない車が結構たくさんいます。
それは、なぜ早く点けたほうが良いのか、分かっていない方が多いからでしょう。
最近「ライトは自分が周りを見るためというより、周りに自分の車の存在を知らせるため、存在をアピールするために点ける」ということを聞きませんか?
暗い中でライトを点けずに道を走れば、当然周りの車からは無灯火で車が見づらいので、危険極まりないですよね。
無灯火だと対向してきた車でさえ、十分見えなくてドキッとすることがありませんか?
つまり、ライトを点ければ周りからその車の存在が分かるので、周りの車が十分注意をしてくれます。
お互いがお互いにライトを点けていれば、お互いが良く見えるので危険が減り、事故に遭う確率が減るわけです。
平たく言ってしまえば、自分の車と自分の命を守るためにライトを点けるのです。
早くライトを点ければ夕方の事故には遭いにくくなるので、ながーい目で見れば修理代や治療費の面でお得と言っても過言ではない、と私は考えます。
ちなみに、まだある程度見える、やや薄暗い時間(トワイライトタイム)が最も事故が起こりやすい時間帯です。
特にミラー越しになると、車の色(黒やグレー等)によっては暗さにまぎれて、とても見づらくなります。
夕方の時間帯では交差点や先の見えないカーブなどは、カーブミラーがあっても相手の車がよく見えなくて出合い頭に衝突、といった事故が多くなるのです。
私はカーブミラーやサイドミラー、ルームミラーでミラー越しに「ちょっと見えづらいかな…?」と思った時には、自分の車のライトをすぐ点けるように心がけています。
さて話が変わりますが、私の今の愛車は、良い車なのでとても気に入っています。
当然、事故に遭いたくないし傷も付けたくありません。
だから、他の車がまだライトも点けていない少し明るいような薄暗いうちから、自分の車の存在を周りにアピールするために、スモールではなくヘッドライトを点けるようにしています。
今の時期ならば午後5時前には、もうライトを点けていますね。
また、真昼でも薄暗いときや雨が降っていて暗いと思った時には、すぐにライトを点けます。
私にとっては薄暗いうちに早くライトを点けることと、車を洗車してピカピカにすることは、車を大事にするということで同じことだと思っているからです。
事故に遭わずに長く大事に愛車に乗り続けたいし、同乗する家族をなるべく交通事故から守りたいですから。
お金をかけて色々手を入れてある車や、洗車の行き届いたピカピカの高級車が、薄暗い時間にライトも点けずスピードを出して走っていくのを見かけるたび、いつも残念に感じています。
皆さんは、どうでしょうか?
自分の車を大切にしたい、家族を守りたい、事故には遭いたくない、と少しでも思うのでしたら、車のライトを薄暗い内からなるべく早く点けるようにすることを、強くお勧めします。
暑すぎた夏も過ぎて涼しくなると共に、日が落ちるのもだいぶ早くなってきました。
さて、皆さんは日が傾いて薄暗くなってきたとき、どのタイミングで車のライトを点けていますか?
よく「ライトは早めに点けましょう」と言われていますが、実際松本の街の車を見るとだいぶ暗くなってもライトを点けない車が結構たくさんいます。
それは、なぜ早く点けたほうが良いのか、分かっていない方が多いからでしょう。
最近「ライトは自分が周りを見るためというより、周りに自分の車の存在を知らせるため、存在をアピールするために点ける」ということを聞きませんか?
暗い中でライトを点けずに道を走れば、当然周りの車からは無灯火で車が見づらいので、危険極まりないですよね。
無灯火だと対向してきた車でさえ、十分見えなくてドキッとすることがありませんか?
つまり、ライトを点ければ周りからその車の存在が分かるので、周りの車が十分注意をしてくれます。
お互いがお互いにライトを点けていれば、お互いが良く見えるので危険が減り、事故に遭う確率が減るわけです。
平たく言ってしまえば、自分の車と自分の命を守るためにライトを点けるのです。
早くライトを点ければ夕方の事故には遭いにくくなるので、ながーい目で見れば修理代や治療費の面でお得と言っても過言ではない、と私は考えます。
ちなみに、まだある程度見える、やや薄暗い時間(トワイライトタイム)が最も事故が起こりやすい時間帯です。
特にミラー越しになると、車の色(黒やグレー等)によっては暗さにまぎれて、とても見づらくなります。
夕方の時間帯では交差点や先の見えないカーブなどは、カーブミラーがあっても相手の車がよく見えなくて出合い頭に衝突、といった事故が多くなるのです。
私はカーブミラーやサイドミラー、ルームミラーでミラー越しに「ちょっと見えづらいかな…?」と思った時には、自分の車のライトをすぐ点けるように心がけています。
さて話が変わりますが、私の今の愛車は、良い車なのでとても気に入っています。
当然、事故に遭いたくないし傷も付けたくありません。
だから、他の車がまだライトも点けていない少し明るいような薄暗いうちから、自分の車の存在を周りにアピールするために、スモールではなくヘッドライトを点けるようにしています。
今の時期ならば午後5時前には、もうライトを点けていますね。
また、真昼でも薄暗いときや雨が降っていて暗いと思った時には、すぐにライトを点けます。
私にとっては薄暗いうちに早くライトを点けることと、車を洗車してピカピカにすることは、車を大事にするということで同じことだと思っているからです。
事故に遭わずに長く大事に愛車に乗り続けたいし、同乗する家族をなるべく交通事故から守りたいですから。
お金をかけて色々手を入れてある車や、洗車の行き届いたピカピカの高級車が、薄暗い時間にライトも点けずスピードを出して走っていくのを見かけるたび、いつも残念に感じています。
皆さんは、どうでしょうか?
自分の車を大切にしたい、家族を守りたい、事故には遭いたくない、と少しでも思うのでしたら、車のライトを薄暗い内からなるべく早く点けるようにすることを、強くお勧めします。
2017/02/05
(この記事は、私が過去 2010.7.21. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
ちょっと交通マナーから話がそれて、シートベルトについてです。
先日、某公共放送のニュースでシートベルト外傷についてやっていました。
シートベルトをしていて事故にあったとき、そのシートベルトが腹部に食い込み、強い圧迫により大怪我をすることがある、というものでした。
それは事実なんですが…、その報道の仕方がなんとも良くない。
理由と対策の掘り込みが浅く、あの放送では「シートベルトってしないほうが良いんじゃない?」と間違えて捉えてしまった方もいるでしょう。
あんなニュースをやるようじゃN○Kもダメだな…。 (- -;;
とそれはさておき、シートベルトの装着は、安全のために絶対に必要です。
シートベルトをしなければ大事故のとき簡単に車外へ放り出されて、死亡する確率が高くなってしまいます。
移動する車内空間においてもっとも安全を確保する方法は、搭乗者がシートに正しく座った上でしっかりシートに固定されていること、です。
そのためにはシートに正しく座り、シートベルトを正しく装着することが大切です。
しかし、これは残念ながら日本の教習所では教えてくれません。
シートベルト外傷になってしまう一番の原因は、正しくシートに座って正しいシートベルトの締め方をしていないから(知らないから)、と言えるかもしれません。
そこで正しいシートの座り方・シートベルトの締め方について書きたいと思います。
しかし長くなる上、文面でうまく説明できるか分かりません。(- -;;
とにかく記していこうと思います。
まずは正しいシートの座り方、です。
シートベルトを正しく機能させるためには、まずは正しくシートに座らなくてはいけません。
シートに腰骨・骨盤をぐっと押し込めるようにして座ります。
おしりをシートの深いところに、「これでもかっ」と押し込めるような感じです。
次に、シートのリクライニングはなるべく起こすようにします。
私の経験上、リクライニングを一番起こした状態から1~4ノッチ(段)くらいが適切だと思います。
正しいリクライニング位置だとシートに背中を預けたとき、自然と腰から肩甲骨辺りまでがシートに当たり、それより上の肩や頭はシートには触れません。
またヘッドレストが稼動するなら、ヘッドレストを後頭部の真後ろにくるように合わせます。
頭はヘッドレストに触れないように。
足は足の裏が床面に着くよう、自然に前に出します。
ちなみにドライバーのときは、左足をフットレストに載せたとき、腿(もも)の裏がシート座面に自然にわずかに触れる程度に、シートの前後を合わせます。
(フットレストが無いときは、かかとを床面に着けてアクセルの上に置いたときに、腿の裏がシート座面に自然にわずかに触れるように)
ちょっと窮屈かな?…と思うかも知れませんが、これが移動する車内での正しい座り方です。
リクライニングを倒して、若干寝そべったような座り方のほうが楽なように思うかもしれません。
しかし、シートを倒すと腰骨・骨盤がシートから浮き上がってしまいます。
腰骨・骨盤がシート面から浮いてしまう座り方は、もっとも悪い座り方の一つです。
また、やや横になった背骨では移動するときの上下の揺れやショックを背骨が正しく受け止められません。
シートを倒しすぎると、背骨や腰に負担をかけて疲れや腰痛の原因にもなります。
また、万一のときはシートベルトに潜り込み(サブマリン現象)が起きて危険ですし、シートベルト外傷にもなりやすいです。
車を停めて休憩するときなどはシートを倒すのも良いですが、移動中は上記のようにリクライニングを起こし気味にして、正しくシートに座りましょう。
ちなみに、最近のミニバンなどで色々なシートアレンジができるからといって、シートを全部倒したり、向かい合わせで座ったりしたまま走行してはいけません。
正しく座れないどころか、シートベルトもろくにできません。
説明書にもシートアレンジしたまま走ってはいけない、ときちんと書いてあるはずです。
自動車は、前向きできちんと正しくシートに座って移動すること。
これは基本的なことであり、自分や同乗者を守るための、最低限のことです。
話がそれました。
では、次に正しいシートベルトの締め方です。
まずシートベルトをバックルにカチッと音がするまで入れます。
ベルトの肩の位置が鎖骨の膨らんだ部分の外側、肩の真ん中かちょっと外側あたりを通っているか確認しましょう。
鎖骨の膨らんだ部分の上をちょうどベルトが通っていると、もし事故とか急制動でベルトに押し付けられた時、最悪の場合鎖骨が折れることがあります。
肩のベルトの位置が合ってない時は、ベルトの高さが変えられる場合は高さを調整して合わせます。
運転席以外のときは、シートの前後位置を動かして合うようにします。
もしそれらをやっても位置が合わないとき、または調整できないタイプのときは、残念ですが車の設計自体が初めからシートベルトを正しく装着できない設計になっていると考えられます。
「そんなバカな」「そんなことある訳ない」と思うかもしれませんが、一部の車、特に日本車には実のところ良くあることです。(特に後部座席のシートベルト)
日本メーカーには「シートベルトは備え付けさえしてれば良い」と考えているところもまだ多く、本来の安全装置として十分に機能を発揮できるか?、といった所は深く考えて作っていないということです…。
残念です。
また話がそれました。
次に腰ベルトを骨盤の位置にくるようにして、腿の上を沿うようになるべく下の方にします。
最後に胸の前の肩ベルトを持って、巻き取り方向へ軽くきゅっと締めます。
肩ベルトは多少ゆるくても良いのですが、腰ベルトはしっかりややきつめくらいがベストです。
2点式のときも同様に、骨盤の位置で腿の上を沿うように装着し、ややきつめに締めましょう。
これで完成です。
ちなみに締め付けられるのが嫌だからといって、腰ベルトをゆるめにしたり、わざわざ洗濯バサミやベルトロック(こういう商品があること自体が間違ってるとは思いますが)を使って緩めてはいけません。
シートベルトが安全装置として正しく機能しませんし、サブマリン現象やシートベルト外傷の原因になります。
車を運転することは正しくシートに座ってきちんとシートベルトを締めることだと理解して、正しい方法でシートベルトを装着してください。
以上となりますが、文章が下手でご理解していただけたか心配です…。(^ ^;;
さて、これからレジャーシーズンです。
慣れない土地で長時間にわたり車を走らせる機会も多くなります。
逆に言えば、それだけ事故に遭う確率が高くなる、ともいえます。
搭乗者全員が正しくシートに座り、正しくシートベルトをすることは安全のためには必須なことです。
この記事を参考にして、安全で快適なドライブができるようにしてみてください。
ちょっと交通マナーから話がそれて、シートベルトについてです。
先日、某公共放送のニュースでシートベルト外傷についてやっていました。
シートベルトをしていて事故にあったとき、そのシートベルトが腹部に食い込み、強い圧迫により大怪我をすることがある、というものでした。
それは事実なんですが…、その報道の仕方がなんとも良くない。
理由と対策の掘り込みが浅く、あの放送では「シートベルトってしないほうが良いんじゃない?」と間違えて捉えてしまった方もいるでしょう。
あんなニュースをやるようじゃN○Kもダメだな…。 (- -;;
とそれはさておき、シートベルトの装着は、安全のために絶対に必要です。
シートベルトをしなければ大事故のとき簡単に車外へ放り出されて、死亡する確率が高くなってしまいます。
移動する車内空間においてもっとも安全を確保する方法は、搭乗者がシートに正しく座った上でしっかりシートに固定されていること、です。
そのためにはシートに正しく座り、シートベルトを正しく装着することが大切です。
しかし、これは残念ながら日本の教習所では教えてくれません。
シートベルト外傷になってしまう一番の原因は、正しくシートに座って正しいシートベルトの締め方をしていないから(知らないから)、と言えるかもしれません。
そこで正しいシートの座り方・シートベルトの締め方について書きたいと思います。
しかし長くなる上、文面でうまく説明できるか分かりません。(- -;;
とにかく記していこうと思います。
まずは正しいシートの座り方、です。
シートベルトを正しく機能させるためには、まずは正しくシートに座らなくてはいけません。
シートに腰骨・骨盤をぐっと押し込めるようにして座ります。
おしりをシートの深いところに、「これでもかっ」と押し込めるような感じです。
次に、シートのリクライニングはなるべく起こすようにします。
私の経験上、リクライニングを一番起こした状態から1~4ノッチ(段)くらいが適切だと思います。
正しいリクライニング位置だとシートに背中を預けたとき、自然と腰から肩甲骨辺りまでがシートに当たり、それより上の肩や頭はシートには触れません。
またヘッドレストが稼動するなら、ヘッドレストを後頭部の真後ろにくるように合わせます。
頭はヘッドレストに触れないように。
足は足の裏が床面に着くよう、自然に前に出します。
ちなみにドライバーのときは、左足をフットレストに載せたとき、腿(もも)の裏がシート座面に自然にわずかに触れる程度に、シートの前後を合わせます。
(フットレストが無いときは、かかとを床面に着けてアクセルの上に置いたときに、腿の裏がシート座面に自然にわずかに触れるように)
ちょっと窮屈かな?…と思うかも知れませんが、これが移動する車内での正しい座り方です。
リクライニングを倒して、若干寝そべったような座り方のほうが楽なように思うかもしれません。
しかし、シートを倒すと腰骨・骨盤がシートから浮き上がってしまいます。
腰骨・骨盤がシート面から浮いてしまう座り方は、もっとも悪い座り方の一つです。
また、やや横になった背骨では移動するときの上下の揺れやショックを背骨が正しく受け止められません。
シートを倒しすぎると、背骨や腰に負担をかけて疲れや腰痛の原因にもなります。
また、万一のときはシートベルトに潜り込み(サブマリン現象)が起きて危険ですし、シートベルト外傷にもなりやすいです。
車を停めて休憩するときなどはシートを倒すのも良いですが、移動中は上記のようにリクライニングを起こし気味にして、正しくシートに座りましょう。
ちなみに、最近のミニバンなどで色々なシートアレンジができるからといって、シートを全部倒したり、向かい合わせで座ったりしたまま走行してはいけません。
正しく座れないどころか、シートベルトもろくにできません。
説明書にもシートアレンジしたまま走ってはいけない、ときちんと書いてあるはずです。
自動車は、前向きできちんと正しくシートに座って移動すること。
これは基本的なことであり、自分や同乗者を守るための、最低限のことです。
話がそれました。
では、次に正しいシートベルトの締め方です。
まずシートベルトをバックルにカチッと音がするまで入れます。
ベルトの肩の位置が鎖骨の膨らんだ部分の外側、肩の真ん中かちょっと外側あたりを通っているか確認しましょう。
鎖骨の膨らんだ部分の上をちょうどベルトが通っていると、もし事故とか急制動でベルトに押し付けられた時、最悪の場合鎖骨が折れることがあります。
肩のベルトの位置が合ってない時は、ベルトの高さが変えられる場合は高さを調整して合わせます。
運転席以外のときは、シートの前後位置を動かして合うようにします。
もしそれらをやっても位置が合わないとき、または調整できないタイプのときは、残念ですが車の設計自体が初めからシートベルトを正しく装着できない設計になっていると考えられます。
「そんなバカな」「そんなことある訳ない」と思うかもしれませんが、一部の車、特に日本車には実のところ良くあることです。(特に後部座席のシートベルト)
日本メーカーには「シートベルトは備え付けさえしてれば良い」と考えているところもまだ多く、本来の安全装置として十分に機能を発揮できるか?、といった所は深く考えて作っていないということです…。
残念です。
また話がそれました。
次に腰ベルトを骨盤の位置にくるようにして、腿の上を沿うようになるべく下の方にします。
最後に胸の前の肩ベルトを持って、巻き取り方向へ軽くきゅっと締めます。
肩ベルトは多少ゆるくても良いのですが、腰ベルトはしっかりややきつめくらいがベストです。
2点式のときも同様に、骨盤の位置で腿の上を沿うように装着し、ややきつめに締めましょう。
これで完成です。
ちなみに締め付けられるのが嫌だからといって、腰ベルトをゆるめにしたり、わざわざ洗濯バサミやベルトロック(こういう商品があること自体が間違ってるとは思いますが)を使って緩めてはいけません。
シートベルトが安全装置として正しく機能しませんし、サブマリン現象やシートベルト外傷の原因になります。
車を運転することは正しくシートに座ってきちんとシートベルトを締めることだと理解して、正しい方法でシートベルトを装着してください。
以上となりますが、文章が下手でご理解していただけたか心配です…。(^ ^;;
さて、これからレジャーシーズンです。
慣れない土地で長時間にわたり車を走らせる機会も多くなります。
逆に言えば、それだけ事故に遭う確率が高くなる、ともいえます。
搭乗者全員が正しくシートに座り、正しくシートベルトをすることは安全のためには必須なことです。
この記事を参考にして、安全で快適なドライブができるようにしてみてください。
2017/02/01
(この記事は、私が過去 2010.7.15. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
書き忘れがあったので、その2です。
信号のない横断歩道で、もう一つ書きたいことは、雨や雪など天候が悪いときのことです。
車に乗っている人は当然屋根があり、雨や雪で濡れることがない上、暖房・冷房の効く快適な環境で移動していますよね。
しかし、歩行者や自転車の人は雨や雪のとき、当然濡れたり汚れたり、また転びやすいなど危険の中、移動をしています。
それだけ大変な中で外を移動している歩行者・自転車に、もっと優しく対応してあげたいと思いませんか。
雨や雪、猛暑・厳寒の気候のときは、横断歩道で普段より優しさをもって積極的に停まってあげましょう。
また夜間で雨や雪のときはさらに大変であると共に、信号のない横断歩道では暗く見づらいので、歩行者が安全に横断することが難しくなってしまいます。
そういう時も車がきちんと停まってあげれば、安全・確実に横断することができます。
夜の雨などでは見づらくて横断する人に気づくのが難しいので、よく注意して走ると共に、横断者がいたときは積極的に停まりましょう。
最初は横断者に気づくのが遅れたり、停まるタイミングが難しかったりするかもしれません。
でも、「停まってあげよう」「もっと歩行者にやさしく接しよう」という気持ちが少しでもあれば、自然と周りが見えるようになって歩行者に気づくのも早くなります。
大切なのは、心の持ちよう、です。
書き忘れがあったので、その2です。
信号のない横断歩道で、もう一つ書きたいことは、雨や雪など天候が悪いときのことです。
車に乗っている人は当然屋根があり、雨や雪で濡れることがない上、暖房・冷房の効く快適な環境で移動していますよね。
しかし、歩行者や自転車の人は雨や雪のとき、当然濡れたり汚れたり、また転びやすいなど危険の中、移動をしています。
それだけ大変な中で外を移動している歩行者・自転車に、もっと優しく対応してあげたいと思いませんか。
雨や雪、猛暑・厳寒の気候のときは、横断歩道で普段より優しさをもって積極的に停まってあげましょう。
また夜間で雨や雪のときはさらに大変であると共に、信号のない横断歩道では暗く見づらいので、歩行者が安全に横断することが難しくなってしまいます。
そういう時も車がきちんと停まってあげれば、安全・確実に横断することができます。
夜の雨などでは見づらくて横断する人に気づくのが難しいので、よく注意して走ると共に、横断者がいたときは積極的に停まりましょう。
最初は横断者に気づくのが遅れたり、停まるタイミングが難しかったりするかもしれません。
でも、「停まってあげよう」「もっと歩行者にやさしく接しよう」という気持ちが少しでもあれば、自然と周りが見えるようになって歩行者に気づくのも早くなります。
大切なのは、心の持ちよう、です。
2017/02/01
(この記事は、私が過去 2010.7.12. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
おひさしぶりです。
2年もほったらかしでした。(- -;;
その間、結構多くの方に読まれたみたいですが…返事もせずに申し訳ありません。
とりあえず、再開です。
やれることを、少しずつ進めていきましょう。
さて、信号の無い横断歩道についてです。
信号の無い横断歩道で、歩行者が横断しようと立っていたとき、運転手のあなたはきちんと停まって歩行者に譲っていますか?
法律では、車は必ず停まって歩行者を安全に渡らせなくてはなりません。
「必ず」、です。
これができている松本の車は…残念ですがかなり少ないですね。
松本人、信州人の方は車に乗ると自己中心に考える人が多く、こういう時歩行者に気づいたとしても、基本素通りです。
自分が急ぐことしか考えてないのか、停まるのが面倒なのか…。
また一番まずい、やってはいけないと思うのは、片方の車が歩行者を譲ろうと停まっているのに、対向車が一向に停まらない状況です。
これは東京・大阪ではまず見られない光景です。
片方が停まれば、だいたい4、5台のうちに譲ってくれる車が現れます。
松本はどうでしょう。
運が悪ければ10、20台くらい余裕で待ちます。
最悪の場合、まったく対向車は停まらず、先に停まっていた車が後ろの車に気を使って発進してしまい、結局歩行者は渡れない…ということもよくあります。
これは、先に停まってあげた車の気持ちを踏みにじる、最低の行為だと言えると思います。
また横断しようとしている歩行者の方も気分が悪くなるだろうし、かわいそうです。
松本のドライバーの皆さん、せめてこういう場面に出くわしたら、積極的に停まってあげましょうよ。
スムーズに渡らしてあげれば気分も良いし、また対向車の流れもスムーズにできます。
また、車がきちんと停まって歩行者を横断させることは、歩行者を安全かつ確実に横断させることができ、事故の危険を減らすことができるんです。
いつでも積極的に自分から停まってあげるのが一番ですが、他人の優しさの便乗でも良いから、まずはこういうところから実行していきましょう。
おひさしぶりです。
2年もほったらかしでした。(- -;;
その間、結構多くの方に読まれたみたいですが…返事もせずに申し訳ありません。
とりあえず、再開です。
やれることを、少しずつ進めていきましょう。
さて、信号の無い横断歩道についてです。
信号の無い横断歩道で、歩行者が横断しようと立っていたとき、運転手のあなたはきちんと停まって歩行者に譲っていますか?
法律では、車は必ず停まって歩行者を安全に渡らせなくてはなりません。
「必ず」、です。
これができている松本の車は…残念ですがかなり少ないですね。
松本人、信州人の方は車に乗ると自己中心に考える人が多く、こういう時歩行者に気づいたとしても、基本素通りです。
自分が急ぐことしか考えてないのか、停まるのが面倒なのか…。
また一番まずい、やってはいけないと思うのは、片方の車が歩行者を譲ろうと停まっているのに、対向車が一向に停まらない状況です。
これは東京・大阪ではまず見られない光景です。
片方が停まれば、だいたい4、5台のうちに譲ってくれる車が現れます。
松本はどうでしょう。
運が悪ければ10、20台くらい余裕で待ちます。
最悪の場合、まったく対向車は停まらず、先に停まっていた車が後ろの車に気を使って発進してしまい、結局歩行者は渡れない…ということもよくあります。
これは、先に停まってあげた車の気持ちを踏みにじる、最低の行為だと言えると思います。
また横断しようとしている歩行者の方も気分が悪くなるだろうし、かわいそうです。
松本のドライバーの皆さん、せめてこういう場面に出くわしたら、積極的に停まってあげましょうよ。
スムーズに渡らしてあげれば気分も良いし、また対向車の流れもスムーズにできます。
また、車がきちんと停まって歩行者を横断させることは、歩行者を安全かつ確実に横断させることができ、事故の危険を減らすことができるんです。
いつでも積極的に自分から停まってあげるのが一番ですが、他人の優しさの便乗でも良いから、まずはこういうところから実行していきましょう。
2017/01/08
(この記事は、私が過去 2008.3.22. に「湊戸ヒサシ」としてY!ブログにアップした記事です)
私が普段通る道に、女鳥羽川を渡る桜橋があります。
これはたまたま移動の途中で、その東側(美ケ原側)堤防道路の信号の無い交差点で実際に見た光景です。
その日は雨が降っていました。
買い物の帰りでしょうか、東(美ヶ原方面)から西(お城方面)の方へ一人のおばあさんが重そうなスーパーの袋を持ち、傘をさしながら、広い歩道をゆっくり歩いています。
橋を渡ろうとその交差点に差し掛かったとき、堤防道路を北(浅間方面)から来た自動車とはちあいました。
堤防道路には一時停止の標識があり、また横断歩道もあるので、明らかに優先されるのはおばあさんの方です。
が、その車は一時停止もせず、ましてや十分な減速もせずに交差点内へ進入、横断歩道を完全に塞ぐように停車しました。
これでは横断できないので、おばあさんは立ち止まって車が行くのを待っています。
しばらくしてその車は堤防道路を直進し、いなくなりました。
しかし、その車のすぐ後ろにいた次の車もすかさず横断歩道に進入、おばあさんの通行を妨げつつ直進していきます。
そして、また次の車も同じように横断歩道のなかへ進入していきます。
結局4台の車が通り過ぎるまで、おばあさんは雨の中、重そうな荷物を持ったまま待ち続け、車がすべていなくなってからようやく横断して行きました。
私はこれを見たとき、非常に怒りが込み上げると同時に、同じドライバーとしてとても情けなくなりました。
4台も車が通る中、一台もおばあさんを渡らせてあげようとしなかったのです。
自動車側が明らかな法律違反であるにもかかわらず。
これが、今の松本の交通事情の現状なのです。
今回の件を補足をすると、その堤防道路は駅前市街地への抜け道のように使われています。
松本人はハンドルを握ると、なぜかゆとりがない自己中心的な運転をする人が多く、相まって急ぐ車などが危険な運転をしがちです。
また車優先という間違ったローカルルールのせいで、停止線や優先されるべき歩道を無視して一気に車道まで飛び出してくる車が、かなり多いのも事実です。
今回のケースの正しい運転は、一時停止では必ず停止線で止まること。
松本人や信州人で、ちゃんと停止線で止まっている方はかなり少ないと思われます。
これは安全運転の基本中の基本、道交法上でも基本中の基本なので、きちんと守りましょう。
そして歩道への進入はゆっくりじわじわとします。
この時、歩道に歩行者・自転車などが近くにいるときは、その通行を絶対に妨げてはいけません。
優先道路の歩道も車道と同じく優先されます。
というより、優先道路に沿っている歩道が、最も優先されるべき道路なのです。
これもきちんと道交法に規定されているので、ドライバーは遵守する義務があります。
ていうか法律云々の前に、私はモラルの問題だとも考えます。
子供やお年寄りなど、交通弱者には格段の思いやりを持ってあげるのが、ドライバーの基本だと思います。
もっと心の余裕と優しい心を持って、ハンドルを握っていきませんか。
(2011.6.25.修正)
私が普段通る道に、女鳥羽川を渡る桜橋があります。
これはたまたま移動の途中で、その東側(美ケ原側)堤防道路の信号の無い交差点で実際に見た光景です。
その日は雨が降っていました。
買い物の帰りでしょうか、東(美ヶ原方面)から西(お城方面)の方へ一人のおばあさんが重そうなスーパーの袋を持ち、傘をさしながら、広い歩道をゆっくり歩いています。
橋を渡ろうとその交差点に差し掛かったとき、堤防道路を北(浅間方面)から来た自動車とはちあいました。
堤防道路には一時停止の標識があり、また横断歩道もあるので、明らかに優先されるのはおばあさんの方です。
が、その車は一時停止もせず、ましてや十分な減速もせずに交差点内へ進入、横断歩道を完全に塞ぐように停車しました。
これでは横断できないので、おばあさんは立ち止まって車が行くのを待っています。
しばらくしてその車は堤防道路を直進し、いなくなりました。
しかし、その車のすぐ後ろにいた次の車もすかさず横断歩道に進入、おばあさんの通行を妨げつつ直進していきます。
そして、また次の車も同じように横断歩道のなかへ進入していきます。
結局4台の車が通り過ぎるまで、おばあさんは雨の中、重そうな荷物を持ったまま待ち続け、車がすべていなくなってからようやく横断して行きました。
私はこれを見たとき、非常に怒りが込み上げると同時に、同じドライバーとしてとても情けなくなりました。
4台も車が通る中、一台もおばあさんを渡らせてあげようとしなかったのです。
自動車側が明らかな法律違反であるにもかかわらず。
これが、今の松本の交通事情の現状なのです。
今回の件を補足をすると、その堤防道路は駅前市街地への抜け道のように使われています。
松本人はハンドルを握ると、なぜかゆとりがない自己中心的な運転をする人が多く、相まって急ぐ車などが危険な運転をしがちです。
また車優先という間違ったローカルルールのせいで、停止線や優先されるべき歩道を無視して一気に車道まで飛び出してくる車が、かなり多いのも事実です。
今回のケースの正しい運転は、一時停止では必ず停止線で止まること。
松本人や信州人で、ちゃんと停止線で止まっている方はかなり少ないと思われます。
これは安全運転の基本中の基本、道交法上でも基本中の基本なので、きちんと守りましょう。
そして歩道への進入はゆっくりじわじわとします。
この時、歩道に歩行者・自転車などが近くにいるときは、その通行を絶対に妨げてはいけません。
優先道路の歩道も車道と同じく優先されます。
というより、優先道路に沿っている歩道が、最も優先されるべき道路なのです。
これもきちんと道交法に規定されているので、ドライバーは遵守する義務があります。
ていうか法律云々の前に、私はモラルの問題だとも考えます。
子供やお年寄りなど、交通弱者には格段の思いやりを持ってあげるのが、ドライバーの基本だと思います。
もっと心の余裕と優しい心を持って、ハンドルを握っていきませんか。
(2011.6.25.修正)