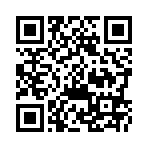2014/09/03
イスラームの話6、イスラームの各宗派をみてみる
(2015.4.3. 加筆)
今回は、イスラームに存在する主な宗派の教義とその違いを見ていきたいと思います。
そのあとに、イスラーム神秘主義(スーフィズム)についても触れてみます。
ではまず、イスラームの各宗派について。
イスラームの宗派は大きく分類すると、スンナ派(スンニ派)、シーア派、ハワーリジュ派の三つに分かれます。
その中で、シーア派にはさらに5つくらいの宗派があります。
以下、簡単ですが主要な宗派について順に見ていきます。
少数派のいくつかについては、申し訳ないのですが省略させていただきます。
1.スンナ派
正確には「スンナとウンマの民」といいます。(テレビなどではスンニ派といわれています)
全てのムスリム(イスラーム教徒)の実に9割がスンナ派となり、圧倒的な多数派で体制派となります。
スンナは「慣行」という意味で、預言者ムハンマドの慣行、すなわちイスラーム法(シャリーア)を表します。
ウンマは「イスラーム共同体」を意味し、ムハンマドが定めたマディーナ憲章による、ウンマの合意(イジュマー)を意味します。
スンナ派は、シャリーアとイジュマーに従う人々の宗派です。
歴史の方でも触れましたが、スンナ派は初めから宗派として存在していたわけではありません。
ウンマからシーア派やハワーリジュ派が分離するにしたがって、相対的に成立していった多数派です。
スンナ派は圧倒的な多数派かつ体制派なので、総じて現実主義であり極端な主張を避けてウンマの統一・合意・秩序を重視します。
またイスラームが発展するにしたがって、スンナ派の中で多くの神学派や法学派が存在してきましたが、分裂することなくいちおうスンナ派として一つにまとまっています。
(スンナ派についての詳細は、教義やイスラーム法など含めまた別の記事にしたいと思います)
しかし、内実的には穏健派、世俗派、復古主義、強硬過激派などなど、多種多様な主義主張が混在していて、正直私たちイスラーム以外の人間からは複雑でよくわからない宗派だともいえます。
スンナ派信徒は、アラブ諸国、トルコ、東南アジア、中国、中央アジア、アフリカ諸国など、イスラームが広まった地域のほとんどにいます。
逆に言うと、シーア派が多いイランとペルシア湾周辺地域を除けばほとんどスンナ派、といっても良いくらいの圧倒的な多数派になります。
2.シーア派
正しくは「シーア・アリー」といいます。
シーアは「党派」という意味で、アリーの党派という意味です。
ウンマの指導者はアリーとその子孫だけがなれる、と主張するグループの総称です。
またシーア派にはさらにいくつか宗派があり、アリーの子孫の中で誰を指導者(イマーム)とするか、またどの系譜を支持するか、をめぐって分派してきました。
歴史で触れましたが、アリーは預言者ムハンマドのいとこであり年の離れた幼なじみで、さらにはムハンマドの娘婿になります。
第4代のカリフであり、シーア派においては初代イマームとなります。
アリーは非常に聡明な人物でムハンマドからの信頼も厚く、ムハンマドの末娘のファーティマと結婚しました。
ムハンマドには三男四女の子供がいましたが、男子は全て幼くして亡くなり、娘もアリーと結婚したファーティマだけに子供が産まれました。
つまり、アリーの子孫はムハンマド直系の子孫にあたります。
預言者直系の血筋であるから、その子孫はウンマの指導者になる資格と能力がある、だからアリーとその子孫のみがウンマの指導者として認められる、というのがシーア派の主張です。
また歴史の流れのなかで、シーア派には反ウマイヤ朝の軍人やアラブ人優遇に反対する非アラブ人(主にペルシア人)などが加わっていったため、シーア派には反体制、反アラブ人といった考えも含まれています。(現在はそれほど強調されていません。しかし、伝統的にアラビア半島の人々とペルシアの人々の心の奥底に、若干の敵対感があるのは事実です)
また、680年のカルバラーの悲劇で無念の死を遂げた第3代イマームのフサインを追悼するアーシューラーの祭は、シーア派独自の重要な祭礼です。
他にシーア派の特徴として、
・啓典クルアーン(コーラン)のシーア派独自の解釈がある。
・聖典ハディースに、預言者以外に歴代シーア派イマームの言行が含まれる。
・巡礼で訪れる聖地に、マッカ・マディーナの他に歴代イマーム廟が含まれる。
・信仰隠し(タキーヤ)が認められていて、シーア派だと分かると危険が及びそうなときはスンナ派のふりをしても良い。
・一時婚(ムトア)が認められていて、期間を決めて婚姻契約を結べる。(一種の買春だという批判もある)
・うろこのない魚(ウナギなど)は食べてはいけない。(他にも宗派・地域などにより独自の食物規定もある)
など、スンナ派と違う教義がいくつかあります。
シーア派は、イラン(ペルシア)地域のイスラーム国家に16世紀から現代に至るまで長く保護されてきたため、シーア派信徒のほとんどはイラン周辺、イラク南部やペルシア湾岸地域にいます。
他にイエメン、シリア、インド、パキスタンなどにいます。
3.ハワーリジュ派
「出ていく人」という意味。
歴史でも触れましたが、ハワーリジュ派はもともとシーア派でした。
アリーとムアーウィアがカリフの座をめぐって対立が激化するなか、アリーとムアーウィアは一時和平を結びました。
その和平に反対したグループがシーア派から分離したのが、ハワーリジュ派です。
ハワーリジュ派は、信仰は外面的な行為・行動に表れるとし、信仰は行為と一致しなければならない、と考えました。
そして、ムスリムの行動に間違いがあればその人は不信仰者でムスリムではない、として厳しく追求・断罪しました。
不信仰者として決め付けることをタクフィールといい、不信仰者は殺害を含めて厳しく断罪するべき、という考えをタクフィール思想といいます。
ハワーリジュ派は、ウマイヤ家を重用した第3代カリフのウスマーンは罪を犯したので不信仰者となり、そのウスマーンの復讐として兵を挙げたムアーウィアも悪であり、悪であるムアーウィアと調停をしたアリーも悪となるのです。
ゆえに、アリーはハワーリジュ派に暗殺されてしまうのです。
ハワーリジュ派にはその過激的な思想のため、主流派とはならず少数の支持者しかいませんでした。
後に過激派と穏健派に分裂して、現在は穏健的なイバード派がオマーンや北アフリカなどに存在しています。
ハワーリジュ派のタクフィール思想はたびたび反政府運動の口実となり、強硬派や過激派によって攻撃・暗殺・殺害のための論理に使われました。
現在でもテロリズムの口実に使われることもあります。
ちなみに他のスンナ派やシーア派は、タクフィール思想を否定しています。
ムスリム個人の信仰心はその行為だけでは計れないとし、ムスリムの最大の罪は多神崇拝(シルク)であってそれを犯さなければ信仰者であるとしました。
また不信仰者かどうかの判断は、最後の審判においてアッラーのみが決めることができる、と考えられています。
1-2.ワッハーブ派(スンナ派系)
スンナ派ハンバル学派の流れをくむ法学派で、アブド・アル=ワッハーブ(1703-92)が唱えた、復古主義的改革思想です。
本来は別の宗派ではなくスンナ派学派の一つなんですが、サウディアラビアでは国教のような扱いとなっているので、いちおうスンナ派系の宗派としてあげておきます。
ワッハーブ派は厳格な復古主義で、スーフィズム(神秘主義)を否定しムハンマドの教えに帰れ、と主張しました。
19世紀半ばにワッハーブ派がアラビア半島のムスリムに広まり、リヤド周辺支配者だったサウード家に強く後押しされる形で一気に勢力を広げ、最終的にアラビア半島の大半を支配した、ワッハーブ派を国教とする現在のサウディアラビア王国となりました。
ワッハーブ派は、ムハンマド時代から正統カリフ時代までのイスラーム法の実践に回帰することをめざして、イスラーム初期のシャリーアを厳格に実践し、またイスラーム中期以降隆盛したスーフィズムをイスラームから逸脱したとして強く否定しました。
その結果、サウディアラビアにおいてはスーフィー聖者廟が破壊されて、スーフィズムはほぼ排除されています。
ワッハーブ派信徒はアラビア半島に多く、サウディアラビアのスンナ派はほぼワッハーブ派と言えます。
2-1.十二イマーム派(12イマーム派、シーア派系)
シーア派の宗派の一つで、イランの国教です。
シーア派の9割近くは十二イマーム派であり、シーア派と言えば十二イマーム派のことを指すことが多いです。
イスラームにはもともと終末論と救世主思想があり、シーア派は長く抑圧されてきた宗派であるがゆえ、特に救世主思想を重視する傾向があります。
十二イマーム派は、特にその救世主思想を第12代イマームのガイバ(お隠れ)思想とあわせて重要な教義としています。
十二イマーム派は、アリーを初代イマームとして第12代イマームのムハンマドまでのイマームの系譜を支持します。
873年、11代イマームのハサン・アル=アスカリーが没したあと、12代イマームをムハンマドが幼くして受け継ぎましたが、突如姿を消してしまいました。
弟子たちは、ムハンマドは異次元空間にお隠れ(ガイバ)になったと言い、ムハンマドは年もとらない異次元空間で長い瞑想に入ったとされます。
そして世界に終末が訪れる直前に、12代イマームのムハンマドは救世主(マフディー)として人間世界に現れ、シーア派の教えによる正しいウンマを導いて地上に楽土を作り上げ、その後終末が来てアッラーによる最後の審判が行われる、とされています。
十二イマーム派の指導者イマームの正統性は血統に基づいており、イマームにはムハンマドとアリーの血によってあらゆる知識が授けられるとされます。
ゆえにイマームは全知であり不可謬(ふかびゅう、イスマ)であり、決して間違いを起こさない完全人間とされます。
十二イマーム派では、完全人間であるイマームがウンマを指導しないと不完全な人間はかならず間違いを起こすとされ、この教義はスンナ派のイジュマー(共同体の合意)と相反するものです。
不完全な人間が生み出す合意は不完全であり、正しい判断は全知であるイマームのみによって行われ、一般信徒はイマームに絶対服従しなければならないとされます。
また完全な知識を持つイマームは、啓典クルアーン(コーラン)やハディースを比喩的解釈を行い、内面的で奥義的な解釈を引き出します。
その結果十二イマーム派には、スンナ派と違う解釈によるクルアーン注釈書があります。
また預言者の言行録、聖典ハディースも預言者ムハンマドの言行だけでなく、歴代イマームの言行が含まれた独自のシーア派四大伝承集が存在します。
十二イマーム派は10世紀イラクのブワイフ朝において基本的な教義が整えられ、16世紀にペルシア(イラン)地域に興ったサファヴィー朝が国教とし保護してきました。
サファヴィー朝から始まる歴代シーア派政権はイラン全土とイラク南部などを支配し、十二イマーム派の信徒はイラン全土とイラク南部、ペルシア湾周辺の地域に存在します。
2-2.イスマーイール派(シーア派系)
イスマーイール派は、シーア派系の宗派で、909年に北アフリカでファーティマ朝を建てた宗派になります。
イスマーイール派の系譜は、765年に6代イマームのジャアファル・サーディクの死後、7代イマームとして息子のイスマーイールを支持したグループです。
その後約百年間の活動は不明ですが、隠れイマームが三代続いたとされます。
そして9世紀後半に、イスマーイール派の指導者は北アフリカで反アッバース朝運動を開始し、近い将来にイスマーイールの息子のムハンマドが救世主(マフディー)として復活し従来のシャリーアが廃棄されると主張し、大々的な宣教運動を始めました。
899年、イスマーイール派の指導者であり隠れイマームの代理人を自称していたアブドゥッラーが、自分がイマームであると宣言して権威を高め、909年には北アフリカにファーティマ朝を建国し、アブドゥッラーはファーティマ朝初代カリフ(イマーム)となりました。
やがてファーティマ朝は勢力を拡大して、969年にはエジプト全域を支配して首都カイロを建設しました。
第4代カリフ、ムイッズの時代には国家体制が整備されて、アズハル大学などのイスラーム学院が建設されます。
ファーティマ朝が安定期に入るとイスマーイール派の教義が修正され、終末は先送りにされてイマームの連続性とイマームに対する服従が強調されるようになりました。
しかし、イスマーイール派内部からは終末を早急に実現しようとする人々が現れ、終末到来を主張する行為や運動が何度も繰り返されてきました。
1169年にファーティマ朝が滅亡すると、エジプトではスンナ派が復興しイスマーイール派は衰退しました。
現在のイスマーイール派はいくつかの分裂を経て、インドやパキスタンなどに存在しています。
終末は先送りにされてイマームへの帰衣が説かれていて、スンナ派との協調も模索されます。
イスマーイール派イマーム、アーガー・ハーンは現在フランスのパリに住んでいて、パキスタンではイマームのカリスマ性と財力に基づいてNGO活動が盛んに行われ、大学への奨学基金や研究機関の運営などをしています。
2-3.ドゥルーズ派(シーア派系)
ドゥルーズ派は、シーア派系の少数一派です。
11世紀初めに、創始者ハムザ・イブン・アリーがイスマーイール派第6代カリフ、ハーキムを神格化してイスマーイール派から分派した一派です。
ハーキムは常軌を逸した行動が多かったといわれ、ある夜一人でロバに乗りカイロ市街を見下ろすムカッタム丘を散策中、姿を消しました。
イスラーム史上、「行方不明」と記録される唯一のカリフです。(暗殺された可能性もあると言われます)
ドゥルーズ派はそのハーキムを神とする教義を持ち、失踪後ハーキムはお隠れ状態にあり終末にマフディーとして再臨するとされます。
またクルアーン(コーラン)に代わる独自の聖典「ラサーイル・ヒクマ」(叡智の書簡集)があります。
輪廻思想を持ち、ドゥルーズ派信徒は必ず再びドゥルーズ派信徒に生まれ変わるといわれ、さらにマッカ巡礼を義務とせず、イスラエルにある預言者シュアイブの墓への参詣を重要としています。
このような独特で変わった教義を持つために、ドゥルーズ派は長く異端視され迫害を受けてきました。
ちなみにドゥルーズとは成立初期に活躍した宣教師ダラズィーに由来します。
発祥のエジプトでは弾圧を受けたためシリアで布教活動を展開し、そこで外部との接触を避けた独自の社会を形成し、近代まで自治を続けてきました。
現在はレバノン、シリア、イスラエルに約100万人の信徒がいます。
またドゥルーズ派は、シリアやレバノンの近現代において重要な役割をしてきました。
1860年にはレバノンでキリスト教系マロン派と宗教紛争に敗れて、シリアへの移住が進みました。
そのシリアではフランスの委任統治に対し、反乱を起こしました。
現在、レバノンでは宗派体制のもと中規模の政治勢力として重要な地位を占め、イスラエルではユダヤ人入植者に協力的だったため、他のムスリムとは違う扱いを受けています。
2-4.アラウィー派(シーア派系)
アラウィー派はシーア派の少数一派で、第4代カリフでありシーア派初代イマームの「アリー」を神格化するという教義を持ちます。
9世紀に十二イマーム派の第10代イマームの側近だったムハンマド・イブン・ヌサイルによって生まれたので、ヌサイリー派ともいいます。
イスマーイール派の影響が大きく、シリア土着の宗教やキリスト教の要素も取り入れられ、初代アリーが最もイマームにふさわしいとしてアリーを神格化し、輪廻転生などの独特の教義を持ちます。
初めはイラクで活動していたが、10世紀後半に拠点をシリアのラタキアに移しました。
しかし、十字軍の攻撃やマムルーク朝、オスマン帝国の迫害にあったため、長く信仰隠し(タキーヤ、隠れ信仰、表向きスンナ派信者のふりをすること)をしてきました。
第一次世界大戦後、フランスのシリア委任統治時代にようやく信仰を認められ、自治が認められました。
現在アラウィー派は、シリア、トルコ南東部、レバノンに存在します。
なお、シリアはアラウィー派による寡頭支配体制が確立していて、大統領はアラウィー派のアサド家に事実上世襲され、政権与党である社会主義政党バアス党や国軍の要職もアラウィー派が占めています。
現在シリアはアラブの春といわれた民主主義運動の余波を受け、現アラウィー派アサド政権と言論の自由と独裁体制打破を目指した反体制派との泥沼の内戦状態にあり混乱が続いていますが、反体制派の分裂やIS(イスラーム国)の台頭、国際社会の足並みの乱れにより、泥沼の長期化をたどっています。
2-5.ザイド派(シーア派系)
ザイド派は、第4代イマーム、ザイヌル・アービディーンの死後、第5代イマームにザイドを支持したグループです。
740年、ザイドが自らが主導してウマイヤ朝に対し反乱を起こしたが、失敗しました。(ザイドの反乱)
その後ザイド派は、アリーの長男ハサンの子孫をイマームに据え、イエメンを拠点に存在してきました。
イエメンではザイド派の支配が続き、特に17世紀前半から1962年に王権が倒れるまで、ザイド派王朝が続いてイマームが政治権力も握っていました。
ザイド派の特徴は、穏健的でスンナ派とも妥協的なところです。
ザイド派はガディール・フムの伝説(預言者ムハンマドが後継者にアリーを指名したとされる伝説)を否定し、アリー以前の三人のカリフを劣ったイマームとして認めています。
また、イマームのガイバ思想も否定しています。
ザイド派は、現在もイエメンを中心に信者が存在しています。
最近イエメン内紛のニュースで取り上げられる武力組織「フーシ」は、ザイド派系の一組織になります。
とりあえず、ここまでざっとみてみました。
イスラームの宗派というと、近年中東地域のイスラーム内で宗派対立が激化してきている印象が強くあります。
しかし、これは宗派的・教義的な対立というより、政治的な対立が主な要因であるということを忘れてはいけません。
例えばイラクでは、フセインの独裁政権時代にシーア派とクルド人が徹底的に弾圧されていました。
スンナ派は妥協的で政権に協力的のため、フセイン政権下では優遇されてきたのです。
しかし、イラク戦争で米軍にフセイン政権が倒されて弾圧から解放されると、シーア派が国内の多数派となって政治的に優勢となり、次第に過去の不満をスンナ派に向けるようになってきたので、今度はスンナ派が不満を覚えるようになりました。
そこでイラク西部・中部で生まれたスンナ派強硬過激派組織IS(イスラーム国)が活動を活発化させ、スンナ派民衆の支持と協力を得て急速にイラクやシリアで支配地域が広まり、各地域で宗派対立がさらに激化していく、、、という悪い流れが起きてしまっています。
そして、そもそもの起こりは、第一次世界大戦後のイギリスやフランスが引いた国境線に問題があり、西洋世界がイスラーム世界を植民地として侵略したことがきっかけでもあります。
この他の宗派対立も実は政治的な思惑が絡んだ対立が色濃く、決して単純な宗教対立ではないことを頭に入れておかなくてはなりません。
最後にもう一つ。
スンナ派は圧倒的多数派でシーア派は少数派ではありますが、特にスンナ派が正統派でシーア派が異端、ということではありません。
イスラームには本山制度や教会制度はなく、どの学説や宗派が正統か異端かを決定するようなシステムが存在しないのです。
あえて言うならばそれを決めるのは信徒の合意、すなわちウンマの合意に基づきます。
ゆえに、ある一定数の信者・信徒がいる宗派は、一宗派として存在が認められることになるのです。
(現実的に迫害や弾圧はありますが…)
以上、イスラームの宗派についてみてきました。
次に、宗派とは異なるのですが、イスラームの神秘主義(スーフィズム)について少し触れておきたいと思います。
スーフィズム(アラビア語ではタサウウフ)とはイスラーム神秘主義のことで、神秘主義者のことをスーフィーといいます。
スーフィーの語源は「スーフ」、羊毛のことで、貧者の衣服を指します。
スーフィズムは八世紀から九世紀に発展していき、イスラーム法を外面的に遵守するだけでは得られなかった、内面的な心の平安を得ようとした活動です。
宗派は関係なくスンナ派シーア派ともにそれぞれ神秘主義が存在し、外面的なイスラーム法だけでなく内面的精神的な修行をする集団のことです。
スーフィズムの起源は大征服時代に生まれた禁欲主義(ズフド)です。
大征服時代にアラブ人支配者層が優遇され次第に富裕化していき、現世の幸福だけを求める傾向が強まりました。
その反発で富裕層を批判する禁欲主義が生まれて、最後の審判を恐れて禁忌・苦行に励む人々が現れました。
さらに九世紀にアッバース朝のもとでイスラーム法の法体系が整うと、イスラーム法の履行、すなわち人間の外面性のみを重視する傾向が強くなってきました。
この動きに対する反発が起きて内面性を強調する動きが出て、それが禁欲主義と相まって発達し、さらに昇華したのが神秘主義となります。
内面性の強調は初め、禁欲主義から始まりました。
しかしその後、ラービア(714-801)という女性スーフィーが登場し、神への愛が大切だと強く主張、神や最後の審判を恐れてひたすら禁欲するのではなく、神を愛し神と人間の霊魂が合一することが重要だと説きました。
この主張を受けて多くの禁欲主義者たちが彼女の思想に同調し、禁欲主義から神秘主義への転換が起きてスーフィズムが生まれたのです。
スーフィズムの修行は神との合一を目指します。
精神的な修行によって自己意識が消えて、神の中に包摂された神との合一状態のことをファナー(消滅)といい、神に意識が支配され人間は没我状態になります。
こうした精神的修行をすることによりムスリムは神を身近に感じ、イスラーム法を外面的に守るだけでは得られなかった内面的な神との合一を感じられるようになったのです。
しかし、スーフィズムが確立するにしたがって、一部のスーフィーたちは反体制的な態度をとったりイスラーム法を軽視したり、さらに飲酒や同性愛などに走る者たちが出てきました。
スーフィズムはイスラーム法を重視するウラマー(イスラーム法学者)たちにとっては危険な存在であり、初期のスーフィズムではスーフィーとウラマーの強い対立がありました。
このスーフィーと法学者の対立を解決し、融和へと導いたのがイスラーム中興の祖ともいわれるガザーリー(1058-1111)です。
彼はもともとエリートで優秀なウラマーで、当時最高といわれたニザーミーヤ学院の教授としてスンナ派学界トップの地位にいましたが、「疑いのない真の知識とは何か?」という懐疑主義に陥り、教授の地位を捨て真理を求めて各地を十年間放浪しました。
放浪の結果、スーフィズムによる直接的体験、つまりファナーによって真理を得ることができると悟って回心し、神学にスーフィズムを取り入れました。
ガザーリーは、ファナーの時に神から与えられる知識が最高の真理であるとしながら、外面的なイスラーム法をきちんと遵守せねば神の道に背くことになると主張し、スーフィズムの立場から法学・神学を解釈しました。
このようなスーフィー理論家が現れたことにより、ウラマーとスーフィーは次第に融和していきました。
そして11世紀までにスーフィズムは一般民衆に普及して、13世紀にはイスラーム社会全体に普及しました。
そして、有名著名なスーフィーのもとに多くの弟子が集まるようになって次第に組織化されていき、12世紀半ばには様々なスーフィー教団(タリーカ)が生まれました。
スーフィー教団ができたころからそのトップである導師のうち、優秀な導師は「聖者」として次第にあがめられるようになりました。
聖者として多くのムスリムに認められたスーフィーは、死後も民衆信仰の対象となり多くの聖者廟が建てられます。
著名なスーフィー廟は、現在でもイスラーム圏各地にあります。
13世紀以降、ほとんどのムスリムがいずれかのスーフィー教団に所属するのが当たり前となり、ムスリムはどこかのタリーカといずれかの法学派に所属し、信仰の内面はタリーカによって、信仰の外面は法学派によって指導を受けていました。
またスーフィー教団はムスリム商人の活動とともに各地へ広がっていき、中央アジアや東南アジアなどへのイスラーム伝播に大きな役割を果たしてきました。
しかし、19世紀以降にワッハーブ派などによる復古回帰主義の隆盛が起こり、スーフィズムは異端視され預言者の教えに反するとして強い批判を受けました。
結果、アラビア半島のサウディアラビアではスーフィズムは廃れてしまい、多くの聖者廟などスーフィー施設が破壊・撤去されてしまいました。
その復古・回帰主義の影響と、植民地時代に西洋列強に強く反発したタリーカへの徹底的弾圧もあって、現在のイスラームではスーフィズムはかつての勢いはなくなってきています。
しかし、現在でも一部のタリーカは活動を続けていて、カーディリー教団、メヴレヴィー教団、リファーイー教団などが有名です。
そして、今でも多くのムスリムたちは中東各地のスーフィー廟を参詣して、聖者の神秘的な力にすがってドゥアー(願い事)などをしています。
以上、イスラームの宗派とスーフィズムを見てみました。
何かの参考になれば、幸いです。
次回は、多数派であるスンナ派を知ることはイスラームを知ること、ということでスンナ派の教義などについて少し深く調べてみたいと思っています。
m(_ _)m
今回は、イスラームに存在する主な宗派の教義とその違いを見ていきたいと思います。
そのあとに、イスラーム神秘主義(スーフィズム)についても触れてみます。
ではまず、イスラームの各宗派について。
イスラームの宗派は大きく分類すると、スンナ派(スンニ派)、シーア派、ハワーリジュ派の三つに分かれます。
その中で、シーア派にはさらに5つくらいの宗派があります。
以下、簡単ですが主要な宗派について順に見ていきます。
少数派のいくつかについては、申し訳ないのですが省略させていただきます。
1.スンナ派
正確には「スンナとウンマの民」といいます。(テレビなどではスンニ派といわれています)
全てのムスリム(イスラーム教徒)の実に9割がスンナ派となり、圧倒的な多数派で体制派となります。
スンナは「慣行」という意味で、預言者ムハンマドの慣行、すなわちイスラーム法(シャリーア)を表します。
ウンマは「イスラーム共同体」を意味し、ムハンマドが定めたマディーナ憲章による、ウンマの合意(イジュマー)を意味します。
スンナ派は、シャリーアとイジュマーに従う人々の宗派です。
歴史の方でも触れましたが、スンナ派は初めから宗派として存在していたわけではありません。
ウンマからシーア派やハワーリジュ派が分離するにしたがって、相対的に成立していった多数派です。
スンナ派は圧倒的な多数派かつ体制派なので、総じて現実主義であり極端な主張を避けてウンマの統一・合意・秩序を重視します。
またイスラームが発展するにしたがって、スンナ派の中で多くの神学派や法学派が存在してきましたが、分裂することなくいちおうスンナ派として一つにまとまっています。
(スンナ派についての詳細は、教義やイスラーム法など含めまた別の記事にしたいと思います)
しかし、内実的には穏健派、世俗派、復古主義、強硬過激派などなど、多種多様な主義主張が混在していて、正直私たちイスラーム以外の人間からは複雑でよくわからない宗派だともいえます。
スンナ派信徒は、アラブ諸国、トルコ、東南アジア、中国、中央アジア、アフリカ諸国など、イスラームが広まった地域のほとんどにいます。
逆に言うと、シーア派が多いイランとペルシア湾周辺地域を除けばほとんどスンナ派、といっても良いくらいの圧倒的な多数派になります。
2.シーア派
正しくは「シーア・アリー」といいます。
シーアは「党派」という意味で、アリーの党派という意味です。
ウンマの指導者はアリーとその子孫だけがなれる、と主張するグループの総称です。
またシーア派にはさらにいくつか宗派があり、アリーの子孫の中で誰を指導者(イマーム)とするか、またどの系譜を支持するか、をめぐって分派してきました。
歴史で触れましたが、アリーは預言者ムハンマドのいとこであり年の離れた幼なじみで、さらにはムハンマドの娘婿になります。
第4代のカリフであり、シーア派においては初代イマームとなります。
アリーは非常に聡明な人物でムハンマドからの信頼も厚く、ムハンマドの末娘のファーティマと結婚しました。
ムハンマドには三男四女の子供がいましたが、男子は全て幼くして亡くなり、娘もアリーと結婚したファーティマだけに子供が産まれました。
つまり、アリーの子孫はムハンマド直系の子孫にあたります。
預言者直系の血筋であるから、その子孫はウンマの指導者になる資格と能力がある、だからアリーとその子孫のみがウンマの指導者として認められる、というのがシーア派の主張です。
また歴史の流れのなかで、シーア派には反ウマイヤ朝の軍人やアラブ人優遇に反対する非アラブ人(主にペルシア人)などが加わっていったため、シーア派には反体制、反アラブ人といった考えも含まれています。(現在はそれほど強調されていません。しかし、伝統的にアラビア半島の人々とペルシアの人々の心の奥底に、若干の敵対感があるのは事実です)
また、680年のカルバラーの悲劇で無念の死を遂げた第3代イマームのフサインを追悼するアーシューラーの祭は、シーア派独自の重要な祭礼です。
他にシーア派の特徴として、
・啓典クルアーン(コーラン)のシーア派独自の解釈がある。
・聖典ハディースに、預言者以外に歴代シーア派イマームの言行が含まれる。
・巡礼で訪れる聖地に、マッカ・マディーナの他に歴代イマーム廟が含まれる。
・信仰隠し(タキーヤ)が認められていて、シーア派だと分かると危険が及びそうなときはスンナ派のふりをしても良い。
・一時婚(ムトア)が認められていて、期間を決めて婚姻契約を結べる。(一種の買春だという批判もある)
・うろこのない魚(ウナギなど)は食べてはいけない。(他にも宗派・地域などにより独自の食物規定もある)
など、スンナ派と違う教義がいくつかあります。
シーア派は、イラン(ペルシア)地域のイスラーム国家に16世紀から現代に至るまで長く保護されてきたため、シーア派信徒のほとんどはイラン周辺、イラク南部やペルシア湾岸地域にいます。
他にイエメン、シリア、インド、パキスタンなどにいます。
3.ハワーリジュ派
「出ていく人」という意味。
歴史でも触れましたが、ハワーリジュ派はもともとシーア派でした。
アリーとムアーウィアがカリフの座をめぐって対立が激化するなか、アリーとムアーウィアは一時和平を結びました。
その和平に反対したグループがシーア派から分離したのが、ハワーリジュ派です。
ハワーリジュ派は、信仰は外面的な行為・行動に表れるとし、信仰は行為と一致しなければならない、と考えました。
そして、ムスリムの行動に間違いがあればその人は不信仰者でムスリムではない、として厳しく追求・断罪しました。
不信仰者として決め付けることをタクフィールといい、不信仰者は殺害を含めて厳しく断罪するべき、という考えをタクフィール思想といいます。
ハワーリジュ派は、ウマイヤ家を重用した第3代カリフのウスマーンは罪を犯したので不信仰者となり、そのウスマーンの復讐として兵を挙げたムアーウィアも悪であり、悪であるムアーウィアと調停をしたアリーも悪となるのです。
ゆえに、アリーはハワーリジュ派に暗殺されてしまうのです。
ハワーリジュ派にはその過激的な思想のため、主流派とはならず少数の支持者しかいませんでした。
後に過激派と穏健派に分裂して、現在は穏健的なイバード派がオマーンや北アフリカなどに存在しています。
ハワーリジュ派のタクフィール思想はたびたび反政府運動の口実となり、強硬派や過激派によって攻撃・暗殺・殺害のための論理に使われました。
現在でもテロリズムの口実に使われることもあります。
ちなみに他のスンナ派やシーア派は、タクフィール思想を否定しています。
ムスリム個人の信仰心はその行為だけでは計れないとし、ムスリムの最大の罪は多神崇拝(シルク)であってそれを犯さなければ信仰者であるとしました。
また不信仰者かどうかの判断は、最後の審判においてアッラーのみが決めることができる、と考えられています。
1-2.ワッハーブ派(スンナ派系)
スンナ派ハンバル学派の流れをくむ法学派で、アブド・アル=ワッハーブ(1703-92)が唱えた、復古主義的改革思想です。
本来は別の宗派ではなくスンナ派学派の一つなんですが、サウディアラビアでは国教のような扱いとなっているので、いちおうスンナ派系の宗派としてあげておきます。
ワッハーブ派は厳格な復古主義で、スーフィズム(神秘主義)を否定しムハンマドの教えに帰れ、と主張しました。
19世紀半ばにワッハーブ派がアラビア半島のムスリムに広まり、リヤド周辺支配者だったサウード家に強く後押しされる形で一気に勢力を広げ、最終的にアラビア半島の大半を支配した、ワッハーブ派を国教とする現在のサウディアラビア王国となりました。
ワッハーブ派は、ムハンマド時代から正統カリフ時代までのイスラーム法の実践に回帰することをめざして、イスラーム初期のシャリーアを厳格に実践し、またイスラーム中期以降隆盛したスーフィズムをイスラームから逸脱したとして強く否定しました。
その結果、サウディアラビアにおいてはスーフィー聖者廟が破壊されて、スーフィズムはほぼ排除されています。
ワッハーブ派信徒はアラビア半島に多く、サウディアラビアのスンナ派はほぼワッハーブ派と言えます。
2-1.十二イマーム派(12イマーム派、シーア派系)
シーア派の宗派の一つで、イランの国教です。
シーア派の9割近くは十二イマーム派であり、シーア派と言えば十二イマーム派のことを指すことが多いです。
イスラームにはもともと終末論と救世主思想があり、シーア派は長く抑圧されてきた宗派であるがゆえ、特に救世主思想を重視する傾向があります。
十二イマーム派は、特にその救世主思想を第12代イマームのガイバ(お隠れ)思想とあわせて重要な教義としています。
十二イマーム派は、アリーを初代イマームとして第12代イマームのムハンマドまでのイマームの系譜を支持します。
873年、11代イマームのハサン・アル=アスカリーが没したあと、12代イマームをムハンマドが幼くして受け継ぎましたが、突如姿を消してしまいました。
弟子たちは、ムハンマドは異次元空間にお隠れ(ガイバ)になったと言い、ムハンマドは年もとらない異次元空間で長い瞑想に入ったとされます。
そして世界に終末が訪れる直前に、12代イマームのムハンマドは救世主(マフディー)として人間世界に現れ、シーア派の教えによる正しいウンマを導いて地上に楽土を作り上げ、その後終末が来てアッラーによる最後の審判が行われる、とされています。
十二イマーム派の指導者イマームの正統性は血統に基づいており、イマームにはムハンマドとアリーの血によってあらゆる知識が授けられるとされます。
ゆえにイマームは全知であり不可謬(ふかびゅう、イスマ)であり、決して間違いを起こさない完全人間とされます。
十二イマーム派では、完全人間であるイマームがウンマを指導しないと不完全な人間はかならず間違いを起こすとされ、この教義はスンナ派のイジュマー(共同体の合意)と相反するものです。
不完全な人間が生み出す合意は不完全であり、正しい判断は全知であるイマームのみによって行われ、一般信徒はイマームに絶対服従しなければならないとされます。
また完全な知識を持つイマームは、啓典クルアーン(コーラン)やハディースを比喩的解釈を行い、内面的で奥義的な解釈を引き出します。
その結果十二イマーム派には、スンナ派と違う解釈によるクルアーン注釈書があります。
また預言者の言行録、聖典ハディースも預言者ムハンマドの言行だけでなく、歴代イマームの言行が含まれた独自のシーア派四大伝承集が存在します。
十二イマーム派は10世紀イラクのブワイフ朝において基本的な教義が整えられ、16世紀にペルシア(イラン)地域に興ったサファヴィー朝が国教とし保護してきました。
サファヴィー朝から始まる歴代シーア派政権はイラン全土とイラク南部などを支配し、十二イマーム派の信徒はイラン全土とイラク南部、ペルシア湾周辺の地域に存在します。
2-2.イスマーイール派(シーア派系)
イスマーイール派は、シーア派系の宗派で、909年に北アフリカでファーティマ朝を建てた宗派になります。
イスマーイール派の系譜は、765年に6代イマームのジャアファル・サーディクの死後、7代イマームとして息子のイスマーイールを支持したグループです。
その後約百年間の活動は不明ですが、隠れイマームが三代続いたとされます。
そして9世紀後半に、イスマーイール派の指導者は北アフリカで反アッバース朝運動を開始し、近い将来にイスマーイールの息子のムハンマドが救世主(マフディー)として復活し従来のシャリーアが廃棄されると主張し、大々的な宣教運動を始めました。
899年、イスマーイール派の指導者であり隠れイマームの代理人を自称していたアブドゥッラーが、自分がイマームであると宣言して権威を高め、909年には北アフリカにファーティマ朝を建国し、アブドゥッラーはファーティマ朝初代カリフ(イマーム)となりました。
やがてファーティマ朝は勢力を拡大して、969年にはエジプト全域を支配して首都カイロを建設しました。
第4代カリフ、ムイッズの時代には国家体制が整備されて、アズハル大学などのイスラーム学院が建設されます。
ファーティマ朝が安定期に入るとイスマーイール派の教義が修正され、終末は先送りにされてイマームの連続性とイマームに対する服従が強調されるようになりました。
しかし、イスマーイール派内部からは終末を早急に実現しようとする人々が現れ、終末到来を主張する行為や運動が何度も繰り返されてきました。
1169年にファーティマ朝が滅亡すると、エジプトではスンナ派が復興しイスマーイール派は衰退しました。
現在のイスマーイール派はいくつかの分裂を経て、インドやパキスタンなどに存在しています。
終末は先送りにされてイマームへの帰衣が説かれていて、スンナ派との協調も模索されます。
イスマーイール派イマーム、アーガー・ハーンは現在フランスのパリに住んでいて、パキスタンではイマームのカリスマ性と財力に基づいてNGO活動が盛んに行われ、大学への奨学基金や研究機関の運営などをしています。
2-3.ドゥルーズ派(シーア派系)
ドゥルーズ派は、シーア派系の少数一派です。
11世紀初めに、創始者ハムザ・イブン・アリーがイスマーイール派第6代カリフ、ハーキムを神格化してイスマーイール派から分派した一派です。
ハーキムは常軌を逸した行動が多かったといわれ、ある夜一人でロバに乗りカイロ市街を見下ろすムカッタム丘を散策中、姿を消しました。
イスラーム史上、「行方不明」と記録される唯一のカリフです。(暗殺された可能性もあると言われます)
ドゥルーズ派はそのハーキムを神とする教義を持ち、失踪後ハーキムはお隠れ状態にあり終末にマフディーとして再臨するとされます。
またクルアーン(コーラン)に代わる独自の聖典「ラサーイル・ヒクマ」(叡智の書簡集)があります。
輪廻思想を持ち、ドゥルーズ派信徒は必ず再びドゥルーズ派信徒に生まれ変わるといわれ、さらにマッカ巡礼を義務とせず、イスラエルにある預言者シュアイブの墓への参詣を重要としています。
このような独特で変わった教義を持つために、ドゥルーズ派は長く異端視され迫害を受けてきました。
ちなみにドゥルーズとは成立初期に活躍した宣教師ダラズィーに由来します。
発祥のエジプトでは弾圧を受けたためシリアで布教活動を展開し、そこで外部との接触を避けた独自の社会を形成し、近代まで自治を続けてきました。
現在はレバノン、シリア、イスラエルに約100万人の信徒がいます。
またドゥルーズ派は、シリアやレバノンの近現代において重要な役割をしてきました。
1860年にはレバノンでキリスト教系マロン派と宗教紛争に敗れて、シリアへの移住が進みました。
そのシリアではフランスの委任統治に対し、反乱を起こしました。
現在、レバノンでは宗派体制のもと中規模の政治勢力として重要な地位を占め、イスラエルではユダヤ人入植者に協力的だったため、他のムスリムとは違う扱いを受けています。
2-4.アラウィー派(シーア派系)
アラウィー派はシーア派の少数一派で、第4代カリフでありシーア派初代イマームの「アリー」を神格化するという教義を持ちます。
9世紀に十二イマーム派の第10代イマームの側近だったムハンマド・イブン・ヌサイルによって生まれたので、ヌサイリー派ともいいます。
イスマーイール派の影響が大きく、シリア土着の宗教やキリスト教の要素も取り入れられ、初代アリーが最もイマームにふさわしいとしてアリーを神格化し、輪廻転生などの独特の教義を持ちます。
初めはイラクで活動していたが、10世紀後半に拠点をシリアのラタキアに移しました。
しかし、十字軍の攻撃やマムルーク朝、オスマン帝国の迫害にあったため、長く信仰隠し(タキーヤ、隠れ信仰、表向きスンナ派信者のふりをすること)をしてきました。
第一次世界大戦後、フランスのシリア委任統治時代にようやく信仰を認められ、自治が認められました。
現在アラウィー派は、シリア、トルコ南東部、レバノンに存在します。
なお、シリアはアラウィー派による寡頭支配体制が確立していて、大統領はアラウィー派のアサド家に事実上世襲され、政権与党である社会主義政党バアス党や国軍の要職もアラウィー派が占めています。
現在シリアはアラブの春といわれた民主主義運動の余波を受け、現アラウィー派アサド政権と言論の自由と独裁体制打破を目指した反体制派との泥沼の内戦状態にあり混乱が続いていますが、反体制派の分裂やIS(イスラーム国)の台頭、国際社会の足並みの乱れにより、泥沼の長期化をたどっています。
2-5.ザイド派(シーア派系)
ザイド派は、第4代イマーム、ザイヌル・アービディーンの死後、第5代イマームにザイドを支持したグループです。
740年、ザイドが自らが主導してウマイヤ朝に対し反乱を起こしたが、失敗しました。(ザイドの反乱)
その後ザイド派は、アリーの長男ハサンの子孫をイマームに据え、イエメンを拠点に存在してきました。
イエメンではザイド派の支配が続き、特に17世紀前半から1962年に王権が倒れるまで、ザイド派王朝が続いてイマームが政治権力も握っていました。
ザイド派の特徴は、穏健的でスンナ派とも妥協的なところです。
ザイド派はガディール・フムの伝説(預言者ムハンマドが後継者にアリーを指名したとされる伝説)を否定し、アリー以前の三人のカリフを劣ったイマームとして認めています。
また、イマームのガイバ思想も否定しています。
ザイド派は、現在もイエメンを中心に信者が存在しています。
最近イエメン内紛のニュースで取り上げられる武力組織「フーシ」は、ザイド派系の一組織になります。
とりあえず、ここまでざっとみてみました。
イスラームの宗派というと、近年中東地域のイスラーム内で宗派対立が激化してきている印象が強くあります。
しかし、これは宗派的・教義的な対立というより、政治的な対立が主な要因であるということを忘れてはいけません。
例えばイラクでは、フセインの独裁政権時代にシーア派とクルド人が徹底的に弾圧されていました。
スンナ派は妥協的で政権に協力的のため、フセイン政権下では優遇されてきたのです。
しかし、イラク戦争で米軍にフセイン政権が倒されて弾圧から解放されると、シーア派が国内の多数派となって政治的に優勢となり、次第に過去の不満をスンナ派に向けるようになってきたので、今度はスンナ派が不満を覚えるようになりました。
そこでイラク西部・中部で生まれたスンナ派強硬過激派組織IS(イスラーム国)が活動を活発化させ、スンナ派民衆の支持と協力を得て急速にイラクやシリアで支配地域が広まり、各地域で宗派対立がさらに激化していく、、、という悪い流れが起きてしまっています。
そして、そもそもの起こりは、第一次世界大戦後のイギリスやフランスが引いた国境線に問題があり、西洋世界がイスラーム世界を植民地として侵略したことがきっかけでもあります。
この他の宗派対立も実は政治的な思惑が絡んだ対立が色濃く、決して単純な宗教対立ではないことを頭に入れておかなくてはなりません。
最後にもう一つ。
スンナ派は圧倒的多数派でシーア派は少数派ではありますが、特にスンナ派が正統派でシーア派が異端、ということではありません。
イスラームには本山制度や教会制度はなく、どの学説や宗派が正統か異端かを決定するようなシステムが存在しないのです。
あえて言うならばそれを決めるのは信徒の合意、すなわちウンマの合意に基づきます。
ゆえに、ある一定数の信者・信徒がいる宗派は、一宗派として存在が認められることになるのです。
(現実的に迫害や弾圧はありますが…)
以上、イスラームの宗派についてみてきました。
次に、宗派とは異なるのですが、イスラームの神秘主義(スーフィズム)について少し触れておきたいと思います。
スーフィズム(アラビア語ではタサウウフ)とはイスラーム神秘主義のことで、神秘主義者のことをスーフィーといいます。
スーフィーの語源は「スーフ」、羊毛のことで、貧者の衣服を指します。
スーフィズムは八世紀から九世紀に発展していき、イスラーム法を外面的に遵守するだけでは得られなかった、内面的な心の平安を得ようとした活動です。
宗派は関係なくスンナ派シーア派ともにそれぞれ神秘主義が存在し、外面的なイスラーム法だけでなく内面的精神的な修行をする集団のことです。
スーフィズムの起源は大征服時代に生まれた禁欲主義(ズフド)です。
大征服時代にアラブ人支配者層が優遇され次第に富裕化していき、現世の幸福だけを求める傾向が強まりました。
その反発で富裕層を批判する禁欲主義が生まれて、最後の審判を恐れて禁忌・苦行に励む人々が現れました。
さらに九世紀にアッバース朝のもとでイスラーム法の法体系が整うと、イスラーム法の履行、すなわち人間の外面性のみを重視する傾向が強くなってきました。
この動きに対する反発が起きて内面性を強調する動きが出て、それが禁欲主義と相まって発達し、さらに昇華したのが神秘主義となります。
内面性の強調は初め、禁欲主義から始まりました。
しかしその後、ラービア(714-801)という女性スーフィーが登場し、神への愛が大切だと強く主張、神や最後の審判を恐れてひたすら禁欲するのではなく、神を愛し神と人間の霊魂が合一することが重要だと説きました。
この主張を受けて多くの禁欲主義者たちが彼女の思想に同調し、禁欲主義から神秘主義への転換が起きてスーフィズムが生まれたのです。
スーフィズムの修行は神との合一を目指します。
精神的な修行によって自己意識が消えて、神の中に包摂された神との合一状態のことをファナー(消滅)といい、神に意識が支配され人間は没我状態になります。
こうした精神的修行をすることによりムスリムは神を身近に感じ、イスラーム法を外面的に守るだけでは得られなかった内面的な神との合一を感じられるようになったのです。
しかし、スーフィズムが確立するにしたがって、一部のスーフィーたちは反体制的な態度をとったりイスラーム法を軽視したり、さらに飲酒や同性愛などに走る者たちが出てきました。
スーフィズムはイスラーム法を重視するウラマー(イスラーム法学者)たちにとっては危険な存在であり、初期のスーフィズムではスーフィーとウラマーの強い対立がありました。
このスーフィーと法学者の対立を解決し、融和へと導いたのがイスラーム中興の祖ともいわれるガザーリー(1058-1111)です。
彼はもともとエリートで優秀なウラマーで、当時最高といわれたニザーミーヤ学院の教授としてスンナ派学界トップの地位にいましたが、「疑いのない真の知識とは何か?」という懐疑主義に陥り、教授の地位を捨て真理を求めて各地を十年間放浪しました。
放浪の結果、スーフィズムによる直接的体験、つまりファナーによって真理を得ることができると悟って回心し、神学にスーフィズムを取り入れました。
ガザーリーは、ファナーの時に神から与えられる知識が最高の真理であるとしながら、外面的なイスラーム法をきちんと遵守せねば神の道に背くことになると主張し、スーフィズムの立場から法学・神学を解釈しました。
このようなスーフィー理論家が現れたことにより、ウラマーとスーフィーは次第に融和していきました。
そして11世紀までにスーフィズムは一般民衆に普及して、13世紀にはイスラーム社会全体に普及しました。
そして、有名著名なスーフィーのもとに多くの弟子が集まるようになって次第に組織化されていき、12世紀半ばには様々なスーフィー教団(タリーカ)が生まれました。
スーフィー教団ができたころからそのトップである導師のうち、優秀な導師は「聖者」として次第にあがめられるようになりました。
聖者として多くのムスリムに認められたスーフィーは、死後も民衆信仰の対象となり多くの聖者廟が建てられます。
著名なスーフィー廟は、現在でもイスラーム圏各地にあります。
13世紀以降、ほとんどのムスリムがいずれかのスーフィー教団に所属するのが当たり前となり、ムスリムはどこかのタリーカといずれかの法学派に所属し、信仰の内面はタリーカによって、信仰の外面は法学派によって指導を受けていました。
またスーフィー教団はムスリム商人の活動とともに各地へ広がっていき、中央アジアや東南アジアなどへのイスラーム伝播に大きな役割を果たしてきました。
しかし、19世紀以降にワッハーブ派などによる復古回帰主義の隆盛が起こり、スーフィズムは異端視され預言者の教えに反するとして強い批判を受けました。
結果、アラビア半島のサウディアラビアではスーフィズムは廃れてしまい、多くの聖者廟などスーフィー施設が破壊・撤去されてしまいました。
その復古・回帰主義の影響と、植民地時代に西洋列強に強く反発したタリーカへの徹底的弾圧もあって、現在のイスラームではスーフィズムはかつての勢いはなくなってきています。
しかし、現在でも一部のタリーカは活動を続けていて、カーディリー教団、メヴレヴィー教団、リファーイー教団などが有名です。
そして、今でも多くのムスリムたちは中東各地のスーフィー廟を参詣して、聖者の神秘的な力にすがってドゥアー(願い事)などをしています。
以上、イスラームの宗派とスーフィズムを見てみました。
何かの参考になれば、幸いです。
次回は、多数派であるスンナ派を知ることはイスラームを知ること、ということでスンナ派の教義などについて少し深く調べてみたいと思っています。
m(_ _)m