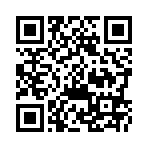2011/05/31
日本の電気の現状(電力について考えてみる4)
原発を減らす話の前に、日本の発電方法や電力使用量の現状を、もう一度しっかり確認しておきたいと思います。
(電気事業連合会サイトの「電気事業のいま」を見てみると、図表もあってよく分かるので、詳しくはそちらを見てください)
2009年の電源(発電方法)別発電電力量の実績は次の通りです。
原子力 29%
火力.石油 7%
火力.石炭 25%
火力.天然ガス 29%
水力 8%
自然エネルギー他 1%
(総計9,565億kwh)
さて、これを見て気付くことはなんでしょうか?
まず目を引くのは、自然エネルギー発電の低さ、です。
水力を除いての数字ですが、全体のたった1%しかありません。
いろいろと話題になっていても、実際はこれだけしかない。
自然エネルギー発電の難しさと、設置・研究ふくめ予算が十分そちらへ回っていないことが、予想できます。
今後十数年で20%にするとか菅さんが言ってましたが、そう簡単にはいかないでしょう。
あと注目点は、火力発電の内訳です。
火力発電は全部で61%と大半を占めますが、使用する燃料の内訳は、石油は7%と低く、主流は石炭と天然ガスとなっています。
石油はオイルショックの経験、近年の価格高騰の問題、将来の枯渇の懸念もあります。
なので、比較的価格が安定していて埋蔵量に余裕があるとされる、石炭・天然ガスへ移行しています。
そして全体で見ると、どれかひとつの燃料に偏りすぎていないということが分かると思います。
これも、資源の少ない日本ならではの対策です。
もし、何かの理由で突然どれかの資源の輸入がストップしてしまっても、一つの資源に偏りすぎないこと(電源の燃料をバランスよく使うこと)によって、電力不足の危機を少なくしよう、という対策です。
つぎに一日の電力需要の動きと、それをどの発電方法(電源という)で供給するかを見てみます。
一日の電力需要を見ると、朝8時ころから需要が伸びていって午前11時〜午後4時が高くなり、午後3時が最も高くなります。
あとはじわりと下がり、午後8時をすぎるとぐっと下がっていって、午前5時〜6時が最も需要が低い時間帯となります。
(いままで最低需要はピーク時の3割といってましたが、電気事業連合会のサイトでは最低需要はピーク時のおよそ4割になっています。しかし揚水水力発電用の電力も含まれているので、実際は3〜4割というのが正しいかと思われます)
また需要変化に応じた電源の組み合わせ(ベストミックス)というグラフを見ると、時間ごとの発電方法の内訳がわかるし、それぞれの電源の役割がよくわかります。
発電のベースとなるのは、やはり24時間発電できる電源で、原子力発電と流込(自流)式水力発電を使います。
火力発電は、もっぱら需要増加に応じて調整するように使われます。
ピーク時にはさらに揚水式、貯水池式、調整池式の水力発電も合わせて、需要を補うようにしています。
さらに発電方法、電源ごとの特徴を確認してみます。
(原発は以前やったので、省略します)
発電の6割を占める火力発電は、まさに電力の中心であり、大規模発電と安定供給にかかせない施設です。
しかし、グラフの通り一日中フルに燃やして発電しているわけではなく、夜間は原子力などが主で、火力はわずかに稼働する程度です。
逆に昼のピーク時は、ほぼフルで稼働することになります。
稼働のオン・オフがしやすいので、供給電力量を調整するのに最も適していると言えます。
また燃料さえしっかり確保できれば、安定した発電が可能です。
最近の火力発電は発電効率が良く、とくに天然ガスではガスタービン式という非常に効率の良い発電ができます。
ひと昔よりCO2排出量が少なくなりましたが、やはり燃料を燃やすことには代わりはなく、他の発電方法よりCO2を多く排出します。
流込式水力発電は、河川から水を水路へ引き込み、そこへ発電機を取り付け、その流れを利用して発電します。
河川水量に余裕がある間は24時間発電することができますが、渇水時などは発電量が落ちることがあります。
発電規模はあまり大きくできず、小〜中規模発電となります。
でもダム式などに比べると建設費は安く、比較的容易に工期も短く建設ができます。
24時間発電できるので、原発と同じくベースの発電として稼働します。
(私が原発代替に良いと思うのは、この流込式です)
貯水池式・調整池式は、いわゆるダム式で、規模の大きいものを貯水池式、小さいものを調整池式といいます。
建設費が高くなりやすく、建設規模も大きくなるので工期が長いことや環境破壊の懸念など、諸問題も多くなります。
発電規模はダム施設により、大きいものから小さいものまで様々です。
発電できる時間は、溜める水の量によりますが、連続して一日から一週間ほどで、それほど長い間発電できません。
現在は需要ピークを補うように稼動しています。
揚水式発電はダム式の一種で、二つの調整池を作り、電力に余裕がある夜間に低い池から高い池へ水を汲み上げ、昼のピーク時などに高い池から低い池へ水を流し、その水で発電します。
汲み上げれば、原則何度でも発電可能ですが、発電時間は貯水量により、おおむね長時間は発電できません。
発電規模はダム施設の大きさによりますが、中規模のものが多いようです。
貯水池式等と同じく、主に昼の需要ピーク時を補うように使われます。
また、電力供給先の変遷と家庭内消費電力の内訳の変遷の図表も見ておいてください。
ざっと説明すると、
近年は一般家庭の消費電力が増えていること
一般家庭では暖房・冷房と冷蔵庫の消費電力が大半を占めること
パソコンなどの普及により家電の電力消費が増えていること
などがポイントとなります。
今回の話は、電気事業連合会のサイトを見るほうが、より良く理解できると思いますので、ぜひ見てみてください。
しかし、説明ばかりでなかなかすすめず、申し訳ないです。
でも今後の電力について語るのなら、最低限の知識は理解しておかないといけないと、私は考えます。
マスメディアみたいに、表面だけなぞって技術の理解や使い方をあまり説明せず、原発はダメだとか太陽光・風力が良いとか議論することが、悲しく中身の薄い議論になってしまうのが解ると思います。
私の電力の話は、長くなりそうですが、気長にお付き合いくださると、有り難いです。m(_ _)m
(次回へつづく)
(電気事業連合会サイトの「電気事業のいま」を見てみると、図表もあってよく分かるので、詳しくはそちらを見てください)
2009年の電源(発電方法)別発電電力量の実績は次の通りです。
原子力 29%
火力.石油 7%
火力.石炭 25%
火力.天然ガス 29%
水力 8%
自然エネルギー他 1%
(総計9,565億kwh)
さて、これを見て気付くことはなんでしょうか?
まず目を引くのは、自然エネルギー発電の低さ、です。
水力を除いての数字ですが、全体のたった1%しかありません。
いろいろと話題になっていても、実際はこれだけしかない。
自然エネルギー発電の難しさと、設置・研究ふくめ予算が十分そちらへ回っていないことが、予想できます。
今後十数年で20%にするとか菅さんが言ってましたが、そう簡単にはいかないでしょう。
あと注目点は、火力発電の内訳です。
火力発電は全部で61%と大半を占めますが、使用する燃料の内訳は、石油は7%と低く、主流は石炭と天然ガスとなっています。
石油はオイルショックの経験、近年の価格高騰の問題、将来の枯渇の懸念もあります。
なので、比較的価格が安定していて埋蔵量に余裕があるとされる、石炭・天然ガスへ移行しています。
そして全体で見ると、どれかひとつの燃料に偏りすぎていないということが分かると思います。
これも、資源の少ない日本ならではの対策です。
もし、何かの理由で突然どれかの資源の輸入がストップしてしまっても、一つの資源に偏りすぎないこと(電源の燃料をバランスよく使うこと)によって、電力不足の危機を少なくしよう、という対策です。
つぎに一日の電力需要の動きと、それをどの発電方法(電源という)で供給するかを見てみます。
一日の電力需要を見ると、朝8時ころから需要が伸びていって午前11時〜午後4時が高くなり、午後3時が最も高くなります。
あとはじわりと下がり、午後8時をすぎるとぐっと下がっていって、午前5時〜6時が最も需要が低い時間帯となります。
(いままで最低需要はピーク時の3割といってましたが、電気事業連合会のサイトでは最低需要はピーク時のおよそ4割になっています。しかし揚水水力発電用の電力も含まれているので、実際は3〜4割というのが正しいかと思われます)
また需要変化に応じた電源の組み合わせ(ベストミックス)というグラフを見ると、時間ごとの発電方法の内訳がわかるし、それぞれの電源の役割がよくわかります。
発電のベースとなるのは、やはり24時間発電できる電源で、原子力発電と流込(自流)式水力発電を使います。
火力発電は、もっぱら需要増加に応じて調整するように使われます。
ピーク時にはさらに揚水式、貯水池式、調整池式の水力発電も合わせて、需要を補うようにしています。
さらに発電方法、電源ごとの特徴を確認してみます。
(原発は以前やったので、省略します)
発電の6割を占める火力発電は、まさに電力の中心であり、大規模発電と安定供給にかかせない施設です。
しかし、グラフの通り一日中フルに燃やして発電しているわけではなく、夜間は原子力などが主で、火力はわずかに稼働する程度です。
逆に昼のピーク時は、ほぼフルで稼働することになります。
稼働のオン・オフがしやすいので、供給電力量を調整するのに最も適していると言えます。
また燃料さえしっかり確保できれば、安定した発電が可能です。
最近の火力発電は発電効率が良く、とくに天然ガスではガスタービン式という非常に効率の良い発電ができます。
ひと昔よりCO2排出量が少なくなりましたが、やはり燃料を燃やすことには代わりはなく、他の発電方法よりCO2を多く排出します。
流込式水力発電は、河川から水を水路へ引き込み、そこへ発電機を取り付け、その流れを利用して発電します。
河川水量に余裕がある間は24時間発電することができますが、渇水時などは発電量が落ちることがあります。
発電規模はあまり大きくできず、小〜中規模発電となります。
でもダム式などに比べると建設費は安く、比較的容易に工期も短く建設ができます。
24時間発電できるので、原発と同じくベースの発電として稼働します。
(私が原発代替に良いと思うのは、この流込式です)
貯水池式・調整池式は、いわゆるダム式で、規模の大きいものを貯水池式、小さいものを調整池式といいます。
建設費が高くなりやすく、建設規模も大きくなるので工期が長いことや環境破壊の懸念など、諸問題も多くなります。
発電規模はダム施設により、大きいものから小さいものまで様々です。
発電できる時間は、溜める水の量によりますが、連続して一日から一週間ほどで、それほど長い間発電できません。
現在は需要ピークを補うように稼動しています。
揚水式発電はダム式の一種で、二つの調整池を作り、電力に余裕がある夜間に低い池から高い池へ水を汲み上げ、昼のピーク時などに高い池から低い池へ水を流し、その水で発電します。
汲み上げれば、原則何度でも発電可能ですが、発電時間は貯水量により、おおむね長時間は発電できません。
発電規模はダム施設の大きさによりますが、中規模のものが多いようです。
貯水池式等と同じく、主に昼の需要ピーク時を補うように使われます。
また、電力供給先の変遷と家庭内消費電力の内訳の変遷の図表も見ておいてください。
ざっと説明すると、
近年は一般家庭の消費電力が増えていること
一般家庭では暖房・冷房と冷蔵庫の消費電力が大半を占めること
パソコンなどの普及により家電の電力消費が増えていること
などがポイントとなります。
今回の話は、電気事業連合会のサイトを見るほうが、より良く理解できると思いますので、ぜひ見てみてください。
しかし、説明ばかりでなかなかすすめず、申し訳ないです。
でも今後の電力について語るのなら、最低限の知識は理解しておかないといけないと、私は考えます。
マスメディアみたいに、表面だけなぞって技術の理解や使い方をあまり説明せず、原発はダメだとか太陽光・風力が良いとか議論することが、悲しく中身の薄い議論になってしまうのが解ると思います。
私の電力の話は、長くなりそうですが、気長にお付き合いくださると、有り難いです。m(_ _)m
(次回へつづく)