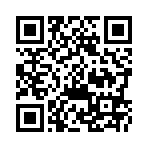2012/06/03
少し前、ストーカーをしていた東京のとある駅員が、駅員であることを利用して、相手の電子マネーカード、パスモのデータを私用で閲覧し、その情報をウェブ掲示板などへ流出させた、という事件がありました。
電子マネーであるがゆえの怖い事件ですね。
さて、皆さんは電子マネーは日常的に使っていますか?
チャージすればチャージした分だけ、切符の代わりや買い物、何にでもまた何回も使えるし、小銭など現金を扱うわずらわしさもないですから、便利ですね。
スイカ、パスモ、エディ、クイックペイ、iD、ワオン、ナナコなどなど、多くの種類があり、使えばポイントも貯まるし、一石二鳥なところも良いところです。
と、さんざんよいしょ?しましたが、実のところ私は一枚も持っていません。
クレディットカードや普通のポイントカードは、たくさん持っていますしよく使いますが、電子マネーのICカードは一つも無いです。
携帯の電子マネー機能もロックしたまま、使ったこともありません。
なぜかというと、電子マネーは「怖い」と思っているからです。
電子マネーには、だれがいつどこで何を買ったか、そのすべてを詳細に記録する機能が付いているものがあります。
そこが、私には恐ろしい、と感じています。
(一部ポイントカードにもその機能が付いているそうです。「Tポイントカード」などの色々なお店でポイントが付けられる汎用性の高いカードです)
その機能は、カード利用者の購買傾向やニーズを把握し、顧客へのサービスを向上させるため、、、というのが名目です。
例えば、よく豚骨味のカップラーメンを買う人がいたとすると、次に出る豚骨味カップ麺の新商品をお知らせするメールや、人気の豚骨ラーメン店の紹介DMが来たり、といったサービスが提供できるので、顧客にも店側にもプラスになるそうです。
「それなら便利そう…」と思うかもしれませんが、私にはどうしても疑問符がつきます。
一番は、だれがいつどこで何を買ったか、そのすべてがデータとして記録が残ってしまう、ということがものすごく恐ろしいと考えています。
例えば、昨日コンビニで買ったもの、その袋の中身が全部記録に残るのです。
具体的には、所在地△区○○2丁目のコンビニ○○2丁目店で、住所が○×市△のカード利用者松宮湊人さん(3?歳)が、幕の内弁当(梅)、伊○衛門緑茶、週刊少年ジ○ンプ、エロ本△(汗)を何年何月何日の何時何分に買いました、、といった詳細なデータが記録されます。
さらに、便利だからと一枚の電子マネーカードで、電車や買い物などをすべて精算して、もし数年間使い続けたとしたら。
そのカードの持ち主が、どういう趣味趣向をもち、どういうものを買っているか、いつも何をどこで買うのか、どこの駅で電車に乗ってどこへ降りるのか、などなどのすべてのデータ(傾向)が記録に残るわけです。
買ったものやその量から推測すれば、何人で暮らしてるか、家族構成や子供はいるか、女性はいるかとかも分かってしまう。
乗り降りする駅から住所だって推測できるし、会社の所在地もだいたい分かる。
何時に出勤して何時に帰宅するのか、日常の行動パターンも分かってしまう。
日頃どういう薬を買っているかを見れば、その人の持病や健康的な悩みが分かってしまうし、ある日電車に乗らずにかぜ薬を買ったりしていたら、その日はかぜをひいて家で寝込んでいたのも分かる。
もっと恐ろしいことを言えば、避妊具をいついくつ買ったとかでその人の男女付き合いや夜の生活を推測できるし、女性用ナプキンをいつ買っているか調べれば、生理が大体いつ頃来ているかも推測できてしまうのです。
恐ろしいと思いませんか?
だから、私は電子マネーを一切使わないのです。
ちなみにクレディットカードの場合は、どこの店で何円の買い物をした、という使ったお店と払った金額しかデータは残りません。
何を買ったのか明細が残ることがないので、電子マネーほど恐怖を感じません。
だから、クレディットカードについては私はそれなりに使っています。
(基本は現金主義ですが)
さて、上で電子マネーの恐ろしさをいろいろ書きましたが、実際はその機能はまだ本格的に使われていない電子マネーのが多いです。
また、中には詳細なデータを記録する機能がない電子マネーもあるそうです。
(それがどのカードか分かれば良いんですけど、、)
各種それぞれの電子マネーは、電子マネーのスタンダードを狙ってそのシェアを増やすためまず普及に専念していることと、プライバシーの問題からまだ詳細データが残らないようにしているカードが多いようです。
しかし、使われてはいなくても上の機能は、電子マネーの基本的な機能として付帯していて、いつでもスタートできる状態といえます。
いつ何時、本格的に機能し始めるかは、わかりません。
ユーザーへ「何月何日から始めます」ときちんとお知らせしてくれれば良いのですが、本当にお知らせしてくれるかどうか、怪しいところです。
都合が悪そうなことはどこかにちょろっと書いておいて、いつの間にやら始めてるのが、企業の常套手段…といえるのではないでしょうか。
また、住所や名前など個人を特定できないようにして(中部地方の30代男性、みたいな形)、すでにデータを集めて集計している、、、はずだと思っています。
いわゆるビッグデータですね。
企業は年齢や性別による購買行動をデータとして集計し、マーケティング調査に使っている可能性はかなり高いでしょう。
それから、集められたデータが、その電子マネーの会社だけにきちんと留まっていればまだ良いのですが、この情報社会ではいつ何時データが漏れるか分かりません。
ネットからの不法アクセスから漏れたり、単純に社員がデータの入ったメモリやノートPCを紛失したということで流出することは、十分にあり得ます。
上記の事件のように、社員により悪意を持って流出させられてしまうかも知れない。
ていうか私は、そういう情報はいつか必ず流出するもの、と考えています。
どんなに強固なファイアウォールや防護策を作っても、人間の単純なミスで簡単に漏れるものです。
なので、情報を漏れても良いものとダメなものと、ある程度線引きしておいて、情報漏洩のリスクをなるべくコントロールするように、心がけています。
つまり、これについては漏れても平気、もしくは調べようと思えばいくらでも調べられてしまうような情報(例えば住所、名前、性別、年齢など)は、そんなには気にしない。
一方、自分以外の家族や子供に絡む情報とか、日常生活に深く踏み込むような情報については、かなり気を使って取り扱うようにしています。
だから、特定の人物の購買情報が事細かにデータとして残るような電子マネーカードは、すごく便利だとしてもなるたけ使わないようにしているのです。
深く気にしすぎ、最悪な方へ考えすぎだ、と色々な人に言われそうです。
でも、リスクは最悪を考えてからそれに応じて行動すべき、と言うのが私のモットーです。
違う話ですが、原発事故だって常に最悪を考えて動いていれば、あそこまで大きな事故にはならなかったでしょう。
この記事を読んだ方には電子マネーに潜む怖さを、多少は理解していただけたかと思います。
かといって、「電子マネーを使うな」と言うつもりはありません。
リスクをよく理解して、うまく使ってほしいと思っています。
例えば1枚のカードに偏りすぎないように、2・3枚のカードをうまく別々に使うとか。
情報漏洩したら嫌だなと思うような物を買うときは、クレディットカードや現金で買うとか。
彼を知り己を知れば、百戦して危うからず、、、。
リスクを知ればいかようにでも、その対策がとれるのです。
ちょっと最近電子マネーを使いすぎかな?、と心当たりがある方は、ちょっと使い方について再考してみることをお薦めします。
雑文、失礼いたしました。m(_ _)m
電子マネーであるがゆえの怖い事件ですね。
さて、皆さんは電子マネーは日常的に使っていますか?
チャージすればチャージした分だけ、切符の代わりや買い物、何にでもまた何回も使えるし、小銭など現金を扱うわずらわしさもないですから、便利ですね。
スイカ、パスモ、エディ、クイックペイ、iD、ワオン、ナナコなどなど、多くの種類があり、使えばポイントも貯まるし、一石二鳥なところも良いところです。
と、さんざんよいしょ?しましたが、実のところ私は一枚も持っていません。
クレディットカードや普通のポイントカードは、たくさん持っていますしよく使いますが、電子マネーのICカードは一つも無いです。
携帯の電子マネー機能もロックしたまま、使ったこともありません。
なぜかというと、電子マネーは「怖い」と思っているからです。
電子マネーには、だれがいつどこで何を買ったか、そのすべてを詳細に記録する機能が付いているものがあります。
そこが、私には恐ろしい、と感じています。
(一部ポイントカードにもその機能が付いているそうです。「Tポイントカード」などの色々なお店でポイントが付けられる汎用性の高いカードです)
その機能は、カード利用者の購買傾向やニーズを把握し、顧客へのサービスを向上させるため、、、というのが名目です。
例えば、よく豚骨味のカップラーメンを買う人がいたとすると、次に出る豚骨味カップ麺の新商品をお知らせするメールや、人気の豚骨ラーメン店の紹介DMが来たり、といったサービスが提供できるので、顧客にも店側にもプラスになるそうです。
「それなら便利そう…」と思うかもしれませんが、私にはどうしても疑問符がつきます。
一番は、だれがいつどこで何を買ったか、そのすべてがデータとして記録が残ってしまう、ということがものすごく恐ろしいと考えています。
例えば、昨日コンビニで買ったもの、その袋の中身が全部記録に残るのです。
具体的には、所在地△区○○2丁目のコンビニ○○2丁目店で、住所が○×市△のカード利用者松宮湊人さん(3?歳)が、幕の内弁当(梅)、伊○衛門緑茶、週刊少年ジ○ンプ、エロ本△(汗)を何年何月何日の何時何分に買いました、、といった詳細なデータが記録されます。
さらに、便利だからと一枚の電子マネーカードで、電車や買い物などをすべて精算して、もし数年間使い続けたとしたら。
そのカードの持ち主が、どういう趣味趣向をもち、どういうものを買っているか、いつも何をどこで買うのか、どこの駅で電車に乗ってどこへ降りるのか、などなどのすべてのデータ(傾向)が記録に残るわけです。
買ったものやその量から推測すれば、何人で暮らしてるか、家族構成や子供はいるか、女性はいるかとかも分かってしまう。
乗り降りする駅から住所だって推測できるし、会社の所在地もだいたい分かる。
何時に出勤して何時に帰宅するのか、日常の行動パターンも分かってしまう。
日頃どういう薬を買っているかを見れば、その人の持病や健康的な悩みが分かってしまうし、ある日電車に乗らずにかぜ薬を買ったりしていたら、その日はかぜをひいて家で寝込んでいたのも分かる。
もっと恐ろしいことを言えば、避妊具をいついくつ買ったとかでその人の男女付き合いや夜の生活を推測できるし、女性用ナプキンをいつ買っているか調べれば、生理が大体いつ頃来ているかも推測できてしまうのです。
恐ろしいと思いませんか?
だから、私は電子マネーを一切使わないのです。
ちなみにクレディットカードの場合は、どこの店で何円の買い物をした、という使ったお店と払った金額しかデータは残りません。
何を買ったのか明細が残ることがないので、電子マネーほど恐怖を感じません。
だから、クレディットカードについては私はそれなりに使っています。
(基本は現金主義ですが)
さて、上で電子マネーの恐ろしさをいろいろ書きましたが、実際はその機能はまだ本格的に使われていない電子マネーのが多いです。
また、中には詳細なデータを記録する機能がない電子マネーもあるそうです。
(それがどのカードか分かれば良いんですけど、、)
各種それぞれの電子マネーは、電子マネーのスタンダードを狙ってそのシェアを増やすためまず普及に専念していることと、プライバシーの問題からまだ詳細データが残らないようにしているカードが多いようです。
しかし、使われてはいなくても上の機能は、電子マネーの基本的な機能として付帯していて、いつでもスタートできる状態といえます。
いつ何時、本格的に機能し始めるかは、わかりません。
ユーザーへ「何月何日から始めます」ときちんとお知らせしてくれれば良いのですが、本当にお知らせしてくれるかどうか、怪しいところです。
都合が悪そうなことはどこかにちょろっと書いておいて、いつの間にやら始めてるのが、企業の常套手段…といえるのではないでしょうか。
また、住所や名前など個人を特定できないようにして(中部地方の30代男性、みたいな形)、すでにデータを集めて集計している、、、はずだと思っています。
いわゆるビッグデータですね。
企業は年齢や性別による購買行動をデータとして集計し、マーケティング調査に使っている可能性はかなり高いでしょう。
それから、集められたデータが、その電子マネーの会社だけにきちんと留まっていればまだ良いのですが、この情報社会ではいつ何時データが漏れるか分かりません。
ネットからの不法アクセスから漏れたり、単純に社員がデータの入ったメモリやノートPCを紛失したということで流出することは、十分にあり得ます。
上記の事件のように、社員により悪意を持って流出させられてしまうかも知れない。
ていうか私は、そういう情報はいつか必ず流出するもの、と考えています。
どんなに強固なファイアウォールや防護策を作っても、人間の単純なミスで簡単に漏れるものです。
なので、情報を漏れても良いものとダメなものと、ある程度線引きしておいて、情報漏洩のリスクをなるべくコントロールするように、心がけています。
つまり、これについては漏れても平気、もしくは調べようと思えばいくらでも調べられてしまうような情報(例えば住所、名前、性別、年齢など)は、そんなには気にしない。
一方、自分以外の家族や子供に絡む情報とか、日常生活に深く踏み込むような情報については、かなり気を使って取り扱うようにしています。
だから、特定の人物の購買情報が事細かにデータとして残るような電子マネーカードは、すごく便利だとしてもなるたけ使わないようにしているのです。
深く気にしすぎ、最悪な方へ考えすぎだ、と色々な人に言われそうです。
でも、リスクは最悪を考えてからそれに応じて行動すべき、と言うのが私のモットーです。
違う話ですが、原発事故だって常に最悪を考えて動いていれば、あそこまで大きな事故にはならなかったでしょう。
この記事を読んだ方には電子マネーに潜む怖さを、多少は理解していただけたかと思います。
かといって、「電子マネーを使うな」と言うつもりはありません。
リスクをよく理解して、うまく使ってほしいと思っています。
例えば1枚のカードに偏りすぎないように、2・3枚のカードをうまく別々に使うとか。
情報漏洩したら嫌だなと思うような物を買うときは、クレディットカードや現金で買うとか。
彼を知り己を知れば、百戦して危うからず、、、。
リスクを知ればいかようにでも、その対策がとれるのです。
ちょっと最近電子マネーを使いすぎかな?、と心当たりがある方は、ちょっと使い方について再考してみることをお薦めします。
雑文、失礼いたしました。m(_ _)m
2012/05/15
(2012.6.28. 修正・加筆)
2012年も5月に入り、ついに原発が稼働ゼロとなりました。
反原発・脱原発の方々にとっては、当然のことと思っているかも知れません。
ただ、私のような現実主義の人間から言わせてもらえば、今の綱渡りの電力供給から見たら、ゆゆしき状態だと言えます。
たぶんこのまま原発稼働ゼロでいくと、そこそこ高い確率で停電(または計画停電)がやってくると私は予想しています。
反原発・脱原発を訴えている方達は、節電とピークシフトでなんとかなると言っています。
原発無しでもこの夏は乗り切れる、やり過ごせる、と。
確かに去年並みの夏の暑さで、節電とピークシフトを徹底できたなら、十分やり過ごせると思います。
でもこれ、残念ながら足りるか足りないかの安直な計算でしか語られていません。
(電力が足りないといってる人たちも、単純な足し算でしか語っていませんが)
そこに落し穴があると思うのです。
確かに、原発を除いても徹底した節電と火力、水力など他の発電所をフルに稼働させてやれば、夏の電力は足りるでしょう。
しかし、フルに稼働させなくてはならない、と言うところが問題点です。
何度も言ってきましたが、現在電力を支えている主力は、火力発電所です。
昨年の原発事故以来、火力発電はまさに24時間フル稼働し続けています。
ガンガン化石燃料を燃やして、どんどんと二酸化炭素を大気に放出しています。
(いい加減マスコミはこの事実に正面から触れて欲しい。地球温暖化の問題は二の次で良いのか?)
本来、火力発電所もフルに稼働し続けることはありません。
必ず一年に一回は定期点検をして、施設や機能に異常がないかチェックしなくてはならないのです。
しかし、昨年原発事故以来、あまり点検は行われていません。
原発で作っていた全電力約3割の電力が、原発稼働停止でなくなってしまったので、当然供給量はぎりぎりです。
どこかの火力発電所を休ませて点検…なんてことができる余裕がないほど、供給量はひっ迫しています。
よって多くの火力発電所は、点検ができないまま、現在まで一年以上稼働し続けているのです。
発電所によっては、すでに二年も連続稼働し続けているところもあります。
これが意味するところは何か?
点検がろくにできていない火力発電所は、いつか何かしらのトラブルで停止してしまうかもしれない、ということです。
何度も言ってきましたが、電力供給はすでにぎりぎりの綱渡り状態。
火力発電所がひとつ止まっただけでも、電力が不足し停電になる確率も高い。
最悪、もし真夏のピーク時にどこかの火力発電所が止まってしまったら、、、恐怖の大停電の発生というのも十分に考えられます。
一番考えられるのは、関西電力管内の停電です。
関電は原発依存度が高く、稼働ゼロとなった今、すでに自前の発電所では電気が足りない状態になっています。
今も比較的余裕のある中部電力や中国電力などから、電力を融通してもらい、供給量を保っています。
この夏は、そうやって他の電力会社から電力を融通してもらったうえ、なおかつ節電とピークシフトをこれでもかと徹底して、なんとか乗り切れる…くらいの状況です。
でも上で言ったとおり、トラブルで火力発電所の停止によっては、停電が起きる可能性は高い。
また他に考えられるケースは、融通してもらっている他の電力会社で火力発電所が止まった場合です。
例えば中部電力はもともと原発依存が低く火力発電に頼っていたため、原発が止まっても電力に余裕があり、関電へは今も約100万kwhを融通しています。
当然その分は、関電が今夏を乗り切るための電力供給量の計算にも、加えられています。
もし真夏に、中電の火力発電所が何かのトラブルで停止したらどうなるか。
すると中電管内への供給に余裕がなくなり、関電への融通量を減らさざるをえない状況になるかも知れません。
そうして融通量を減らされて、関電管内は電力不足となり、停電が起きる可能性があります。
そこを考えると、関電へ融通する中部電力、北陸電力、中国電力を含めた全体の供給状態が、停電をにぎる鍵になってくるのです。
自分の管内だけ見てれば良いという訳ではないので、これは結構やっかいなことだと思います。
また、火力発電が止まる原因のひとつに、中東イランの問題が考えられます。
中東イランの核開発疑惑の問題は、ホムルズ海峡封鎖を含めた石油輸入の問題とも絡んでいます。
もしイラン情勢が最悪の結果となり、中東からの石油がストップしてしまったら、、、当然火力発電にも影響してくるでしょう。
火力発電といっても、石油をはじめ、石炭、天然ガスなど、燃料にはいくつか種類があります。
石油による火力発電は、火力での発電量全体でいうと2割程度と多くはありません。
しかし、今まで言ってきたとおり電力は厳しい状況です。
使われなくなった古い火力発電所や、いわゆる直焚きといわれる原油をそのまま燃やす効率の悪い発電所も動かしています。
その石油による発電の2割が止まるだけでも、停電の可能性は大きくなるわけです。
欧州のイランへの本格的な制裁は7月に始まるそうです。
ちょうど夏の暑いころですねぇ、、。汗
そのころ何か動きが出るのか、国際情勢も注目していく必要もあるでしょう。
私は脱原発の立場ではありますが、やはり原発は拙速に止めるべきではないと考えています。
脱原発依存は、10年20年の長いスパンで行うべきです。
電力供給に不安がある中では、安全性を十分確保できたなら動かせる原発はなるべく稼働させる。
原発を稼働させながら、酷使している火力発電の点検をし、同時に自然エネルギー発電をはじめ電源(発電方法)の見直しを進めるべきです。
今回、関電大飯原発の再稼働をめぐっては、政府が原発稼働がゼロになるのを必要以上に恐れて、ばたばたとあわてて再稼働へ動いたのがまずかった。
原発再稼働は、電力不足の恐れがある7月くらいまでに間に合えば、十分だったはず。
それまでは、粛々と確実に再稼働へむけて準備していけば良かったのに、急に話を進めたら国民が不信感を覚えるのは当たり前です。
明らかに政府のミスです。
(これは黒幕の仙石さんのミスでしょう)
仮にもし私が電力について色々決められる立場だったら、原発の稼働が一時的にゼロになっても良いから、再稼働の準備はゆっくり確実に進めて行き、基本的に安全が十分確保できるまでは動かさない。
ただし、電力がどうしても不足しそうなときは、安全が十分でなくても稼動させます。
大規模停電は、国民の生命と財産が脅かされる可能性が、非常に大きい。
だから、電力が足りないときは、安全が十分でなくても躊躇せず原発を再稼働させます。
そのことはあらかじめ、国民にしっかり説明して理解を促しておくことは必要でしょう。
原発稼働ゼロで夏を乗り越えられたとしても、それはそれでOK。
でも、電力供給が綱渡り状態であることには変わらないので、安全性が十分に確認された原発はなるべく早く速やかに稼働させます。
原発を動かしながら、他の電源を模索して今後も進めていき、少しづつ原発依存から抜け出していく。
日本がとるべき道は、これしかないと私は思うんですが…。
とりあえずの目標は、原発稼動率を5〜10年で半分の15%、20年後にはできればゼロ、多くても5%くらいにする。
原発を減らした分は、水力、地熱、温水など、24時間発電できる電源を建設・研究・実用化させ、なんとか割り当てる。
そして、火力への依存率は増やすことなく逆に減らすよう、努力したいところです。
ま、これはあくまで私の勝手な考えですけど…。
あと国・政府も、国・政府としてのこういった電力のグランドデザインを早く提示するべきです。
グランドデザインをはっきり明示しないから、メディアや反原発の方々に必要以上につつかれるのだと思います。
ゆっくり会議で決めてないで、だいたいの数字でいいので政府のほうから早く出すべき、と考えます。
この夏も厳しい節電は避けられません。
特に関西電力では、停電対策を含めた複合的な対策が求められるでしょう。
そして私たちは、節電をしながら今後の「電気」をどうしていくべきか、深く考えていかなければなりません。
日本では、電気はあって当たり前、と言うくらい安定供給され続けていた国でした。
そのため、今の電力会社の独占状態が認められてきたし、原発もたくさん作られてきた。
そのありがたさとすごさを深く考えずとも、その電気の豊かさにどっぷりつかって享受してきた私たち国民は、今後の電力についてもっと真剣に考える義務があると思います。
原発事故を受けて、今後の電力は多少ではありますが、不安定な供給が続くはずだからです。
そのために、まずは原子力はじめ火力、水力、自然エネルギーなど色々な電源のメリット・デメリットを含めた最低限の知識を知っておかなくてはならないでしょう。
それがある程度理解できてから、どう組み合わせてどう発電していくのが良いか、という話にようやく進むことができると思うのです。
(私の電力と原発に関する考えは、過去のこちらの記事を参考にしてください(かなり長いです汗)→電力について考えてみる1~6)
「原発は危なくて怖いからダメ」「放射能が危険だからダメ」という原発事故の一面だけで、物事を考えるのはよくありません。
もっと多角的で客観的で科学的な思考が求められます。
マスメディアのように表面だけの情報でなく、でも反原発だけの情報ではなく、かといって原発推進派だけではない、いろいろな話・情報をあちこちから得て、自分の頭で考えてみる。
この記事も自分の考えをまとめるための、ひとつの情報として見ていただき、後でしっかり自分で考えてみてください。
そうした「自分の考え」をしっかり持っていることが大事です。
でもだからといって、その考えに固執し過ぎるのもいけません。
一度出した自分の考えでも、間違いがあったらその間違いを正して、変えられるくらいの柔軟さも必要です。(私自身が出来てるとは言えませんが…汗)
また話が長くなりました。(;^_^A
とにもかくにも、まずは電気について、いま一度しっかり考えてみましょう。
それが、はじめの一歩となるはずです。
m(_ _)m
2012年も5月に入り、ついに原発が稼働ゼロとなりました。
反原発・脱原発の方々にとっては、当然のことと思っているかも知れません。
ただ、私のような現実主義の人間から言わせてもらえば、今の綱渡りの電力供給から見たら、ゆゆしき状態だと言えます。
たぶんこのまま原発稼働ゼロでいくと、そこそこ高い確率で停電(または計画停電)がやってくると私は予想しています。
反原発・脱原発を訴えている方達は、節電とピークシフトでなんとかなると言っています。
原発無しでもこの夏は乗り切れる、やり過ごせる、と。
確かに去年並みの夏の暑さで、節電とピークシフトを徹底できたなら、十分やり過ごせると思います。
でもこれ、残念ながら足りるか足りないかの安直な計算でしか語られていません。
(電力が足りないといってる人たちも、単純な足し算でしか語っていませんが)
そこに落し穴があると思うのです。
確かに、原発を除いても徹底した節電と火力、水力など他の発電所をフルに稼働させてやれば、夏の電力は足りるでしょう。
しかし、フルに稼働させなくてはならない、と言うところが問題点です。
何度も言ってきましたが、現在電力を支えている主力は、火力発電所です。
昨年の原発事故以来、火力発電はまさに24時間フル稼働し続けています。
ガンガン化石燃料を燃やして、どんどんと二酸化炭素を大気に放出しています。
(いい加減マスコミはこの事実に正面から触れて欲しい。地球温暖化の問題は二の次で良いのか?)
本来、火力発電所もフルに稼働し続けることはありません。
必ず一年に一回は定期点検をして、施設や機能に異常がないかチェックしなくてはならないのです。
しかし、昨年原発事故以来、あまり点検は行われていません。
原発で作っていた全電力約3割の電力が、原発稼働停止でなくなってしまったので、当然供給量はぎりぎりです。
どこかの火力発電所を休ませて点検…なんてことができる余裕がないほど、供給量はひっ迫しています。
よって多くの火力発電所は、点検ができないまま、現在まで一年以上稼働し続けているのです。
発電所によっては、すでに二年も連続稼働し続けているところもあります。
これが意味するところは何か?
点検がろくにできていない火力発電所は、いつか何かしらのトラブルで停止してしまうかもしれない、ということです。
何度も言ってきましたが、電力供給はすでにぎりぎりの綱渡り状態。
火力発電所がひとつ止まっただけでも、電力が不足し停電になる確率も高い。
最悪、もし真夏のピーク時にどこかの火力発電所が止まってしまったら、、、恐怖の大停電の発生というのも十分に考えられます。
一番考えられるのは、関西電力管内の停電です。
関電は原発依存度が高く、稼働ゼロとなった今、すでに自前の発電所では電気が足りない状態になっています。
今も比較的余裕のある中部電力や中国電力などから、電力を融通してもらい、供給量を保っています。
この夏は、そうやって他の電力会社から電力を融通してもらったうえ、なおかつ節電とピークシフトをこれでもかと徹底して、なんとか乗り切れる…くらいの状況です。
でも上で言ったとおり、トラブルで火力発電所の停止によっては、停電が起きる可能性は高い。
また他に考えられるケースは、融通してもらっている他の電力会社で火力発電所が止まった場合です。
例えば中部電力はもともと原発依存が低く火力発電に頼っていたため、原発が止まっても電力に余裕があり、関電へは今も約100万kwhを融通しています。
当然その分は、関電が今夏を乗り切るための電力供給量の計算にも、加えられています。
もし真夏に、中電の火力発電所が何かのトラブルで停止したらどうなるか。
すると中電管内への供給に余裕がなくなり、関電への融通量を減らさざるをえない状況になるかも知れません。
そうして融通量を減らされて、関電管内は電力不足となり、停電が起きる可能性があります。
そこを考えると、関電へ融通する中部電力、北陸電力、中国電力を含めた全体の供給状態が、停電をにぎる鍵になってくるのです。
自分の管内だけ見てれば良いという訳ではないので、これは結構やっかいなことだと思います。
また、火力発電が止まる原因のひとつに、中東イランの問題が考えられます。
中東イランの核開発疑惑の問題は、ホムルズ海峡封鎖を含めた石油輸入の問題とも絡んでいます。
もしイラン情勢が最悪の結果となり、中東からの石油がストップしてしまったら、、、当然火力発電にも影響してくるでしょう。
火力発電といっても、石油をはじめ、石炭、天然ガスなど、燃料にはいくつか種類があります。
石油による火力発電は、火力での発電量全体でいうと2割程度と多くはありません。
しかし、今まで言ってきたとおり電力は厳しい状況です。
使われなくなった古い火力発電所や、いわゆる直焚きといわれる原油をそのまま燃やす効率の悪い発電所も動かしています。
その石油による発電の2割が止まるだけでも、停電の可能性は大きくなるわけです。
欧州のイランへの本格的な制裁は7月に始まるそうです。
ちょうど夏の暑いころですねぇ、、。汗
そのころ何か動きが出るのか、国際情勢も注目していく必要もあるでしょう。
私は脱原発の立場ではありますが、やはり原発は拙速に止めるべきではないと考えています。
脱原発依存は、10年20年の長いスパンで行うべきです。
電力供給に不安がある中では、安全性を十分確保できたなら動かせる原発はなるべく稼働させる。
原発を稼働させながら、酷使している火力発電の点検をし、同時に自然エネルギー発電をはじめ電源(発電方法)の見直しを進めるべきです。
今回、関電大飯原発の再稼働をめぐっては、政府が原発稼働がゼロになるのを必要以上に恐れて、ばたばたとあわてて再稼働へ動いたのがまずかった。
原発再稼働は、電力不足の恐れがある7月くらいまでに間に合えば、十分だったはず。
それまでは、粛々と確実に再稼働へむけて準備していけば良かったのに、急に話を進めたら国民が不信感を覚えるのは当たり前です。
明らかに政府のミスです。
(これは黒幕の仙石さんのミスでしょう)
仮にもし私が電力について色々決められる立場だったら、原発の稼働が一時的にゼロになっても良いから、再稼働の準備はゆっくり確実に進めて行き、基本的に安全が十分確保できるまでは動かさない。
ただし、電力がどうしても不足しそうなときは、安全が十分でなくても稼動させます。
大規模停電は、国民の生命と財産が脅かされる可能性が、非常に大きい。
だから、電力が足りないときは、安全が十分でなくても躊躇せず原発を再稼働させます。
そのことはあらかじめ、国民にしっかり説明して理解を促しておくことは必要でしょう。
原発稼働ゼロで夏を乗り越えられたとしても、それはそれでOK。
でも、電力供給が綱渡り状態であることには変わらないので、安全性が十分に確認された原発はなるべく早く速やかに稼働させます。
原発を動かしながら、他の電源を模索して今後も進めていき、少しづつ原発依存から抜け出していく。
日本がとるべき道は、これしかないと私は思うんですが…。
とりあえずの目標は、原発稼動率を5〜10年で半分の15%、20年後にはできればゼロ、多くても5%くらいにする。
原発を減らした分は、水力、地熱、温水など、24時間発電できる電源を建設・研究・実用化させ、なんとか割り当てる。
そして、火力への依存率は増やすことなく逆に減らすよう、努力したいところです。
ま、これはあくまで私の勝手な考えですけど…。
あと国・政府も、国・政府としてのこういった電力のグランドデザインを早く提示するべきです。
グランドデザインをはっきり明示しないから、メディアや反原発の方々に必要以上につつかれるのだと思います。
ゆっくり会議で決めてないで、だいたいの数字でいいので政府のほうから早く出すべき、と考えます。
この夏も厳しい節電は避けられません。
特に関西電力では、停電対策を含めた複合的な対策が求められるでしょう。
そして私たちは、節電をしながら今後の「電気」をどうしていくべきか、深く考えていかなければなりません。
日本では、電気はあって当たり前、と言うくらい安定供給され続けていた国でした。
そのため、今の電力会社の独占状態が認められてきたし、原発もたくさん作られてきた。
そのありがたさとすごさを深く考えずとも、その電気の豊かさにどっぷりつかって享受してきた私たち国民は、今後の電力についてもっと真剣に考える義務があると思います。
原発事故を受けて、今後の電力は多少ではありますが、不安定な供給が続くはずだからです。
そのために、まずは原子力はじめ火力、水力、自然エネルギーなど色々な電源のメリット・デメリットを含めた最低限の知識を知っておかなくてはならないでしょう。
それがある程度理解できてから、どう組み合わせてどう発電していくのが良いか、という話にようやく進むことができると思うのです。
(私の電力と原発に関する考えは、過去のこちらの記事を参考にしてください(かなり長いです汗)→電力について考えてみる1~6)
「原発は危なくて怖いからダメ」「放射能が危険だからダメ」という原発事故の一面だけで、物事を考えるのはよくありません。
もっと多角的で客観的で科学的な思考が求められます。
マスメディアのように表面だけの情報でなく、でも反原発だけの情報ではなく、かといって原発推進派だけではない、いろいろな話・情報をあちこちから得て、自分の頭で考えてみる。
この記事も自分の考えをまとめるための、ひとつの情報として見ていただき、後でしっかり自分で考えてみてください。
そうした「自分の考え」をしっかり持っていることが大事です。
でもだからといって、その考えに固執し過ぎるのもいけません。
一度出した自分の考えでも、間違いがあったらその間違いを正して、変えられるくらいの柔軟さも必要です。(私自身が出来てるとは言えませんが…汗)
また話が長くなりました。(;^_^A
とにもかくにも、まずは電気について、いま一度しっかり考えてみましょう。
それが、はじめの一歩となるはずです。
m(_ _)m
2012/03/04
早いもので、あの日から一年が経とうとしています。
日本の歴史の転換点となった巨大地震、東日本大震災(東北関東大震災)。
すでに政治、経済、文化など、多くの分野で混乱と転換が起きてきています。
それだけ、あの地震は大きな出来事でした。
一年を期に、色々とちょっと深く考えてみようと思います。
だいぶ本音で書こうと思っています。
えらそうなことも言うと思います。
なので、気分を害する方もいるでしょう。
先に謝罪しておきます、申し訳ありません。
しかし、これからの日本のことを考えれば、避けてはいけないことだと思うのです。
厳しいことを言うと思いますが、きちんと考えて認識しておかなければならないことでしょう。
もともと本音を話すつもりのブログだから、ご容赦ください。
さて、沖縄の米軍基地の問題、原子力発電所の問題、その風評被害の問題、そして被災地で復興の妨げとなっているがれきの問題、、、。
これら諸問題は別々のように見えて、実はその根っこでは共通の部分があります。
それは何だと思いますか?
答えは「それら問題について、国民のほとんどが知識と理解が浅い」こと。
そして「いまいち関心が薄い」ことです。
厳しい言葉で言い換えるならば、多くの国民が対岸の火事のようにしか見ていないのです。
これには、多くの方から批判があるでしょう。
しかし、私はあえて本音を言っておきたい。
米軍基地を例えに話を進めてみます。
ひところ国会で、前の防衛大臣が、米軍兵士による少女暴行事件について詳しく知らなかったからと、野党からたたかれていました。
一部メディアも同様に前大臣を責めていました。
結果、今年になってから更迭のように交代、という運びになりました、が…。
ここで皆さんに問いたい。
はたして、その少女暴行事件の詳細を、沖縄県以外の国民が、国会議員が、報道関係者が、どれだけ詳しく知っていたのでしょうか?
私も正直に言えば、あの大臣が話した内容に、僅かにプラスした程度の知識しかありませんでした。
私自身がうろ覚えなのに、その大臣を責めることは、私にはできません。
そしてきっと、多くの国民が、その事件の詳細なんて知らなかった、もしくは記憶が薄れていたと思います。
すなわち、それだけ理解と関心が低かった、ということです。
沖縄の基地の問題が、いまいち前進しない理由は、沖縄を除く日本国民の多くが、米軍がなぜ日本に駐留しているか、その基地がなぜ沖縄に集中しているのか、沖縄の歴史と現状がどうなのかということを、ほとんど理解していないからです。
知らないから世論は動かないし、有効な対策が出せない。
日本全体の世論が大きく動かなければ、国が政府が本腰入れて動くはずがありません。
また沖縄の基地は、多くの国民は可哀相だ、何とかしたいと考えていると思います。
でも、たとえば自分が住む町に基地を移転するといったら、どうでしょう。
確実に、多くの方が反対すると思います。
どうにかしてあげたい、けど私の住む町へは困る…。
米軍基地ってなんか危なそうだから、私の町にはもってこないで…。
つまり、やっぱり理解と関心が低いのです。
何がどう危険なのか理解せず、何となく危険…と考えているから、いつまでたっても根本的な解決とはならない。
いつぞや、全国知事会で沖縄基地負担軽減のために、基地移転もしくは訓練移転をしても良い都道府県があるか?と言うような話題があがったことがあります。
その時、手を挙げた知事は何人いたと思いますか?
答えは47都道府県の中で、たった一人。
当時大阪府知事の橋下さんだけでした。
これが現実なのです。
いま震災復興の妨げになっている東北のがれきの問題や風評被害、原発の問題も、根っこは同じことです。
要は、国民の知識と理解が足りない。
何がどう危険なのか、よく理解することなく、メディアの表面をなぞった情報を聞いて、がれきは放射能に汚染されてるらしい、関東と東北の食物は危ないらしい、放射能は危ないから怖い、原発は危ないから怖い、と思い込んでいます。
震災で発生した大量のがれきは、とても現地だけで片付けることはできません。
日本全体で協力しあい、助け合ってがれきの片付けをするのが筋でしょう。
でも現状はどうですか?
放射能がこわいとか、全国に放射能をばらまくことになるとかで、あまり話は進んでいません。
。
復興、がんばれ、と応援しながら、がれきは何となく怖いから引き受けません、という状況です。
またどこぞのスーパーは、放射能に汚染されたものは一切売らない、だから安心、と大々的にCMをしてます。
でもそれは、風評被害に苦しむ関東や東北の生産者の品は、取り扱わないと言っているのと同じです。
ただでさえ風評被害で苦しいのに、業界大手のスーパーが取り扱ってくれないとなれば、さらに痛手となるでしょう。
被災者でもある生産者の、首を絞めることになりかねません。
でも、消費者のニーズに答えたと、スーパーは言っています。
我々のニーズでそうなったのなら、私たちが放射能を十分理解せず、漠然と怖い、危険と思っているから、こういう結果が生まれていると言えます。
今回の事故を受け、原発は危なくて怖いから、もういらない、必要ない、ということで、多くの原発が停止しています。
でも原発を拙速に止めてしまったため、その裏では燃費の悪い古い火力発電所まで導入して、石油、ガスなど化石燃料をがんがん燃やして電気を作っています。
まさに二酸化炭素の垂れ流し状態です。
ストップ温暖化はどこへいったんでしょう?
このことをメディアは、真正面から報道しようとは思わないようです。
これら諸問題は、根本はそれぞれ知識と理解が浅いから、起きている問題です。
知識と理解を深めるには、具体的に何が危険なのか、どこが問題なのか、よく調べてある程度頭に入れることが必要です。
知識と理解を深めれば、危険に対しどう対応するべきか、どうすれば危険を減らすことができるのか、対策が見えてくるはずです。
でも、信じられる知識・情報をどこから手に入れればよいか分からない、国の情報も信じられない、と嘆く人もいると思います。
それについては、以前から何度も言っているように、正しい情報を見極める力が必要となってきます。
自ら考え精査し、正しい知識として自分に蓄える力です。
それは、残念ですが個人個人で鍛えなくてはならないことだと思います。
色々なアンテナを立て色々な情報を手に入れ、それを精査し正しい情報・知識を身につける。
そして一歩引いて、客観的に考えてみる。
そうすると、物事の真実が見えてくると思います。
そしてもう一点。
いま東北の被災地では、復興の作業が進んでいます。
が、今のところほんの僅かしか進んでいないのが、現状です。
しかしマスメディアでは、支援ありがとう、東北は頑張ってます、復興に向けてまた一歩進む、、、みたいなプラスなイメージの報道ばかりが、目立ちます。
(震災一年を迎えるため、最近は厳しい内容の報道が増えてはいますが、、)
視聴者はプラスな報道ばかり見てるので、少しづつ復興してる、良くなってきている、何となく復興してきている、と漠然とプラスなイメージを抱いてきていると思われます。
何となく復興してると思っているため、次第に支援の手がゆるんだり、興味が薄れたりということが、現実に起きてきています。
私が調べたかぎりでは、復興と言えるはほんの一部だけ。
そして一部が復興途中、残り大半はまったく手付かずの状態です。
復興とは程遠く、まだ始まったばかりといっても過言ではないでしょう。
しかし現在、ボランティアの数は減る一方、支援も少しづつ減ってきています。
私たちの「何となく復興してきている」という漠然としたイメージが、被災地への関心を薄れさせています。
まだまだ支援は必要です。
そう、まだまだです。
もう一度、改めて被災地への関心を寄せましょう。
もう一度、被災地の現状がどうなのか、調べてみましょう。
まだやれること、手伝えること、支援できることはたくさんあるはずなんです。
私は最低でも、10年間は継続的な支援が必要だと考えています。
手を抜くことなく、長く続けていかなければなりません。
続きはまたの機会にしたいと思います。m(_ _)m
日本の歴史の転換点となった巨大地震、東日本大震災(東北関東大震災)。
すでに政治、経済、文化など、多くの分野で混乱と転換が起きてきています。
それだけ、あの地震は大きな出来事でした。
一年を期に、色々とちょっと深く考えてみようと思います。
だいぶ本音で書こうと思っています。
えらそうなことも言うと思います。
なので、気分を害する方もいるでしょう。
先に謝罪しておきます、申し訳ありません。
しかし、これからの日本のことを考えれば、避けてはいけないことだと思うのです。
厳しいことを言うと思いますが、きちんと考えて認識しておかなければならないことでしょう。
もともと本音を話すつもりのブログだから、ご容赦ください。
さて、沖縄の米軍基地の問題、原子力発電所の問題、その風評被害の問題、そして被災地で復興の妨げとなっているがれきの問題、、、。
これら諸問題は別々のように見えて、実はその根っこでは共通の部分があります。
それは何だと思いますか?
答えは「それら問題について、国民のほとんどが知識と理解が浅い」こと。
そして「いまいち関心が薄い」ことです。
厳しい言葉で言い換えるならば、多くの国民が対岸の火事のようにしか見ていないのです。
これには、多くの方から批判があるでしょう。
しかし、私はあえて本音を言っておきたい。
米軍基地を例えに話を進めてみます。
ひところ国会で、前の防衛大臣が、米軍兵士による少女暴行事件について詳しく知らなかったからと、野党からたたかれていました。
一部メディアも同様に前大臣を責めていました。
結果、今年になってから更迭のように交代、という運びになりました、が…。
ここで皆さんに問いたい。
はたして、その少女暴行事件の詳細を、沖縄県以外の国民が、国会議員が、報道関係者が、どれだけ詳しく知っていたのでしょうか?
私も正直に言えば、あの大臣が話した内容に、僅かにプラスした程度の知識しかありませんでした。
私自身がうろ覚えなのに、その大臣を責めることは、私にはできません。
そしてきっと、多くの国民が、その事件の詳細なんて知らなかった、もしくは記憶が薄れていたと思います。
すなわち、それだけ理解と関心が低かった、ということです。
沖縄の基地の問題が、いまいち前進しない理由は、沖縄を除く日本国民の多くが、米軍がなぜ日本に駐留しているか、その基地がなぜ沖縄に集中しているのか、沖縄の歴史と現状がどうなのかということを、ほとんど理解していないからです。
知らないから世論は動かないし、有効な対策が出せない。
日本全体の世論が大きく動かなければ、国が政府が本腰入れて動くはずがありません。
また沖縄の基地は、多くの国民は可哀相だ、何とかしたいと考えていると思います。
でも、たとえば自分が住む町に基地を移転するといったら、どうでしょう。
確実に、多くの方が反対すると思います。
どうにかしてあげたい、けど私の住む町へは困る…。
米軍基地ってなんか危なそうだから、私の町にはもってこないで…。
つまり、やっぱり理解と関心が低いのです。
何がどう危険なのか理解せず、何となく危険…と考えているから、いつまでたっても根本的な解決とはならない。
いつぞや、全国知事会で沖縄基地負担軽減のために、基地移転もしくは訓練移転をしても良い都道府県があるか?と言うような話題があがったことがあります。
その時、手を挙げた知事は何人いたと思いますか?
答えは47都道府県の中で、たった一人。
当時大阪府知事の橋下さんだけでした。
これが現実なのです。
いま震災復興の妨げになっている東北のがれきの問題や風評被害、原発の問題も、根っこは同じことです。
要は、国民の知識と理解が足りない。
何がどう危険なのか、よく理解することなく、メディアの表面をなぞった情報を聞いて、がれきは放射能に汚染されてるらしい、関東と東北の食物は危ないらしい、放射能は危ないから怖い、原発は危ないから怖い、と思い込んでいます。
震災で発生した大量のがれきは、とても現地だけで片付けることはできません。
日本全体で協力しあい、助け合ってがれきの片付けをするのが筋でしょう。
でも現状はどうですか?
放射能がこわいとか、全国に放射能をばらまくことになるとかで、あまり話は進んでいません。
。
復興、がんばれ、と応援しながら、がれきは何となく怖いから引き受けません、という状況です。
またどこぞのスーパーは、放射能に汚染されたものは一切売らない、だから安心、と大々的にCMをしてます。
でもそれは、風評被害に苦しむ関東や東北の生産者の品は、取り扱わないと言っているのと同じです。
ただでさえ風評被害で苦しいのに、業界大手のスーパーが取り扱ってくれないとなれば、さらに痛手となるでしょう。
被災者でもある生産者の、首を絞めることになりかねません。
でも、消費者のニーズに答えたと、スーパーは言っています。
我々のニーズでそうなったのなら、私たちが放射能を十分理解せず、漠然と怖い、危険と思っているから、こういう結果が生まれていると言えます。
今回の事故を受け、原発は危なくて怖いから、もういらない、必要ない、ということで、多くの原発が停止しています。
でも原発を拙速に止めてしまったため、その裏では燃費の悪い古い火力発電所まで導入して、石油、ガスなど化石燃料をがんがん燃やして電気を作っています。
まさに二酸化炭素の垂れ流し状態です。
ストップ温暖化はどこへいったんでしょう?
このことをメディアは、真正面から報道しようとは思わないようです。
これら諸問題は、根本はそれぞれ知識と理解が浅いから、起きている問題です。
知識と理解を深めるには、具体的に何が危険なのか、どこが問題なのか、よく調べてある程度頭に入れることが必要です。
知識と理解を深めれば、危険に対しどう対応するべきか、どうすれば危険を減らすことができるのか、対策が見えてくるはずです。
でも、信じられる知識・情報をどこから手に入れればよいか分からない、国の情報も信じられない、と嘆く人もいると思います。
それについては、以前から何度も言っているように、正しい情報を見極める力が必要となってきます。
自ら考え精査し、正しい知識として自分に蓄える力です。
それは、残念ですが個人個人で鍛えなくてはならないことだと思います。
色々なアンテナを立て色々な情報を手に入れ、それを精査し正しい情報・知識を身につける。
そして一歩引いて、客観的に考えてみる。
そうすると、物事の真実が見えてくると思います。
そしてもう一点。
いま東北の被災地では、復興の作業が進んでいます。
が、今のところほんの僅かしか進んでいないのが、現状です。
しかしマスメディアでは、支援ありがとう、東北は頑張ってます、復興に向けてまた一歩進む、、、みたいなプラスなイメージの報道ばかりが、目立ちます。
(震災一年を迎えるため、最近は厳しい内容の報道が増えてはいますが、、)
視聴者はプラスな報道ばかり見てるので、少しづつ復興してる、良くなってきている、何となく復興してきている、と漠然とプラスなイメージを抱いてきていると思われます。
何となく復興してると思っているため、次第に支援の手がゆるんだり、興味が薄れたりということが、現実に起きてきています。
私が調べたかぎりでは、復興と言えるはほんの一部だけ。
そして一部が復興途中、残り大半はまったく手付かずの状態です。
復興とは程遠く、まだ始まったばかりといっても過言ではないでしょう。
しかし現在、ボランティアの数は減る一方、支援も少しづつ減ってきています。
私たちの「何となく復興してきている」という漠然としたイメージが、被災地への関心を薄れさせています。
まだまだ支援は必要です。
そう、まだまだです。
もう一度、改めて被災地への関心を寄せましょう。
もう一度、被災地の現状がどうなのか、調べてみましょう。
まだやれること、手伝えること、支援できることはたくさんあるはずなんです。
私は最低でも、10年間は継続的な支援が必要だと考えています。
手を抜くことなく、長く続けていかなければなりません。
続きはまたの機会にしたいと思います。m(_ _)m
2011/07/14
ちょっと職業柄、お墓と地震について考えてみたいと思います。
私、一応石工職人ゆえ、間違いはないと思いますが、絶対の自信はありませんので、あしからず…。
さて、率直に言ってしまうと、石のお墓は地震には弱いと言えます。
石は重量が重いうえ、和型となればその形状からして、バランスの悪い形をしています。
いわゆる「和型の三段墓」は、諸説ありますが仏壇などの位牌(木主)をかたどったものとか、修験道の板碑から派生したともいわれ、石塔部分は細長く背が高いものが多いです。
背が高ければ重心は高くなり、石塔の底の部分が小さくすわりが悪ければ当然バランスが悪く、倒れやすいといえます。
また、最近主流になりつつある地上納骨堂や、お墓の入口に階段を付けるなどして基段を周囲より高くするなどして、まさに見上げるようなお墓もあります。
しかし、地震という観点からみれば、高ければ高いほど揺れの影響が大きく、地震には弱いといえます。
逆に低ければ低いほど地震の影響は減ります。
当たり前といえば当たり前なんですが、大きく、高く、立派なお墓を好まれる方やそういう風潮・地域性もあり、一時期においてはシンプルでこじんまりというより、とにかく大きく立派なお墓が作られた時代もありました。
他にも墓誌や灯籠などが地震で多く倒れました。
墓誌は形状が板状なので前後バランスが悪く、前後方向へ揺れると簡単にぱたんと倒れやすくなってしまいます。
灯籠も丸灯籠や春日灯籠などで、細くて背が高く、そして上部の笠・火袋が大きいような、頭が重くバランスが悪い形の灯籠が倒れたケースが多いようです。
では、具体的な対策としては、どうしたら良いのでしょうか?
ここ十数年でお墓の耐震技術は、とても向上しました。
特に耐震性が高い、接着剤(石材用弾性接着剤)の効果は高いようです。
その接着剤を使った耐震施工で、がっちりと据え直すという手があります。
しかし、震度5までは耐えられても、震度6以上の非常に強い揺れにも耐えられるかどうかは、私には正直分かりません。
個人的にはかなり厳しいんじゃないかと思っています。
(接着剤そのものは強固で弾性があったとしても、石材そのものが揺れの強さに耐えられないという可能性もあります。つまり、石の方が割れてしまってくっついた接着剤ごと取れてしまう、という事例も多く見られます。同様に、基礎部コンクリートの方が割れて石が取れてしまうというケースもあります)
ではどうしたらいいか?と私が勝手に考えるには、耐震施工をしっかりやったうえに、お墓の形状自体も地震に強い形にすれば、さらに地震に強いお墓ができるんじゃないかと考えます。
具体的には…。
まずは、お墓の背を高くしすぎないことです。
地上納骨堂の高さを低くするとか、基段作らず周囲より高くしすぎないなど。
思い切って地上納骨をやめて、少し不便ですが地下納骨式や半地下式にするという方法もあります。
また、特にお墓の形状にこだわらないのなら、石塔を背の低い洋型(横形)にするとか。
和型でも、よく目にする石塔の、高さを半分くらいの低い石塔にしてしまう、という手もあるかと思います。
(
ちなみに「和型の三段墓」は、あの形・形状でなければいけないという、決定的な理由はありません。例えば五輪塔にはちゃんとしたいわれが記述された経典(お経)があります。しかし、和型の三段墓にはそういうものはありません。もともとその成り立ちやいわれに諸説あり、形に福禄寿の意味があるとする説もありますが、これも近年になっていわれるようになったと考えられます。3つの石の積み石形状(三段)であった方が良いと考えられますが、三段墓の形・バランス自体には、あまりこだわらなくても良いのではないかと思っています。
)
三段墓には、このぐらいの高さ、形だと見た目が良いという、いわゆる黄金比がいくつかありますが、そのバランスが気にならないなら、低い和型の三段墓というのも良いと私は考えます。
また、バランスの悪い板状の墓誌は思い切ってやめてしまう、という手があります。
昔は墓誌などなく、石塔の後ろや横などに、直接名前や戒名などを彫っていました。
とりあえず、戒名などは石塔に彫っていって、戒名等がいっぱいになって彫れなくなるまで墓誌はなくても良いと私は思います。
またお墓の広さに余裕があるなら、墓誌を板状のものではなく、洋型石塔のような厚くがっちりしっかりしたものにするとか、西洋などで見られるプレート式(敷石みたいに平たく埋め込んでしまうもの)にするという手もあります。
次に灯籠ですが、とにかく低くて安定したものを選ぶと良いです。
背が高いものでも、なるべく太くがっちりしていて、形状が安定しているものを選ぶ方が良いでしょう。
墓前灯篭で使われるいわゆる丸型灯籠は、安定が悪く危険性が高いので、できればやめることをお薦めしたいです。
一応ざっと一通り見てきましたが、参考になれば幸いです。
気になった方は、改めて石工さんに相談するのが良いでしょう。
さて、上記の対策をすれば、地震に強いお墓ができるとは思います。
しかしながら、自分のお墓は大丈夫でも、おとなりのお墓が倒れてきて被害を受けてしまう、という被害は残念ながら避けることができません。(- -;
絶対に大丈夫とは、言い切れないのが実情なんです。
それでも、地震への対応策をしっかり講じておけば、少なくとも他人に迷惑を掛けることがないという、安心感はあります。
この機会に、お墓の耐震を考えてみるのも、良いのかも知れません。
m(_ _)m
私、一応石工職人ゆえ、間違いはないと思いますが、絶対の自信はありませんので、あしからず…。
さて、率直に言ってしまうと、石のお墓は地震には弱いと言えます。
石は重量が重いうえ、和型となればその形状からして、バランスの悪い形をしています。
いわゆる「和型の三段墓」は、諸説ありますが仏壇などの位牌(木主)をかたどったものとか、修験道の板碑から派生したともいわれ、石塔部分は細長く背が高いものが多いです。
背が高ければ重心は高くなり、石塔の底の部分が小さくすわりが悪ければ当然バランスが悪く、倒れやすいといえます。
また、最近主流になりつつある地上納骨堂や、お墓の入口に階段を付けるなどして基段を周囲より高くするなどして、まさに見上げるようなお墓もあります。
しかし、地震という観点からみれば、高ければ高いほど揺れの影響が大きく、地震には弱いといえます。
逆に低ければ低いほど地震の影響は減ります。
当たり前といえば当たり前なんですが、大きく、高く、立派なお墓を好まれる方やそういう風潮・地域性もあり、一時期においてはシンプルでこじんまりというより、とにかく大きく立派なお墓が作られた時代もありました。
他にも墓誌や灯籠などが地震で多く倒れました。
墓誌は形状が板状なので前後バランスが悪く、前後方向へ揺れると簡単にぱたんと倒れやすくなってしまいます。
灯籠も丸灯籠や春日灯籠などで、細くて背が高く、そして上部の笠・火袋が大きいような、頭が重くバランスが悪い形の灯籠が倒れたケースが多いようです。
では、具体的な対策としては、どうしたら良いのでしょうか?
ここ十数年でお墓の耐震技術は、とても向上しました。
特に耐震性が高い、接着剤(石材用弾性接着剤)の効果は高いようです。
その接着剤を使った耐震施工で、がっちりと据え直すという手があります。
しかし、震度5までは耐えられても、震度6以上の非常に強い揺れにも耐えられるかどうかは、私には正直分かりません。
個人的にはかなり厳しいんじゃないかと思っています。
(接着剤そのものは強固で弾性があったとしても、石材そのものが揺れの強さに耐えられないという可能性もあります。つまり、石の方が割れてしまってくっついた接着剤ごと取れてしまう、という事例も多く見られます。同様に、基礎部コンクリートの方が割れて石が取れてしまうというケースもあります)
ではどうしたらいいか?と私が勝手に考えるには、耐震施工をしっかりやったうえに、お墓の形状自体も地震に強い形にすれば、さらに地震に強いお墓ができるんじゃないかと考えます。
具体的には…。
まずは、お墓の背を高くしすぎないことです。
地上納骨堂の高さを低くするとか、基段作らず周囲より高くしすぎないなど。
思い切って地上納骨をやめて、少し不便ですが地下納骨式や半地下式にするという方法もあります。
また、特にお墓の形状にこだわらないのなら、石塔を背の低い洋型(横形)にするとか。
和型でも、よく目にする石塔の、高さを半分くらいの低い石塔にしてしまう、という手もあるかと思います。
(
ちなみに「和型の三段墓」は、あの形・形状でなければいけないという、決定的な理由はありません。例えば五輪塔にはちゃんとしたいわれが記述された経典(お経)があります。しかし、和型の三段墓にはそういうものはありません。もともとその成り立ちやいわれに諸説あり、形に福禄寿の意味があるとする説もありますが、これも近年になっていわれるようになったと考えられます。3つの石の積み石形状(三段)であった方が良いと考えられますが、三段墓の形・バランス自体には、あまりこだわらなくても良いのではないかと思っています。
)
三段墓には、このぐらいの高さ、形だと見た目が良いという、いわゆる黄金比がいくつかありますが、そのバランスが気にならないなら、低い和型の三段墓というのも良いと私は考えます。
また、バランスの悪い板状の墓誌は思い切ってやめてしまう、という手があります。
昔は墓誌などなく、石塔の後ろや横などに、直接名前や戒名などを彫っていました。
とりあえず、戒名などは石塔に彫っていって、戒名等がいっぱいになって彫れなくなるまで墓誌はなくても良いと私は思います。
またお墓の広さに余裕があるなら、墓誌を板状のものではなく、洋型石塔のような厚くがっちりしっかりしたものにするとか、西洋などで見られるプレート式(敷石みたいに平たく埋め込んでしまうもの)にするという手もあります。
次に灯籠ですが、とにかく低くて安定したものを選ぶと良いです。
背が高いものでも、なるべく太くがっちりしていて、形状が安定しているものを選ぶ方が良いでしょう。
墓前灯篭で使われるいわゆる丸型灯籠は、安定が悪く危険性が高いので、できればやめることをお薦めしたいです。
一応ざっと一通り見てきましたが、参考になれば幸いです。
気になった方は、改めて石工さんに相談するのが良いでしょう。
さて、上記の対策をすれば、地震に強いお墓ができるとは思います。
しかしながら、自分のお墓は大丈夫でも、おとなりのお墓が倒れてきて被害を受けてしまう、という被害は残念ながら避けることができません。(- -;
絶対に大丈夫とは、言い切れないのが実情なんです。
それでも、地震への対応策をしっかり講じておけば、少なくとも他人に迷惑を掛けることがないという、安心感はあります。
この機会に、お墓の耐震を考えてみるのも、良いのかも知れません。
m(_ _)m